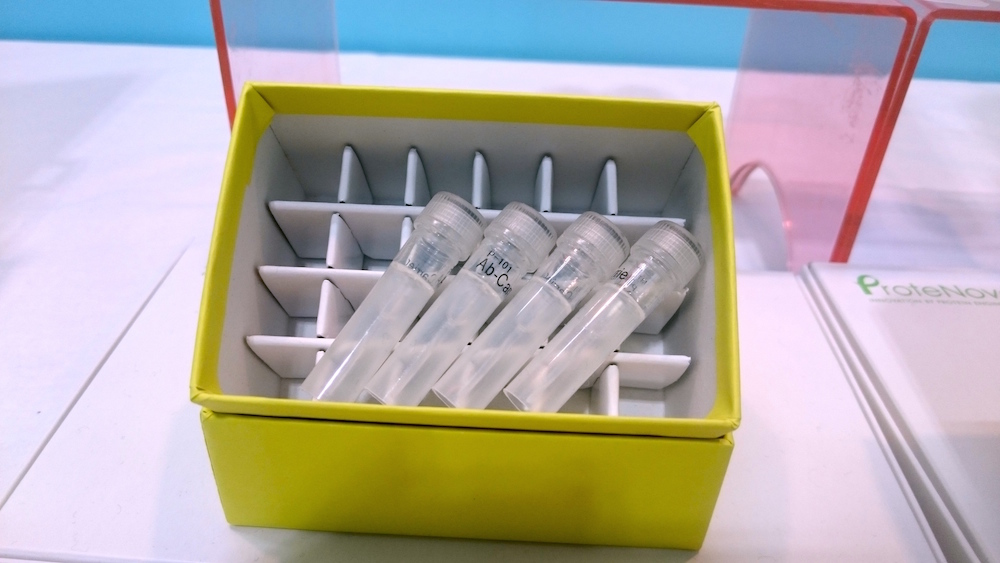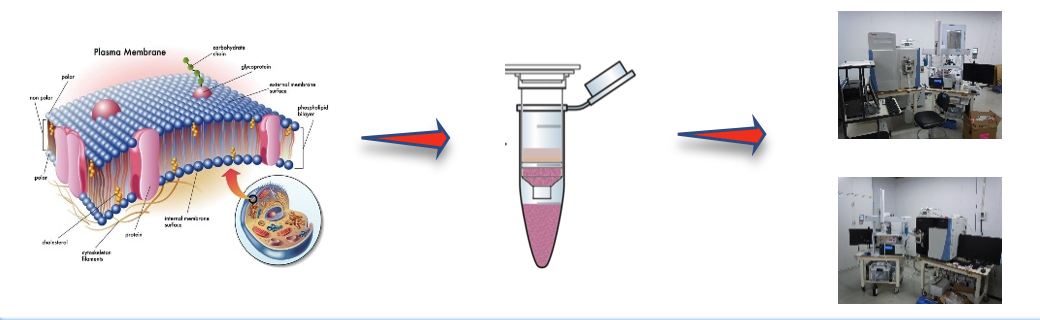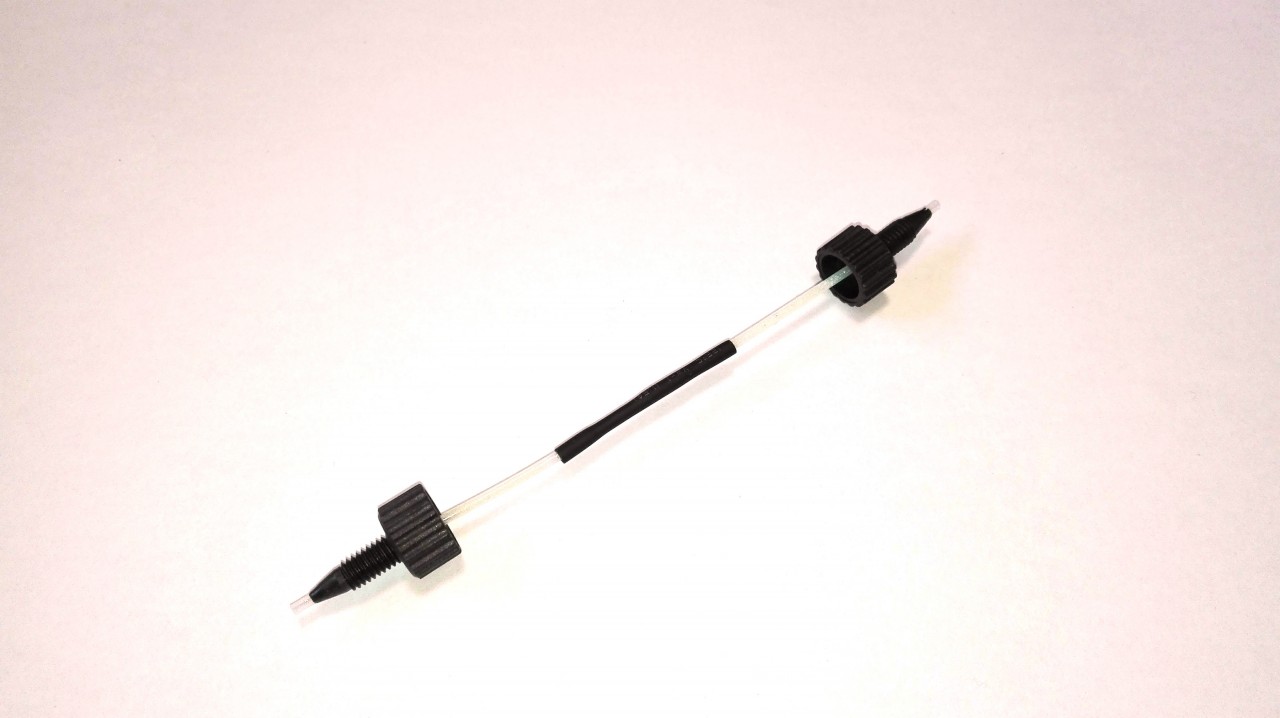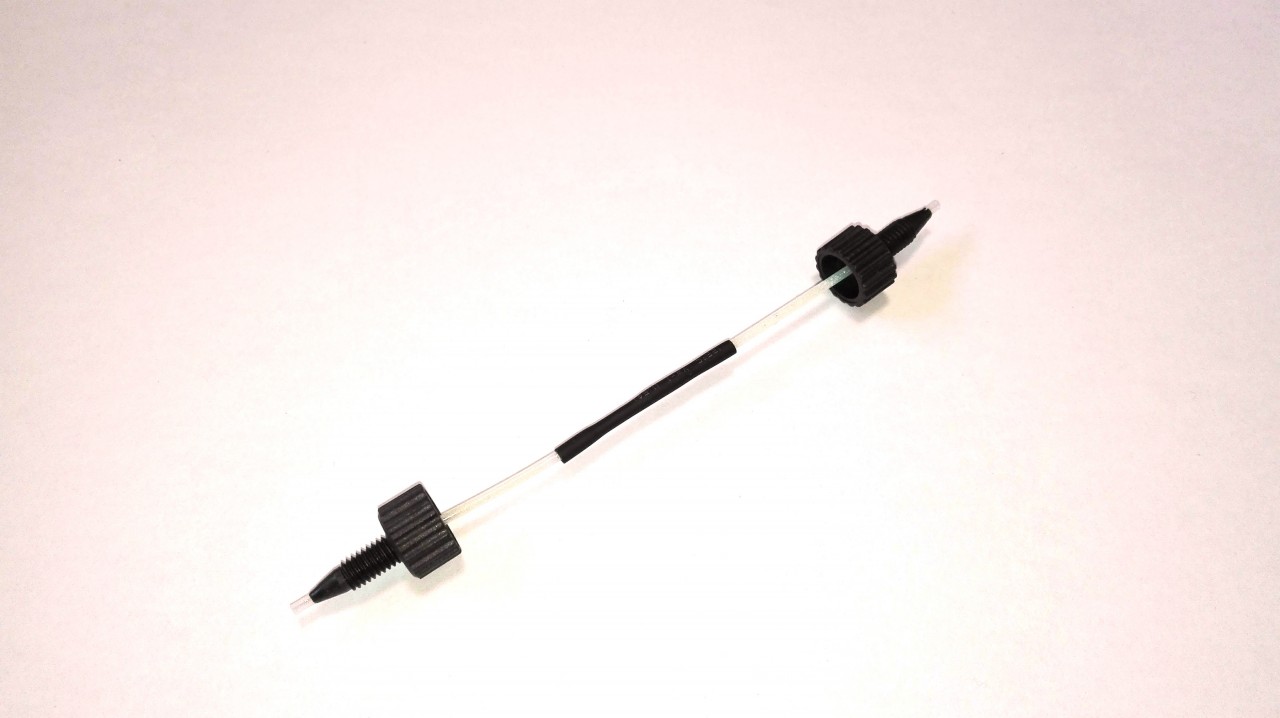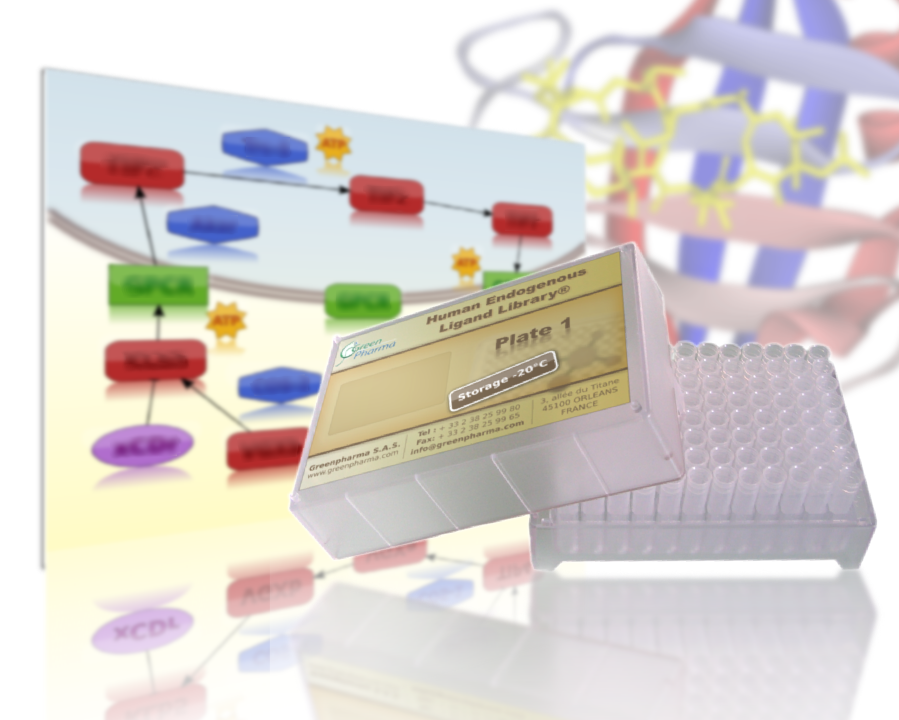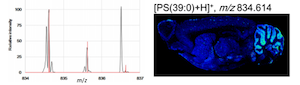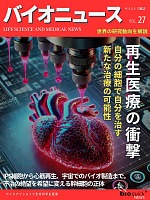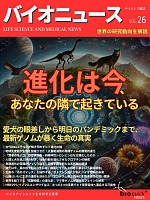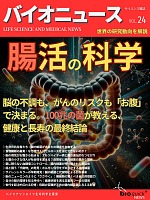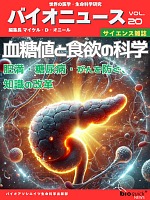温度で性が変わるトカゲの謎、ゲノム解読でついに解明へ!
 オスとメスの性が遺伝子だけでなく、卵が置かれた巣の「温度」によっても決まる――そんな不思議なトカゲがいます。ペットとしても人気のフトアゴヒゲトカゲです。長年、科学者たちを惹きつけてきたこの性の謎を解き明かすため、2つの研究チームが別々のアプローチでそのゲノムのほぼ完全な解読に挑みました。そして驚くべきことに、両チームは同じ「性のマスター遺伝子」候補を発見したのです。
2025年8月19日、フトアゴヒゲトカゲ(Pogona vitticeps)のほぼ完全な参照ゲノムを提示する2つの異なる研究が発表されました。このトカゲはオーストラリア中東部に広く分布し、欧米やアジアでペットとしても人気があります。この種は、その性が遺伝だけでなく巣の温度にも依存するという、動物としては珍しい特徴を持っています。このため、性決定の生物学的基盤を研究するための有用なモデルとされてきました。そして、ゲノム科学における巨大な技術的進歩により、ついにゲノム上の特定の領域と、雄の性分化の中心となる可能性が高いマスター性決定遺伝子候補が発見されたのです。この発見が、2つの異なるグループによって2つの異なるアプローチを用いて独立して検証されたことで、その信頼性は非常に高いものとなりました。
フトアゴヒゲトカゲは、遺伝と環境要因、特に温度の両方に影響される珍しい性決定システムを持っています。ほとんどの動物では性が染色体のみによって決まりますが、フトアゴヒゲトカゲは高い抱卵温度によって性が雄から雌に逆転することがあります。つまり、雄の染色体を持つトカゲでも、卵が十分に暖かい温度で抱卵されれば、繁殖可能な雌として発生するのです。
鳥類や多くの爬虫類と同様に、この種はZZ/ZW型性染色体システムを持ち、雌は不対のZW染色体を、雄は対になるZZ染色体を持っています。さらにこの種の性決定を複雑にしているのは、Z
オスとメスの性が遺伝子だけでなく、卵が置かれた巣の「温度」によっても決まる――そんな不思議なトカゲがいます。ペットとしても人気のフトアゴヒゲトカゲです。長年、科学者たちを惹きつけてきたこの性の謎を解き明かすため、2つの研究チームが別々のアプローチでそのゲノムのほぼ完全な解読に挑みました。そして驚くべきことに、両チームは同じ「性のマスター遺伝子」候補を発見したのです。
2025年8月19日、フトアゴヒゲトカゲ(Pogona vitticeps)のほぼ完全な参照ゲノムを提示する2つの異なる研究が発表されました。このトカゲはオーストラリア中東部に広く分布し、欧米やアジアでペットとしても人気があります。この種は、その性が遺伝だけでなく巣の温度にも依存するという、動物としては珍しい特徴を持っています。このため、性決定の生物学的基盤を研究するための有用なモデルとされてきました。そして、ゲノム科学における巨大な技術的進歩により、ついにゲノム上の特定の領域と、雄の性分化の中心となる可能性が高いマスター性決定遺伝子候補が発見されたのです。この発見が、2つの異なるグループによって2つの異なるアプローチを用いて独立して検証されたことで、その信頼性は非常に高いものとなりました。
フトアゴヒゲトカゲは、遺伝と環境要因、特に温度の両方に影響される珍しい性決定システムを持っています。ほとんどの動物では性が染色体のみによって決まりますが、フトアゴヒゲトカゲは高い抱卵温度によって性が雄から雌に逆転することがあります。つまり、雄の染色体を持つトカゲでも、卵が十分に暖かい温度で抱卵されれば、繁殖可能な雌として発生するのです。
鳥類や多くの爬虫類と同様に、この種はZZ/ZW型性染色体システムを持ち、雌は不対のZW染色体を、雄は対になるZZ染色体を持っています。さらにこの種の性決定を複雑にしているのは、Z
老化の個人差を生む400以上の遺伝子を発見
 なぜ加齢に個人差が?老化を加速させる400以上の遺伝子を特定
90代になっても心身ともに健康な人がいる一方で、ずっと若い時期から糖尿病やアルツハイマー病、運動機能の問題に悩まされる人もいます。転倒やインフルエンザといった不調からすぐに回復できる人もいれば、そうでない人もいます。なぜ、このような違いが生まれるのでしょうか?この長年の疑問に光を当てる新しい研究が登場しました。
2025年8月4日、コロラド大学ボルダー校が主導する研究チームが、学術誌「Nature Genetics」に、加速する老化に関連する400以上の遺伝子を特定したと発表しました。この研究は、老化のタイプが一つではないことを示唆しており、将来の老化治療に新たな道を開くかもしれません。
この研究論文のタイトルは「Uncovering the Multivariate Genetic Architecture of Frailty with Genomic Structural Equation Modeling(ゲノム構造方程式モデリングを用いた虚弱性の多変量遺伝的構造の解明)」です。
この論文で、国際的な共同研究チームは、7つの異なるサブタイプにわたって加速する老化に関連する400以上の遺伝子を特定しました。この研究により、認知機能の低下から運動能力の問題、社会的孤立に至るまで、「虚弱性」として知られる老化のタイプごとに、異なる遺伝子群がその背景にあることが明らかになりました。
この発見は、「ジェロサイエンス仮説」として知られる考え方を裏付けるものです。つまり、加齢に伴う複数の慢性疾患を治療するためには、老化そのものを治療する必要があるという考え方です。
論文の筆頭著者であり、コロラド大学行動遺伝学研究所の博士研究員であるイザベル・フット博士(Isabelle Foote, PhD)は、「加
なぜ加齢に個人差が?老化を加速させる400以上の遺伝子を特定
90代になっても心身ともに健康な人がいる一方で、ずっと若い時期から糖尿病やアルツハイマー病、運動機能の問題に悩まされる人もいます。転倒やインフルエンザといった不調からすぐに回復できる人もいれば、そうでない人もいます。なぜ、このような違いが生まれるのでしょうか?この長年の疑問に光を当てる新しい研究が登場しました。
2025年8月4日、コロラド大学ボルダー校が主導する研究チームが、学術誌「Nature Genetics」に、加速する老化に関連する400以上の遺伝子を特定したと発表しました。この研究は、老化のタイプが一つではないことを示唆しており、将来の老化治療に新たな道を開くかもしれません。
この研究論文のタイトルは「Uncovering the Multivariate Genetic Architecture of Frailty with Genomic Structural Equation Modeling(ゲノム構造方程式モデリングを用いた虚弱性の多変量遺伝的構造の解明)」です。
この論文で、国際的な共同研究チームは、7つの異なるサブタイプにわたって加速する老化に関連する400以上の遺伝子を特定しました。この研究により、認知機能の低下から運動能力の問題、社会的孤立に至るまで、「虚弱性」として知られる老化のタイプごとに、異なる遺伝子群がその背景にあることが明らかになりました。
この発見は、「ジェロサイエンス仮説」として知られる考え方を裏付けるものです。つまり、加齢に伴う複数の慢性疾患を治療するためには、老化そのものを治療する必要があるという考え方です。
論文の筆頭著者であり、コロラド大学行動遺伝学研究所の博士研究員であるイザベル・フット博士(Isabelle Foote, PhD)は、「加
10年の謎解明!ヒトデを「溶かす」消耗病の原因菌を特定。生態系回復へ光
 2013年以降、メキシコからアラスカにかけての沿岸で、何十億ものヒトデがまるで「溶ける」ように死んでいく謎の病気が蔓延しています。10年以上にわたり海洋生態系に壊滅的な被害をもたらしてきたこの「ヒトデ消耗病」。その原因がついに特定され、生態系回復への重要な一歩が踏み出されました。ブリティッシュ・コロンビア大学(UBC)の研究者たちが、ヒトデ消耗病の背後にいた細菌の犯人を特定し、10年来の謎を解明しました。
2013年以来、メキシコからアラスカにかけて何十億ものヒトデを死滅させてきた消耗病の原因は、ビブリオ・ペクテニシダという細菌の一種であることが特定されました。このFHCF-3と名付けられた菌株の詳細は、UBC、ハカイ研究所、ワシントン大学の科学者たちによって、2025年8月4日付の科学雑誌『Nature Ecology & Evolution』に掲載された新しい論文で詳述されています。論文のタイトルは「Vibrio pectenicida Strain FHCF-3 Is a Causative Agent of Sea Star Wasting Disease(Vibrio pectenicida FHCF-3株はヒトデ消耗病の原因菌である)」です。
「消耗病は、野生における史上最大規模の海洋伝染病とされていますが、その決定的な原因はこれまで謎に包まれていました。今回、病原体を特定したことで、この伝染病の影響を軽減する方法の検討を開始できます」と、筆頭著者であり、UBC地球・海洋・大気科学科(EOAS)およびハカイ研究所の研究員であるメラニー・プレンティス博士(Melanie Prentice, PhD)は述べています。
ビブリオ属の細菌は、サンゴや貝類、そして人間にも感染することが知られており、コレラ菌もこの仲間です。
他のビブリオ属菌が温かい
2013年以降、メキシコからアラスカにかけての沿岸で、何十億ものヒトデがまるで「溶ける」ように死んでいく謎の病気が蔓延しています。10年以上にわたり海洋生態系に壊滅的な被害をもたらしてきたこの「ヒトデ消耗病」。その原因がついに特定され、生態系回復への重要な一歩が踏み出されました。ブリティッシュ・コロンビア大学(UBC)の研究者たちが、ヒトデ消耗病の背後にいた細菌の犯人を特定し、10年来の謎を解明しました。
2013年以来、メキシコからアラスカにかけて何十億ものヒトデを死滅させてきた消耗病の原因は、ビブリオ・ペクテニシダという細菌の一種であることが特定されました。このFHCF-3と名付けられた菌株の詳細は、UBC、ハカイ研究所、ワシントン大学の科学者たちによって、2025年8月4日付の科学雑誌『Nature Ecology & Evolution』に掲載された新しい論文で詳述されています。論文のタイトルは「Vibrio pectenicida Strain FHCF-3 Is a Causative Agent of Sea Star Wasting Disease(Vibrio pectenicida FHCF-3株はヒトデ消耗病の原因菌である)」です。
「消耗病は、野生における史上最大規模の海洋伝染病とされていますが、その決定的な原因はこれまで謎に包まれていました。今回、病原体を特定したことで、この伝染病の影響を軽減する方法の検討を開始できます」と、筆頭著者であり、UBC地球・海洋・大気科学科(EOAS)およびハカイ研究所の研究員であるメラニー・プレンティス博士(Melanie Prentice, PhD)は述べています。
ビブリオ属の細菌は、サンゴや貝類、そして人間にも感染することが知られており、コレラ菌もこの仲間です。
他のビブリオ属菌が温かい
週3回のフライドポテトで糖尿病リスク20%増。全粒穀物への置き換えが鍵
 「ここでの公衆衛生上のメッセージは、シンプルかつ強力です。日々の食生活の小さな変化が、2型糖尿病のリスクに重要な影響を与える可能性があるということです。」多くの人に愛されているジャガイモですが、その調理法によっては、健康に大きな影響を及ぼすかもしれません。特に、人気のフライドポテトが、ある生活習慣病のリスクを高める可能性が、ハーバード大学公衆衛生大学院が主導する大規模な研究で明らかになりました。この研究は、ジャガイモの食べ方と健康について、私たちに新たな視点を提供してくれます。
研究の要点
ハーバード大学公衆衛生大学院(Harvard T.H. Chan School of Public Health)が主導した研究で、205,000人以上の成人を数十年にわたり追跡調査した結果、週に3食のフライドポテトの摂取が、2型糖尿病を発症するリスクを20%増加させることが関連付けられました。一方で、ベイクドポテト、茹でたポテト、マッシュポテトの摂取と糖尿病リスクとの間に有意な関連は見られませんでした。しかし、調理法に関わらずジャガイモを全粒穀物に置き換えることで、T2Dのリスクが低下すると推定されました。
この研究は、ジャガイモとT2Dリスクに関するこれまでで最も包括的な知見を提供するものです。過去の研究では、ジャガイモを他の食品に置き換える効果については検討されていませんでした。
研究者らによると、この発見は、より健康的な食品選択を目指す個人や、国の食事ガイドラインを検討する政策立案者にとって有益な情報となり得るとのことです。
この研究は、2025年8月6日付の医学雑誌『BMJ』に掲載されました。オープンアクセスの論文タイトルは「Total and Specific Potato Intake and Risk of Type 2 Diabetes: Results
「ここでの公衆衛生上のメッセージは、シンプルかつ強力です。日々の食生活の小さな変化が、2型糖尿病のリスクに重要な影響を与える可能性があるということです。」多くの人に愛されているジャガイモですが、その調理法によっては、健康に大きな影響を及ぼすかもしれません。特に、人気のフライドポテトが、ある生活習慣病のリスクを高める可能性が、ハーバード大学公衆衛生大学院が主導する大規模な研究で明らかになりました。この研究は、ジャガイモの食べ方と健康について、私たちに新たな視点を提供してくれます。
研究の要点
ハーバード大学公衆衛生大学院(Harvard T.H. Chan School of Public Health)が主導した研究で、205,000人以上の成人を数十年にわたり追跡調査した結果、週に3食のフライドポテトの摂取が、2型糖尿病を発症するリスクを20%増加させることが関連付けられました。一方で、ベイクドポテト、茹でたポテト、マッシュポテトの摂取と糖尿病リスクとの間に有意な関連は見られませんでした。しかし、調理法に関わらずジャガイモを全粒穀物に置き換えることで、T2Dのリスクが低下すると推定されました。
この研究は、ジャガイモとT2Dリスクに関するこれまでで最も包括的な知見を提供するものです。過去の研究では、ジャガイモを他の食品に置き換える効果については検討されていませんでした。
研究者らによると、この発見は、より健康的な食品選択を目指す個人や、国の食事ガイドラインを検討する政策立案者にとって有益な情報となり得るとのことです。
この研究は、2025年8月6日付の医学雑誌『BMJ』に掲載されました。オープンアクセスの論文タイトルは「Total and Specific Potato Intake and Risk of Type 2 Diabetes: Results
驚異の記憶力を持つ高齢者「スーパーエイジャー」の脳は、何が違うのか?
 年齢を重ねると、物忘れが増えるのは仕方がないこと…そう考えていませんか?しかし、80歳を超えても30歳以上若い人と同じレベルの記憶力を保ち続ける「スーパーエイジャー」と呼ばれる人々がいます。25年にわたる彼らの研究が、認知機能の低下は必ずしも避けられない運命ではないことを示し、健康な脳を維持するための新たなヒントを与えてくれています。ノースウェスタン大学医学部の科学者たちは、25年間にわたり「スーパーエイジャー」と名付けられた80歳以上の人々を研究し、彼らがなぜ特別なのかを解明しようと努めてきました。
スーパーエイジャーは、少なくとも30歳は年下の同等レベルという卓越した記憶力を示し、認知機能の低下が加齢に伴う避けられない現象であるという長年の定説に疑問を投げかけています。
この四半世紀にわたる研究で、科学者たちはスーパーエイジャーと一般的な加齢をたどる人々との間に、社交的であるといった顕著なライフスタイルや性格の違いを見出してきました。しかし、「私たちにとって本当に衝撃的だったのは、彼らの脳内で発見されたことです」と、ノースウェスタン大学ファインバーグ医学部の精神医学・行動科学および神経学の教授であるサンドラ・ワイントラウブ博士(Sandra Weintraub, PhD)は述べています。
スーパーエイジングに関連する生物学的および行動的特性を特定することで、科学者たちは認知的な回復力を促進し、アルツハイマー病やその他の認知機能低下や認知症を引き起こす疾患を遅らせる、あるいは予防するための新しい戦略を発見することを目指しています。
「私たちの発見は、高齢期における卓越した記憶が可能であるだけでなく、それが明確な神経生物学的特徴と関連していることを示しています。これは、人生の後半においても脳の健康を維持することを目的とした新しい介入への扉を開くものです」と、今回
年齢を重ねると、物忘れが増えるのは仕方がないこと…そう考えていませんか?しかし、80歳を超えても30歳以上若い人と同じレベルの記憶力を保ち続ける「スーパーエイジャー」と呼ばれる人々がいます。25年にわたる彼らの研究が、認知機能の低下は必ずしも避けられない運命ではないことを示し、健康な脳を維持するための新たなヒントを与えてくれています。ノースウェスタン大学医学部の科学者たちは、25年間にわたり「スーパーエイジャー」と名付けられた80歳以上の人々を研究し、彼らがなぜ特別なのかを解明しようと努めてきました。
スーパーエイジャーは、少なくとも30歳は年下の同等レベルという卓越した記憶力を示し、認知機能の低下が加齢に伴う避けられない現象であるという長年の定説に疑問を投げかけています。
この四半世紀にわたる研究で、科学者たちはスーパーエイジャーと一般的な加齢をたどる人々との間に、社交的であるといった顕著なライフスタイルや性格の違いを見出してきました。しかし、「私たちにとって本当に衝撃的だったのは、彼らの脳内で発見されたことです」と、ノースウェスタン大学ファインバーグ医学部の精神医学・行動科学および神経学の教授であるサンドラ・ワイントラウブ博士(Sandra Weintraub, PhD)は述べています。
スーパーエイジングに関連する生物学的および行動的特性を特定することで、科学者たちは認知的な回復力を促進し、アルツハイマー病やその他の認知機能低下や認知症を引き起こす疾患を遅らせる、あるいは予防するための新しい戦略を発見することを目指しています。
「私たちの発見は、高齢期における卓越した記憶が可能であるだけでなく、それが明確な神経生物学的特徴と関連していることを示しています。これは、人生の後半においても脳の健康を維持することを目的とした新しい介入への扉を開くものです」と、今回
ジャガイモの祖先はトマトとのハーフだった!ゲノム解析が解き明かす900万年前の出会い
 食卓に欠かせないジャガイモ。そのルーツを辿ると、なんとトマトとの意外な出会いがあったことをご存知でしょうか?約900万年前、南米大陸で起きた壮大な自然のドラマが、私たちが知るジャガイモを誕生させました。最新のゲノム解析技術が、この世界で最も重要な作物の一つであるジャガイモの、長く謎に包まれていた誕生の秘密を解き明かしたのです。驚きに満ちた進化の物語をご紹介します。
国際的な研究チームが、約900万年前にトマトの祖先にあたる植物と、南米原産のジャガイモに似た種との間で起こった自然交雑が、現代のジャガイモを生み出したことを突き止めました。2025年7月31日にCell Press社の学術誌Cellで発表された研究で、研究者たちは、この古代の進化的イベントが「塊茎(かいけい)」、つまりジャガイモやヤムイモ、タロイモなどに見られる、栄養を蓄える肥大化した地下構造の形成を引き起こしたと示唆しています。このオープンアクセスの論文は、「Ancient Hybridization Underlies Tuberization and Radiation of the Potato Lineage(古代の交雑がジャガイモ系統の塊茎形成と多様化の基盤である)」と題されています。「私たちの発見は、種間の交雑イベントが、いかにして新しい形質の進化を促し、さらなる種の出現を可能にするかを示しています」と、責任著者である中国農業科学院のサンウェン・フアン博士(Sanwen Huang, PhD)は語ります。「私たちはついに、ジャガイモがどこから来たのかという謎を解明したのです。」
世界で最も重要な作物の一つとして、ジャガイモの起源は長い間、科学者たちを悩ませてきました。見た目において、現代のジャガイモの地上部分は、チリに自生するEtuberosumと呼ばれる3種のジャガイモに似た植物とほぼ同一
食卓に欠かせないジャガイモ。そのルーツを辿ると、なんとトマトとの意外な出会いがあったことをご存知でしょうか?約900万年前、南米大陸で起きた壮大な自然のドラマが、私たちが知るジャガイモを誕生させました。最新のゲノム解析技術が、この世界で最も重要な作物の一つであるジャガイモの、長く謎に包まれていた誕生の秘密を解き明かしたのです。驚きに満ちた進化の物語をご紹介します。
国際的な研究チームが、約900万年前にトマトの祖先にあたる植物と、南米原産のジャガイモに似た種との間で起こった自然交雑が、現代のジャガイモを生み出したことを突き止めました。2025年7月31日にCell Press社の学術誌Cellで発表された研究で、研究者たちは、この古代の進化的イベントが「塊茎(かいけい)」、つまりジャガイモやヤムイモ、タロイモなどに見られる、栄養を蓄える肥大化した地下構造の形成を引き起こしたと示唆しています。このオープンアクセスの論文は、「Ancient Hybridization Underlies Tuberization and Radiation of the Potato Lineage(古代の交雑がジャガイモ系統の塊茎形成と多様化の基盤である)」と題されています。「私たちの発見は、種間の交雑イベントが、いかにして新しい形質の進化を促し、さらなる種の出現を可能にするかを示しています」と、責任著者である中国農業科学院のサンウェン・フアン博士(Sanwen Huang, PhD)は語ります。「私たちはついに、ジャガイモがどこから来たのかという謎を解明したのです。」
世界で最も重要な作物の一つとして、ジャガイモの起源は長い間、科学者たちを悩ませてきました。見た目において、現代のジャガイモの地上部分は、チリに自生するEtuberosumと呼ばれる3種のジャガイモに似た植物とほぼ同一
自己免疫疾患の謎に迫る!免疫が「自分」と「敵」を見分ける仕組みとは?
 私たちの体は、ウイルスや細菌が侵入すると「RNA」という物質を感知し、免疫システムが作動して攻撃を始めます。しかし、実は私たちの正常な細胞にもRNAは存在しています。それなのに、なぜ免疫システムは自身の細胞を攻撃しないのでしょうか?この長年の謎を解き明かす、驚くべき発見が報告されました。私たちの体には、自身のRNAを巧みに隠し、免疫の攻撃から守るための巧妙な「目印」があったのです。
コネチカット大学医学部のヴィジャイ・ラティナム博士(Vijay Rathinam, PhD)、ボストン小児病院のライアン・フリン医学博士(Ryan Flynn, MD)らの研究チームが、2025年8月6日付の科学雑誌『Nature』に発表した論文「RNA N-Glycosylation Enables Immune Evasion and Homeostatic Efferocytosis(RNAのN-グリコシル化は免疫回避と恒常性エフェロサイトーシスを可能にする)」でその詳細が報告されています。
リボ核酸は、ウイルス、細菌、動物など、すべての生命体にとって不可欠な高分子です。麻疹、インフルエンザ、SARS-CoV-2、狂犬病など多種多様なウイルスがRNAを持っているため、免疫システムは血中などでRNAを検知すると攻撃を開始します。しかし、私たちの細胞も表面にRNAを提示していることがあり、免疫細胞の目に触れているにもかかわらず、通常は無視されます。
「RNAを感染の兆候として認識することは、私たちの体のすべての細胞がRNAを持っているため、問題を引き起こす可能性があります」と、コネチカット大学医学部の免疫学者であるラティナム博士は述べています。問題は、私たちの免疫システムが、自身のRNAと危険な侵入者のRNAをどのように見分けているのか、ということです。
ボストン小児病院とスタンフ
私たちの体は、ウイルスや細菌が侵入すると「RNA」という物質を感知し、免疫システムが作動して攻撃を始めます。しかし、実は私たちの正常な細胞にもRNAは存在しています。それなのに、なぜ免疫システムは自身の細胞を攻撃しないのでしょうか?この長年の謎を解き明かす、驚くべき発見が報告されました。私たちの体には、自身のRNAを巧みに隠し、免疫の攻撃から守るための巧妙な「目印」があったのです。
コネチカット大学医学部のヴィジャイ・ラティナム博士(Vijay Rathinam, PhD)、ボストン小児病院のライアン・フリン医学博士(Ryan Flynn, MD)らの研究チームが、2025年8月6日付の科学雑誌『Nature』に発表した論文「RNA N-Glycosylation Enables Immune Evasion and Homeostatic Efferocytosis(RNAのN-グリコシル化は免疫回避と恒常性エフェロサイトーシスを可能にする)」でその詳細が報告されています。
リボ核酸は、ウイルス、細菌、動物など、すべての生命体にとって不可欠な高分子です。麻疹、インフルエンザ、SARS-CoV-2、狂犬病など多種多様なウイルスがRNAを持っているため、免疫システムは血中などでRNAを検知すると攻撃を開始します。しかし、私たちの細胞も表面にRNAを提示していることがあり、免疫細胞の目に触れているにもかかわらず、通常は無視されます。
「RNAを感染の兆候として認識することは、私たちの体のすべての細胞がRNAを持っているため、問題を引き起こす可能性があります」と、コネチカット大学医学部の免疫学者であるラティナム博士は述べています。問題は、私たちの免疫システムが、自身のRNAと危険な侵入者のRNAをどのように見分けているのか、ということです。
ボストン小児病院とスタンフ
関節リウマチ治療に新たな希望:ナノ粒子が病気の進行を遅らせ、辛い「再燃」を抑制
 関節リウマチ治療に新たな希望:ナノ粒子が病気の進行を遅らせ、辛い「再燃」を抑制する
関節リウマチは、一度発症すると完治が難しい慢性疾患です。そのため、現在の治療は病気の管理と進行の抑制に重点が置かれています。既存の治療法は多くの患者さんで症状をコントロールするのに役立ちますが、病気の発症そのものや、「フレア」と呼ばれる痛みを伴う症状の再燃を防ぐことはできませんでした。
もし、この辛いフレアの重症度を和らげ、病気の進行自体を遅らせることができる新しい治療法が登場したらどうでしょうか。今回、2025年8月6日発行の『ACS Central Science』誌に掲載された研究で、まさにその可能性を秘めたナノ粒子が開発されました。ヒトの血液サンプルと、関節リウマチ様の疾患を持つマウスモデルでの試験結果に基づいています。このオープンアクセスの論文は、「Immunomodulatory Nanoparticles Enable Combination Therapies to Enhance Disease Prevention and Flare Control in Rheumatoid Arthritis(免疫調節ナノ粒子は、関節リウマチにおける疾患予防と再燃制御を強化するための併用療法を可能にする)」と題されています。
関節リウマチ(RA: rheumatoid arthritis)と診断された人の体内では、免疫系が関節を構成する組織を攻撃し、炎症、腫れ、痛みを引き起こします。そして、病気が進行すると、放置すれば深刻な軟骨や骨の損傷につながる可能性があります。アバタセプトなどの疾患修飾性抗リウマチ薬は、疾患の活動性を低下させ、症状の進行を遅らせますが、DMARDsを服用しているほとんどの人は依然として症状のフレアを経験します。また、RAの自己抗体が検出されるものの症状
関節リウマチ治療に新たな希望:ナノ粒子が病気の進行を遅らせ、辛い「再燃」を抑制する
関節リウマチは、一度発症すると完治が難しい慢性疾患です。そのため、現在の治療は病気の管理と進行の抑制に重点が置かれています。既存の治療法は多くの患者さんで症状をコントロールするのに役立ちますが、病気の発症そのものや、「フレア」と呼ばれる痛みを伴う症状の再燃を防ぐことはできませんでした。
もし、この辛いフレアの重症度を和らげ、病気の進行自体を遅らせることができる新しい治療法が登場したらどうでしょうか。今回、2025年8月6日発行の『ACS Central Science』誌に掲載された研究で、まさにその可能性を秘めたナノ粒子が開発されました。ヒトの血液サンプルと、関節リウマチ様の疾患を持つマウスモデルでの試験結果に基づいています。このオープンアクセスの論文は、「Immunomodulatory Nanoparticles Enable Combination Therapies to Enhance Disease Prevention and Flare Control in Rheumatoid Arthritis(免疫調節ナノ粒子は、関節リウマチにおける疾患予防と再燃制御を強化するための併用療法を可能にする)」と題されています。
関節リウマチ(RA: rheumatoid arthritis)と診断された人の体内では、免疫系が関節を構成する組織を攻撃し、炎症、腫れ、痛みを引き起こします。そして、病気が進行すると、放置すれば深刻な軟骨や骨の損傷につながる可能性があります。アバタセプトなどの疾患修飾性抗リウマチ薬は、疾患の活動性を低下させ、症状の進行を遅らせますが、DMARDsを服用しているほとんどの人は依然として症状のフレアを経験します。また、RAの自己抗体が検出されるものの症状
血液凝固の常識を覆す:主役は血小板だけではなかった!赤血球の知られざる重要な役割
 血液凝固の常識を覆す発見:主役は血小板だけではなかった!赤血球の知られざる役割
けがをした時に血が固まるのは、私たちの体を守るための重要な仕組みです。この血液凝固の主役は、長年「血小板」であると考えられてきました。しかし、もし血液中で最も数が多い「赤血球」が、これまで考えられていたような単なる傍観者ではなく、実は血栓を固めるプロセスに積極的に参加しているとしたらどうでしょうか?
ペンシルベニア大学の研究者たちによる最新の研究が、まさにその驚くべき事実を明らかにしました。「この発見は、私たちの体における最も重要なプロセスの一つについての理解を根本から変えるものです」と、同大学ペレルマン医学部の上級研究員であり、本研究の共著者であるルステム・リトビノフ博士(Rustem Litvinov, PhD)は述べています。「過剰な出血や、脳卒中で見られるような危険な血栓を引き起こす凝固障害の研究、そして治療に新たな道を開くものです。」
この発見は2025年7月10日に『Blood Advances』誌に掲載され、傷口を最初に塞ぐ小さな細胞片である血小板だけが血栓の収縮を駆動するという長年の定説を覆しました。ペンシルベニア大学の研究チームは、赤血球自身が血栓を収縮させ安定化させるという、この重要なプロセスに貢献していることを見出したのです。このオープンアクセスの論文は、「Red Blood Cell Aggregation within a Blood Clot Causes Platelet-Independent Clot Shrinkage(血栓内での赤血球の凝集が血小板に依存しない血栓収縮を引き起こす)」と題されています。
「赤血球は17世紀から研究されてきました」と、もう一人の共著者であり、ペンシルベニア大学工学部 機械工学・応用力学の教授であるプラシャント・プロヒ
血液凝固の常識を覆す発見:主役は血小板だけではなかった!赤血球の知られざる役割
けがをした時に血が固まるのは、私たちの体を守るための重要な仕組みです。この血液凝固の主役は、長年「血小板」であると考えられてきました。しかし、もし血液中で最も数が多い「赤血球」が、これまで考えられていたような単なる傍観者ではなく、実は血栓を固めるプロセスに積極的に参加しているとしたらどうでしょうか?
ペンシルベニア大学の研究者たちによる最新の研究が、まさにその驚くべき事実を明らかにしました。「この発見は、私たちの体における最も重要なプロセスの一つについての理解を根本から変えるものです」と、同大学ペレルマン医学部の上級研究員であり、本研究の共著者であるルステム・リトビノフ博士(Rustem Litvinov, PhD)は述べています。「過剰な出血や、脳卒中で見られるような危険な血栓を引き起こす凝固障害の研究、そして治療に新たな道を開くものです。」
この発見は2025年7月10日に『Blood Advances』誌に掲載され、傷口を最初に塞ぐ小さな細胞片である血小板だけが血栓の収縮を駆動するという長年の定説を覆しました。ペンシルベニア大学の研究チームは、赤血球自身が血栓を収縮させ安定化させるという、この重要なプロセスに貢献していることを見出したのです。このオープンアクセスの論文は、「Red Blood Cell Aggregation within a Blood Clot Causes Platelet-Independent Clot Shrinkage(血栓内での赤血球の凝集が血小板に依存しない血栓収縮を引き起こす)」と題されています。
「赤血球は17世紀から研究されてきました」と、もう一人の共著者であり、ペンシルベニア大学工学部 機械工学・応用力学の教授であるプラシャント・プロヒ
個別化モデルが拓く未来:腸内細菌「C. diff」の感染リスクを予測し、あなたに合ったプロバイオティクスで予防
 あなたの腸にも潜む日和見菌!個別化モデルで「C. diff」感染リスクを予測し、標的プロバイオティクスで制御する新アプローチ
私たちの腸内には、気づかないうちに危険な細菌が潜んでいることがあります。その一つが、米国だけで年間50万人以上が感染し、最大3万人の命を奪うステルスのような脅威、クロストリディオイデス・ディフィシル(Clostridioides difficile)、通称「C. diff」です。
C. diffは、病院や長期介護施設などを中心とした医療関連感染症の主な原因菌として知られています。しかし、この菌を保有していても誰もが発症するわけではありません。驚くことに、私たちの30~40%は、今この瞬間も腸内にこの菌を保有しているとされています。C. diffは科学者が「日和見病原菌」と呼ぶ存在で、命を脅かす病気を引き起こす能力を持ちながら、普段は腸内で静かに共生し、抗生物質の使用後など、特定の条件下で活動を開始し、深刻な事態を引き起こします。もし、この感染が本格化する前にリスクを特定できたらどうでしょうか?
2025年8月6日に『Cell Systems』誌で発表された新しい研究で、システム生物学研究所(ISB: Institute for Systems Biology)の研究者たちは、個人の腸内にC. diffが定着しやすいかどうかを予測し、特定のプロバイオティクス治療がその定着を防いだり、あるいは改善したりできるかを検証するための、強力な個別化モデリングの枠組みを開発しました。この論文は、「Personalized Clostridioides difficile Colonization Risk Prediction and Probiotic Therapy Assessment in the Human Gut(ヒト腸内におけるクロストリデ
あなたの腸にも潜む日和見菌!個別化モデルで「C. diff」感染リスクを予測し、標的プロバイオティクスで制御する新アプローチ
私たちの腸内には、気づかないうちに危険な細菌が潜んでいることがあります。その一つが、米国だけで年間50万人以上が感染し、最大3万人の命を奪うステルスのような脅威、クロストリディオイデス・ディフィシル(Clostridioides difficile)、通称「C. diff」です。
C. diffは、病院や長期介護施設などを中心とした医療関連感染症の主な原因菌として知られています。しかし、この菌を保有していても誰もが発症するわけではありません。驚くことに、私たちの30~40%は、今この瞬間も腸内にこの菌を保有しているとされています。C. diffは科学者が「日和見病原菌」と呼ぶ存在で、命を脅かす病気を引き起こす能力を持ちながら、普段は腸内で静かに共生し、抗生物質の使用後など、特定の条件下で活動を開始し、深刻な事態を引き起こします。もし、この感染が本格化する前にリスクを特定できたらどうでしょうか?
2025年8月6日に『Cell Systems』誌で発表された新しい研究で、システム生物学研究所(ISB: Institute for Systems Biology)の研究者たちは、個人の腸内にC. diffが定着しやすいかどうかを予測し、特定のプロバイオティクス治療がその定着を防いだり、あるいは改善したりできるかを検証するための、強力な個別化モデリングの枠組みを開発しました。この論文は、「Personalized Clostridioides difficile Colonization Risk Prediction and Probiotic Therapy Assessment in the Human Gut(ヒト腸内におけるクロストリデ
老化の犯人は遺伝子の傷だった!「体細胞変異」が筋力低下や血管老化を引き起こすことを解明
 年齢を重ねるとともに、筋力が衰えたり、血管が硬くなったりするのはなぜでしょうか。これまで、その原因は漠然とした「老化」という言葉で片付けられがちでした。しかし、スウェーデンの最新研究が、私たちの体内で生涯を通じて発生し蓄積していく遺伝子の変異(体細胞変異)が、筋力低下や血管の老化を直接引き起こす犯人であることを突き止めました。この発見は、老化関連疾患の治療に新たな道を開くかもしれません。
スウェーデンのカロリンスカ研究所による2つの新しい研究が、時間とともに筋肉や血管で生じる変異が老化にどのように影響するかを調査しました。科学雑誌『Nature Aging』に掲載されたこれらの研究は、そのような変異が筋力を低下させ、血管の老化を加速させる可能性があることを示しています。この結果は、加齢関連疾患の治療にとって重要な意味を持つ可能性があります。
体細胞変異とは、遺伝しない遺伝子の変化であり、生涯を通じて環境要因や、細胞が分裂前にDNAを複製する際のランダムなエラーによって生じます。この変異はがんを引き起こす可能性がありますが、それ以外の影響については議論が分かれていました。「私たちは、筋肉細胞や血管に蓄積する変異が、組織の機能や再生能力、つまり損傷した組織を新しい健康な細胞で置き換える能力に影響を与える可能性があることを発見しました。この能力もまた、加齢とともに低下するものです」と、主任研究者であり、カロリンスカ研究所フディンゲ校医学部のマリア・エリクソン教授(Maria Eriksson)は述べています。
早老症プロジェリアと同じ変異
2003年、エリクソン教授は、急速な老化と心血管系の合併症を特徴とする、極めて稀な小児の遺伝性疾患であるプロジェリアの遺伝的原因を発見しました。この病気の子供は、プロジェリンと呼ばれる病原性タンパク質の形成につながる変異を持っ
年齢を重ねるとともに、筋力が衰えたり、血管が硬くなったりするのはなぜでしょうか。これまで、その原因は漠然とした「老化」という言葉で片付けられがちでした。しかし、スウェーデンの最新研究が、私たちの体内で生涯を通じて発生し蓄積していく遺伝子の変異(体細胞変異)が、筋力低下や血管の老化を直接引き起こす犯人であることを突き止めました。この発見は、老化関連疾患の治療に新たな道を開くかもしれません。
スウェーデンのカロリンスカ研究所による2つの新しい研究が、時間とともに筋肉や血管で生じる変異が老化にどのように影響するかを調査しました。科学雑誌『Nature Aging』に掲載されたこれらの研究は、そのような変異が筋力を低下させ、血管の老化を加速させる可能性があることを示しています。この結果は、加齢関連疾患の治療にとって重要な意味を持つ可能性があります。
体細胞変異とは、遺伝しない遺伝子の変化であり、生涯を通じて環境要因や、細胞が分裂前にDNAを複製する際のランダムなエラーによって生じます。この変異はがんを引き起こす可能性がありますが、それ以外の影響については議論が分かれていました。「私たちは、筋肉細胞や血管に蓄積する変異が、組織の機能や再生能力、つまり損傷した組織を新しい健康な細胞で置き換える能力に影響を与える可能性があることを発見しました。この能力もまた、加齢とともに低下するものです」と、主任研究者であり、カロリンスカ研究所フディンゲ校医学部のマリア・エリクソン教授(Maria Eriksson)は述べています。
早老症プロジェリアと同じ変異
2003年、エリクソン教授は、急速な老化と心血管系の合併症を特徴とする、極めて稀な小児の遺伝性疾患であるプロジェリアの遺伝的原因を発見しました。この病気の子供は、プロジェリンと呼ばれる病原性タンパク質の形成につながる変異を持っ
遺伝子を操る「影の司令塔」lncRNAの新たな制御メカニズムを発見
 私たちの体の設計図である遺伝子。その働きを調整する「影の司令塔」がいることをご存知でしょうか?それは、タンパク質にはならない不思議なRNA、「長鎖ノンコーディングRNA」です。これまで謎に包まれてきたこの分子が、実は遺伝子のオン・オフを巧みに操るだけでなく、まるで二人三脚のようにターゲットとなる遺伝子を徹底的に管理する、驚くべき仕組みが明らかになりました。がんなどの病気の解明にもつながる、遺伝子制御の新たな世界を覗いてみましょう。
長鎖ノンコーディングRNA(lncRNA: long non-coding RNA)は、タンパク質を作るための情報を持たないRNA分子の一種です。その代わりに、他の遺伝子がどのように発現するか(働くか)に影響を与えます。ヒトの体内には何万ものlncRNAが存在し、その多くは特定のがんのような組織や疾患で活発に機能しています。しかし、それらが具体的に何をしているのかを解明することは、これまで大きな課題でした。ベイラー医科大学の筆頭著者であるホア・シェン・チウ博士(Hua-Sheng Chiu, PhD)とソナル・ソムバンシ博士(Sonal Somvanshi, PhD)が率いる、ベイラー医科大学、ベルギーのゲント大学、中国の清華大学、およびその他の共同研究機関の研究者たちは、lncRNAがどのように機能するのかをより深く理解するために協力しました。その結果、lncRNAがこれまで知られていなかった協調的な方法で遺伝子発現を制御しているように見えることが明らかになりました。この研究は、今月(8月号)の「Cell Genomics」誌の表紙を飾り、オープンアクセス論文は「Coordinated Regulation by lncRNAs Results in Tight lncRNA-Target Couplings(lncRNAによる協調的制御
私たちの体の設計図である遺伝子。その働きを調整する「影の司令塔」がいることをご存知でしょうか?それは、タンパク質にはならない不思議なRNA、「長鎖ノンコーディングRNA」です。これまで謎に包まれてきたこの分子が、実は遺伝子のオン・オフを巧みに操るだけでなく、まるで二人三脚のようにターゲットとなる遺伝子を徹底的に管理する、驚くべき仕組みが明らかになりました。がんなどの病気の解明にもつながる、遺伝子制御の新たな世界を覗いてみましょう。
長鎖ノンコーディングRNA(lncRNA: long non-coding RNA)は、タンパク質を作るための情報を持たないRNA分子の一種です。その代わりに、他の遺伝子がどのように発現するか(働くか)に影響を与えます。ヒトの体内には何万ものlncRNAが存在し、その多くは特定のがんのような組織や疾患で活発に機能しています。しかし、それらが具体的に何をしているのかを解明することは、これまで大きな課題でした。ベイラー医科大学の筆頭著者であるホア・シェン・チウ博士(Hua-Sheng Chiu, PhD)とソナル・ソムバンシ博士(Sonal Somvanshi, PhD)が率いる、ベイラー医科大学、ベルギーのゲント大学、中国の清華大学、およびその他の共同研究機関の研究者たちは、lncRNAがどのように機能するのかをより深く理解するために協力しました。その結果、lncRNAがこれまで知られていなかった協調的な方法で遺伝子発現を制御しているように見えることが明らかになりました。この研究は、今月(8月号)の「Cell Genomics」誌の表紙を飾り、オープンアクセス論文は「Coordinated Regulation by lncRNAs Results in Tight lncRNA-Target Couplings(lncRNAによる協調的制御
ヘビ毒が効かないトカゲの秘密!進化がもたらした驚異の「毒耐性」メカニズムとは?
 捕食者と被食者の間で繰り広げられる、終わりのない進化の軍拡競争。強力な「矛」である毒を持つヘビに対し、あるトカゲは驚くべき「盾」をその身に宿していました。オーストラリアに生息するスキンクが、ヘビの猛毒を無力化するために進化させた驚異のメカニズムが、このたび明らかになりました。これは、未来のヘビ咬傷治療に新たな光を当てるかもしれません。
クイーンズランド大学が主導した研究により、オーストラリアのスキンク(トカゲの一種)が、ヘビの毒によって筋肉が機能停止するのを防ぐため、筋肉の受容体に突然変異を進化させてきたことが明らかになりました。同大学環境学部のブライアン・フライ教授(Bryan Fry)は、スキンクがどのようにして死を回避しているのかを正確に明らかにすることが、人間のヘビ咬傷を治療するための生物医学的アプローチに情報を提供する可能性があると述べています。
「私たちがスキンクで目にしたのは、最も巧妙な形での進化でした」とフライ教授は語ります。
「オーストラリアのスキンクは、ニコチン性アセチルコリン受容体と呼ばれる重要な筋肉の受容体に、微細な変化を進化させてきました。」
「この受容体は通常、神経毒の標的となります。神経毒がこの受容体に結合すると、神経と筋肉の間のコミュニケーションが遮断され、急速な麻痺と死を引き起こします。」
「しかし、自然界の見事なカウンターパンチとも言える例として、スキンクがこの結合部位に変異を起こし、毒の付着をブロックする進化を、独立して25回も遂げていたことを発見しました。」
「これは、毒ヘビがオーストラリア大陸に到達し、広まった後に、当時の無防備なトカゲたちを捕食することで、いかに巨大な進化的圧力をかけたかの証です。」
「信じられないことに、同じ突然変異はコブラを食べるマングースのような他の動物でも進化していました。」
「私たちの
捕食者と被食者の間で繰り広げられる、終わりのない進化の軍拡競争。強力な「矛」である毒を持つヘビに対し、あるトカゲは驚くべき「盾」をその身に宿していました。オーストラリアに生息するスキンクが、ヘビの猛毒を無力化するために進化させた驚異のメカニズムが、このたび明らかになりました。これは、未来のヘビ咬傷治療に新たな光を当てるかもしれません。
クイーンズランド大学が主導した研究により、オーストラリアのスキンク(トカゲの一種)が、ヘビの毒によって筋肉が機能停止するのを防ぐため、筋肉の受容体に突然変異を進化させてきたことが明らかになりました。同大学環境学部のブライアン・フライ教授(Bryan Fry)は、スキンクがどのようにして死を回避しているのかを正確に明らかにすることが、人間のヘビ咬傷を治療するための生物医学的アプローチに情報を提供する可能性があると述べています。
「私たちがスキンクで目にしたのは、最も巧妙な形での進化でした」とフライ教授は語ります。
「オーストラリアのスキンクは、ニコチン性アセチルコリン受容体と呼ばれる重要な筋肉の受容体に、微細な変化を進化させてきました。」
「この受容体は通常、神経毒の標的となります。神経毒がこの受容体に結合すると、神経と筋肉の間のコミュニケーションが遮断され、急速な麻痺と死を引き起こします。」
「しかし、自然界の見事なカウンターパンチとも言える例として、スキンクがこの結合部位に変異を起こし、毒の付着をブロックする進化を、独立して25回も遂げていたことを発見しました。」
「これは、毒ヘビがオーストラリア大陸に到達し、広まった後に、当時の無防備なトカゲたちを捕食することで、いかに巨大な進化的圧力をかけたかの証です。」
「信じられないことに、同じ突然変異はコブラを食べるマングースのような他の動物でも進化していました。」
「私たちの
ゲノム編集の新時代へ。大規模な遺伝子改変を「傷跡なく」実現するPCE技術とは?
 まるで文書を編集するように、生物の設計図であるゲノムを自在に書き換える「ゲノム編集技術」。この技術が、これまで不可能だった大規模かつ精密な操作を可能にする、新たなステージへと進化を遂げました。中国科学院、遺伝学・発生生物学研究所のカイシャ・ガオ教授(Caixia Gao)が率いる研究チームは、「プログラム可能な染色体工学(PCE: Programmable Chromosome Engineering)」システムとして知られる2つの新しいゲノム編集技術を開発しました。
2025年8月4日に科学誌Cellにオンライン掲載されたこの研究は、特に植物などの高等生物において、キロベースからメガベース規模に及ぶ、複数タイプの精密なDNA操作を達成するものです。論文のタイトルは「Iterative Recombinase Technologies for Efficient and Precise Genome Engineering Across Kilobase to Megabase Scales(キロベースからメガベーススケールにわたる効率的かつ精密なゲノム工学のための反復的リコンビナーゼ技術)」です。
これまで、部位特異的リコンビナーゼであるCre-Loxシステムは、精密な染色体操作において絶大な可能性を秘めていることが多くの研究で示されてきました。しかし、その幅広い応用は、3つの重大な限界によって妨げられていました。(1) Loxサイトの対称的な性質に起因する可逆的な組換え反応が、目的の編集を元に戻してしまうこと、(2) Creリコンビナーゼが四量体を形成する性質がタンパク質改変を複雑にし、活性の最適化を困難にしていること、(3) 組換え後にLoxサイトが残存し、編集の精密さを損なう可能性があることです。
研究チームはこれらの課題の一つ一つに取り組み、この技術をさ
まるで文書を編集するように、生物の設計図であるゲノムを自在に書き換える「ゲノム編集技術」。この技術が、これまで不可能だった大規模かつ精密な操作を可能にする、新たなステージへと進化を遂げました。中国科学院、遺伝学・発生生物学研究所のカイシャ・ガオ教授(Caixia Gao)が率いる研究チームは、「プログラム可能な染色体工学(PCE: Programmable Chromosome Engineering)」システムとして知られる2つの新しいゲノム編集技術を開発しました。
2025年8月4日に科学誌Cellにオンライン掲載されたこの研究は、特に植物などの高等生物において、キロベースからメガベース規模に及ぶ、複数タイプの精密なDNA操作を達成するものです。論文のタイトルは「Iterative Recombinase Technologies for Efficient and Precise Genome Engineering Across Kilobase to Megabase Scales(キロベースからメガベーススケールにわたる効率的かつ精密なゲノム工学のための反復的リコンビナーゼ技術)」です。
これまで、部位特異的リコンビナーゼであるCre-Loxシステムは、精密な染色体操作において絶大な可能性を秘めていることが多くの研究で示されてきました。しかし、その幅広い応用は、3つの重大な限界によって妨げられていました。(1) Loxサイトの対称的な性質に起因する可逆的な組換え反応が、目的の編集を元に戻してしまうこと、(2) Creリコンビナーゼが四量体を形成する性質がタンパク質改変を複雑にし、活性の最適化を困難にしていること、(3) 組換え後にLoxサイトが残存し、編集の精密さを損なう可能性があることです。
研究チームはこれらの課題の一つ一つに取り組み、この技術をさ
パーキンソン病の進行を止める鍵?失われた脳細胞の「アンテナ」を回復させる新アプローチ
 私たちの脳細胞には、周囲の情報をキャッチするための小さな「アンテナ」が無数に存在することをご存知でしょうか。このアンテナが正常に機能することで、細胞同士はスムーズに情報をやり取りし、私たちの体をコントロールしています。しかし、もしこのアンテナが壊れてしまったら…? 実は、ある特定の遺伝子変異によって引き起こされるパーキンソン病では、まさにそのような事態が神経細胞に起きているのです。今回、スタンフォード大学医学部が主導したマウスによる最新の研究で、この壊れたアンテナを修復し、パーキンソン病の進行を食い止める可能性を秘めた治療法が示されました。
この研究によると、ある単一の遺伝子変異が原因で発症するタイプのパーキンソン病では、神経細胞の死滅を食い止められるかもしれません。この遺伝子変異は、LRRK2(leucine-rich repeat kinase 2: ロイシンリッチリピートキナーゼ2)と呼ばれる酵素を過剰に活性化させます。LRRK2酵素の活性が高すぎると、脳細胞の構造が変化し、神経伝達物質であるドーパミンを作り出すニューロンと、脳の深部にあり運動や意欲、意思決定に関わるドーパミンシステムの一部である線条体の細胞との間の重要なコミュニケーションが妨げられてしまうのです。
「この研究結果は、LRRK2酵素を阻害することで、もし患者様を十分に早期に発見できれば、症状の進行を安定させられる可能性を示唆しています」と、スタンフォード大学医学部のエマ・ファイファー・マーナー教授であり、生化学の教授でもあるスザンヌ・ペフェール(Suzanne Pfeffer)博士は述べています。研究者たちは、MLi-2 LRRK2キナーゼ阻害剤という分子を用いて、過剰に活性化したLRRK2を抑制することができます。この分子は酵素に結合し、その活性を低下させる働きをします。
ペフェール博士は
私たちの脳細胞には、周囲の情報をキャッチするための小さな「アンテナ」が無数に存在することをご存知でしょうか。このアンテナが正常に機能することで、細胞同士はスムーズに情報をやり取りし、私たちの体をコントロールしています。しかし、もしこのアンテナが壊れてしまったら…? 実は、ある特定の遺伝子変異によって引き起こされるパーキンソン病では、まさにそのような事態が神経細胞に起きているのです。今回、スタンフォード大学医学部が主導したマウスによる最新の研究で、この壊れたアンテナを修復し、パーキンソン病の進行を食い止める可能性を秘めた治療法が示されました。
この研究によると、ある単一の遺伝子変異が原因で発症するタイプのパーキンソン病では、神経細胞の死滅を食い止められるかもしれません。この遺伝子変異は、LRRK2(leucine-rich repeat kinase 2: ロイシンリッチリピートキナーゼ2)と呼ばれる酵素を過剰に活性化させます。LRRK2酵素の活性が高すぎると、脳細胞の構造が変化し、神経伝達物質であるドーパミンを作り出すニューロンと、脳の深部にあり運動や意欲、意思決定に関わるドーパミンシステムの一部である線条体の細胞との間の重要なコミュニケーションが妨げられてしまうのです。
「この研究結果は、LRRK2酵素を阻害することで、もし患者様を十分に早期に発見できれば、症状の進行を安定させられる可能性を示唆しています」と、スタンフォード大学医学部のエマ・ファイファー・マーナー教授であり、生化学の教授でもあるスザンヌ・ペフェール(Suzanne Pfeffer)博士は述べています。研究者たちは、MLi-2 LRRK2キナーゼ阻害剤という分子を用いて、過剰に活性化したLRRK2を抑制することができます。この分子は酵素に結合し、その活性を低下させる働きをします。
ペフェール博士は
腸内のカンジダ菌、定着の鍵は「毒素」だった?日和見感染予防の新たな標的
 私たちの腸内には、実に8割もの人が「カンジダ菌」というカビの一種を飼っていることをご存知でしたか?普段は大人しくしているこの"同居人"は、何かのきっかけで豹変し、全身で深刻な感染症を引き起こす危険な存在になることがあります。
では、この「寝た子」をどうすれば起こさずに済むのでしょうか?
ベイラー医科大学の研究チームが、カンジダ菌が私たちの腸に住み着くために使う、意外な「武器」を発見しました。驚くべきことに、病気を引き起こすはずの毒素こそが、腸内に定着するために不可欠だったのです。この常識を覆す発見の全貌に迫ります。
約80%の人々の腸内には、真菌であるカンジダ・アルビカンス(Candida albicans)が存在しています。ほとんどの場合、この菌は何年もの間気づかれることなく潜伏し、健康上の問題を引き起こしません。しかし、カンジダ・アルビカンスは、尿路、肺、脳を含む多くの臓器で深刻な疾患を引き起こす危険な微生物に豹変することがあります。この真菌がどのようにして腸内に定着するのかを理解することは、それが有害になるのを防ぐための鍵となります。
ベイラー医科大学の研究者と海外の共同研究者たちは、マウスモデルを用いた研究で、カンジダ・アルビカンスが腸内に定着し、持続するのを助ける予想外の要因を発見しました。この発見は、真菌と腸の相互作用に関する私たちの知識を広げ、定着を減らすための潜在的な解決策を提供するものです。この研究は、2025年7月30日付の『Microbiology Spectrum』誌に掲載されました。このオープンアクセスの論文は、「Commensal Colonization of Candida albicans in the Mouse Gastrointestinal Tract Is Mediated Via Expression of Cand
私たちの腸内には、実に8割もの人が「カンジダ菌」というカビの一種を飼っていることをご存知でしたか?普段は大人しくしているこの"同居人"は、何かのきっかけで豹変し、全身で深刻な感染症を引き起こす危険な存在になることがあります。
では、この「寝た子」をどうすれば起こさずに済むのでしょうか?
ベイラー医科大学の研究チームが、カンジダ菌が私たちの腸に住み着くために使う、意外な「武器」を発見しました。驚くべきことに、病気を引き起こすはずの毒素こそが、腸内に定着するために不可欠だったのです。この常識を覆す発見の全貌に迫ります。
約80%の人々の腸内には、真菌であるカンジダ・アルビカンス(Candida albicans)が存在しています。ほとんどの場合、この菌は何年もの間気づかれることなく潜伏し、健康上の問題を引き起こしません。しかし、カンジダ・アルビカンスは、尿路、肺、脳を含む多くの臓器で深刻な疾患を引き起こす危険な微生物に豹変することがあります。この真菌がどのようにして腸内に定着するのかを理解することは、それが有害になるのを防ぐための鍵となります。
ベイラー医科大学の研究者と海外の共同研究者たちは、マウスモデルを用いた研究で、カンジダ・アルビカンスが腸内に定着し、持続するのを助ける予想外の要因を発見しました。この発見は、真菌と腸の相互作用に関する私たちの知識を広げ、定着を減らすための潜在的な解決策を提供するものです。この研究は、2025年7月30日付の『Microbiology Spectrum』誌に掲載されました。このオープンアクセスの論文は、「Commensal Colonization of Candida albicans in the Mouse Gastrointestinal Tract Is Mediated Via Expression of Cand
「ただの機械」ではなかったリボソーム。その多様性が生命の鍵を握る
 私たちの体を作る設計図はDNAですが、その情報を元に、生命活動を実際に担うタンパク質を組み立てる「工場」があることをご存知でしょうか? それが、細胞内に無数に存在する「リボソーム」です。かつては、ただ黙々と指示通りに働き続ける単純な作業機械だと考えられていました。しかし、もしこの小さな工場が、それぞれに個性と専門性を持ち、がんや神経難病といった病の発症に深く関わっているとしたら…?
スタンフォード大学医学部の研究チームが開発した画期的なツールが、この小さな工場の驚くべき秘密を暴き、新たな治療法への扉を開こうとしています。
新しいツールが、細胞のタンパク質工場であるリボソームが、がんや神経変性疾患などの治療法を切り開く可能性のある方法で、いかにして専門化しているかを明らかにしています。スタンフォード大学医学部のマリア・バルナ博士(Maria Barna, PhD)と彼女のチームが、その深淵に迫っています。
私たちが生命の設計図について考えるとき、私たちは体のあらゆる細胞に保存されている遺伝コード、すなわちDNAに注目しがちです。しかし、DNAは物語の一部に過ぎません。その指示が意味を持つためには、それらが読み取られ、生命活動を実際に担う分子であるタンパク質に変換されなければなりません。そこで登場するのがリボソームです。私たちの体にある平均的な細胞には数百万個のリボソームが含まれており、それらは生命にとって絶対不可欠な存在です。リボソームは、遺伝コードを読み取って、代謝を動かす酵素から感染と戦うのを助ける抗体まで、あらゆるタンパク質を生産する分子機械なのです。
スタンフォード大学医学部の遺伝学准教授であるマリア・バルナ博士(Maria Barna, PhD)は、リボソームがどのように機能し、どのように専門化して異なるタンパク質を生産するのか、そしていつどこで
私たちの体を作る設計図はDNAですが、その情報を元に、生命活動を実際に担うタンパク質を組み立てる「工場」があることをご存知でしょうか? それが、細胞内に無数に存在する「リボソーム」です。かつては、ただ黙々と指示通りに働き続ける単純な作業機械だと考えられていました。しかし、もしこの小さな工場が、それぞれに個性と専門性を持ち、がんや神経難病といった病の発症に深く関わっているとしたら…?
スタンフォード大学医学部の研究チームが開発した画期的なツールが、この小さな工場の驚くべき秘密を暴き、新たな治療法への扉を開こうとしています。
新しいツールが、細胞のタンパク質工場であるリボソームが、がんや神経変性疾患などの治療法を切り開く可能性のある方法で、いかにして専門化しているかを明らかにしています。スタンフォード大学医学部のマリア・バルナ博士(Maria Barna, PhD)と彼女のチームが、その深淵に迫っています。
私たちが生命の設計図について考えるとき、私たちは体のあらゆる細胞に保存されている遺伝コード、すなわちDNAに注目しがちです。しかし、DNAは物語の一部に過ぎません。その指示が意味を持つためには、それらが読み取られ、生命活動を実際に担う分子であるタンパク質に変換されなければなりません。そこで登場するのがリボソームです。私たちの体にある平均的な細胞には数百万個のリボソームが含まれており、それらは生命にとって絶対不可欠な存在です。リボソームは、遺伝コードを読み取って、代謝を動かす酵素から感染と戦うのを助ける抗体まで、あらゆるタンパク質を生産する分子機械なのです。
スタンフォード大学医学部の遺伝学准教授であるマリア・バルナ博士(Maria Barna, PhD)は、リボソームがどのように機能し、どのように専門化して異なるタンパク質を生産するのか、そしていつどこで
ウミグモのゲノムが解き明かす、クモやサソリなど8本脚の生物の進化の謎
 脚が8本ある生き物といえば、何を思い浮かべますか?クモやサソリ、あるいはカブトガニかもしれません。多種多様な彼らの進化の歴史には、まだ多くの謎が残されています。そのミステリーを解き明かす鍵が、深海に住む「ウミグモ」という、世にも奇妙な生物にあるかもしれません。一見すると、脚だらけで体が見当たらない不思議な姿。しかし、最新の研究によって、このウミグモがクモやサソリたちの進化の道のりを解き明かす「羅針盤」のような役割を果たすことがわかってきました。その驚くべき生態と、ゲノムに隠された秘密に迫ります。
ウミグモを見て、それが8本脚を持つほぼ全ての生物の進化を解明するのに役立つほど、その仲間を代表する動物だと見抜くのは簡単ではありません。しかし、ある新しい研究が、この細長く、際立って奇妙な海底生物にその可能性を見出しました。脚の数を数え終わると、現在知られている約1,300種のウミグモと、正真正銘のクモやサソリ、ダニ、カブトガニといった近縁種との間に、似ている点はほとんど見つからなくなります。
ウミグモは皮膚を通して呼吸し、一種の蠕動運動(食べ物を喉に送り込むのと似た筋肉の収縮)を使って体中に酸素を運びます。繁殖の時期になると、オスは受精卵を自分の体に塗り固め、孵化するまで運び続けます。そもそも体と呼べる部分はほとんどなく、ウミグモはまるで配管の設計図のようです。腹部がないため、彼らはほとんど管だけでできています。その腹部は、サソリの毒針を備え、満腹のダニが血液を蓄え、タランチュラに毛むくじゃらの大きな塊を与えている、あの体の後ろの部分です。
「彼らは奇妙です」と語るのは、そういった種類の生物を専門とする研究者、プラシャント・シャルマ博士(Prashant Sharma, PhD)です。彼のウィスコンシン大学マディソン校の研究室には、東地中海の限られた洞窟にしか生息しない
脚が8本ある生き物といえば、何を思い浮かべますか?クモやサソリ、あるいはカブトガニかもしれません。多種多様な彼らの進化の歴史には、まだ多くの謎が残されています。そのミステリーを解き明かす鍵が、深海に住む「ウミグモ」という、世にも奇妙な生物にあるかもしれません。一見すると、脚だらけで体が見当たらない不思議な姿。しかし、最新の研究によって、このウミグモがクモやサソリたちの進化の道のりを解き明かす「羅針盤」のような役割を果たすことがわかってきました。その驚くべき生態と、ゲノムに隠された秘密に迫ります。
ウミグモを見て、それが8本脚を持つほぼ全ての生物の進化を解明するのに役立つほど、その仲間を代表する動物だと見抜くのは簡単ではありません。しかし、ある新しい研究が、この細長く、際立って奇妙な海底生物にその可能性を見出しました。脚の数を数え終わると、現在知られている約1,300種のウミグモと、正真正銘のクモやサソリ、ダニ、カブトガニといった近縁種との間に、似ている点はほとんど見つからなくなります。
ウミグモは皮膚を通して呼吸し、一種の蠕動運動(食べ物を喉に送り込むのと似た筋肉の収縮)を使って体中に酸素を運びます。繁殖の時期になると、オスは受精卵を自分の体に塗り固め、孵化するまで運び続けます。そもそも体と呼べる部分はほとんどなく、ウミグモはまるで配管の設計図のようです。腹部がないため、彼らはほとんど管だけでできています。その腹部は、サソリの毒針を備え、満腹のダニが血液を蓄え、タランチュラに毛むくじゃらの大きな塊を与えている、あの体の後ろの部分です。
「彼らは奇妙です」と語るのは、そういった種類の生物を専門とする研究者、プラシャント・シャルマ博士(Prashant Sharma, PhD)です。彼のウィスコンシン大学マディソン校の研究室には、東地中海の限られた洞窟にしか生息しない
AIで植物の免疫をアップグレード!病気に強い作物を作る新技術
 畑の野菜も、実は私たちと同じように病原菌と戦うための「免疫システム」を持っています。しかし、賢い病原菌は姿を変えてその監視網をすり抜けてしまいます。もし、最新のAI技術で植物の免疫を「アップグレード」し、見えない敵を見破る力を与えられたら?カリフォルニア大学の研究者たちが、そんなSFのようなアイデアを現実のものとし、未来の食料安全保障への道を切り拓こうとしています。
カリフォルニア大学(UC)デービス校の科学者たちは、人工知能(AI)を用いて、植物がより広範囲の細菌の脅威を認識できるようにしました。この成果は、トマトやジャガイモなどの作物を壊滅的な病気から守るための新しい方法につながる可能性があります。この研究は2025年7月28日に学術誌「Nature Plants」に掲載されました。論文のタイトルは「Unlocking Expanded Flagellin Perception Through Rational Receptor Engineering(合理的な受容体工学によるフラジェリン認識能力の拡大)」です。
植物は動物と同様に免疫システムを持っています。その防御ツールの一部には、細菌を検知し防御する能力を与える免疫受容体が含まれます。その受容体の一つであるFLS2は、細菌が泳ぐために使用する小さな尾にあるタンパク質「フラジェリン」を植物が認識するのを助けます。しかし、細菌は狡猾で、検知を避けるために常に進化しています。「細菌は宿主である植物との間で軍拡競争を繰り広げており、フラジェリンの基となるアミノ酸を変化させて検知を回避することができます」と、責任著者であり植物病理学科の教授であるギッタ・コーカー博士(Gitta Coaker, PhD)は説明します。
植物がこの競争に遅れを取らないようにするため、コーカー博士のチームは自然界に存在する多様な受容体の
畑の野菜も、実は私たちと同じように病原菌と戦うための「免疫システム」を持っています。しかし、賢い病原菌は姿を変えてその監視網をすり抜けてしまいます。もし、最新のAI技術で植物の免疫を「アップグレード」し、見えない敵を見破る力を与えられたら?カリフォルニア大学の研究者たちが、そんなSFのようなアイデアを現実のものとし、未来の食料安全保障への道を切り拓こうとしています。
カリフォルニア大学(UC)デービス校の科学者たちは、人工知能(AI)を用いて、植物がより広範囲の細菌の脅威を認識できるようにしました。この成果は、トマトやジャガイモなどの作物を壊滅的な病気から守るための新しい方法につながる可能性があります。この研究は2025年7月28日に学術誌「Nature Plants」に掲載されました。論文のタイトルは「Unlocking Expanded Flagellin Perception Through Rational Receptor Engineering(合理的な受容体工学によるフラジェリン認識能力の拡大)」です。
植物は動物と同様に免疫システムを持っています。その防御ツールの一部には、細菌を検知し防御する能力を与える免疫受容体が含まれます。その受容体の一つであるFLS2は、細菌が泳ぐために使用する小さな尾にあるタンパク質「フラジェリン」を植物が認識するのを助けます。しかし、細菌は狡猾で、検知を避けるために常に進化しています。「細菌は宿主である植物との間で軍拡競争を繰り広げており、フラジェリンの基となるアミノ酸を変化させて検知を回避することができます」と、責任著者であり植物病理学科の教授であるギッタ・コーカー博士(Gitta Coaker, PhD)は説明します。
植物がこの競争に遅れを取らないようにするため、コーカー博士のチームは自然界に存在する多様な受容体の
幹細胞が拓く新時代:薬に頼らない腎移植、患者たちの希望の物語
 臓器移植後の人生を、ずっと薬と共に歩まなければならないとしたら…?もし、その負担から解放される未来があるとしたら、あなたはどう思いますか?
ウィスコンシン大学マディソン校で進められている最先端の臨床試験が、そんな夢のような話を現実に変えようとしています。この記事では、拒絶反応を抑えるための薬を毎日飲む必要なく、移植された腎臓と共に健康で充実した日々を取り戻した人々の、驚くべきストーリーをご紹介します。彼らの体験の裏には、長年の研究に支えられた画期的な治療法がありました。一体どのような技術が、移植医療の未来を塗り替えようとしているのでしょうか。
ウィスコンシン大学マディソン校の画期的な臨床試験のおかげで、移植患者たちは拒絶反応抑制剤なしで健康な生活を取り戻しつつあります。
ショーン・ウィーダーヘフト氏(Shawn Wiederhoeft)は、30代のどこにでもいるごく普通の男性です。マディソン出身の彼は、ビデオゲーム開発者として働き、アクティブなライフスタイルを送っています。健康状態は人生で最高のコンディションにあり、ウィスコンシン州南部で友人や家族と定期的に過ごしています。しかし、ウィーダーヘフトがこれほどまでに充実した人生を送れることは、かつては決して当たり前のことではありませんでした。実際、「ショーンおじさん」として家族に親しまれている彼が今日健康でいられるのは、2020年にウォーワトサに住む姉のミーガン・ハーン氏(Meagan Hahn)から提供された新しい腎臓のおかげなのです。移植された腎臓はウィーダーヘフトに新たな人生のチャンスを与えました。そして、彼と姉がウィスコンシン大学医学公衆衛生大学院の最先端の臨床試験への参加を決めたことで、彼は拒絶反応抑制剤を必要としない生活をも手に入れることができたのです。
毎日の服薬もなく、時折の健康診断を受けるだけ
臓器移植後の人生を、ずっと薬と共に歩まなければならないとしたら…?もし、その負担から解放される未来があるとしたら、あなたはどう思いますか?
ウィスコンシン大学マディソン校で進められている最先端の臨床試験が、そんな夢のような話を現実に変えようとしています。この記事では、拒絶反応を抑えるための薬を毎日飲む必要なく、移植された腎臓と共に健康で充実した日々を取り戻した人々の、驚くべきストーリーをご紹介します。彼らの体験の裏には、長年の研究に支えられた画期的な治療法がありました。一体どのような技術が、移植医療の未来を塗り替えようとしているのでしょうか。
ウィスコンシン大学マディソン校の画期的な臨床試験のおかげで、移植患者たちは拒絶反応抑制剤なしで健康な生活を取り戻しつつあります。
ショーン・ウィーダーヘフト氏(Shawn Wiederhoeft)は、30代のどこにでもいるごく普通の男性です。マディソン出身の彼は、ビデオゲーム開発者として働き、アクティブなライフスタイルを送っています。健康状態は人生で最高のコンディションにあり、ウィスコンシン州南部で友人や家族と定期的に過ごしています。しかし、ウィーダーヘフトがこれほどまでに充実した人生を送れることは、かつては決して当たり前のことではありませんでした。実際、「ショーンおじさん」として家族に親しまれている彼が今日健康でいられるのは、2020年にウォーワトサに住む姉のミーガン・ハーン氏(Meagan Hahn)から提供された新しい腎臓のおかげなのです。移植された腎臓はウィーダーヘフトに新たな人生のチャンスを与えました。そして、彼と姉がウィスコンシン大学医学公衆衛生大学院の最先端の臨床試験への参加を決めたことで、彼は拒絶反応抑制剤を必要としない生活をも手に入れることができたのです。
毎日の服薬もなく、時折の健康診断を受けるだけ
細胞膜は無法者じゃなかった!ナノスケールの視点が解き明かす生命の統一法則
 私たちの体を構成する数十兆個の細胞。その一つ一つを優しく包み込み、生命の門番として機能するのが「細胞膜」です。しかしこの膜、実は科学者たちを長年悩ませてきた「気まぐれな無法者」だったのです。物理法則を無視するかのようなその振る舞いの謎が、この度ついに解き明かされました。鍵となったのは、視点を変え、もっともっとミクロな世界を覗き込むことでした。
細胞膜は、生きた細胞を包み込み、保護し、門番の役割を果たしています。膜は、細胞がどのように振る舞うかにさえ影響を与えることができます。しかし、膜自身の気まぐれな振る舞いは、長年科学者たちを悩ませてきました。結局のところ、それはすべて視点の問題だったようです。バージニア工科大学の物理学者、ラナ・アシュカー博士(Rana Ashkar, PhD)のチームがナノスケールで膜の振る舞いを観察したところ、膜がずっと従ってきた統一された生物物理学的な法則を特定することができたのです。2025年7月31日に学術誌Nature Communicationsで発表されたこれらの発見は、疾患への介入方法、ドラッグデリバリー応用、人工細胞技術、そして膜生物物理学の次の段階にとって重要な意味を持ちます。このオープンアクセスの論文は、「Cholesterol Modulates Membrane Elasticity Via Unified Biophysical Laws(コレステロールは統一された生物物理学的法則を介して膜の弾性を調節する)」と題されています。
組成を変化させるスーパーヒーロー
主に脂質と呼ばれる脂肪性化合物で構成される膜は、非常に高い適応性を持ちます。膜は環境要因に応じて脂質組成を変化させ、食事、圧力、温度の変化に、時にはわずか数時間で応答することができます。恒常性(ホメオスタシス)と呼ばれるこの特性は、私たちの細胞という
私たちの体を構成する数十兆個の細胞。その一つ一つを優しく包み込み、生命の門番として機能するのが「細胞膜」です。しかしこの膜、実は科学者たちを長年悩ませてきた「気まぐれな無法者」だったのです。物理法則を無視するかのようなその振る舞いの謎が、この度ついに解き明かされました。鍵となったのは、視点を変え、もっともっとミクロな世界を覗き込むことでした。
細胞膜は、生きた細胞を包み込み、保護し、門番の役割を果たしています。膜は、細胞がどのように振る舞うかにさえ影響を与えることができます。しかし、膜自身の気まぐれな振る舞いは、長年科学者たちを悩ませてきました。結局のところ、それはすべて視点の問題だったようです。バージニア工科大学の物理学者、ラナ・アシュカー博士(Rana Ashkar, PhD)のチームがナノスケールで膜の振る舞いを観察したところ、膜がずっと従ってきた統一された生物物理学的な法則を特定することができたのです。2025年7月31日に学術誌Nature Communicationsで発表されたこれらの発見は、疾患への介入方法、ドラッグデリバリー応用、人工細胞技術、そして膜生物物理学の次の段階にとって重要な意味を持ちます。このオープンアクセスの論文は、「Cholesterol Modulates Membrane Elasticity Via Unified Biophysical Laws(コレステロールは統一された生物物理学的法則を介して膜の弾性を調節する)」と題されています。
組成を変化させるスーパーヒーロー
主に脂質と呼ばれる脂肪性化合物で構成される膜は、非常に高い適応性を持ちます。膜は環境要因に応じて脂質組成を変化させ、食事、圧力、温度の変化に、時にはわずか数時間で応答することができます。恒常性(ホメオスタシス)と呼ばれるこの特性は、私たちの細胞という
常識を覆すオオカミの子育て!赤ちゃんを運び20km移動する驚きの理由
 生まれたばかりの赤ちゃんを抱えて、険しい山道を20km以上も旅する――。人間でも大変なこの旅を、ハイイロオオカミの母親が、まだ目も見えない我が子を口にくわえて決行していることがわかりました。これまでの常識を覆すこの驚くべき行動の裏には、愛する家族を養うための必死の戦略が隠されていました。オオカミの驚異的な適応能力と親子の絆に迫ります。
UCバークレー主導の研究チームが、北極圏外のハイイロオオカミが子育て期に回遊することを初めて観察
ハイイロオオカミの子は、目も見えず、耳も聞こえず、年長者の鋭い嗅覚も持たない、ほぼ無力な状態で生まれます。彼らは通常、生後少なくとも3週間になるまで、安全な巣穴の中に留まります。だからこそ、UCバークレーの生物学者たちは、イエローストーン国立公園近郊のハイイロオオカミが、生まれたばかりの子を連れて、険しい山岳地帯を20キロメートル以上も移動するのを観察して驚いたのです。「オオカミが子を運んでいるカメラトラップの写真を初めて見たとき、思わず笑ってしまいました。だってお尻をくわえられて運ばれているんですから」と、この発見を発表した新しい研究の筆頭著者であるアベリー・ショウラー博士(Avery Shawler, PhD)は語ります。この研究は本日(2025年8月1日)オンラインで学術誌Current Biologyに掲載されました。「じたばたする子供を、お母さんが『はいはい、行くわよ』とばかりに運んでいる様子が目に浮かぶようです。」このオープンアクセスの論文は、「Wolves Use Diverse Tactics to Track Partially Migratory Prey(オオカミは部分的に回遊する獲物を追跡するために多様な戦術を用いる)」と題されています。
ショウラー博士と他の研究者たちは、オオカミがこの危険な旅を行ったのは、彼ら
生まれたばかりの赤ちゃんを抱えて、険しい山道を20km以上も旅する――。人間でも大変なこの旅を、ハイイロオオカミの母親が、まだ目も見えない我が子を口にくわえて決行していることがわかりました。これまでの常識を覆すこの驚くべき行動の裏には、愛する家族を養うための必死の戦略が隠されていました。オオカミの驚異的な適応能力と親子の絆に迫ります。
UCバークレー主導の研究チームが、北極圏外のハイイロオオカミが子育て期に回遊することを初めて観察
ハイイロオオカミの子は、目も見えず、耳も聞こえず、年長者の鋭い嗅覚も持たない、ほぼ無力な状態で生まれます。彼らは通常、生後少なくとも3週間になるまで、安全な巣穴の中に留まります。だからこそ、UCバークレーの生物学者たちは、イエローストーン国立公園近郊のハイイロオオカミが、生まれたばかりの子を連れて、険しい山岳地帯を20キロメートル以上も移動するのを観察して驚いたのです。「オオカミが子を運んでいるカメラトラップの写真を初めて見たとき、思わず笑ってしまいました。だってお尻をくわえられて運ばれているんですから」と、この発見を発表した新しい研究の筆頭著者であるアベリー・ショウラー博士(Avery Shawler, PhD)は語ります。この研究は本日(2025年8月1日)オンラインで学術誌Current Biologyに掲載されました。「じたばたする子供を、お母さんが『はいはい、行くわよ』とばかりに運んでいる様子が目に浮かぶようです。」このオープンアクセスの論文は、「Wolves Use Diverse Tactics to Track Partially Migratory Prey(オオカミは部分的に回遊する獲物を追跡するために多様な戦術を用いる)」と題されています。
ショウラー博士と他の研究者たちは、オオカミがこの危険な旅を行ったのは、彼ら
聴覚の謎を解明!体外で「生きた蝸牛」を観察する画期的な技術が難聴治療に光
 私たちは、なぜささやき声から音楽の繊細な音色まで、驚くほど幅広い音を聞き分けることができるのでしょうか。その驚異的な能力の鍵を握るのが、内耳にあるカタツムリのような形をした「蝸牛(かぎゅう)」という小さな器官です。しかし、この器官は非常にデリケートで体の奥深くにあるため、その働きを生きたまま詳しく調べることは長年の課題でした。この難問に生涯をかけて挑んだ研究者がいます。2025年8月に亡くなられたロックフェラー大学のA・ジェームズ・ハズペス医学博士(A. James Hudspeth, MD)です。博士と彼の感覚神経科学研究室のチームは、その逝去の直前、世界で初めて蝸牛の微小な断片を体外で生かし、機能させたまま維持するという画期的な技術的進歩を成し遂げました。
この新しい装置によって、蝸牛が持つ並外れた聴覚能力(卓越した感度、鋭い周波数チューニング、広範囲の音強度を符号化する能力など)の生体力学(バイオメカニクス)をライブで捉えることが可能になったのです。「私たちは今、これまで不可能だった制御された方法で、聴覚プロセスの最初のステップを観察できるのです」と、共同筆頭著者であり、ハズペス研究室の博士研究員であるフランチェスコ・ジャノーリ博士(Francesco Gianoli, PhD)は語ります。
この革新的な技術は、最近発表された2つの論文(それぞれ『PNAS』誌と『Hearing Research』誌に掲載)で詳述されており、ハズペス博士が50年にわたり取り組んできた聴覚の分子的・神経的メカニズム解明の集大成です。彼の洞察は、難聴を予防または回復させるための新たな道を照らしてきました。2025年7月14日に公開された『PNAS』誌のオープンアクセス論文は、「Amplification Through Local Critical Behavior in th
私たちは、なぜささやき声から音楽の繊細な音色まで、驚くほど幅広い音を聞き分けることができるのでしょうか。その驚異的な能力の鍵を握るのが、内耳にあるカタツムリのような形をした「蝸牛(かぎゅう)」という小さな器官です。しかし、この器官は非常にデリケートで体の奥深くにあるため、その働きを生きたまま詳しく調べることは長年の課題でした。この難問に生涯をかけて挑んだ研究者がいます。2025年8月に亡くなられたロックフェラー大学のA・ジェームズ・ハズペス医学博士(A. James Hudspeth, MD)です。博士と彼の感覚神経科学研究室のチームは、その逝去の直前、世界で初めて蝸牛の微小な断片を体外で生かし、機能させたまま維持するという画期的な技術的進歩を成し遂げました。
この新しい装置によって、蝸牛が持つ並外れた聴覚能力(卓越した感度、鋭い周波数チューニング、広範囲の音強度を符号化する能力など)の生体力学(バイオメカニクス)をライブで捉えることが可能になったのです。「私たちは今、これまで不可能だった制御された方法で、聴覚プロセスの最初のステップを観察できるのです」と、共同筆頭著者であり、ハズペス研究室の博士研究員であるフランチェスコ・ジャノーリ博士(Francesco Gianoli, PhD)は語ります。
この革新的な技術は、最近発表された2つの論文(それぞれ『PNAS』誌と『Hearing Research』誌に掲載)で詳述されており、ハズペス博士が50年にわたり取り組んできた聴覚の分子的・神経的メカニズム解明の集大成です。彼の洞察は、難聴を予防または回復させるための新たな道を照らしてきました。2025年7月14日に公開された『PNAS』誌のオープンアクセス論文は、「Amplification Through Local Critical Behavior in th
光が鍵!ユリの鮮やかな花色を生み出す分子メカニズムを世界で初めて解明
 夏の陽射しを浴びて、ひときわ鮮やかに咲き誇るユリの花。なぜ光を浴びると、その花びらは美しいピンクや紫色に染まるのでしょうか?その秘密は、花びらの中で働く、まるで二人一組の「色の演出家」のような遺伝子にありました。中国の研究チームが解き明かした、光と色が織りなすミクロの世界の物語を覗いてみましょう。ユリは、その美しさと商業的魅力から、世界で最も愛されている観賞用花卉の一つです。
その特徴的なピンクや紫の色合いは、植物が環境ストレスから身を守るのにも役立つ植物色素、アントシアニンに由来します。アントシアニンを生産する化学経路は植物全体で保存されていますが、ユリのような単子葉植物において、光によってその活性化を制御する調節システムは、ほとんど解明されていませんでした。MYBやBBXのような転写因子が色素の制御に関与することは知られていますが、光に応答して遺伝子発現を調節する特定の相互作用は不明なままでした。これらの未解決問題のため、光照射下での転写調節に関するより深い調査が急務とされていました。この度、中国の瀋陽農業大学の研究チームが、光がユリの花びらの色をどのように形成するかの解読において、大きな一歩を踏み出しました。2024年7月30日に学術誌Horticulture Researchで発表されたこの研究(DOI: 10.1093/hr/uhae211)は、2つの転写因子—LvBBX24とLvbZIP44—が調節デュオを形成し、アントシアニン生合成に不可欠な遺伝子であるLvMYB5を活性化することを特定しました。彼らの研究は、光照射が鮮やかな花びらの色彩に変換される新しい分子メカニズムを明らかにし、観賞植物の育種や植物分子生物学に貴重な知見を提供します。このオープンアクセスの論文は、「Transcription Factors LvBBX24 and LvbZIP44
夏の陽射しを浴びて、ひときわ鮮やかに咲き誇るユリの花。なぜ光を浴びると、その花びらは美しいピンクや紫色に染まるのでしょうか?その秘密は、花びらの中で働く、まるで二人一組の「色の演出家」のような遺伝子にありました。中国の研究チームが解き明かした、光と色が織りなすミクロの世界の物語を覗いてみましょう。ユリは、その美しさと商業的魅力から、世界で最も愛されている観賞用花卉の一つです。
その特徴的なピンクや紫の色合いは、植物が環境ストレスから身を守るのにも役立つ植物色素、アントシアニンに由来します。アントシアニンを生産する化学経路は植物全体で保存されていますが、ユリのような単子葉植物において、光によってその活性化を制御する調節システムは、ほとんど解明されていませんでした。MYBやBBXのような転写因子が色素の制御に関与することは知られていますが、光に応答して遺伝子発現を調節する特定の相互作用は不明なままでした。これらの未解決問題のため、光照射下での転写調節に関するより深い調査が急務とされていました。この度、中国の瀋陽農業大学の研究チームが、光がユリの花びらの色をどのように形成するかの解読において、大きな一歩を踏み出しました。2024年7月30日に学術誌Horticulture Researchで発表されたこの研究(DOI: 10.1093/hr/uhae211)は、2つの転写因子—LvBBX24とLvbZIP44—が調節デュオを形成し、アントシアニン生合成に不可欠な遺伝子であるLvMYB5を活性化することを特定しました。彼らの研究は、光照射が鮮やかな花びらの色彩に変換される新しい分子メカニズムを明らかにし、観賞植物の育種や植物分子生物学に貴重な知見を提供します。このオープンアクセスの論文は、「Transcription Factors LvBBX24 and LvbZIP44
もう採血は不要?唾液でわかる糖尿病リスク!UBCが発見した画期的な早期診断法
 健康診断での採血が、ちょっと苦手だと感じる方は多いのではないでしょうか。もし、あのチクッとする痛みなしで、唾液を出すだけで将来の生活習慣病のリスクがわかるとしたら?カナダの研究チームが、そんな夢のような検査方法の可能性を発見しました。あなたの唾液に隠された、健康の早期警告サインとは一体何なのでしょうか。
UBCの研究が慢性疾患の早期警告サインを検出する非侵襲的な方法を明らかに
血中のインスリン濃度が高い状態、すなわち高インスリン血症を測定することは、メタボリックヘルスを評価する実証済みの方法であり、2型糖尿病、肥満、心臓病を含む将来の健康問題を発症するリスクを示すことができます。この度、ブリティッシュ・コロンビア大学(UBC)オカナガン校の研究チームが、唾液中のインスリン濃度を測定することで、針や研究室での血液検査を必要とせずに同じ検査を行える非侵襲的な方法を発見しました。UBCオカナガン校 健康運動科学部の教授であるジョナサン・リトル博士(Jonathan Little, PhD)は、簡単な唾液検査はそれ以上のことができると述べています。それは、肥満やその他の健康リスクに関連する初期の代謝変化を検出するためにも使用できるのです。
2025年5月16日に学術誌Applied Physiology, Nutrition, and Metabolismで発表されたこの研究には、様々な体格の健康な参加者94名が含まれていました。絶食期間の後、各参加者は標準化された代替食シェイクを飲み、その後、唾液サンプルを提供し、指先穿刺による血糖値検査を受けました。この論文は、「Saliva Insulin Concentration Following Ingestion of a Standardized Mixed Meal Tolerance Test: Influence
健康診断での採血が、ちょっと苦手だと感じる方は多いのではないでしょうか。もし、あのチクッとする痛みなしで、唾液を出すだけで将来の生活習慣病のリスクがわかるとしたら?カナダの研究チームが、そんな夢のような検査方法の可能性を発見しました。あなたの唾液に隠された、健康の早期警告サインとは一体何なのでしょうか。
UBCの研究が慢性疾患の早期警告サインを検出する非侵襲的な方法を明らかに
血中のインスリン濃度が高い状態、すなわち高インスリン血症を測定することは、メタボリックヘルスを評価する実証済みの方法であり、2型糖尿病、肥満、心臓病を含む将来の健康問題を発症するリスクを示すことができます。この度、ブリティッシュ・コロンビア大学(UBC)オカナガン校の研究チームが、唾液中のインスリン濃度を測定することで、針や研究室での血液検査を必要とせずに同じ検査を行える非侵襲的な方法を発見しました。UBCオカナガン校 健康運動科学部の教授であるジョナサン・リトル博士(Jonathan Little, PhD)は、簡単な唾液検査はそれ以上のことができると述べています。それは、肥満やその他の健康リスクに関連する初期の代謝変化を検出するためにも使用できるのです。
2025年5月16日に学術誌Applied Physiology, Nutrition, and Metabolismで発表されたこの研究には、様々な体格の健康な参加者94名が含まれていました。絶食期間の後、各参加者は標準化された代替食シェイクを飲み、その後、唾液サンプルを提供し、指先穿刺による血糖値検査を受けました。この論文は、「Saliva Insulin Concentration Following Ingestion of a Standardized Mixed Meal Tolerance Test: Influence
数十年の眠りから覚める卵子、その驚くべき生命力の秘密
 女性の体内で、時には50年近くもの間、静かに出番を待ち続ける「卵子」。その驚くべき忍耐強さと、時を経ても生命を生み出す力を失わない秘密が、最新の研究によって解き明かされようとしています。この発見は、世界中で多くの人々が臨む不妊治療の未来に、新たな光を灯すかもしれません。2025年7月16日に科学誌「The EMBO Journal」に掲載された研究によると、ヒトの卵子は成熟する過程で、細胞内部の老廃物処理システムの活動を意図的に低下させることが明らかになりました。
これは、代謝を低く保ち、細胞へのダメージを最小限に抑えるための、進化の過程で獲得した巧みな設計である可能性が高いと考えられます。この研究論文は、「The Proteostatic Landscape of Healthy Human Oocytes(健康なヒト卵母細胞におけるプロテオスタシス(タンパク質恒常性)の全体像)」と題されています。「この種の研究では過去最大となる、100個以上の新鮮な提供卵子を調べることで、細胞が長年にわたって pristine(汚染されていない pristine)な状態を保つための、驚くほどミニマリストな戦略を発見しました」と、研究のシニア著者兼責任著者であり、バルセロナのゲノム制御センター(CRG)でグループリーダーを務めるエルヴァン・ボケ博士(Elvan Böke, PhD)は語ります。
女性は生まれつき100万から200万個の未成熟な卵子を持っており、その数は閉経期までには数百個にまで減少します。一つ一つの卵子は、妊娠を支えることができるようになるまで、最大で50年間も消耗を避けなければなりません。今回の新しい研究は、卵子がどのようにしてそれを成し遂げているのかを示唆しています。
タンパク質のリサイクルは細胞にとって不可欠な「大掃除」であり、リソソームとプロテアソームが
女性の体内で、時には50年近くもの間、静かに出番を待ち続ける「卵子」。その驚くべき忍耐強さと、時を経ても生命を生み出す力を失わない秘密が、最新の研究によって解き明かされようとしています。この発見は、世界中で多くの人々が臨む不妊治療の未来に、新たな光を灯すかもしれません。2025年7月16日に科学誌「The EMBO Journal」に掲載された研究によると、ヒトの卵子は成熟する過程で、細胞内部の老廃物処理システムの活動を意図的に低下させることが明らかになりました。
これは、代謝を低く保ち、細胞へのダメージを最小限に抑えるための、進化の過程で獲得した巧みな設計である可能性が高いと考えられます。この研究論文は、「The Proteostatic Landscape of Healthy Human Oocytes(健康なヒト卵母細胞におけるプロテオスタシス(タンパク質恒常性)の全体像)」と題されています。「この種の研究では過去最大となる、100個以上の新鮮な提供卵子を調べることで、細胞が長年にわたって pristine(汚染されていない pristine)な状態を保つための、驚くほどミニマリストな戦略を発見しました」と、研究のシニア著者兼責任著者であり、バルセロナのゲノム制御センター(CRG)でグループリーダーを務めるエルヴァン・ボケ博士(Elvan Böke, PhD)は語ります。
女性は生まれつき100万から200万個の未成熟な卵子を持っており、その数は閉経期までには数百個にまで減少します。一つ一つの卵子は、妊娠を支えることができるようになるまで、最大で50年間も消耗を避けなければなりません。今回の新しい研究は、卵子がどのようにしてそれを成し遂げているのかを示唆しています。
タンパク質のリサイクルは細胞にとって不可欠な「大掃除」であり、リソソームとプロテアソームが
腹壁破裂の赤ちゃんに希望を。現地で製造可能な医療機器「SimpleSilo」の挑戦
 生まれてすぐに命の危機に瀕する赤ちゃんがいます。お腹の壁が閉じていない状態で生まれ、腸が体の外に出てしまう「腹壁破裂」という病気です。先進国では助かる命も、医療資源の乏しい地域では、高価な器具が手に入らないために失われがちです。この悲しい現実を変えようと、ライス大学のエンジニアと学生、そして小児外科医たちが立ち上がりました。病院にある身近な材料から生まれた、わずか2ドルの「袋」が、小さな命を救う大きな希望になろうとしています。
医療資源が限られた環境では、腹壁破裂—腹壁の穴を通して発育中の腸が体外に露出する先天性疾患—を持って生まれた赤ちゃんは、生命を脅かす困難に直面します。高所得国では、高度な医療機器と新生児ケアのおかげで生存率が90%を超えていますが、資源に制約のある医療現場の乳児は、依然として高い死亡率に直面しています。その一因は、この状態を治療するために必要な救命器具へのアクセスがないことです。ライス大学のグローバルヘルス技術研究所「Rice360」が率いるエンジニアと小児外科医のチームは、その状況を変えるために取り組んでいます。彼らのイノベーションは、「SimpleSilo」として知られる、シンプルで低コスト、かつ現地で製造可能な医療機器です。これは、腹壁破裂の救命治療を現在の数分の一のコストで提供し、現地で入手可能な材料から作られるように設計されています。
「私たちは、手頃な価格でありながら、デザインをできるだけシンプルで機能的に保つことに重点を置きました」と、ライス大学を最近卒業し、2025年8月号のJournal of Pediatric Surgeryに掲載された本研究の筆頭著者であるヴァンシカ・ジョンサ氏(Vanshika Jhonsa)は述べています。現在UTHealth Houstonの医学生であるジョンサ氏は、このプロジェクトで2023年
生まれてすぐに命の危機に瀕する赤ちゃんがいます。お腹の壁が閉じていない状態で生まれ、腸が体の外に出てしまう「腹壁破裂」という病気です。先進国では助かる命も、医療資源の乏しい地域では、高価な器具が手に入らないために失われがちです。この悲しい現実を変えようと、ライス大学のエンジニアと学生、そして小児外科医たちが立ち上がりました。病院にある身近な材料から生まれた、わずか2ドルの「袋」が、小さな命を救う大きな希望になろうとしています。
医療資源が限られた環境では、腹壁破裂—腹壁の穴を通して発育中の腸が体外に露出する先天性疾患—を持って生まれた赤ちゃんは、生命を脅かす困難に直面します。高所得国では、高度な医療機器と新生児ケアのおかげで生存率が90%を超えていますが、資源に制約のある医療現場の乳児は、依然として高い死亡率に直面しています。その一因は、この状態を治療するために必要な救命器具へのアクセスがないことです。ライス大学のグローバルヘルス技術研究所「Rice360」が率いるエンジニアと小児外科医のチームは、その状況を変えるために取り組んでいます。彼らのイノベーションは、「SimpleSilo」として知られる、シンプルで低コスト、かつ現地で製造可能な医療機器です。これは、腹壁破裂の救命治療を現在の数分の一のコストで提供し、現地で入手可能な材料から作られるように設計されています。
「私たちは、手頃な価格でありながら、デザインをできるだけシンプルで機能的に保つことに重点を置きました」と、ライス大学を最近卒業し、2025年8月号のJournal of Pediatric Surgeryに掲載された本研究の筆頭著者であるヴァンシカ・ジョンサ氏(Vanshika Jhonsa)は述べています。現在UTHealth Houstonの医学生であるジョンサ氏は、このプロジェクトで2023年
冬眠動物のスーパーパワーは遺伝子にあった。ゲノム解析が解き明かす健康長寿の鍵
 冬眠する動物は、何か月も食べずに過ごしても筋肉は衰えず、春には元気に目覚めます。まるでスーパーパワーのようですが、もしその力が私たち人間のDNAにも眠っているとしたらどうでしょう?ユタ大学の最新研究が、冬眠の謎を遺伝子レベルで解き明かし、アルツハイマー病や糖尿病といった難病治療への全く新しい扉を開こうとしています。私たちの体内に秘められた可能性を探る、驚くべき発見の物語です。
冬眠する動物は、信じられないほどの回復力を持っています。彼らは数ヶ月間、食べ物も水もなしで過ごし、筋肉は萎縮せず、代謝や脳活動が這うように遅くなるにつれて体温は氷点近くまで下がります。冬眠から目覚めると、2型糖尿病、アルツハイマー病、脳卒中で見られるような危険な健康上の変化から回復します。新しい遺伝子研究は、冬眠動物の持つスーパーパワーが私たち自身のDNAにも隠されている可能性を示唆しており、それを解き放つための手がかりを提供しています。これにより、いつの日か神経変性や糖尿病を回復させる可能性のある治療法を開発する道が開かれます。この結果を詳述する2つの研究は、2025年7月31日に学術誌Scienceに、「Conserved Noncoding Cis-Elements Associated with Hibernation Modulate Metabolic and Behavioral Adaptations in Mice(冬眠に関連する保存された非コードシスエレメントがマウスの代謝および行動適応を調節する)」および「Genomic Convergence in Hibernating Mammals Elucidates the Genetics of Metabolic Regulation in the Hypothalamus(冬眠哺乳類におけるゲノム収斂が視床下部における代謝
冬眠する動物は、何か月も食べずに過ごしても筋肉は衰えず、春には元気に目覚めます。まるでスーパーパワーのようですが、もしその力が私たち人間のDNAにも眠っているとしたらどうでしょう?ユタ大学の最新研究が、冬眠の謎を遺伝子レベルで解き明かし、アルツハイマー病や糖尿病といった難病治療への全く新しい扉を開こうとしています。私たちの体内に秘められた可能性を探る、驚くべき発見の物語です。
冬眠する動物は、信じられないほどの回復力を持っています。彼らは数ヶ月間、食べ物も水もなしで過ごし、筋肉は萎縮せず、代謝や脳活動が這うように遅くなるにつれて体温は氷点近くまで下がります。冬眠から目覚めると、2型糖尿病、アルツハイマー病、脳卒中で見られるような危険な健康上の変化から回復します。新しい遺伝子研究は、冬眠動物の持つスーパーパワーが私たち自身のDNAにも隠されている可能性を示唆しており、それを解き放つための手がかりを提供しています。これにより、いつの日か神経変性や糖尿病を回復させる可能性のある治療法を開発する道が開かれます。この結果を詳述する2つの研究は、2025年7月31日に学術誌Scienceに、「Conserved Noncoding Cis-Elements Associated with Hibernation Modulate Metabolic and Behavioral Adaptations in Mice(冬眠に関連する保存された非コードシスエレメントがマウスの代謝および行動適応を調節する)」および「Genomic Convergence in Hibernating Mammals Elucidates the Genetics of Metabolic Regulation in the Hypothalamus(冬眠哺乳類におけるゲノム収斂が視床下部における代謝
糖尿病リスクは生まれつき決まる?膵臓β細胞の「個性」を解明した最新研究
 「最近、周りで糖尿病になったという話をよく聞く…」そう感じていませんか?国民病ともいえる糖尿病ですが、そのなりやすさが、実はあなたが生まれる前、お母さんのお腹の中にいた頃の環境や、もっと言えば、あなたの体を作る細胞の「個性」によって左右されているとしたらどうでしょう。最新の研究が、糖尿病リスクの鍵を握る膵臓の細胞の多様性に迫り、将来の予防法や治療法に繋がるかもしれない発見を報告しました。
あなたの知人の中に糖尿病を発症する人が増えているように感じるとしたら、それは間違いではありません。米国糖尿病協会によると、2021年には米国の人口の10%以上にあたる約3840万人が糖尿病を患っており、毎年120万人が新たに診断されています。2型糖尿病(T2D)は、血中のグルコース濃度を調節するホルモンであるインスリンに対する抵抗性を体が発現することで起こります。インスリンはβ細胞と呼ばれる膵臓の細胞から分泌され、T2Dでは、これらの細胞が血糖値を調節しようとインスリン産生を増やしますが、それでも不十分で、最終的にβ細胞は時間とともに疲弊してしまいます。この重要性から、機能的なβ細胞量、つまりβ細胞の総数とその機能が、個人の糖尿病リスクを決定します。
β細胞は一個人でさえ均一ではなく、それぞれが独自の分泌機能、生存能力、分裂能力を持つ異なる「サブタイプ」で構成されています。言い換えれば、各β細胞サブタイプは異なるレベルの「適応度(フィットネス)」を持ち、それは高いほど良いということになります。糖尿病が発症すると、一部のβ細胞サブタイプの比率が変化します。しかし、重要な疑問が残されていました。それは、異なるβ細胞サブタイプの比率と適応度は糖尿病によって変化するのか、それともその変化が病気の原因なのか、という点です。
この問いに答えるべく立ち上がったのが、ヴァンダービルト大学の教
「最近、周りで糖尿病になったという話をよく聞く…」そう感じていませんか?国民病ともいえる糖尿病ですが、そのなりやすさが、実はあなたが生まれる前、お母さんのお腹の中にいた頃の環境や、もっと言えば、あなたの体を作る細胞の「個性」によって左右されているとしたらどうでしょう。最新の研究が、糖尿病リスクの鍵を握る膵臓の細胞の多様性に迫り、将来の予防法や治療法に繋がるかもしれない発見を報告しました。
あなたの知人の中に糖尿病を発症する人が増えているように感じるとしたら、それは間違いではありません。米国糖尿病協会によると、2021年には米国の人口の10%以上にあたる約3840万人が糖尿病を患っており、毎年120万人が新たに診断されています。2型糖尿病(T2D)は、血中のグルコース濃度を調節するホルモンであるインスリンに対する抵抗性を体が発現することで起こります。インスリンはβ細胞と呼ばれる膵臓の細胞から分泌され、T2Dでは、これらの細胞が血糖値を調節しようとインスリン産生を増やしますが、それでも不十分で、最終的にβ細胞は時間とともに疲弊してしまいます。この重要性から、機能的なβ細胞量、つまりβ細胞の総数とその機能が、個人の糖尿病リスクを決定します。
β細胞は一個人でさえ均一ではなく、それぞれが独自の分泌機能、生存能力、分裂能力を持つ異なる「サブタイプ」で構成されています。言い換えれば、各β細胞サブタイプは異なるレベルの「適応度(フィットネス)」を持ち、それは高いほど良いということになります。糖尿病が発症すると、一部のβ細胞サブタイプの比率が変化します。しかし、重要な疑問が残されていました。それは、異なるβ細胞サブタイプの比率と適応度は糖尿病によって変化するのか、それともその変化が病気の原因なのか、という点です。
この問いに答えるべく立ち上がったのが、ヴァンダービルト大学の教
結核から次なるパンデミックまで。科学者たちのチームワークが未来の医療を創る
 パンデミックが世界を襲った時、科学者たちはどう立ち向かったのか?その答えの一つが、専門分野の垣根を越えた「協力」です。ロックフェラー大学では、ノーベル賞受賞者が率いる新しい研究所が触媒となり、異分野の研究者たちを結びつけています。化学と遺伝学、物理学と生物学。それぞれの才能が出会う時、感染症との戦いに新たな突破口が開かれます。
今年5月、ロックフェラー大学のキャスパリー講堂のステージに数十人の感染症研究者が登壇した際、彼らが語ったのは、ヒトの免疫応答、ウイルスの生存戦略、あるいは薬剤耐性結核との戦いにおける最近の飛躍的進歩を駆け足で紹介するだけではありませんでした。スタブロス・ニアルコス財団グローバル感染症研究所(SNFiRU: Stavros Niarchos Foundation Institute for Global Infectious Disease Research)の第3回年次シンポジウムで行われたこれらの発表は、卓越した基礎科学のショーケースであると同時に、一つの「招待状」でもあったのです。
「コラボレーションは生物医学研究の鍵であり、このシンポジウムはそれを育むために企画されています」と、ノーベル賞受賞者であり、同研究所の所長でもあるチャールズ・M・ライス氏(Charles M. Rice)は言います。「感染症という広範かつ緊急の課題に取り組むには、あらゆる専門知識を結集する必要があります。」
SNFiRUの中核的な使命は、新たな病原体や持続的な世界的脅威に対する新しい治療法の開発を加速させることです。スタブロス・ニアルコス財団からの革新的な助成金により2023年に設立されたこの研究所は、ロックフェラー大学の研究室のほぼ半数が感染症研究に舵を切ったCOVID-19パンデミック時に生まれた勢いを基盤としています。
ケミカルプロテオミクスを用
パンデミックが世界を襲った時、科学者たちはどう立ち向かったのか?その答えの一つが、専門分野の垣根を越えた「協力」です。ロックフェラー大学では、ノーベル賞受賞者が率いる新しい研究所が触媒となり、異分野の研究者たちを結びつけています。化学と遺伝学、物理学と生物学。それぞれの才能が出会う時、感染症との戦いに新たな突破口が開かれます。
今年5月、ロックフェラー大学のキャスパリー講堂のステージに数十人の感染症研究者が登壇した際、彼らが語ったのは、ヒトの免疫応答、ウイルスの生存戦略、あるいは薬剤耐性結核との戦いにおける最近の飛躍的進歩を駆け足で紹介するだけではありませんでした。スタブロス・ニアルコス財団グローバル感染症研究所(SNFiRU: Stavros Niarchos Foundation Institute for Global Infectious Disease Research)の第3回年次シンポジウムで行われたこれらの発表は、卓越した基礎科学のショーケースであると同時に、一つの「招待状」でもあったのです。
「コラボレーションは生物医学研究の鍵であり、このシンポジウムはそれを育むために企画されています」と、ノーベル賞受賞者であり、同研究所の所長でもあるチャールズ・M・ライス氏(Charles M. Rice)は言います。「感染症という広範かつ緊急の課題に取り組むには、あらゆる専門知識を結集する必要があります。」
SNFiRUの中核的な使命は、新たな病原体や持続的な世界的脅威に対する新しい治療法の開発を加速させることです。スタブロス・ニアルコス財団からの革新的な助成金により2023年に設立されたこの研究所は、ロックフェラー大学の研究室のほぼ半数が感染症研究に舵を切ったCOVID-19パンデミック時に生まれた勢いを基盤としています。
ケミカルプロテオミクスを用
生命のON/OFFスイッチ!形を変える「RNAスイッチ」を数百種類発見
 遺伝子の情報をコピーして運ぶメッセンジャー。RNAの役割はそれだけだと思っていませんか?実は、RNAはまるで電気のスイッチのように自身の形をカチッと切り替え、生命活動を巧みにON/OFFする「変身能力」を持っていたのです。最新の研究が、この驚くべきRNAスイッチの存在を数百も発見し、新しい治療法への扉を開こうとしています。
RNA分子は、タンパク質をコードする情報を運ぶだけでなく、複雑な二次および三次構造をとることができます。特筆すべきは、同じ一つのRNA分子がONとOFFの構造を切り替えることで、リボソームがRNAに結合してタンパク質へと翻訳する能力を調節できる点です。フローニンゲン大学の分子生物学者であるダニー・インカルナート氏(Danny Incarnato)と、筆頭著者である博士研究員のイワナ・ボロフスカ博士(Dr. Ivana Borovska, PhD)が主導した新しい研究は、大腸菌とヒト細胞において、このような調節機能を持つRNAスイッチを数百種類も特定しました。この研究成果は、2025年7月25日付の「Nature Biotechnology」誌に掲載されました。論文のタイトルは「Identification of Conserved RNA Regulatory Switches in Living Cells Using RNA Secondary Structure Ensemble Mapping and Covariation Analysis(RNA二次構造アンサンブルマッピングと共変動解析を用いた生細胞における保存されたRNA制御スイッチの同定)」です。
数年前、インカルナート氏は生きた細胞内でRNA分子がとる代替的な形状をマッピングする手法を開発しました。この手法を用いて、彼は2つの異なる構造間で形を変えることができるRNAの領域を特
遺伝子の情報をコピーして運ぶメッセンジャー。RNAの役割はそれだけだと思っていませんか?実は、RNAはまるで電気のスイッチのように自身の形をカチッと切り替え、生命活動を巧みにON/OFFする「変身能力」を持っていたのです。最新の研究が、この驚くべきRNAスイッチの存在を数百も発見し、新しい治療法への扉を開こうとしています。
RNA分子は、タンパク質をコードする情報を運ぶだけでなく、複雑な二次および三次構造をとることができます。特筆すべきは、同じ一つのRNA分子がONとOFFの構造を切り替えることで、リボソームがRNAに結合してタンパク質へと翻訳する能力を調節できる点です。フローニンゲン大学の分子生物学者であるダニー・インカルナート氏(Danny Incarnato)と、筆頭著者である博士研究員のイワナ・ボロフスカ博士(Dr. Ivana Borovska, PhD)が主導した新しい研究は、大腸菌とヒト細胞において、このような調節機能を持つRNAスイッチを数百種類も特定しました。この研究成果は、2025年7月25日付の「Nature Biotechnology」誌に掲載されました。論文のタイトルは「Identification of Conserved RNA Regulatory Switches in Living Cells Using RNA Secondary Structure Ensemble Mapping and Covariation Analysis(RNA二次構造アンサンブルマッピングと共変動解析を用いた生細胞における保存されたRNA制御スイッチの同定)」です。
数年前、インカルナート氏は生きた細胞内でRNA分子がとる代替的な形状をマッピングする手法を開発しました。この手法を用いて、彼は2つの異なる構造間で形を変えることができるRNAの領域を特
太古のコオロギの鳴き声を再現!計算モデリングが解き明かす「音の化石」
 夏の夜、どこからともなく聞こえてくるコオロギの涼しげな鳴き声。私たちにとって馴染み深いこの音色が、実は何百万年も前の地球の音を解き明かす鍵になるかもしれません。もし、博物館に眠る古い標本から、まるで生きているかのようにその鳴き声を再現できるとしたら、驚きませんか?カナダの研究チームが、まさにそんな夢のような技術を開発しました。最新のコンピューター技術と昆虫の翅(はね)の秘密に迫る、興味深い研究の世界を覗いてみましょう。
ウェスタン大学の研究者たちが、保存されているコオロギの翅の物理的な形状に基づき、その鳴き声を再構築する革新的な方法を開発しました。この研究は、保存標本からの測定値と計算モデリングを駆使したものです。この新しい最良規範は、2025年7月30日に学術誌Royal Society Open Scienceで発表されました。研究を主導したのは、ウェスタン大学生物学教授であり、無脊椎動物の神経生物学におけるカナダリサーチチェアを務めるナターシャ・マハトレ博士(Natasha Mhatre)と、彼女の研究室に所属していた3人の元学部生です。彼女の研究室では、昆虫やクモのコミュニケーションにおける生物物理学を調査しています。このオープンアクセスの論文は、「Reliable Reconstruction of Cricket Song from Biophysical Models and Preserved Specimens(生物物理モデルと保存標本からのコオロギの歌の信頼性の高い再構築)」と題されています。
今回の新しい研究で、マハトレ博士とその共同研究者たちは、これまでの試みよりもコオロギの実際の物理的特徴に忠実な、新しいコンピューターモデリング手法を詳述しています。この新モデルは、モデルの基になっていない新しい翅であっても、その正確な振動パターンを予測する
夏の夜、どこからともなく聞こえてくるコオロギの涼しげな鳴き声。私たちにとって馴染み深いこの音色が、実は何百万年も前の地球の音を解き明かす鍵になるかもしれません。もし、博物館に眠る古い標本から、まるで生きているかのようにその鳴き声を再現できるとしたら、驚きませんか?カナダの研究チームが、まさにそんな夢のような技術を開発しました。最新のコンピューター技術と昆虫の翅(はね)の秘密に迫る、興味深い研究の世界を覗いてみましょう。
ウェスタン大学の研究者たちが、保存されているコオロギの翅の物理的な形状に基づき、その鳴き声を再構築する革新的な方法を開発しました。この研究は、保存標本からの測定値と計算モデリングを駆使したものです。この新しい最良規範は、2025年7月30日に学術誌Royal Society Open Scienceで発表されました。研究を主導したのは、ウェスタン大学生物学教授であり、無脊椎動物の神経生物学におけるカナダリサーチチェアを務めるナターシャ・マハトレ博士(Natasha Mhatre)と、彼女の研究室に所属していた3人の元学部生です。彼女の研究室では、昆虫やクモのコミュニケーションにおける生物物理学を調査しています。このオープンアクセスの論文は、「Reliable Reconstruction of Cricket Song from Biophysical Models and Preserved Specimens(生物物理モデルと保存標本からのコオロギの歌の信頼性の高い再構築)」と題されています。
今回の新しい研究で、マハトレ博士とその共同研究者たちは、これまでの試みよりもコオロギの実際の物理的特徴に忠実な、新しいコンピューターモデリング手法を詳述しています。この新モデルは、モデルの基になっていない新しい翅であっても、その正確な振動パターンを予測する
データサイエンスが暴く子宮内膜症と600以上の病気のつながり
 10人に1人の女性が苦しむと言われる子宮内膜症。その激しい痛みや不妊の原因は、長年謎に包まれてきました。しかし、最新のデータサイエンスが、この病気の全体像を大きく変えようとしています。カリフォルニア大学の研究者たちが、数百万人の医療記録を解析した結果、子宮内膜症が、がんや片頭痛といった、これまであまり関係がないと思われていた多くの病気と関連していることが明らかになったのです。あなたのその不調、もしかしたら子宮内膜症と意外な病気が関係しているかもしれません。
カリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF)の科学者たちは、女性の10%が罹患しているにもかかわらず、診断されずに見過ごされることが多い痛みを伴う慢性疾患である子宮内膜症が、がん、クローン病、片頭痛といった疾患としばしば併発することを発見しました。この研究は、子宮内膜症の診断方法、そして最終的には治療方法を改善する可能性を秘めています。そして、有病率の高さに反して謎に包まれているこの疾患について、これまでで最も鮮明な全体像を描き出しています。2025年7月31日に学術誌Cell Reports Medicineに掲載されたこの研究は、UCSFで開発された計算手法を用いて、カリフォルニア大学の6つの医療センターで収集された匿名化された患者記録を分析したものです。このオープンアクセスの論文は、「Comorbidity Analysis and Clustering of Endometriosis Patients Using Electronic Health Records(電子カルテを用いた子宮内膜症患者の併存疾患分析とクラスタリング)」と題されています。「私たちは今、子宮内膜症に苦しむ膨大な数の人々のために変化をもたらすためのツールとデータの両方を手にしています」と、UCSFベイカー計算健康科学研究所の暫
10人に1人の女性が苦しむと言われる子宮内膜症。その激しい痛みや不妊の原因は、長年謎に包まれてきました。しかし、最新のデータサイエンスが、この病気の全体像を大きく変えようとしています。カリフォルニア大学の研究者たちが、数百万人の医療記録を解析した結果、子宮内膜症が、がんや片頭痛といった、これまであまり関係がないと思われていた多くの病気と関連していることが明らかになったのです。あなたのその不調、もしかしたら子宮内膜症と意外な病気が関係しているかもしれません。
カリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF)の科学者たちは、女性の10%が罹患しているにもかかわらず、診断されずに見過ごされることが多い痛みを伴う慢性疾患である子宮内膜症が、がん、クローン病、片頭痛といった疾患としばしば併発することを発見しました。この研究は、子宮内膜症の診断方法、そして最終的には治療方法を改善する可能性を秘めています。そして、有病率の高さに反して謎に包まれているこの疾患について、これまでで最も鮮明な全体像を描き出しています。2025年7月31日に学術誌Cell Reports Medicineに掲載されたこの研究は、UCSFで開発された計算手法を用いて、カリフォルニア大学の6つの医療センターで収集された匿名化された患者記録を分析したものです。このオープンアクセスの論文は、「Comorbidity Analysis and Clustering of Endometriosis Patients Using Electronic Health Records(電子カルテを用いた子宮内膜症患者の併存疾患分析とクラスタリング)」と題されています。「私たちは今、子宮内膜症に苦しむ膨大な数の人々のために変化をもたらすためのツールとデータの両方を手にしています」と、UCSFベイカー計算健康科学研究所の暫
未来の薬剤耐性菌を予測せよ!土壌ゲノムから「長く効く抗生物質」を設計する新戦略
 効くはずの薬が効かない―。薬剤耐性菌の脅威は、静かに、しかし確実に私たちの未来を蝕んでいます。毎年500万人が命を落とすこの戦いで、人類は後手に回りがちでした。しかし、もし未来に出現する「敵」を先読みし、それを無力化する武器をあらかじめ開発できるとしたら?最新の研究が、土の中に眠る膨大な遺伝子情報から未来の脅威を予測し、より長く効き続ける抗生物質を設計する画期的な方法を提案しています。
多剤耐性菌により、毎年500万人が死亡しており、科学者が治療法を開発するよりも速いペースで新たな耐性菌が出現しています。今回、研究者たちは、臨床現場で出現する前に環境中にすでに存在する薬剤耐性遺伝子を特定し、その情報を耐性を回避する抗生物質の設計に直接結びつけるプラットフォームを開発しました。2025年5月19日に米国科学アカデミー紀要(PNAS)に掲載されたこの発見は、いわゆる「レジストーム(薬剤耐性遺伝子の総体)」のメタゲノム調査を早期警戒システムとして利用し、将来問題となる可能性のある耐性について科学者に警告するものです。この情報をもとに、開発中の抗生物質を積極的に最適化し、微生物という敵に対してより強靭なものにすることができます。このPNAS論文のタイトルは「Environmental Resistome–Guided Development of Resistance-Tolerant Antibiotics(環境レジストームに導かれた耐性克服型抗生物質の開発)」です。
「私たちは、将来問題となりそうな耐性の種類を予測しているのです」と、ロックフェラー大学のショーン・F・ブレイディ氏(Sean F. Brady)の研究室に所属する筆頭著者のジェームズ・ピーク氏(James Peek)は言います。「私たちのプラットフォームが、抗生物質の臨床的寿命を延ばす一助となることを願
効くはずの薬が効かない―。薬剤耐性菌の脅威は、静かに、しかし確実に私たちの未来を蝕んでいます。毎年500万人が命を落とすこの戦いで、人類は後手に回りがちでした。しかし、もし未来に出現する「敵」を先読みし、それを無力化する武器をあらかじめ開発できるとしたら?最新の研究が、土の中に眠る膨大な遺伝子情報から未来の脅威を予測し、より長く効き続ける抗生物質を設計する画期的な方法を提案しています。
多剤耐性菌により、毎年500万人が死亡しており、科学者が治療法を開発するよりも速いペースで新たな耐性菌が出現しています。今回、研究者たちは、臨床現場で出現する前に環境中にすでに存在する薬剤耐性遺伝子を特定し、その情報を耐性を回避する抗生物質の設計に直接結びつけるプラットフォームを開発しました。2025年5月19日に米国科学アカデミー紀要(PNAS)に掲載されたこの発見は、いわゆる「レジストーム(薬剤耐性遺伝子の総体)」のメタゲノム調査を早期警戒システムとして利用し、将来問題となる可能性のある耐性について科学者に警告するものです。この情報をもとに、開発中の抗生物質を積極的に最適化し、微生物という敵に対してより強靭なものにすることができます。このPNAS論文のタイトルは「Environmental Resistome–Guided Development of Resistance-Tolerant Antibiotics(環境レジストームに導かれた耐性克服型抗生物質の開発)」です。
「私たちは、将来問題となりそうな耐性の種類を予測しているのです」と、ロックフェラー大学のショーン・F・ブレイディ氏(Sean F. Brady)の研究室に所属する筆頭著者のジェームズ・ピーク氏(James Peek)は言います。「私たちのプラットフォームが、抗生物質の臨床的寿命を延ばす一助となることを願
メタボの病態ネットワークを解明!マイクロRNAが操る「AGE/RAGE経路」の謎
 肥満、高血圧、糖尿病...。多くの現代人を悩ませるメタボリックシンドローム。これらの病気が体内でどのように連鎖していくのか、その鍵を握る「AGE/RAGE経路」という重要な仕組みがあります。そして今回、この仕組みの暴走をコントロールする極小の分子「マイクロRNA」の役割を、全く新しい手法で解き明かした画期的な研究が発表されました。複雑な病気のネットワークを理解し、新たな治療法を切り拓くヒントがここにあります。
腹部肥満、高血圧、脂質異常症、インスリン抵抗性を特徴とするメタボリックシンドロームは、その有病率が世界的に増加しており、深刻な健康危機となっています。2型糖尿病、非アルコール性脂肪性肝疾患、アテローム性動脈硬化、多嚢胞性卵巣症候群(といったMetSの併存疾患は、根底にある分子的経路を共有しています。その中でも、終末糖化産物受容体とそのリガンド(終末糖化産物(AGEs)、HMGB1、S100タンパク質)から成るAGE/RAGE経路は、MetSにおける炎症、酸化ストレス、組織損傷の主要な駆動因子です。この経路を標的とすることは有望な治療戦略ですが、その調節不全におけるマイクロRNAの役割は十分に理解されていませんでした。
2025年6月30日に学術誌「Gene Expression」に掲載されたこの総説論文は、MetSにおけるAGE/RAGE経路のmiRNAを介した調節不全を体系的にマッピングしたものです。この研究では、従来の文献レビューの限界を克服するため、新しい二重手法アプローチが採用されました。論文のタイトルは「miRNA Dysregulation of AGE/RAGE Pathway in Metabolic Syndrome: A Novel Analysis Strategy Utilizing miRNA-profiling Data(メタボリッ
肥満、高血圧、糖尿病...。多くの現代人を悩ませるメタボリックシンドローム。これらの病気が体内でどのように連鎖していくのか、その鍵を握る「AGE/RAGE経路」という重要な仕組みがあります。そして今回、この仕組みの暴走をコントロールする極小の分子「マイクロRNA」の役割を、全く新しい手法で解き明かした画期的な研究が発表されました。複雑な病気のネットワークを理解し、新たな治療法を切り拓くヒントがここにあります。
腹部肥満、高血圧、脂質異常症、インスリン抵抗性を特徴とするメタボリックシンドロームは、その有病率が世界的に増加しており、深刻な健康危機となっています。2型糖尿病、非アルコール性脂肪性肝疾患、アテローム性動脈硬化、多嚢胞性卵巣症候群(といったMetSの併存疾患は、根底にある分子的経路を共有しています。その中でも、終末糖化産物受容体とそのリガンド(終末糖化産物(AGEs)、HMGB1、S100タンパク質)から成るAGE/RAGE経路は、MetSにおける炎症、酸化ストレス、組織損傷の主要な駆動因子です。この経路を標的とすることは有望な治療戦略ですが、その調節不全におけるマイクロRNAの役割は十分に理解されていませんでした。
2025年6月30日に学術誌「Gene Expression」に掲載されたこの総説論文は、MetSにおけるAGE/RAGE経路のmiRNAを介した調節不全を体系的にマッピングしたものです。この研究では、従来の文献レビューの限界を克服するため、新しい二重手法アプローチが採用されました。論文のタイトルは「miRNA Dysregulation of AGE/RAGE Pathway in Metabolic Syndrome: A Novel Analysis Strategy Utilizing miRNA-profiling Data(メタボリッ
あなたの「体内年齢」を予測!RNAで老化を測る新指標『TraMA』登場
 上の年齢と、体の本当の「生物学的年齢」が違うことはご存知ですか?もし、血液中の遺伝子の働きから、あなたの将来の健康リスクや死亡率まで予測できるとしたらどうでしょう。最新の研究が、そんな未来を可能にするかもしれない新しい「老化のものさし」を開発しました。「TraMAは、健康と老化の根底にある生物学的プロセスを理解することに関心のある研究者や、健康と老化に関する社会的、心理的、疫学的、人口統計学的な研究にとって、特に価値が高いと考えられます。」
2025年6月13日、学術誌「Aging (Aging-US)」の第17巻第6号に、「Development of a Novel Transcriptomic Measure of Aging: Transcriptomic Mortality-Risk Age (TraMA)(老化の新たなトランスクリプトーム尺度の開発:トランスクリプトーム死亡リスク年齢)」と題された新しいオープンアクセス論文が掲載されました。南カリフォルニア大学のエリック・T・クロパック氏(Eric T. Klopack)が主導したこの研究で、研究者たちは健康リスクと死亡率を予測する、リボ核酸に基づく新しい老化の尺度を作成しました。トランスクリプトーム死亡リスク年齢と名付けられたこの尺度は、遺伝子発現データを用いて個人の生物学的年齢を推定します。この発見は、特に高齢者の老化を追跡し、健康リスクを理解するための、新しく、より正確な方法を提供するものです。
老化は、体内の複数のシステムに影響を与え、病気や死亡のリスクを高める複雑な生物学的プロセスです。科学者たちは長年、生物学的年齢を測定する信頼性の高い方法を探求してきました。DNAメチル化や血液バイオマーカーが一般的に使用されていますが、この研究では遺伝子の活動を反映する分子であるRNAに焦点を当
上の年齢と、体の本当の「生物学的年齢」が違うことはご存知ですか?もし、血液中の遺伝子の働きから、あなたの将来の健康リスクや死亡率まで予測できるとしたらどうでしょう。最新の研究が、そんな未来を可能にするかもしれない新しい「老化のものさし」を開発しました。「TraMAは、健康と老化の根底にある生物学的プロセスを理解することに関心のある研究者や、健康と老化に関する社会的、心理的、疫学的、人口統計学的な研究にとって、特に価値が高いと考えられます。」
2025年6月13日、学術誌「Aging (Aging-US)」の第17巻第6号に、「Development of a Novel Transcriptomic Measure of Aging: Transcriptomic Mortality-Risk Age (TraMA)(老化の新たなトランスクリプトーム尺度の開発:トランスクリプトーム死亡リスク年齢)」と題された新しいオープンアクセス論文が掲載されました。南カリフォルニア大学のエリック・T・クロパック氏(Eric T. Klopack)が主導したこの研究で、研究者たちは健康リスクと死亡率を予測する、リボ核酸に基づく新しい老化の尺度を作成しました。トランスクリプトーム死亡リスク年齢と名付けられたこの尺度は、遺伝子発現データを用いて個人の生物学的年齢を推定します。この発見は、特に高齢者の老化を追跡し、健康リスクを理解するための、新しく、より正確な方法を提供するものです。
老化は、体内の複数のシステムに影響を与え、病気や死亡のリスクを高める複雑な生物学的プロセスです。科学者たちは長年、生物学的年齢を測定する信頼性の高い方法を探求してきました。DNAメチル化や血液バイオマーカーが一般的に使用されていますが、この研究では遺伝子の活動を反映する分子であるRNAに焦点を当
伝統生薬ベニバナの力!サフラワー黄色素が心臓病を多角的に治療するメカニズム
 古くから染料や生薬として親しまれてきた「ベニバナ」。その鮮やかな黄色い色素に、現代人の命を脅かす心臓病を治療する驚くべき力が秘められていることが、最新の研究で明らかになりつつあります。伝統医学の知恵が、科学の力でどのように解き明かされ、未来の医療を切り拓くのか。その最前線に迫ります。アテローム性動脈硬化による心筋虚血を特徴とする冠状動脈性心疾患は、中国において依然として主要な死亡原因です。ベニバナ(学名: Carthamus tinctorius L.)の主要な生理活性成分であるサフラワー黄色素(SYPs: Safflower yellow pigments)は、主にキノカルコンC-グリコシドから構成され、ヒドロキシサフロル黄色素A(HSYA: hydroxysafflor yellow A)とアンヒドロサフロル黄色素B(AHSYB: anhydrosafflor yellow B)を主成分としています。
2025年6月に学術誌「Future Integrative Medicine」に掲載されたこの総説論文は、CHD管理におけるSYPsの作用機序、治療応用、そして将来の方向性に関するエビデンスを統合したものです。
化学組成と体内動態
SYPsは、HSYAやAHSYBを含む20以上の同定された化合物で構成されており、これらが心血管保護作用、抗炎症作用、抗酸化作用をもたらします。薬物動態学的研究によると、消化管での加水分解、低い膜透過性、肝臓での初回通過効果のため、経口での生物学的利用能は非常に低い(HSYA: 1.2%; AHSYB: 0.3%)ことが明らかになっています。HSYAは各臓器に広く分布し(腎臓 > 肝臓 > 肺 > 心臓)、代謝されて糞便(経口投与時)または尿(静脈内投与時)を介して排泄されます。
CHD治療におけるサ
古くから染料や生薬として親しまれてきた「ベニバナ」。その鮮やかな黄色い色素に、現代人の命を脅かす心臓病を治療する驚くべき力が秘められていることが、最新の研究で明らかになりつつあります。伝統医学の知恵が、科学の力でどのように解き明かされ、未来の医療を切り拓くのか。その最前線に迫ります。アテローム性動脈硬化による心筋虚血を特徴とする冠状動脈性心疾患は、中国において依然として主要な死亡原因です。ベニバナ(学名: Carthamus tinctorius L.)の主要な生理活性成分であるサフラワー黄色素(SYPs: Safflower yellow pigments)は、主にキノカルコンC-グリコシドから構成され、ヒドロキシサフロル黄色素A(HSYA: hydroxysafflor yellow A)とアンヒドロサフロル黄色素B(AHSYB: anhydrosafflor yellow B)を主成分としています。
2025年6月に学術誌「Future Integrative Medicine」に掲載されたこの総説論文は、CHD管理におけるSYPsの作用機序、治療応用、そして将来の方向性に関するエビデンスを統合したものです。
化学組成と体内動態
SYPsは、HSYAやAHSYBを含む20以上の同定された化合物で構成されており、これらが心血管保護作用、抗炎症作用、抗酸化作用をもたらします。薬物動態学的研究によると、消化管での加水分解、低い膜透過性、肝臓での初回通過効果のため、経口での生物学的利用能は非常に低い(HSYA: 1.2%; AHSYB: 0.3%)ことが明らかになっています。HSYAは各臓器に広く分布し(腎臓 > 肝臓 > 肺 > 心臓)、代謝されて糞便(経口投与時)または尿(静脈内投与時)を介して排泄されます。
CHD治療におけるサ
アルツハイマー病の新発見。脳細胞間の「メッセージ」不足が原因の可能性
 私たちの脳内では、細胞同士が絶えず「会話」を交わすことで、その健康が保たれています。そのコミュニケーションに使われるのが、「エクソソーム」と呼ばれる、目には見えないほど小さなメッセージカプセルです。もし、この重要な情報のやり取りが滞ってしまったら、脳では一体何が起こるのでしょうか。この度、デンマークとドイツの研究チームが、まさにこの細胞間のコミュニケーション不全がアルツハイマー病の発症に深く関わっている可能性を突き止めました。認知症患者に見られる特定の遺伝子変異が、この「エクソソーム」の生産に深刻な欠陥を引き起こしていたのです。この画期的な発見は、アルツハイマー病の謎を解き明かし、全く新しい治療法開発への扉を開くかもしれません。
デンマークのオーフス大学とドイツのマックス・デルブリュック分子医学センターの共同研究者たちは、認知症患者に見られる遺伝子変異に関連して、細胞における「エクソソーム」の生産に欠陥があることを特定しました。
それらは極小の粒子ですが、人間にとっては巨大な意味を持つ可能性があります。オーフス大学とマックス・デルブリュック分子医学センターの研究者たちは、認知症患者に見られる遺伝子変異に関連して、細胞における「エクソソーム」の生産に欠陥があることを特定しました。これは、アルツハイマー病の発症、そしておそらくは治療法についての理解を深めることにつながる可能性があります。
エクソソームは microscopic(微細)の典型です。米粒の先端だけで数百万個に相当するほど小さいのです。にもかかわらず、オーフス大学生物医学部の新しい研究は、それらがアルツハイマー病の発症に重要な役割を果たしている可能性を示しています。助教のクリスチャン・ユール-マドセン氏(Kristian Juul-Madsen)は、科学誌Alzheimer’s & Dementi
私たちの脳内では、細胞同士が絶えず「会話」を交わすことで、その健康が保たれています。そのコミュニケーションに使われるのが、「エクソソーム」と呼ばれる、目には見えないほど小さなメッセージカプセルです。もし、この重要な情報のやり取りが滞ってしまったら、脳では一体何が起こるのでしょうか。この度、デンマークとドイツの研究チームが、まさにこの細胞間のコミュニケーション不全がアルツハイマー病の発症に深く関わっている可能性を突き止めました。認知症患者に見られる特定の遺伝子変異が、この「エクソソーム」の生産に深刻な欠陥を引き起こしていたのです。この画期的な発見は、アルツハイマー病の謎を解き明かし、全く新しい治療法開発への扉を開くかもしれません。
デンマークのオーフス大学とドイツのマックス・デルブリュック分子医学センターの共同研究者たちは、認知症患者に見られる遺伝子変異に関連して、細胞における「エクソソーム」の生産に欠陥があることを特定しました。
それらは極小の粒子ですが、人間にとっては巨大な意味を持つ可能性があります。オーフス大学とマックス・デルブリュック分子医学センターの研究者たちは、認知症患者に見られる遺伝子変異に関連して、細胞における「エクソソーム」の生産に欠陥があることを特定しました。これは、アルツハイマー病の発症、そしておそらくは治療法についての理解を深めることにつながる可能性があります。
エクソソームは microscopic(微細)の典型です。米粒の先端だけで数百万個に相当するほど小さいのです。にもかかわらず、オーフス大学生物医学部の新しい研究は、それらがアルツハイマー病の発症に重要な役割を果たしている可能性を示しています。助教のクリスチャン・ユール-マドセン氏(Kristian Juul-Madsen)は、科学誌Alzheimer’s & Dementi
あなたの糖尿病薬は大丈夫?グリピジドの心血管リスクを最新研究が解明
 糖尿病の治療で毎日飲んでいるその薬、本当に安全でしょうか?広く使われているある薬が、心臓病のリスクを高める可能性があるという、少し気になる研究結果が報告されました。あなたの健康を守るために知っておくべき、最新の情報をお届けします。マス・ジェネラル・ブリガムとその共同研究者たちによる新しい研究で、広く使用されている2型糖尿病治療薬「グリピジド」が、他の作用機序を持つ薬と比較して心臓関連疾患の発生率が高いことと関連している可能性が示唆されました。この研究は、異なるスルホニル尿素薬で治療された約5万人の患者の全米データを調査したもので、このクラスの中で米国で最も広く使用されているグリピジドが、ジペプチジルペプチダーゼ-4阻害薬と比較して、心不全、関連する入院、および死亡の発生率の上昇と関連していることを見出しました。
この研究結果は、2025年7月24日付の「JAMA Network Open」に掲載されました。論文のタイトルは「Cardiovascular Events in Individuals Treated with Sulfonylureas or Dipeptidyl Peptidase 4 Inhibitors(スルホニル尿素薬またはジペプチジルペプチダーゼ4阻害薬で治療された個人の心血管イベント)」です。
「2型糖尿病の患者さんは、脳卒中や心停止といった心血管系の有害事象のリスクが高まっています」と、マス・ジェネラル・ブリガム医療システムの一員であるブリガム・アンド・ウィメンズ病院内分泌科の責任著者、アレクサンダー・ターチン医学博士(Alexander Turchin, MD, MS)は述べています。「スルホニル尿素薬は一般的で手頃な価格の糖尿病治療薬ですが、心臓の健康に対してより中立的な代替薬であるDPP-4阻害薬と比較して、長期的にどのような影響を与
糖尿病の治療で毎日飲んでいるその薬、本当に安全でしょうか?広く使われているある薬が、心臓病のリスクを高める可能性があるという、少し気になる研究結果が報告されました。あなたの健康を守るために知っておくべき、最新の情報をお届けします。マス・ジェネラル・ブリガムとその共同研究者たちによる新しい研究で、広く使用されている2型糖尿病治療薬「グリピジド」が、他の作用機序を持つ薬と比較して心臓関連疾患の発生率が高いことと関連している可能性が示唆されました。この研究は、異なるスルホニル尿素薬で治療された約5万人の患者の全米データを調査したもので、このクラスの中で米国で最も広く使用されているグリピジドが、ジペプチジルペプチダーゼ-4阻害薬と比較して、心不全、関連する入院、および死亡の発生率の上昇と関連していることを見出しました。
この研究結果は、2025年7月24日付の「JAMA Network Open」に掲載されました。論文のタイトルは「Cardiovascular Events in Individuals Treated with Sulfonylureas or Dipeptidyl Peptidase 4 Inhibitors(スルホニル尿素薬またはジペプチジルペプチダーゼ4阻害薬で治療された個人の心血管イベント)」です。
「2型糖尿病の患者さんは、脳卒中や心停止といった心血管系の有害事象のリスクが高まっています」と、マス・ジェネラル・ブリガム医療システムの一員であるブリガム・アンド・ウィメンズ病院内分泌科の責任著者、アレクサンダー・ターチン医学博士(Alexander Turchin, MD, MS)は述べています。「スルホニル尿素薬は一般的で手頃な価格の糖尿病治療薬ですが、心臓の健康に対してより中立的な代替薬であるDPP-4阻害薬と比較して、長期的にどのような影響を与
AIは科学をどう変えるか?Caltech発、数学から気候、創薬まで最前線レポート
 純粋数学という、人間の思考の最も深遠な領域。そこにAIが足を踏み入れたら何が起こるのか?約5年前、ある数学者が、純粋にその可能性を探るため、人工知能の基礎であるニューラルネットワークの構築を独学で始めました。彼は当初、純粋数学が問いかける極めて複雑な問題は、AIの情報処理能力の範囲外だろうと懐疑的だったと認めています。しかし今日、彼はもはや懐疑論者ではありません。
「純粋数学の研究者というと、屋根裏部屋に座って、他の人間にはおろか、機械には到底理解できないような難解な定理を証明している人物を思い浮かべがちです」と語るのは、カリフォルニア工科大学(Caltech)の理論物理学・数学のジョン・D・マッカーサー教授であるセルゲイ・グコフ氏(Sergei Gukov)です。彼は、AIが自身の研究分野には無関係であることを示すつもりでニューラルネットワークを学び始めましたが、その過程で全く逆の結論にたどり着いたのです。
AIは数学というゲームをどうプレイするか
なぜAIが純粋数学の役に立つのかを理解するには、難解な数学問題を解くことを一種のゲームと捉えることが重要だとグコフ氏は言います。これらの問題には、数学者が真実であるべきだと信じる主張が含まれており、彼らの挑戦はその主張が真実であることを証明することです。つまり、これらの問題は本質的にA地点からB地点への道筋を探す探索なのです。「私たちは仮説を知っていて、ゴールもわかっています。しかし、それらをつなぐものが欠けているのです」と彼は言います。
これらの問題を非常に難しくしているのは、AからBへのステップ数です。平均的なチェスの試合が30〜40手で終わるのに対し、これらの問題の解決には100万以上のステップ、つまり「手」が必要となる場合があります。ニューラルネットワークを研究した後、グコフ氏は、AIが自身と対戦する
純粋数学という、人間の思考の最も深遠な領域。そこにAIが足を踏み入れたら何が起こるのか?約5年前、ある数学者が、純粋にその可能性を探るため、人工知能の基礎であるニューラルネットワークの構築を独学で始めました。彼は当初、純粋数学が問いかける極めて複雑な問題は、AIの情報処理能力の範囲外だろうと懐疑的だったと認めています。しかし今日、彼はもはや懐疑論者ではありません。
「純粋数学の研究者というと、屋根裏部屋に座って、他の人間にはおろか、機械には到底理解できないような難解な定理を証明している人物を思い浮かべがちです」と語るのは、カリフォルニア工科大学(Caltech)の理論物理学・数学のジョン・D・マッカーサー教授であるセルゲイ・グコフ氏(Sergei Gukov)です。彼は、AIが自身の研究分野には無関係であることを示すつもりでニューラルネットワークを学び始めましたが、その過程で全く逆の結論にたどり着いたのです。
AIは数学というゲームをどうプレイするか
なぜAIが純粋数学の役に立つのかを理解するには、難解な数学問題を解くことを一種のゲームと捉えることが重要だとグコフ氏は言います。これらの問題には、数学者が真実であるべきだと信じる主張が含まれており、彼らの挑戦はその主張が真実であることを証明することです。つまり、これらの問題は本質的にA地点からB地点への道筋を探す探索なのです。「私たちは仮説を知っていて、ゴールもわかっています。しかし、それらをつなぐものが欠けているのです」と彼は言います。
これらの問題を非常に難しくしているのは、AからBへのステップ数です。平均的なチェスの試合が30〜40手で終わるのに対し、これらの問題の解決には100万以上のステップ、つまり「手」が必要となる場合があります。ニューラルネットワークを研究した後、グコフ氏は、AIが自身と対戦する
エボラ治療の新たな標的:CRISPRと画像解析でウイルスの「協力者」を特定
 致死率が高く、治療法も限られているエボラウイルス。この恐ろしい敵と戦うための新しい戦略は、ウイルスそのものではなく、私たちの細胞の中に隠された「協力者」を無力化することかもしれません。最先端のイメージング技術、遺伝子スクリーニング、そして機械学習を組み合わせることで、研究者たちはエボラウイルスの感染能力を変えてしまう、ヒトの細胞内の新たな因子を発見しました。
エボラウイルスの発生は稀ですが、その病状は重く、しばしば死に至るため、治療の選択肢はほとんどありません。ウイルス自体を標的とするのではなく、ウイルスが感染・増殖するために利用するヒトの宿主細胞内のタンパク質の働きを妨害するという治療法が有望視されています。しかし、既存の方法でウイルスの感染を制御する因子を見つけることは難しく、特にエボラのような最も危険なウイルスでは、厳格なバイオセーフティ対策が施された施設での実験が必要となるため、なおさら困難でした。
今回、ブロード研究所とボストン大学の米国新興感染症研究所の研究者たちは、ブロード研究所で開発された画像ベースのスクリーニング法を用いて、その働きを抑制するとエボラウイルスの感染能力を損なうヒトの遺伝子を特定しました。この手法はオプティカル・プール・スクリーニングとして知られ、これにより科学者たちは、CRISPR技術で遺伝子操作された約4000万個のヒト細胞を使い、ヒトゲノムの各遺伝子を抑制することがウイルスの複製にどう影響するかを検証することができたのです。
機械学習を用いた細胞画像の解析により、研究チームはエボラウイルス感染の様々な段階に関与する複数の宿主タンパク質を特定し、それらを抑制するとウイルスの複製能力が著しく低下することを発見しました。これらのウイルス制御因子は、いつの日か治療的に介入し、すでにウイルスに感染した人々の重症度を軽減するための道筋を示
致死率が高く、治療法も限られているエボラウイルス。この恐ろしい敵と戦うための新しい戦略は、ウイルスそのものではなく、私たちの細胞の中に隠された「協力者」を無力化することかもしれません。最先端のイメージング技術、遺伝子スクリーニング、そして機械学習を組み合わせることで、研究者たちはエボラウイルスの感染能力を変えてしまう、ヒトの細胞内の新たな因子を発見しました。
エボラウイルスの発生は稀ですが、その病状は重く、しばしば死に至るため、治療の選択肢はほとんどありません。ウイルス自体を標的とするのではなく、ウイルスが感染・増殖するために利用するヒトの宿主細胞内のタンパク質の働きを妨害するという治療法が有望視されています。しかし、既存の方法でウイルスの感染を制御する因子を見つけることは難しく、特にエボラのような最も危険なウイルスでは、厳格なバイオセーフティ対策が施された施設での実験が必要となるため、なおさら困難でした。
今回、ブロード研究所とボストン大学の米国新興感染症研究所の研究者たちは、ブロード研究所で開発された画像ベースのスクリーニング法を用いて、その働きを抑制するとエボラウイルスの感染能力を損なうヒトの遺伝子を特定しました。この手法はオプティカル・プール・スクリーニングとして知られ、これにより科学者たちは、CRISPR技術で遺伝子操作された約4000万個のヒト細胞を使い、ヒトゲノムの各遺伝子を抑制することがウイルスの複製にどう影響するかを検証することができたのです。
機械学習を用いた細胞画像の解析により、研究チームはエボラウイルス感染の様々な段階に関与する複数の宿主タンパク質を特定し、それらを抑制するとウイルスの複製能力が著しく低下することを発見しました。これらのウイルス制御因子は、いつの日か治療的に介入し、すでにウイルスに感染した人々の重症度を軽減するための道筋を示
心の病の根源は胎児期に?最新研究が解き明かす脳発達の謎
 心の健康に関する悩みや、アルツハイマー病のような脳の病気。その根源は、私たちが生まれるずっと前、母親のお腹の中にいた頃の、脳が形作られ始めるまさにその瞬間に隠されているのかもしれません。最新の研究が、これまで考えられていたよりもさらに遡った胎児期の脳発達の初期段階に、その起源がある可能性を明らかにしました。これは、私たちの脳と心の健康についての理解を、根底から変えるかもしれない発見です。
この画期的な研究は、バルセロナのデル・マール病院研究所とイェール大学の共同チームによるもので、2025年7月9日付の科学誌「Nature Communications」に掲載されました。研究論文のタイトルは「Early Developmental Origins of Cortical Disorders Modeled in Human Neural Stem Cells(ヒト神経幹細胞でモデル化された皮質障害の初期発生起源)」です。
この研究は、「精神疾患の起源を、胎児期の発達、特に脳の幹細胞という最も初期の段階に探すことに焦点を当てました」と、デル・マール病院研究所の生物医学情報研究プログラム神経ゲノミクス研究グループのコーディネーターであるガブリエル・サントペレ博士(Dr. Gabriel Santpere)は説明します。研究チームは、精神神経疾患、神経変性疾患、皮質形成異常に関連する約3,000の遺伝子リストを用い、これらの遺伝子の変化が脳の発達に関わる細胞にどのような影響を与えるかをシミュレーションしました。その結果、これらの遺伝子の多くが、脳を構築する前駆細胞である幹細胞の段階、つまりニューロンやその支持構造が作られる胎児期のごく初期の段階で、すでに機能していることが示されたのです。
しかし、この成果にたどり着くのは容易ではありませんでした。脳が発達するこの時期を研
心の健康に関する悩みや、アルツハイマー病のような脳の病気。その根源は、私たちが生まれるずっと前、母親のお腹の中にいた頃の、脳が形作られ始めるまさにその瞬間に隠されているのかもしれません。最新の研究が、これまで考えられていたよりもさらに遡った胎児期の脳発達の初期段階に、その起源がある可能性を明らかにしました。これは、私たちの脳と心の健康についての理解を、根底から変えるかもしれない発見です。
この画期的な研究は、バルセロナのデル・マール病院研究所とイェール大学の共同チームによるもので、2025年7月9日付の科学誌「Nature Communications」に掲載されました。研究論文のタイトルは「Early Developmental Origins of Cortical Disorders Modeled in Human Neural Stem Cells(ヒト神経幹細胞でモデル化された皮質障害の初期発生起源)」です。
この研究は、「精神疾患の起源を、胎児期の発達、特に脳の幹細胞という最も初期の段階に探すことに焦点を当てました」と、デル・マール病院研究所の生物医学情報研究プログラム神経ゲノミクス研究グループのコーディネーターであるガブリエル・サントペレ博士(Dr. Gabriel Santpere)は説明します。研究チームは、精神神経疾患、神経変性疾患、皮質形成異常に関連する約3,000の遺伝子リストを用い、これらの遺伝子の変化が脳の発達に関わる細胞にどのような影響を与えるかをシミュレーションしました。その結果、これらの遺伝子の多くが、脳を構築する前駆細胞である幹細胞の段階、つまりニューロンやその支持構造が作られる胎児期のごく初期の段階で、すでに機能していることが示されたのです。
しかし、この成果にたどり着くのは容易ではありませんでした。脳が発達するこの時期を研
失った視力を取り戻す鍵は「リンゴガイ」に?眼を完全再生する驚異の能力を解明
 失った視力を取り戻す鍵は「カタツムリ」に?眼を完全再生する驚異の能力から学ぶ再生医療の未来
一度失われると二度と元には戻らない、複雑でかけがえのない人間の眼。しかし、淡水に生息するリンゴガイ(apple snail)は、私たちと非常によく似た構造の眼を持ちながら、それを完全に再生させる驚異的な能力を持っています。
この不思議な能力の謎を解き明かし、将来的には人間の視力回復に応用することを目指しているのが、カリフォルニア大学デービス校 分子細胞生物学部の助教、アリス・アコルシ博士(Alice Accorsi, PhD)です。2025年8月6日に『Nature Communications』誌で発表された新しい研究で、アコルシ博士はリンゴガイと人間の眼が、解剖学的にも遺伝的にも多くの特徴を共有していることを明らかにしました。このオープンアクセスの論文は、「A Genetically Tractable Non-Vertebrate System to Study Complete Camera-Type Eye Regeneration(カメラ眼の完全な再生を研究するための遺伝学的に扱いやすい非脊椎動物システム)」と題されています。
「リンゴガイは並外れた生物です」とアコルシ博士は語ります。「彼らは、複雑な感覚器官の再生を研究するまたとない機会を提供してくれます。これまでは、眼全体の再生を研究するための適切なモデル生物がいませんでした。」彼女の研究チームはまた、リンゴガイのゲノム編集技術も開発し、これにより眼の再生の背景にある遺伝的・分子的メカニズムの探求が可能になります。
カタツムリらしからぬ、驚異的な繁殖力
ゴールデンアップルスネイル(学名: Pomacea canaliculata)は南米原産の淡水性の巻貝です。現在では世界の多くの地域で侵略的外来種と
失った視力を取り戻す鍵は「カタツムリ」に?眼を完全再生する驚異の能力から学ぶ再生医療の未来
一度失われると二度と元には戻らない、複雑でかけがえのない人間の眼。しかし、淡水に生息するリンゴガイ(apple snail)は、私たちと非常によく似た構造の眼を持ちながら、それを完全に再生させる驚異的な能力を持っています。
この不思議な能力の謎を解き明かし、将来的には人間の視力回復に応用することを目指しているのが、カリフォルニア大学デービス校 分子細胞生物学部の助教、アリス・アコルシ博士(Alice Accorsi, PhD)です。2025年8月6日に『Nature Communications』誌で発表された新しい研究で、アコルシ博士はリンゴガイと人間の眼が、解剖学的にも遺伝的にも多くの特徴を共有していることを明らかにしました。このオープンアクセスの論文は、「A Genetically Tractable Non-Vertebrate System to Study Complete Camera-Type Eye Regeneration(カメラ眼の完全な再生を研究するための遺伝学的に扱いやすい非脊椎動物システム)」と題されています。
「リンゴガイは並外れた生物です」とアコルシ博士は語ります。「彼らは、複雑な感覚器官の再生を研究するまたとない機会を提供してくれます。これまでは、眼全体の再生を研究するための適切なモデル生物がいませんでした。」彼女の研究チームはまた、リンゴガイのゲノム編集技術も開発し、これにより眼の再生の背景にある遺伝的・分子的メカニズムの探求が可能になります。
カタツムリらしからぬ、驚異的な繁殖力
ゴールデンアップルスネイル(学名: Pomacea canaliculata)は南米原産の淡水性の巻貝です。現在では世界の多くの地域で侵略的外来種と
働きすぎると酵素もストライキ?β-カロテンが解決の鍵に!
 私たちの体内で起こる代謝から、植物の成長、さらには工業製品の生産に至るまで、酵素は数え切れないほどの生命活動や化学プロセスを支える重要な働きをしています。しかし、そんな働き者の酵素の中には、仕事を与えすぎるとかえって働きが鈍ってしまう、少し変わった性質を持つものがいることをご存知でしょうか。この「基質阻害」として知られる現象は、医薬品の効果や工業プロセスの効率を妨げる可能性があり、長年の謎でした。
しかしこの度、ミュンヘン工科大学(TUM)の研究者たちがこのメカニズムの一端を解明し、ニンジンなどに含まれるβ-カロテンがその解決策になる可能性を発見しました。この研究成果は、2025年3月29日付の Nature Communications 誌に掲載されたオープンアクセス論文、「β-Carotene Alleviates Substrate Inhibition Caused by Asymmetric Cooperativity(β-カロテンは非対称的な協同性によって引き起こされる基質阻害を緩和する)」で発表されました。
酵素は、私たちの衣服を洗い、消化を助け、パンを膨らませるなど、日常生活の様々な場面で活躍しています。通常、酵素は処理すべき対象(基質)が増えれば増えるほど、その活性も高まります。しかし、知られている酵素の約20%は異なる挙動を示します。一度にあまりにも多くの分子に囲まれると、その働きを遅らせたり、時には完全に停止してしまったりするのです。
これまで、基質阻害のメカニズムは十分に理解されていませんでした。科学者たちは、これが細胞内の調節機能の一つだと考えていますが、時には裏目に出ることもあります。「特定の薬剤を用いた実験では、基質阻害が医薬品の作用に影響を与える可能性が示唆されています」と、TUMの天然物バイオテクノロジーの教授であるヴィルフリート
私たちの体内で起こる代謝から、植物の成長、さらには工業製品の生産に至るまで、酵素は数え切れないほどの生命活動や化学プロセスを支える重要な働きをしています。しかし、そんな働き者の酵素の中には、仕事を与えすぎるとかえって働きが鈍ってしまう、少し変わった性質を持つものがいることをご存知でしょうか。この「基質阻害」として知られる現象は、医薬品の効果や工業プロセスの効率を妨げる可能性があり、長年の謎でした。
しかしこの度、ミュンヘン工科大学(TUM)の研究者たちがこのメカニズムの一端を解明し、ニンジンなどに含まれるβ-カロテンがその解決策になる可能性を発見しました。この研究成果は、2025年3月29日付の Nature Communications 誌に掲載されたオープンアクセス論文、「β-Carotene Alleviates Substrate Inhibition Caused by Asymmetric Cooperativity(β-カロテンは非対称的な協同性によって引き起こされる基質阻害を緩和する)」で発表されました。
酵素は、私たちの衣服を洗い、消化を助け、パンを膨らませるなど、日常生活の様々な場面で活躍しています。通常、酵素は処理すべき対象(基質)が増えれば増えるほど、その活性も高まります。しかし、知られている酵素の約20%は異なる挙動を示します。一度にあまりにも多くの分子に囲まれると、その働きを遅らせたり、時には完全に停止してしまったりするのです。
これまで、基質阻害のメカニズムは十分に理解されていませんでした。科学者たちは、これが細胞内の調節機能の一つだと考えていますが、時には裏目に出ることもあります。「特定の薬剤を用いた実験では、基質阻害が医薬品の作用に影響を与える可能性が示唆されています」と、TUMの天然物バイオテクノロジーの教授であるヴィルフリート
ヤスデは人類の救世主?その分泌物から神経疾患の新薬候補を発見
 足がたくさんあることから「気味が悪い生き物」として敬遠されがちなヤスデ。しかし、もしこのヤスデの分泌物が、神経疾患や痛みの治療に役立つ新薬開発の鍵を握っているとしたら、少し見方が変わるかもしれません。この度、バージニア工科大学の研究者と国立がん研究所の共同研究者が、ヤスデの分泌物に含まれる、これまで知られていなかった複雑な構造を持つ新しい化合物を発見しました。この発見は、私たちの未来の医療に大きな光を当てる可能性があります。
化学者のエミリー・メヴァース博士(Emily Mevers, PhD)が率いる研究チームは、この新発見の化合物が、アリの脳に存在する特定の神経受容体を調節する機能を持つことを突き止めました。この化合物は、自然界に存在するアルカロイドと呼ばれる物質群に分類されます。研究チームは、この化合物を発見したヤスデの種類「Andrognathus corticarius」にちなんで、「アンドログナタノール」および「アンドログナチン」と名付けました。このヤスデは、バージニア工科大学のブラックスバーグキャンパス内にあるスタジアムウッズで発見されたものです。
これらの画期的な発見は、2025年7月17日付の Journal of the American Chemical Society(米国化学会誌)に掲載されたオープンアクセス論文、「The Discovery of Complex Heterocycles from Millipede Secretions(ヤスデの分泌物からの複雑な複素環式化合物の発見)」で詳述されています。
新しい化合物の発見
メヴァース博士は、創薬という目標を掲げ、これまであまり研究されてこなかった生態学的ニッチ、今回の場合はヤスデが持つ化学的性質の解明を専門としています。
メヴァース博士と研究チームは、スタジアムウッズの
足がたくさんあることから「気味が悪い生き物」として敬遠されがちなヤスデ。しかし、もしこのヤスデの分泌物が、神経疾患や痛みの治療に役立つ新薬開発の鍵を握っているとしたら、少し見方が変わるかもしれません。この度、バージニア工科大学の研究者と国立がん研究所の共同研究者が、ヤスデの分泌物に含まれる、これまで知られていなかった複雑な構造を持つ新しい化合物を発見しました。この発見は、私たちの未来の医療に大きな光を当てる可能性があります。
化学者のエミリー・メヴァース博士(Emily Mevers, PhD)が率いる研究チームは、この新発見の化合物が、アリの脳に存在する特定の神経受容体を調節する機能を持つことを突き止めました。この化合物は、自然界に存在するアルカロイドと呼ばれる物質群に分類されます。研究チームは、この化合物を発見したヤスデの種類「Andrognathus corticarius」にちなんで、「アンドログナタノール」および「アンドログナチン」と名付けました。このヤスデは、バージニア工科大学のブラックスバーグキャンパス内にあるスタジアムウッズで発見されたものです。
これらの画期的な発見は、2025年7月17日付の Journal of the American Chemical Society(米国化学会誌)に掲載されたオープンアクセス論文、「The Discovery of Complex Heterocycles from Millipede Secretions(ヤスデの分泌物からの複雑な複素環式化合物の発見)」で詳述されています。
新しい化合物の発見
メヴァース博士は、創薬という目標を掲げ、これまであまり研究されてこなかった生態学的ニッチ、今回の場合はヤスデが持つ化学的性質の解明を専門としています。
メヴァース博士と研究チームは、スタジアムウッズの
遺伝的に同じマウスの個体差、エピジェネティクスは主因ではなかった?
 遺伝子情報は全く同じはずなのに、なぜか一方は茶色でスリム、もう一方は黄色で肥満。そんな不思議なマウスが存在します。この違いを生むカギとして、長年「エピジェネティクス」という仕組みが注目されてきました。しかし、この常識を覆すかもしれない、驚きの研究結果が発表されました。20年以上にわたる謎に、ついに終止符が打たれるのでしょうか?
遺伝的に同一な「アグーチ生存黄」マウスの中には、茶色で痩せている個体もいれば、黄色で肥満の個体もいます。これらの違いは、エピジェネティクスによるものです。エピジェネティクスとは、発生の過程でDNAにメチル基などの分子タグが付加され、異なる細胞種での遺伝子発現を決定するシステムです。2003年のある研究では、メスマウスの妊娠前および妊娠中の食事に「メチル供与体」となる栄養素を補給するだけで、生まれてくるAvyマウスの多くが痩せた茶色の体になると示されました。Avy遺伝子は「メタステーブルエピエール」として知られています。これは、そのDNAメチル化のレベルが初期胚発生の段階でランダムに決まるためです。2003年の研究は、メタステーブルエピエールがマウスには一般的に存在する可能性があり、近交系マウスの間で見られる説明のつかない多くのばらつき(例えば、高脂肪食を与えた際の体重増加の違いなど)を説明できるかもしれないという考えを提起しました。しかし、いくつかの小規模な研究はあったものの、マウスにおけるメタステーブルエピエールの数は20年以上にわたって不明なままでした。
しかし、それもこれまでです。
この度、ベイラー医科大学の小児栄養学教授であり、米国農務省/農業研究サービス(USDA/ARS)小児栄養研究センターおよびダンLダンカン総合がんセンターのメンバーである、責任著者のロバート・A・ウォーターランド博士(Dr. Robert A. Wate
遺伝子情報は全く同じはずなのに、なぜか一方は茶色でスリム、もう一方は黄色で肥満。そんな不思議なマウスが存在します。この違いを生むカギとして、長年「エピジェネティクス」という仕組みが注目されてきました。しかし、この常識を覆すかもしれない、驚きの研究結果が発表されました。20年以上にわたる謎に、ついに終止符が打たれるのでしょうか?
遺伝的に同一な「アグーチ生存黄」マウスの中には、茶色で痩せている個体もいれば、黄色で肥満の個体もいます。これらの違いは、エピジェネティクスによるものです。エピジェネティクスとは、発生の過程でDNAにメチル基などの分子タグが付加され、異なる細胞種での遺伝子発現を決定するシステムです。2003年のある研究では、メスマウスの妊娠前および妊娠中の食事に「メチル供与体」となる栄養素を補給するだけで、生まれてくるAvyマウスの多くが痩せた茶色の体になると示されました。Avy遺伝子は「メタステーブルエピエール」として知られています。これは、そのDNAメチル化のレベルが初期胚発生の段階でランダムに決まるためです。2003年の研究は、メタステーブルエピエールがマウスには一般的に存在する可能性があり、近交系マウスの間で見られる説明のつかない多くのばらつき(例えば、高脂肪食を与えた際の体重増加の違いなど)を説明できるかもしれないという考えを提起しました。しかし、いくつかの小規模な研究はあったものの、マウスにおけるメタステーブルエピエールの数は20年以上にわたって不明なままでした。
しかし、それもこれまでです。
この度、ベイラー医科大学の小児栄養学教授であり、米国農務省/農業研究サービス(USDA/ARS)小児栄養研究センターおよびダンLダンカン総合がんセンターのメンバーである、責任著者のロバート・A・ウォーターランド博士(Dr. Robert A. Wate
全ゲノムシーケンシングが解き明かす神経発達障害「ReNU症候群」の新事実
 お子さんの発達に気がかりな点があっても、検査を重ねても原因が分からない。そんな「診断がつかない」期間は、ご家族にとって長く辛い道のりです。しかし今、最先端の遺伝子解析技術が、これまで見つけられなかった原因を突き止め、長く続いた診断の旅に終わりをもたらす新たな光となっています。最新の発見は、ある神経発達障害の謎を解き明かす、重要な一歩となりました。
2025年7月25日、ベイラー・ジェネティクス社は、全ゲノムシーケンシングを用いて小児患者からRNU4-2遺伝子の病的バリアントを発見し、診断に至った事例についての調査結果を発表しました。ReNU症候群は、RNU4-2遺伝子の病的バリアントによって引き起こされる、2024年に新たに報告された神経発達障害です。この疾患に関連する症状には、全般的な発達遅延、知的障害、筋緊張低下、けいれん、脳の異常などがあります。ベイラー・ジェネティクス社は、第1回ReNU Hope科学シンポジウムにおいて、「Utility of Whole Genome Sequencing to Detect RNU4-2 Variants Associated with ReNU Syndrome(ReNU症候群に関連するRNU4-2バリアントを検出するための全ゲノムシーケンシングの有用性)」と題した科学ポスターを発表し、この神経発達障害に関する最新の臨床的知見に光を当てました。このポスターは、ベイラー・ジェネティクス社のメディカルアフェアーズ部門シニアマネージャーであり、認定遺伝カウンセラーのロバート・リゴベロ氏(Robert Rigobello, MS)によって発表されました。
最近の文献によれば、ReNU症候群はすべての神経発達障害の推定0.4%を占めるとされています。
このポスターでは、ベイラー・ジェネティクス社が主導し、WGSを用いて小児患
お子さんの発達に気がかりな点があっても、検査を重ねても原因が分からない。そんな「診断がつかない」期間は、ご家族にとって長く辛い道のりです。しかし今、最先端の遺伝子解析技術が、これまで見つけられなかった原因を突き止め、長く続いた診断の旅に終わりをもたらす新たな光となっています。最新の発見は、ある神経発達障害の謎を解き明かす、重要な一歩となりました。
2025年7月25日、ベイラー・ジェネティクス社は、全ゲノムシーケンシングを用いて小児患者からRNU4-2遺伝子の病的バリアントを発見し、診断に至った事例についての調査結果を発表しました。ReNU症候群は、RNU4-2遺伝子の病的バリアントによって引き起こされる、2024年に新たに報告された神経発達障害です。この疾患に関連する症状には、全般的な発達遅延、知的障害、筋緊張低下、けいれん、脳の異常などがあります。ベイラー・ジェネティクス社は、第1回ReNU Hope科学シンポジウムにおいて、「Utility of Whole Genome Sequencing to Detect RNU4-2 Variants Associated with ReNU Syndrome(ReNU症候群に関連するRNU4-2バリアントを検出するための全ゲノムシーケンシングの有用性)」と題した科学ポスターを発表し、この神経発達障害に関する最新の臨床的知見に光を当てました。このポスターは、ベイラー・ジェネティクス社のメディカルアフェアーズ部門シニアマネージャーであり、認定遺伝カウンセラーのロバート・リゴベロ氏(Robert Rigobello, MS)によって発表されました。
最近の文献によれば、ReNU症候群はすべての神経発達障害の推定0.4%を占めるとされています。
このポスターでは、ベイラー・ジェネティクス社が主導し、WGSを用いて小児患
腸にも脳神経のような通信網があった!幹細胞の制御メカニズムを解明
 私たちの腸は、数日ごとに生まれ変わる驚異的な再生能力を持っています。その鍵を握るのが「腸管幹細胞」ですが、この細胞がどのようにして正確な指示を受け取っているのかは、長年の謎でした。しかし今回、シンガポールの研究チームが、まるで脳の神経細胞のように、特定の細胞が幹細胞に直接シグナルを届けるという、驚くべき「有線通信」システムを発見しました。この発見は、腸の健康や再生医療の常識を覆すかもしれません。
再生医療と腸の健康における重要な進展として、デューク-NUSメディカルスクールと南洋理工大学シンガポール校(NTUシンガポール)の科学者たちが、腸内における精密かつ予期せぬコミュニケーションシステムを解明しました。テロサイトとして知られる支持細胞が、脳のニューロンのように微細な突起を使い、腸管幹細胞に直接シグナルを送達しているのです。2025年7月23日に科学雑誌『Developmental Cell』に掲載されたこの研究は、腸がどのようにして自己を維持し修復するかについての長年の定説に挑戦するものであり、炎症性腸疾患(IBD: inflammatory bowel disease)や大腸がんといった疾患に対するより良い治療法につながる可能性があります。この論文のタイトルは、「Telocytes Deliver Essential Wnts Directly to Murine Intestinal Stem Cells Via Synapse-Like Contacts(テロサイトはシナプス様接触を介して必須Wntをマウス腸管幹細胞に直接送達する)」です。
腸の内壁は、人体で最も活発な組織の一つです。腸壁にある陰窩(クリプト)と呼ばれる微小なくぼみの奥深くに存在する少数の幹細胞のおかげで、数日ごとに自己再生を繰り返しています。これらの幹細胞は分裂して特殊化し、腸を健康で
私たちの腸は、数日ごとに生まれ変わる驚異的な再生能力を持っています。その鍵を握るのが「腸管幹細胞」ですが、この細胞がどのようにして正確な指示を受け取っているのかは、長年の謎でした。しかし今回、シンガポールの研究チームが、まるで脳の神経細胞のように、特定の細胞が幹細胞に直接シグナルを届けるという、驚くべき「有線通信」システムを発見しました。この発見は、腸の健康や再生医療の常識を覆すかもしれません。
再生医療と腸の健康における重要な進展として、デューク-NUSメディカルスクールと南洋理工大学シンガポール校(NTUシンガポール)の科学者たちが、腸内における精密かつ予期せぬコミュニケーションシステムを解明しました。テロサイトとして知られる支持細胞が、脳のニューロンのように微細な突起を使い、腸管幹細胞に直接シグナルを送達しているのです。2025年7月23日に科学雑誌『Developmental Cell』に掲載されたこの研究は、腸がどのようにして自己を維持し修復するかについての長年の定説に挑戦するものであり、炎症性腸疾患(IBD: inflammatory bowel disease)や大腸がんといった疾患に対するより良い治療法につながる可能性があります。この論文のタイトルは、「Telocytes Deliver Essential Wnts Directly to Murine Intestinal Stem Cells Via Synapse-Like Contacts(テロサイトはシナプス様接触を介して必須Wntをマウス腸管幹細胞に直接送達する)」です。
腸の内壁は、人体で最も活発な組織の一つです。腸壁にある陰窩(クリプト)と呼ばれる微小なくぼみの奥深くに存在する少数の幹細胞のおかげで、数日ごとに自己再生を繰り返しています。これらの幹細胞は分裂して特殊化し、腸を健康で
蚊を殺す薬でマラリアを防ぐ!集団投薬が拓く新たな感染症対策
 長年、人類を苦しめてきた感染症、マラリア。既存の対策が限界を迎えつつある中、意外な薬が新たな希望の光として注目されています。もともとは寄生虫の駆除に使われていた「イベルメクチン」。この薬が、蚊を介したマラリアの感染を劇的に減らす可能性があることが、大規模な臨床試験で示されました。この記事では、マラリアとの闘いに新たな武器をもたらす可能性を秘めた、BOHEMIA試験の驚くべき結果について詳しく解説します。
住民全体にイベルメクチンを投与することでマラリアの伝播が大幅に減少し、この病気との闘いに新たな希望がもたらされました。マラリアに対するイベルメクチンに関するこれまでで最大規模の研究であるBOHEMIA試験では、既存の蚊帳の使用に加えて、新規のマラリア感染が26%減少したことが示され、マラリア対策における補完的なツールとしてのイベルメクチンの可能性を強く裏付ける証拠となりました。このプロジェクトは、バルセロナ・グローバルヘルス研究所(ISGlobal)―「ラ・カイシャ」財団の支援を受ける機関―が、マニサ保健研究センター(CISM)およびKEMRI-ウェルカムトラスト研究プログラムと協力して調整したもので、その結果は2025年7月23日に『The New England Journal of Medicine』に掲載されました。このオープンアクセス論文のタイトルは、「Ivermectin to Control Malaria — A Cluster-Randomized Trial(マラリア制御のためのイベルメクチン — クラスターランダム化試験)」です。
マラリアは依然として世界的な健康課題であり、2023年には2億6,300万人の症例と59万7,000人の死亡が報告されています。長時間持続型殺虫剤処理蚊帳(LLINs: long-lasting insecticid
長年、人類を苦しめてきた感染症、マラリア。既存の対策が限界を迎えつつある中、意外な薬が新たな希望の光として注目されています。もともとは寄生虫の駆除に使われていた「イベルメクチン」。この薬が、蚊を介したマラリアの感染を劇的に減らす可能性があることが、大規模な臨床試験で示されました。この記事では、マラリアとの闘いに新たな武器をもたらす可能性を秘めた、BOHEMIA試験の驚くべき結果について詳しく解説します。
住民全体にイベルメクチンを投与することでマラリアの伝播が大幅に減少し、この病気との闘いに新たな希望がもたらされました。マラリアに対するイベルメクチンに関するこれまでで最大規模の研究であるBOHEMIA試験では、既存の蚊帳の使用に加えて、新規のマラリア感染が26%減少したことが示され、マラリア対策における補完的なツールとしてのイベルメクチンの可能性を強く裏付ける証拠となりました。このプロジェクトは、バルセロナ・グローバルヘルス研究所(ISGlobal)―「ラ・カイシャ」財団の支援を受ける機関―が、マニサ保健研究センター(CISM)およびKEMRI-ウェルカムトラスト研究プログラムと協力して調整したもので、その結果は2025年7月23日に『The New England Journal of Medicine』に掲載されました。このオープンアクセス論文のタイトルは、「Ivermectin to Control Malaria — A Cluster-Randomized Trial(マラリア制御のためのイベルメクチン — クラスターランダム化試験)」です。
マラリアは依然として世界的な健康課題であり、2023年には2億6,300万人の症例と59万7,000人の死亡が報告されています。長時間持続型殺虫剤処理蚊帳(LLINs: long-lasting insecticid
ME/CFS(慢性疲労症候群)の原因解明へ:過剰な自然免疫応答と慢性炎症の関連を特定
 慢性疲労症候群(ME/CFS)の原因解明へ、過剰な免疫応答が鍵か
「気のせいではないか」「怠けているだけだ」——原因不明の極度の疲労感に苦しみながらも、周囲の無理解に悩まされてきた方々がいます。しかし今、その長く続いた苦しみの原因が、分子レベルで解き明かされようとしています。最新の研究により、筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群の患者さんでは、細菌やウイルスに対する免疫システムが過剰に反応していることが明らかになり、新たな治療法への希望の光が見えてきました。
コロンビア大学メールマン公衆衛生大学院の感染免疫センターの研究者らが主導し、ME/CFS研究をリードする複数のセンターからなるチームが行ったこの新しい研究は、ME/CFSが炎症と免疫応答に及ぼす持続的な影響を分子レベルで詳述するものです。この成果は、ME/CFSや、ライム病後症候群、ロングコビッドといった他の感染後症候群の症状を軽減するための標的治療法の開発に情報を提供する可能性があります。この研究結果は、2025年9月1日付の学術誌『npj Metabolic Health and Disease』に掲載されました。論文タイトルは、「Heightened Innate Immunity May Trigger Chronic Inflammation, Fatigue and Post-Exertional Malaise in ME/CFS(ME/CFSにおける亢進した自然免疫が慢性炎症、疲労、労作後倦怠感を引き起こす可能性)」です。
ME/CFSの症状には、原因不明の疲労、労作後倦怠感、認知機能障害などがあります。アメリカ疾病予防管理センターによると、米国だけでも最大330万人のME/CFS患者がおり、年間経済負担は最大510億ドルに上ります。かつては心理的な障害と考えられていましたが、血液、筋肉、脳の研
慢性疲労症候群(ME/CFS)の原因解明へ、過剰な免疫応答が鍵か
「気のせいではないか」「怠けているだけだ」——原因不明の極度の疲労感に苦しみながらも、周囲の無理解に悩まされてきた方々がいます。しかし今、その長く続いた苦しみの原因が、分子レベルで解き明かされようとしています。最新の研究により、筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群の患者さんでは、細菌やウイルスに対する免疫システムが過剰に反応していることが明らかになり、新たな治療法への希望の光が見えてきました。
コロンビア大学メールマン公衆衛生大学院の感染免疫センターの研究者らが主導し、ME/CFS研究をリードする複数のセンターからなるチームが行ったこの新しい研究は、ME/CFSが炎症と免疫応答に及ぼす持続的な影響を分子レベルで詳述するものです。この成果は、ME/CFSや、ライム病後症候群、ロングコビッドといった他の感染後症候群の症状を軽減するための標的治療法の開発に情報を提供する可能性があります。この研究結果は、2025年9月1日付の学術誌『npj Metabolic Health and Disease』に掲載されました。論文タイトルは、「Heightened Innate Immunity May Trigger Chronic Inflammation, Fatigue and Post-Exertional Malaise in ME/CFS(ME/CFSにおける亢進した自然免疫が慢性炎症、疲労、労作後倦怠感を引き起こす可能性)」です。
ME/CFSの症状には、原因不明の疲労、労作後倦怠感、認知機能障害などがあります。アメリカ疾病予防管理センターによると、米国だけでも最大330万人のME/CFS患者がおり、年間経済負担は最大510億ドルに上ります。かつては心理的な障害と考えられていましたが、血液、筋肉、脳の研
マラリア撲滅へ新戦略!CRISPRで蚊の分子を1つ変えるだけで感染をブロック
 毎年、他のどの動物よりも多くの人々の命を奪っている蚊。その蚊が媒介するマラリアとの闘いは、殺虫剤や治療薬への耐性が広がることで、近年ますます困難を極めています。しかし、この絶望的な状況を打破するかもしれない画期的な技術が開発されました。たった1つの分子を入れ替えるだけで、蚊を「マラリアを運べない体」に変えることができるというのです。
カリフォルニア大学サンディエゴ校、ジョンズ・ホプキンス大学、カリフォルニア大学バークレー校、そしてサンパウロ大学の研究者たちが、蚊によるマラリアの伝播を遺伝的にブロックする新しい手法を開発しました。蚊は依然としてマラリア患者を刺して血液中から原虫を体内に取り込みますが、その原虫を他の人に広めることはできなくなります。この新しいシステムは、マラリアへの耐性を持つ形質を蚊の集団全体に遺伝的に広げ、最終的にその地域の蚊が病気を媒介しなくなるように設計されています。
この画期的な研究は、カリフォルニア大学サンディエゴ校の生物学者であるジーチエン・リー氏(Zhiqian Li)とイーサン・ビア教授(Ethan Bier)、そしてジョンズ・ホプキンス大学のユエメイ・ドン氏(Yuemei Dong)とジョージ・ディモプロス教授(George Dimopoulos)によって主導されました。彼らは、CRISPRをベースとした遺伝子編集システムを構築し、蚊の体内にあるたった1つの分子を変化させることで、マラリア原虫の伝播プロセスを阻止することに成功しました。
「蚊のたった1つのアミノ酸を、マラリア原虫に感染しなくなる別の自然な変異体に置き換え、その有益な形質を蚊の集団全体に広げることは、まさにゲームチェンジャーです」と、カリフォルニア大学サンディエゴ校 生物科学部 細胞・発生生物学部門のビア教授は語ります。「この、たった1つの小さな変化が、これほど劇的な
毎年、他のどの動物よりも多くの人々の命を奪っている蚊。その蚊が媒介するマラリアとの闘いは、殺虫剤や治療薬への耐性が広がることで、近年ますます困難を極めています。しかし、この絶望的な状況を打破するかもしれない画期的な技術が開発されました。たった1つの分子を入れ替えるだけで、蚊を「マラリアを運べない体」に変えることができるというのです。
カリフォルニア大学サンディエゴ校、ジョンズ・ホプキンス大学、カリフォルニア大学バークレー校、そしてサンパウロ大学の研究者たちが、蚊によるマラリアの伝播を遺伝的にブロックする新しい手法を開発しました。蚊は依然としてマラリア患者を刺して血液中から原虫を体内に取り込みますが、その原虫を他の人に広めることはできなくなります。この新しいシステムは、マラリアへの耐性を持つ形質を蚊の集団全体に遺伝的に広げ、最終的にその地域の蚊が病気を媒介しなくなるように設計されています。
この画期的な研究は、カリフォルニア大学サンディエゴ校の生物学者であるジーチエン・リー氏(Zhiqian Li)とイーサン・ビア教授(Ethan Bier)、そしてジョンズ・ホプキンス大学のユエメイ・ドン氏(Yuemei Dong)とジョージ・ディモプロス教授(George Dimopoulos)によって主導されました。彼らは、CRISPRをベースとした遺伝子編集システムを構築し、蚊の体内にあるたった1つの分子を変化させることで、マラリア原虫の伝播プロセスを阻止することに成功しました。
「蚊のたった1つのアミノ酸を、マラリア原虫に感染しなくなる別の自然な変異体に置き換え、その有益な形質を蚊の集団全体に広げることは、まさにゲームチェンジャーです」と、カリフォルニア大学サンディエゴ校 生物科学部 細胞・発生生物学部門のビア教授は語ります。「この、たった1つの小さな変化が、これほど劇的な
ゲノムの"暗黒領域"を解読!ヒトの多様性と疾患の謎に迫る最新研究
 私たちの生命の設計図「ヒトゲノム」。その中でも特に解読が困難で、長らく謎に包まれてきた領域があります。しかし今、国際的な科学者チームが最新技術を駆使し、この"暗黒領域"の解読に成功しました。この発見は、ヒト生物学の常識を覆し、病気の原因解明や「プレシジョン・メディシン」を新たな次元へと導く画期的な一歩となります。この記事では、ゲノムの謎に挑んだ研究の最前線に迫ります。
国際的な科学者チームが、多様な祖先を持つ65人の完全なゲノム配列を用いて、これまで解読が最も困難だったヒトゲノム領域のいくつかを解読しました。ジャクソン研究所(JAX)が共同で主導し、2025年7月23日に科学雑誌『Nature』オンライン版で発表されたこの研究は、消化や免疫反応から筋肉の制御に至るまで、あらゆるものに影響を与える隠れたDNAのバリエーションを明らかにしました。これは、特定の疾患が一部の集団でより深刻な影響を及ぼす理由を説明できる可能性があります。このオープンアクセス論文のタイトルは、「Complex Genetic Variation in Nearly Complete Human Genomes(ほぼ完全なヒトゲノムにおける複雑な遺伝的多様性)」です。
このマイルストーンは、ゲノム科学の分野を再構築した2つの基礎研究に基づいています。2022年、研究者たちは史上初となる単一のヒトゲノムの完全な配列解読を達成し、オリジナルのヒトゲノム計画で残された主要なギャップを埋めました。2023年には、科学者たちは47人の個人から構築されたパンゲノムのドラフト版を公開しました。これは、世界の遺伝的多様性を表現するための重要な一歩でした。今回の新しい研究は、これらの両方の取り組みを大幅に拡張し、残っていたデータギャップの92%を埋め、これまでにない広さと解像度で様々な祖先にわたるゲノムのバリエー
私たちの生命の設計図「ヒトゲノム」。その中でも特に解読が困難で、長らく謎に包まれてきた領域があります。しかし今、国際的な科学者チームが最新技術を駆使し、この"暗黒領域"の解読に成功しました。この発見は、ヒト生物学の常識を覆し、病気の原因解明や「プレシジョン・メディシン」を新たな次元へと導く画期的な一歩となります。この記事では、ゲノムの謎に挑んだ研究の最前線に迫ります。
国際的な科学者チームが、多様な祖先を持つ65人の完全なゲノム配列を用いて、これまで解読が最も困難だったヒトゲノム領域のいくつかを解読しました。ジャクソン研究所(JAX)が共同で主導し、2025年7月23日に科学雑誌『Nature』オンライン版で発表されたこの研究は、消化や免疫反応から筋肉の制御に至るまで、あらゆるものに影響を与える隠れたDNAのバリエーションを明らかにしました。これは、特定の疾患が一部の集団でより深刻な影響を及ぼす理由を説明できる可能性があります。このオープンアクセス論文のタイトルは、「Complex Genetic Variation in Nearly Complete Human Genomes(ほぼ完全なヒトゲノムにおける複雑な遺伝的多様性)」です。
このマイルストーンは、ゲノム科学の分野を再構築した2つの基礎研究に基づいています。2022年、研究者たちは史上初となる単一のヒトゲノムの完全な配列解読を達成し、オリジナルのヒトゲノム計画で残された主要なギャップを埋めました。2023年には、科学者たちは47人の個人から構築されたパンゲノムのドラフト版を公開しました。これは、世界の遺伝的多様性を表現するための重要な一歩でした。今回の新しい研究は、これらの両方の取り組みを大幅に拡張し、残っていたデータギャップの92%を埋め、これまでにない広さと解像度で様々な祖先にわたるゲノムのバリエー
1000ゲノム計画から10年、最新技術が解き明かすヒト遺伝子の新たな謎
 かつてヒトゲノム研究に革命をもたらした「1000ゲノムプロジェクト」。その完了から10年の時を経て、残された貴重なサンプルが最新技術の力で再び輝きを放ち始めました。これまで誰も見ることができなかった、ヒトの遺伝的バリエーションの全体像が、今、驚くほど鮮明に描き出されようとしています。この記事では、私たちの生命の設計図に隠された新たな物語を解き明かす、最先端の研究成果をご紹介します。
2003年に完了したヒトゲノム計画は、私たちに初めてのヒトゲノム配列をもたらしましたが、それはごく少数の人々のDNAに基づいたものでした。この成功を礎に、2007年に1000ゲノムプロジェクトが構想されました。このプロジェクトは、1,000人のヒトゲノムを解読するという野心的な目標から始まり、それを超える成果を上げ、2015年には様々な祖先を持つ2,500人以上の個人のデータを発表しました。これらのプロジェクトは、私たち一人ひとりをユニークにし、生命活動の基盤となる遺伝学に関する知識の多くに貢献してきました。そして今、10年の時を経て、欧州分子生物学研究所(EMBL)の科学者とその共同研究者たちは、10年前には利用できなかった手法や技術を駆使して、この膨大なリソースのサンプルをより深く分析し、ヒト生物学に関する新たな知見を明らかにしました。2025年7月23日に科学雑誌『Nature』で連続して発表された2つの論文で共有されたデータセットは、今日における最も完全なヒトゲノムの全体像と言えるかもしれません。
EMBLハイデルベルクのグループリーダー兼暫定責任者であり、今回の新しい研究の共同シニアオーサーであるヤン・コーベル氏(Jan Korbel)は次のように述べています。「約15年前、ほとんどのヒトゲノムシーケンシングは、DNAの短い断片からの『リード』に依存していました。これはゲノム全
かつてヒトゲノム研究に革命をもたらした「1000ゲノムプロジェクト」。その完了から10年の時を経て、残された貴重なサンプルが最新技術の力で再び輝きを放ち始めました。これまで誰も見ることができなかった、ヒトの遺伝的バリエーションの全体像が、今、驚くほど鮮明に描き出されようとしています。この記事では、私たちの生命の設計図に隠された新たな物語を解き明かす、最先端の研究成果をご紹介します。
2003年に完了したヒトゲノム計画は、私たちに初めてのヒトゲノム配列をもたらしましたが、それはごく少数の人々のDNAに基づいたものでした。この成功を礎に、2007年に1000ゲノムプロジェクトが構想されました。このプロジェクトは、1,000人のヒトゲノムを解読するという野心的な目標から始まり、それを超える成果を上げ、2015年には様々な祖先を持つ2,500人以上の個人のデータを発表しました。これらのプロジェクトは、私たち一人ひとりをユニークにし、生命活動の基盤となる遺伝学に関する知識の多くに貢献してきました。そして今、10年の時を経て、欧州分子生物学研究所(EMBL)の科学者とその共同研究者たちは、10年前には利用できなかった手法や技術を駆使して、この膨大なリソースのサンプルをより深く分析し、ヒト生物学に関する新たな知見を明らかにしました。2025年7月23日に科学雑誌『Nature』で連続して発表された2つの論文で共有されたデータセットは、今日における最も完全なヒトゲノムの全体像と言えるかもしれません。
EMBLハイデルベルクのグループリーダー兼暫定責任者であり、今回の新しい研究の共同シニアオーサーであるヤン・コーベル氏(Jan Korbel)は次のように述べています。「約15年前、ほとんどのヒトゲノムシーケンシングは、DNAの短い断片からの『リード』に依存していました。これはゲノム全
HTLV-1感染症に光明!既存のHIV治療薬が感染予防に有効であることを発見
 世界で約1000万人が感染しながらも、有効な予防法も治療法も確立されていない「忘れられたウイルス」、ヒトT細胞白血病ウイルス1型。しかし今、その状況を覆すかもしれない画期的なニュースがオーストラリアから届きました。なんと、既存のHIV治療薬が、この難病の感染拡大を防ぐ鍵になるというのです。オーストラリアの研究者らが共同で主導したこの画期的な研究は、既存のHIV治療薬がマウスにおけるHTLV-1ウイルスの伝播を抑制できることを発見しました。2025年7月10日に学術誌Cellに掲載されたこの研究は、オーストラリア中央部を含む世界の多くの先住民族コミュニティで流行しているこのウイルスの拡大を防ぐ、初めての治療法につながる可能性があります。
このオープンアクセスの論文のタイトルは、「Combination Antiretroviral Therapy and MCL-1 Inhibition Mitigate HTLV-1 Infection in Vivo(抗レトロウイルス薬併用療法とMCL-1阻害がin vivoでのHTLV-1感染を軽減する)」です。
WEHI(ウォルター・アンド・イライザ・ホール医学研究所)とピーター・ドハーティー感染免疫研究所(ドハーティー研究所)によるこの研究は、既に感染が成立している人々からHTLV-1陽性細胞を除去し、病気の進行を防ぐ可能性のある新しい創薬ターゲットも特定しました。
研究概要:
WEHIとドハーティー研究所が共同で主導した新研究は、世界で最も複雑で顧みられていないウイルスの一つであるHTLV-1に対する初の予防的治療法につながる可能性があります。
この研究では、すでに市場に出ている2種類の特定のHIV抗ウイルス薬が、ヒト化マウスにおけるHTLV-1の伝播を抑制し、病気を予防できることが判明し、HTLV-1に対する
世界で約1000万人が感染しながらも、有効な予防法も治療法も確立されていない「忘れられたウイルス」、ヒトT細胞白血病ウイルス1型。しかし今、その状況を覆すかもしれない画期的なニュースがオーストラリアから届きました。なんと、既存のHIV治療薬が、この難病の感染拡大を防ぐ鍵になるというのです。オーストラリアの研究者らが共同で主導したこの画期的な研究は、既存のHIV治療薬がマウスにおけるHTLV-1ウイルスの伝播を抑制できることを発見しました。2025年7月10日に学術誌Cellに掲載されたこの研究は、オーストラリア中央部を含む世界の多くの先住民族コミュニティで流行しているこのウイルスの拡大を防ぐ、初めての治療法につながる可能性があります。
このオープンアクセスの論文のタイトルは、「Combination Antiretroviral Therapy and MCL-1 Inhibition Mitigate HTLV-1 Infection in Vivo(抗レトロウイルス薬併用療法とMCL-1阻害がin vivoでのHTLV-1感染を軽減する)」です。
WEHI(ウォルター・アンド・イライザ・ホール医学研究所)とピーター・ドハーティー感染免疫研究所(ドハーティー研究所)によるこの研究は、既に感染が成立している人々からHTLV-1陽性細胞を除去し、病気の進行を防ぐ可能性のある新しい創薬ターゲットも特定しました。
研究概要:
WEHIとドハーティー研究所が共同で主導した新研究は、世界で最も複雑で顧みられていないウイルスの一つであるHTLV-1に対する初の予防的治療法につながる可能性があります。
この研究では、すでに市場に出ている2種類の特定のHIV抗ウイルス薬が、ヒト化マウスにおけるHTLV-1の伝播を抑制し、病気を予防できることが判明し、HTLV-1に対する
女王アリか働きアリか?運命を分けるのは遺伝子で決まる「大きさの境界線」だった
 アリの世界では、多くの場合、カースト(階級)がその一生の運命を決定します。女王は大きく育ち、翅を伸ばして卵を産むことに専念し、働きアリは小さいままで翅も持たず、ひたすら働き続けます。しかし、このカーストがどのようにして発達し、若いアリの将来が遺伝と環境によってどう決まるのかは、これまで明確ではありませんでした。この「生まれ」と「育ち」の謎に、最新の研究が光を当てました。
新しい研究は、アリの体の大きさとカーストが密接に関連していることを示唆しています。一般的に、大きいアリは女王になり、小さいアリは働きアリになります。そして、アリがどれだけ大きく成長するかには、遺伝子と環境の両方が影響します。しかし、2025年7月22日に米国科学アカデミー紀要(PNAS)に掲載されたこの研究は、女王になるための「大きさの境界線」は遺伝子だけで決まることも示唆しています。同じ環境で育った、同じ大きさの遺伝的に異なるアリたちが、カーストに関連する形態において違いを見せることがあるのです。これらの結果は、遺伝子が単に大きさに影響を与えるだけでなく、その「大きさ」がコロニーにとって持つ意味そのものを変えることを示しています。比較的小さな2匹のアリが、女王になる確率は全く異なる可能性があるのです。このオープンアクセスの論文は、「Static Allometries of Caste-Associated Traits Vary with Genotype But Not Environment in the Clonal Raider Ant(クローン性ツノヒメサスライアリにおいて、カースト関連形質の静的アロメトリーは環境ではなく遺伝子型によって変化する)」と題されています。
「私たちの目標の一つは、昆虫社会がどのように機能するかを理解することです」と、ロックフェラー大学のスタンレー S. &
アリの世界では、多くの場合、カースト(階級)がその一生の運命を決定します。女王は大きく育ち、翅を伸ばして卵を産むことに専念し、働きアリは小さいままで翅も持たず、ひたすら働き続けます。しかし、このカーストがどのようにして発達し、若いアリの将来が遺伝と環境によってどう決まるのかは、これまで明確ではありませんでした。この「生まれ」と「育ち」の謎に、最新の研究が光を当てました。
新しい研究は、アリの体の大きさとカーストが密接に関連していることを示唆しています。一般的に、大きいアリは女王になり、小さいアリは働きアリになります。そして、アリがどれだけ大きく成長するかには、遺伝子と環境の両方が影響します。しかし、2025年7月22日に米国科学アカデミー紀要(PNAS)に掲載されたこの研究は、女王になるための「大きさの境界線」は遺伝子だけで決まることも示唆しています。同じ環境で育った、同じ大きさの遺伝的に異なるアリたちが、カーストに関連する形態において違いを見せることがあるのです。これらの結果は、遺伝子が単に大きさに影響を与えるだけでなく、その「大きさ」がコロニーにとって持つ意味そのものを変えることを示しています。比較的小さな2匹のアリが、女王になる確率は全く異なる可能性があるのです。このオープンアクセスの論文は、「Static Allometries of Caste-Associated Traits Vary with Genotype But Not Environment in the Clonal Raider Ant(クローン性ツノヒメサスライアリにおいて、カースト関連形質の静的アロメトリーは環境ではなく遺伝子型によって変化する)」と題されています。
「私たちの目標の一つは、昆虫社会がどのように機能するかを理解することです」と、ロックフェラー大学のスタンレー S. &
病気の引き金「ミトコンドリアDNAの損傷」を未然に防ぐ!画期的な分子ツールが開発される
 私たちの体を蝕む環境ストレス。細胞の中にあるエネルギー工場「ミトコンドリア」が持つ独自のDNAが傷つけられると、それは心臓病や神経変性疾患、そして慢性的な炎症といった、様々な病気の引き金となる負の連鎖を始めることがあります。しかしこの度、その連鎖を根本で断ち切り、病気につながるダメージが深刻化する前にDNAを守る、画期的な化学ツールが開発されました。
カリフォルニア大学リバーサイド校(UC Riverside)で開発されたこの新しい分子に関する研究は、2025年7月15日にドイツ化学会誌Angewandte Chemie International Editionに掲載されました。この研究が焦点を当てたのは、細胞の核に収められているDNAとは別に存在するミトコンドリアDNAです。核のDNAが遺伝コードの大部分を保持しているのに対し、ミトコンドリアはエネルギー生産を含む細胞機能に不可欠な、それ自身の小さなゲノムを持っています。このオープンアクセスの論文のタイトルは、「Mitochondria-Targeting Abasic Site-Reactive Probe (mTAP) Enables the Manipulation of Mitochondrial DNA Levels(ミトコンドリアを標的とするアベイシック部位反応性プローブ(mTAP)によるミトコンドリアDNAレベルの操作)」です。
ミトコンドリアDNAは、1つの細胞内に多数のコピーが存在しますが、損傷が起こると、修復されるよりも分解されてしまうことがよくあります。この分解が放置されると、組織の機能が損なわれ、炎症を引き起こす可能性があります。
研究者たちは、損傷したmtDNAの部位に結合し、その分解につながる酵素の働きをブロックする化学プローブを開発しました。このアプローチは、損傷を「修復」するので
私たちの体を蝕む環境ストレス。細胞の中にあるエネルギー工場「ミトコンドリア」が持つ独自のDNAが傷つけられると、それは心臓病や神経変性疾患、そして慢性的な炎症といった、様々な病気の引き金となる負の連鎖を始めることがあります。しかしこの度、その連鎖を根本で断ち切り、病気につながるダメージが深刻化する前にDNAを守る、画期的な化学ツールが開発されました。
カリフォルニア大学リバーサイド校(UC Riverside)で開発されたこの新しい分子に関する研究は、2025年7月15日にドイツ化学会誌Angewandte Chemie International Editionに掲載されました。この研究が焦点を当てたのは、細胞の核に収められているDNAとは別に存在するミトコンドリアDNAです。核のDNAが遺伝コードの大部分を保持しているのに対し、ミトコンドリアはエネルギー生産を含む細胞機能に不可欠な、それ自身の小さなゲノムを持っています。このオープンアクセスの論文のタイトルは、「Mitochondria-Targeting Abasic Site-Reactive Probe (mTAP) Enables the Manipulation of Mitochondrial DNA Levels(ミトコンドリアを標的とするアベイシック部位反応性プローブ(mTAP)によるミトコンドリアDNAレベルの操作)」です。
ミトコンドリアDNAは、1つの細胞内に多数のコピーが存在しますが、損傷が起こると、修復されるよりも分解されてしまうことがよくあります。この分解が放置されると、組織の機能が損なわれ、炎症を引き起こす可能性があります。
研究者たちは、損傷したmtDNAの部位に結合し、その分解につながる酵素の働きをブロックする化学プローブを開発しました。このアプローチは、損傷を「修復」するので
肥満リスクは遺伝子で予測できる?500万人のデータが示す早期予防の可能性
 将来、自分が肥満になるかどうか、もし子どもの頃に予測できるとしたらどうでしょう?最新の研究により、500万人以上の膨大な遺伝子データを解析することで、それが現実のものとなるかもしれません。この画期的な発見は、肥満という世界的な健康課題へのアプローチを根本から変える可能性を秘めています。コペンハーゲン大学とブリストル大学が主導した新しい研究は、若いうちに遺伝子を分析することが、将来の肥満発症を防ぐための早期戦略につながる可能性を示しました。
世界肥満連盟は、2035年までに世界人口の半数以上が過体重または肥満になると予測しています。しかし、生活習慣の改善、外科手術、薬物療法といった治療戦略は、誰もが利用できるわけではなく、また常に効果的とは限りません。そこで国際的な研究チームは、500万人以上の遺伝子データを活用し、多遺伝子リスクスコアと呼ばれる指標を作成しました。このスコアは、成人期の肥満と確実に相関し、さらに幼少期においても一貫性のある指標的なパターンを示すことが明らかになりました。
この研究成果は、将来肥満になる遺伝的リスクが高い子どもや思春期の若者を特定し、より若い年齢から生活習慣の改善といった的を絞った予防戦略の恩恵を受けられるようにするのに役立つ可能性があります。2025年7月21日に学術誌Nature Medicineに掲載されたこの研究の筆頭著者である、コペンハーゲン大学のルーロフ・スミット助教(Roelof Smit)は次のように述べています。「このスコアが非常に強力なのは、5歳になる前から成人期に至るまで、遺伝子スコアとボディマス指数との間に関連性の一貫性が見られる点です。これは、他のリスク要因が小児期後半の体重に影響を与え始めるよりもずっと早いタイミングです。この時点で介入できれば、理論的には非常に大きな影響を与えられる可能性があります。」このオ
将来、自分が肥満になるかどうか、もし子どもの頃に予測できるとしたらどうでしょう?最新の研究により、500万人以上の膨大な遺伝子データを解析することで、それが現実のものとなるかもしれません。この画期的な発見は、肥満という世界的な健康課題へのアプローチを根本から変える可能性を秘めています。コペンハーゲン大学とブリストル大学が主導した新しい研究は、若いうちに遺伝子を分析することが、将来の肥満発症を防ぐための早期戦略につながる可能性を示しました。
世界肥満連盟は、2035年までに世界人口の半数以上が過体重または肥満になると予測しています。しかし、生活習慣の改善、外科手術、薬物療法といった治療戦略は、誰もが利用できるわけではなく、また常に効果的とは限りません。そこで国際的な研究チームは、500万人以上の遺伝子データを活用し、多遺伝子リスクスコアと呼ばれる指標を作成しました。このスコアは、成人期の肥満と確実に相関し、さらに幼少期においても一貫性のある指標的なパターンを示すことが明らかになりました。
この研究成果は、将来肥満になる遺伝的リスクが高い子どもや思春期の若者を特定し、より若い年齢から生活習慣の改善といった的を絞った予防戦略の恩恵を受けられるようにするのに役立つ可能性があります。2025年7月21日に学術誌Nature Medicineに掲載されたこの研究の筆頭著者である、コペンハーゲン大学のルーロフ・スミット助教(Roelof Smit)は次のように述べています。「このスコアが非常に強力なのは、5歳になる前から成人期に至るまで、遺伝子スコアとボディマス指数との間に関連性の一貫性が見られる点です。これは、他のリスク要因が小児期後半の体重に影響を与え始めるよりもずっと早いタイミングです。この時点で介入できれば、理論的には非常に大きな影響を与えられる可能性があります。」このオ
リボソームの製造工場「核小体」、その設計図はRNA自身だった!構造操作も可能に
 私たちの細胞が生命活動を維持するために欠かせないタンパク質。その製造工場である「リボソーム」が、どこで、どのようにして生まれるのか、その誕生の瞬間は長らく謎に包まれていました。特に、リボソームRNA(rRNA: ribosomal RNA)が新しいリボソームへと姿を変える場所である、細胞核内の高密度領域「核小体」の内部を覗き見る方法がなかったためです。しかし今回、ついにそのブラックボックスの扉を開く画期的な研究成果が発表されました。
2025年7月2日に科学雑誌Natureに掲載されたこの論文は、ロックフェラー大学、プリンストン大学、ブリュッセル自由大学の共同研究によるものです。この研究は、rRNAがどのようにしてリボソームを作り出すのかを明らかにしただけでなく、rRNA自身が核小体の「設計図」の役割を果たしていること、そして、その設計図を少し書き換えるだけで核小体の形や構造を作り変えることさえ可能であることを示しました。このオープンアクセスの論文のタイトルは、「Mapping and Engineering RNA-Driven Architecture of the Multiphase Nucleolus(RNAが駆動する多相的な核小体の構造のマッピングと操作)」です。
「私たちは今や、細胞小器官(オルガネラ)全体の構造を設計し、操作することができるのです」と、ロックフェラー大学タンパク質・核酸化学研究室を率いるセバスチャン・クリンゲ(Sebastian Klinge)博士は語ります。「これにより、原子レベルの構造と細胞全体の構成との間のギャップを埋め、オルガネラの形と機能を司る正確な分子メカニズムを解き明かすことに、また一歩近づきました。」
リボソームの誕生
核小体は、初めて観察されたオルガネラのひとつで、細胞核の中でひときわ濃く見えるため、見
私たちの細胞が生命活動を維持するために欠かせないタンパク質。その製造工場である「リボソーム」が、どこで、どのようにして生まれるのか、その誕生の瞬間は長らく謎に包まれていました。特に、リボソームRNA(rRNA: ribosomal RNA)が新しいリボソームへと姿を変える場所である、細胞核内の高密度領域「核小体」の内部を覗き見る方法がなかったためです。しかし今回、ついにそのブラックボックスの扉を開く画期的な研究成果が発表されました。
2025年7月2日に科学雑誌Natureに掲載されたこの論文は、ロックフェラー大学、プリンストン大学、ブリュッセル自由大学の共同研究によるものです。この研究は、rRNAがどのようにしてリボソームを作り出すのかを明らかにしただけでなく、rRNA自身が核小体の「設計図」の役割を果たしていること、そして、その設計図を少し書き換えるだけで核小体の形や構造を作り変えることさえ可能であることを示しました。このオープンアクセスの論文のタイトルは、「Mapping and Engineering RNA-Driven Architecture of the Multiphase Nucleolus(RNAが駆動する多相的な核小体の構造のマッピングと操作)」です。
「私たちは今や、細胞小器官(オルガネラ)全体の構造を設計し、操作することができるのです」と、ロックフェラー大学タンパク質・核酸化学研究室を率いるセバスチャン・クリンゲ(Sebastian Klinge)博士は語ります。「これにより、原子レベルの構造と細胞全体の構成との間のギャップを埋め、オルガネラの形と機能を司る正確な分子メカニズムを解き明かすことに、また一歩近づきました。」
リボソームの誕生
核小体は、初めて観察されたオルガネラのひとつで、細胞核の中でひときわ濃く見えるため、見
パーキンソン病の原因は「無害なウイルス」?脳内での意外な関連性が明らかに
 誰もが持っているかもしれない、ありふれた「無害なウイルス」。もし、そのウイルスがパーキンソン病のような難病の引き金になっているとしたら…?
そんな驚くべき可能性を示唆する研究結果が、このたびノースウェスタン大学医学部から発表されました。研究チームは、パーキンソン病患者の脳内から、これまで全く関連が疑われていなかった特定のウイルスを検出。これまで原因の多くが不明とされてきたパーキンソン病の謎を解き明かす、新たな鍵が見つかったのかもしれません。
ノースウェスタン大学医学部の新しい研究により、パーキンソン病患者の脳内で、一般的ではあるものの通常は無害なウイルスが検出されました。
2025年7月8日に『JCI Insight』誌で発表されたこの研究は、米国で100万人以上が罹患しているパーキンソン病の環境的な引き金、あるいは寄与因子として、これまで知られていなかったウイルスが関与している可能性を示唆しています。パーキンソン病には遺伝的要因が関連するケースもありますが、ほとんどの症例では原因が不明のままです。このオープンアクセス論文のタイトルは「Human Pegivirus Alters Brain and Blood Immune and Transcriptomic Profiles of Patients with Parkinson’s Disease(ヒトペギウイルスはパーキンソン病患者の脳および血液の免疫・トランスクリプトームプロファイルを変化させる)」です。
「私たちは、パーキンソン病の一因となりうるウイルスなどの潜在的な環境要因を調査したいと考えていました」と、神経学部門の神経感染症・グローバル神経学の責任者であるイゴール・コラルニク医師(Igor Koralnik, MD)は述べています。「『ViroFind』というツールを用いて、パーキンソン病患者と
誰もが持っているかもしれない、ありふれた「無害なウイルス」。もし、そのウイルスがパーキンソン病のような難病の引き金になっているとしたら…?
そんな驚くべき可能性を示唆する研究結果が、このたびノースウェスタン大学医学部から発表されました。研究チームは、パーキンソン病患者の脳内から、これまで全く関連が疑われていなかった特定のウイルスを検出。これまで原因の多くが不明とされてきたパーキンソン病の謎を解き明かす、新たな鍵が見つかったのかもしれません。
ノースウェスタン大学医学部の新しい研究により、パーキンソン病患者の脳内で、一般的ではあるものの通常は無害なウイルスが検出されました。
2025年7月8日に『JCI Insight』誌で発表されたこの研究は、米国で100万人以上が罹患しているパーキンソン病の環境的な引き金、あるいは寄与因子として、これまで知られていなかったウイルスが関与している可能性を示唆しています。パーキンソン病には遺伝的要因が関連するケースもありますが、ほとんどの症例では原因が不明のままです。このオープンアクセス論文のタイトルは「Human Pegivirus Alters Brain and Blood Immune and Transcriptomic Profiles of Patients with Parkinson’s Disease(ヒトペギウイルスはパーキンソン病患者の脳および血液の免疫・トランスクリプトームプロファイルを変化させる)」です。
「私たちは、パーキンソン病の一因となりうるウイルスなどの潜在的な環境要因を調査したいと考えていました」と、神経学部門の神経感染症・グローバル神経学の責任者であるイゴール・コラルニク医師(Igor Koralnik, MD)は述べています。「『ViroFind』というツールを用いて、パーキンソン病患者と
治療法のないミトコンドリア病に希望の光!「3人の親を持つ」技術で8人の健康な赤ちゃんが誕生
 母親から子へと受け継がれる、治療法のない難病「ミトコンドリア病」。この過酷な運命の連鎖を断ち切るため、英国で開発された画期的な生殖医療技術が、大きな希望の光を灯しています。「ミトコンドリアドネーション」として知られるこの技術によって、これまでに8人の健康な赤ちゃんが誕生したことが、最新の研究で報告されました。赤ちゃんたちは全員、ミトコンドリアDNA病の兆候を見せていません。これは、遺伝性疾患に悩む多くの家族にとって、まさに待ち望んだ朗報と言えるでしょう。
英国のニューカッスルで実施された、ミトコンドリア病のリスクを低減するための先駆的な認可済み体外受精技術により、8人の赤ちゃんが誕生したことが発表された研究で明らかになりました。8人の赤ちゃん全員が、ミトコ-ンドリアDNA病の兆候を示していません。
4人の女児と4人の男児(うち1組は一卵性双生児)からなる赤ちゃんたちは、ミトコンドリアDNAの変異による重篤な疾患を子に伝えるリスクが高い7人の女性から生まれました。受精ヒト卵子を用いたミトコンドリアドネーションを開拓したニューカッスルの研究チームによって2025年6月16日に報告されたこの研究結果は、前核移植として知られる新しい治療法が、これまで不治とされてきたミトコンドリアDNA病のリスクを低減するのに有効であることを示しています。
この成果は、『The New England Journal of Medicine(NEJM)』誌に掲載された2つの論文、「Mitochondrial Donation in a Reproductive Care Pathway for mtDNA Disease(mtDNA疾患に対する生殖医療経路におけるミトコンドリアドネーション)」および「Mitochondrial Donation and Preimplantation Ge
母親から子へと受け継がれる、治療法のない難病「ミトコンドリア病」。この過酷な運命の連鎖を断ち切るため、英国で開発された画期的な生殖医療技術が、大きな希望の光を灯しています。「ミトコンドリアドネーション」として知られるこの技術によって、これまでに8人の健康な赤ちゃんが誕生したことが、最新の研究で報告されました。赤ちゃんたちは全員、ミトコンドリアDNA病の兆候を見せていません。これは、遺伝性疾患に悩む多くの家族にとって、まさに待ち望んだ朗報と言えるでしょう。
英国のニューカッスルで実施された、ミトコンドリア病のリスクを低減するための先駆的な認可済み体外受精技術により、8人の赤ちゃんが誕生したことが発表された研究で明らかになりました。8人の赤ちゃん全員が、ミトコ-ンドリアDNA病の兆候を示していません。
4人の女児と4人の男児(うち1組は一卵性双生児)からなる赤ちゃんたちは、ミトコンドリアDNAの変異による重篤な疾患を子に伝えるリスクが高い7人の女性から生まれました。受精ヒト卵子を用いたミトコンドリアドネーションを開拓したニューカッスルの研究チームによって2025年6月16日に報告されたこの研究結果は、前核移植として知られる新しい治療法が、これまで不治とされてきたミトコンドリアDNA病のリスクを低減するのに有効であることを示しています。
この成果は、『The New England Journal of Medicine(NEJM)』誌に掲載された2つの論文、「Mitochondrial Donation in a Reproductive Care Pathway for mtDNA Disease(mtDNA疾患に対する生殖医療経路におけるミトコンドリアドネーション)」および「Mitochondrial Donation and Preimplantation Ge
無から生まれる「de novo遺伝子」の謎を解明!遺伝子制御の新たな地平を拓く
 私たちの体を形作る設計図、遺伝子。そのほとんどは、はるか昔から存在し、多くの生物種で共有されているものです。しかし、中にはつい最近、これまで何もコードしていなかったDNA領域から、まるで無から生まれるように出現した「新しい遺伝子」が存在することをご存知でしょうか?この「de novo(デノボ)遺伝子」と呼ばれる新参者の遺伝子が、どのようにして生命活動のネットワークに組み込まれ、機能し始めるのかは、進化生物学における大きな謎の一つでした。
この度、ロックフェラー大学の研究者たちが、約10年にわたるショウジョウバエの研究を通じて、この謎に満ちたde novo遺伝子の制御メカニズムを初めて解明しました。この画期的な発見は、生命の進化の謎を解き明かすだけでなく、がんなどの疾患研究にも新たな光を当てるものとして注目されています。
新しい遺伝子と、古くからの疑問
ほとんどの遺伝子は古代から存在し、種を超えて共有されています。しかし、遺伝子のごく一部は比較的新しく、かつては何も情報をコードしていなかったDNA領域から自然発生的に出現したものです。今回、ロックフェラー大学の研究者たちは、ショウジョウバエでこれらの遺伝子を約10年間追い続けた結果、これらのde novo遺伝子がどのように制御されているかを発見しました。『Nature Ecology & Evolution』誌と『PNAS』誌に掲載された2つの補完的な研究で、研究チームは転写因子とゲノム上の隣接遺伝子が、これらの新しい遺伝子のスイッチを入れ、細胞内のネットワークに統合する仕組みを明らかにしました。これは、その主要な制御因子を特定した初めての研究となります。これらの発見は、新しい遺伝子がどのように機能的になるかに光を当てるものであり、進化生物学や遺伝子制御、そしてそれらの機能不全から生じる疾患の理解に広
私たちの体を形作る設計図、遺伝子。そのほとんどは、はるか昔から存在し、多くの生物種で共有されているものです。しかし、中にはつい最近、これまで何もコードしていなかったDNA領域から、まるで無から生まれるように出現した「新しい遺伝子」が存在することをご存知でしょうか?この「de novo(デノボ)遺伝子」と呼ばれる新参者の遺伝子が、どのようにして生命活動のネットワークに組み込まれ、機能し始めるのかは、進化生物学における大きな謎の一つでした。
この度、ロックフェラー大学の研究者たちが、約10年にわたるショウジョウバエの研究を通じて、この謎に満ちたde novo遺伝子の制御メカニズムを初めて解明しました。この画期的な発見は、生命の進化の謎を解き明かすだけでなく、がんなどの疾患研究にも新たな光を当てるものとして注目されています。
新しい遺伝子と、古くからの疑問
ほとんどの遺伝子は古代から存在し、種を超えて共有されています。しかし、遺伝子のごく一部は比較的新しく、かつては何も情報をコードしていなかったDNA領域から自然発生的に出現したものです。今回、ロックフェラー大学の研究者たちは、ショウジョウバエでこれらの遺伝子を約10年間追い続けた結果、これらのde novo遺伝子がどのように制御されているかを発見しました。『Nature Ecology & Evolution』誌と『PNAS』誌に掲載された2つの補完的な研究で、研究チームは転写因子とゲノム上の隣接遺伝子が、これらの新しい遺伝子のスイッチを入れ、細胞内のネットワークに統合する仕組みを明らかにしました。これは、その主要な制御因子を特定した初めての研究となります。これらの発見は、新しい遺伝子がどのように機能的になるかに光を当てるものであり、進化生物学や遺伝子制御、そしてそれらの機能不全から生じる疾患の理解に広
髪か皮膚か?幹細胞の「運命の決断」を司る栄養素セリンの役割
 私たちの皮膚の下では、細胞たちが状況に応じてその役割を巧みに切り替える、驚くべきドラマが繰り広げられています。普段は髪の毛を作ることに専念している細胞が、いざという時にはその仕事を中断し、傷ついた皮膚を治すための「応援」に駆けつけるのです。この細胞の賢い「キャリアチェンジ」の裏には、一体どのような仕組みがあるのでしょうか。最新の研究が、その謎を解き明かす鍵となるシグナルを突き止めました。
皮膚には、表皮幹細胞と毛包幹細胞という2種類の成体幹細胞が存在します。それぞれの仕事は、皮膚を維持するか、髪の成長を維持するか、とはっきりと定義されているように見えます。しかし、ロックフェラー大学の研究が示したように、毛包幹細胞は、皮膚が傷を負った際にチームを乗り換え、治癒に協力することができます。では、これらの細胞はどのようにして役割転換の時を知るのでしょうか?
この最初の発見をした研究室が、今回、HFSCに毛髪サイクルを中断して皮膚修復に着手するよう指示する重要なシグナルを特定しました。それは、幹細胞にエネルギーを必須のタスクのために温存するよう指示する、統合的ストレス応答です。皮膚において、栄養不足は、肉や穀物、牛乳などの一般的な食品に含まれるセリンとして知られる非必須アミノ酸によって感知されます。2025年6月12日に「Cell Metabolism」誌に掲載された研究で実証されたように、セリンのレベルが低下するとISRが活性化し、HFSCは髪の生産を遅らせます。栄養不足に加えて皮膚が損傷すると、ISRはさらに強く活性化し、髪の生産を停止させて、そのエネルギーを皮膚の修復へと振り向けます。この優先順位の再設定が、治癒プロセスを加速させるのです。このオープンアクセス論文のタイトルは「The Integrated Stress Response Fine-Tunes Stem
私たちの皮膚の下では、細胞たちが状況に応じてその役割を巧みに切り替える、驚くべきドラマが繰り広げられています。普段は髪の毛を作ることに専念している細胞が、いざという時にはその仕事を中断し、傷ついた皮膚を治すための「応援」に駆けつけるのです。この細胞の賢い「キャリアチェンジ」の裏には、一体どのような仕組みがあるのでしょうか。最新の研究が、その謎を解き明かす鍵となるシグナルを突き止めました。
皮膚には、表皮幹細胞と毛包幹細胞という2種類の成体幹細胞が存在します。それぞれの仕事は、皮膚を維持するか、髪の成長を維持するか、とはっきりと定義されているように見えます。しかし、ロックフェラー大学の研究が示したように、毛包幹細胞は、皮膚が傷を負った際にチームを乗り換え、治癒に協力することができます。では、これらの細胞はどのようにして役割転換の時を知るのでしょうか?
この最初の発見をした研究室が、今回、HFSCに毛髪サイクルを中断して皮膚修復に着手するよう指示する重要なシグナルを特定しました。それは、幹細胞にエネルギーを必須のタスクのために温存するよう指示する、統合的ストレス応答です。皮膚において、栄養不足は、肉や穀物、牛乳などの一般的な食品に含まれるセリンとして知られる非必須アミノ酸によって感知されます。2025年6月12日に「Cell Metabolism」誌に掲載された研究で実証されたように、セリンのレベルが低下するとISRが活性化し、HFSCは髪の生産を遅らせます。栄養不足に加えて皮膚が損傷すると、ISRはさらに強く活性化し、髪の生産を停止させて、そのエネルギーを皮膚の修復へと振り向けます。この優先順位の再設定が、治癒プロセスを加速させるのです。このオープンアクセス論文のタイトルは「The Integrated Stress Response Fine-Tunes Stem
あなたの愛犬が農業を救う?ペットが害虫探知犬になる最新研究
 もし、あなたの愛犬が大好きなおやつやオモチャを探す遊びが、国のブドウ園や果樹園、そして森林を破壊的な侵略者から守る活動につながるとしたら、どう思いますか?実は、それが可能かもしれないのです。バージニア工科大学が主導した新しい研究により、ごく普通の人々とそのペットで構成されるボランティアの犬とハンドラーのチームが、マダラランフライという侵略的な昆虫の、見つけにくい卵塊を効果的に検出できることが明らかになりました。この昆虫は、アメリカ東部から中部にかけての農場や森林に深刻な被害をもたらしています。この研究成果は、2025年7月16日にオープンアクセス論文として「PeerJ Life and Environment」誌に掲載され、そのタイトルは「Evaluating the Effectiveness of Participatory Science Dog Teams to Detect Devitalized Spotted Lanternfly (Lycorma delicatula) Egg Masses(市民科学者の犬チームによる不活化マダラランタンフライ卵塊の検出効果の評価)」です。市民の犬とハンドラーのチームが、プロの自然保護探知犬に匹敵する検出成功率を達成できることを示した、初めての研究となります。
「これらのチームは、市民科学者とその愛犬が、侵略的外来種から農業と環境を守る上で意義のある役割を果たせることを証明しました」と、この研究の筆頭著者であり、最近バージニア工科大学の農学・生命科学部で博士号を取得したサリー・ディキンソン博士(Sally Dickinson, PhD)は語ります。「適切な訓練を積めば、飼い主は自分のペットを環境保護のための強力なパートナーに変えることができるのです。」
侵略的な害虫、隠された標的
アジア原産のマダラランタンフ
もし、あなたの愛犬が大好きなおやつやオモチャを探す遊びが、国のブドウ園や果樹園、そして森林を破壊的な侵略者から守る活動につながるとしたら、どう思いますか?実は、それが可能かもしれないのです。バージニア工科大学が主導した新しい研究により、ごく普通の人々とそのペットで構成されるボランティアの犬とハンドラーのチームが、マダラランフライという侵略的な昆虫の、見つけにくい卵塊を効果的に検出できることが明らかになりました。この昆虫は、アメリカ東部から中部にかけての農場や森林に深刻な被害をもたらしています。この研究成果は、2025年7月16日にオープンアクセス論文として「PeerJ Life and Environment」誌に掲載され、そのタイトルは「Evaluating the Effectiveness of Participatory Science Dog Teams to Detect Devitalized Spotted Lanternfly (Lycorma delicatula) Egg Masses(市民科学者の犬チームによる不活化マダラランタンフライ卵塊の検出効果の評価)」です。市民の犬とハンドラーのチームが、プロの自然保護探知犬に匹敵する検出成功率を達成できることを示した、初めての研究となります。
「これらのチームは、市民科学者とその愛犬が、侵略的外来種から農業と環境を守る上で意義のある役割を果たせることを証明しました」と、この研究の筆頭著者であり、最近バージニア工科大学の農学・生命科学部で博士号を取得したサリー・ディキンソン博士(Sally Dickinson, PhD)は語ります。「適切な訓練を積めば、飼い主は自分のペットを環境保護のための強力なパートナーに変えることができるのです。」
侵略的な害虫、隠された標的
アジア原産のマダラランタンフ
老化による慢性炎症は避けられる?キツネザルの研究が示すアンチエイジングの新常識
 年を重ねるとともに体内で静かに進行する「慢性炎症」。これが心臓病やがんなど、さまざまな病気の引き金になることをご存知ですか? この「加齢性炎症(インフラメイジング)」は、人間にとって避けられない運命なのでしょうか。この長年の謎を解く鍵は、意外にも、遠い親戚である愛らしいキツネザルが握っていました。
この研究は、なぜ私たちが加齢に伴う疾患に苦しむのかについての手がかりを提供してくれます。
キツネザルは、ヒトの炎症と老化、いわゆる「加齢性炎症」について何を教えてくれるのでしょうか? それは、霊長類の生活史と老化の進化を研究するデューク大学の生物人類学者、エレイン・ゲバラ博士(Elaine Guevara, PhD)が解明しようとした問いです。ワオキツネザルとシファカキツネザルにおける加齢に伴う炎症に関する新たに発表された研究で、ゲバラ博士は、私たちがヒトにおけるインフラメイジングの不可避性について、考え直すべきかもしれないことを発見しました。多くの点で似ていながらも、ワオキツネザルとシファカキツネザルは生活ペースや寿命に違いがあり、有益な比較対象となります。キツネザルとヒトは同じ霊長類であり、数百万年前に生きていた共通の祖先を持つため、ヒトの進化について貴重な洞察を与えてくれます。ゲバラ博士によれば、彼女の発見は「驚くべきもの」でした。
「私たちの予測とは反対に、どちらの種も酸化ストレスのマーカーに加齢に伴う変化を示しませんでした。どちらのキツネザルも加齢に伴う炎症の変化を示さなかったのです。それどころか、私たちの予測に反して、ワオキツネザルは加齢とともに炎症がわずかに減少する傾向を示しました」とゲバラ博士は述べています。
この発見は、他の非ヒト霊長類に関する最近のいくつかの研究と一致しており、キツネザルがヒトで広く観察される「インフラメイジング」の現象を回避し
年を重ねるとともに体内で静かに進行する「慢性炎症」。これが心臓病やがんなど、さまざまな病気の引き金になることをご存知ですか? この「加齢性炎症(インフラメイジング)」は、人間にとって避けられない運命なのでしょうか。この長年の謎を解く鍵は、意外にも、遠い親戚である愛らしいキツネザルが握っていました。
この研究は、なぜ私たちが加齢に伴う疾患に苦しむのかについての手がかりを提供してくれます。
キツネザルは、ヒトの炎症と老化、いわゆる「加齢性炎症」について何を教えてくれるのでしょうか? それは、霊長類の生活史と老化の進化を研究するデューク大学の生物人類学者、エレイン・ゲバラ博士(Elaine Guevara, PhD)が解明しようとした問いです。ワオキツネザルとシファカキツネザルにおける加齢に伴う炎症に関する新たに発表された研究で、ゲバラ博士は、私たちがヒトにおけるインフラメイジングの不可避性について、考え直すべきかもしれないことを発見しました。多くの点で似ていながらも、ワオキツネザルとシファカキツネザルは生活ペースや寿命に違いがあり、有益な比較対象となります。キツネザルとヒトは同じ霊長類であり、数百万年前に生きていた共通の祖先を持つため、ヒトの進化について貴重な洞察を与えてくれます。ゲバラ博士によれば、彼女の発見は「驚くべきもの」でした。
「私たちの予測とは反対に、どちらの種も酸化ストレスのマーカーに加齢に伴う変化を示しませんでした。どちらのキツネザルも加齢に伴う炎症の変化を示さなかったのです。それどころか、私たちの予測に反して、ワオキツネザルは加齢とともに炎症がわずかに減少する傾向を示しました」とゲバラ博士は述べています。
この発見は、他の非ヒト霊長類に関する最近のいくつかの研究と一致しており、キツネザルがヒトで広く観察される「インフラメイジング」の現象を回避し
ネアンデルタール人のDNAが原因?神経疾患「キアリ奇形」の起源に迫る最新研究
 もし、現代人を悩ませるある病気の起源が、私たちの遠い祖先と、今はもう絶滅してしまった古代の親戚との出会いにまで遡るとしたら、どう思われるでしょうか。サイモンフレーザー大学(SFU)が主導した新しい研究は、ネアンデルタール人との異種交配が、今日、最大で100人に1人が罹患すると推定されるある神経学的疾患の起源である可能性を明らかにしました。
この研究は、2025年6月27日に「Evolution, Medicine, and Public Health」誌に掲載され、SFUの元博士研究員であるキンバリー・プロンプ氏(Kimberly Plomp)と、人類進化学カナダ研究チェアであり考古学部の教授であるマーク・コラード博士(Mark Collard, PhD)が主導しました。研究チームの発見は、深刻で時には命にかかわる神経疾患であるキアリ奇形1型が、数万年前に異種交配を通じてヒトの遺伝子プールに入り込んだネアンデルタール人の遺伝子に関連している可能性を示唆しています。このオープンアクセス論文のタイトルは、「A test of the Archaic Homo Introgression Hypothesis for the Chiari Malformation Type I(キアリ奇形1型に対する古代ヒトからの遺伝子移入仮説の検証)」です。
キアリ奇形1型は、後頭部の頭蓋骨が脳を適切に収容するには小さすぎる場合に発生し、脳の基部の一部が頭蓋骨から脊柱管にはみ出してしまいます。これにより、はみ出した脳の部分が圧迫され、頭痛、首の痛み、めまいなどの症状を引き起こし、重症の場合には脳のはみ出しが大きすぎると死に至ることもあります。
「他の科学分野と同様に、医学においても原因と結果の連鎖を明らかにすることは重要です。病状を引き起こす因果関係の連鎖をより明確にできれば、そ
もし、現代人を悩ませるある病気の起源が、私たちの遠い祖先と、今はもう絶滅してしまった古代の親戚との出会いにまで遡るとしたら、どう思われるでしょうか。サイモンフレーザー大学(SFU)が主導した新しい研究は、ネアンデルタール人との異種交配が、今日、最大で100人に1人が罹患すると推定されるある神経学的疾患の起源である可能性を明らかにしました。
この研究は、2025年6月27日に「Evolution, Medicine, and Public Health」誌に掲載され、SFUの元博士研究員であるキンバリー・プロンプ氏(Kimberly Plomp)と、人類進化学カナダ研究チェアであり考古学部の教授であるマーク・コラード博士(Mark Collard, PhD)が主導しました。研究チームの発見は、深刻で時には命にかかわる神経疾患であるキアリ奇形1型が、数万年前に異種交配を通じてヒトの遺伝子プールに入り込んだネアンデルタール人の遺伝子に関連している可能性を示唆しています。このオープンアクセス論文のタイトルは、「A test of the Archaic Homo Introgression Hypothesis for the Chiari Malformation Type I(キアリ奇形1型に対する古代ヒトからの遺伝子移入仮説の検証)」です。
キアリ奇形1型は、後頭部の頭蓋骨が脳を適切に収容するには小さすぎる場合に発生し、脳の基部の一部が頭蓋骨から脊柱管にはみ出してしまいます。これにより、はみ出した脳の部分が圧迫され、頭痛、首の痛み、めまいなどの症状を引き起こし、重症の場合には脳のはみ出しが大きすぎると死に至ることもあります。
「他の科学分野と同様に、医学においても原因と結果の連鎖を明らかにすることは重要です。病状を引き起こす因果関係の連鎖をより明確にできれば、そ
犬の嗅覚がパーキンソン病を早期発見?最新研究が示す驚きの可能性
 もし、すぐそばにいる犬が、目に見えない病気のサインを嗅ぎ分けてくれるとしたら、未来の医療はどのように変わるでしょうか。そんなSFのような話が、現実のものとなるかもしれません。最新の研究で、訓練された犬が皮膚の匂いからパーキンソン病を驚くべき精度で検出できることが明らかになりました。この記事では、未来の診断方法に革命をもたらすかもしれない、犬と科学者たちの素晴らしい挑戦についてご紹介します。
パーキンソン病を患う人々は特有の匂いを持ち、訓練された犬が皮膚から採取した綿棒の匂いを確実に嗅ぎ分けられることが、新しい研究で示されました。この研究は、英国の慈善団体であるメディカル・ディテクション・ドッグズ(Medical Detection Dogs)および、ブリストル大学、マンチェスター大学との共同で行われ、2025年7月15日付の「パーキンソン病ジャーナル」に掲載されました。このオープンアクセスの論文は、「Trained Dogs Can Detect the Odor of Parkinson’s Disease(訓練された犬はパーキンソン病の匂いを検出できる)」と題されています。
メディカル・ディテクション・ドッグズによって訓練された2頭の犬は、パーキンソン病患者とそうでない人々の皮脂(sebum)サンプルの違いを識別するよう教え込まれました。二重盲検試験において、研究者たちは最大80%の感度と最大98%の特異度という高い精度を示しました。さらに驚くべきことに、犬たちは他の疾患を併発している患者のサンプルからも、パーキンソン病の匂いを検出することができたのです。
犬たちは、パーキンソン病と診断された人々からの200以上の匂いサンプルと、健常者からの対照サンプルを用いて、数週間にわたる訓練を受けました。サンプルはスタンドに設置され、犬たちは陽性サンプルを正しく指示した
もし、すぐそばにいる犬が、目に見えない病気のサインを嗅ぎ分けてくれるとしたら、未来の医療はどのように変わるでしょうか。そんなSFのような話が、現実のものとなるかもしれません。最新の研究で、訓練された犬が皮膚の匂いからパーキンソン病を驚くべき精度で検出できることが明らかになりました。この記事では、未来の診断方法に革命をもたらすかもしれない、犬と科学者たちの素晴らしい挑戦についてご紹介します。
パーキンソン病を患う人々は特有の匂いを持ち、訓練された犬が皮膚から採取した綿棒の匂いを確実に嗅ぎ分けられることが、新しい研究で示されました。この研究は、英国の慈善団体であるメディカル・ディテクション・ドッグズ(Medical Detection Dogs)および、ブリストル大学、マンチェスター大学との共同で行われ、2025年7月15日付の「パーキンソン病ジャーナル」に掲載されました。このオープンアクセスの論文は、「Trained Dogs Can Detect the Odor of Parkinson’s Disease(訓練された犬はパーキンソン病の匂いを検出できる)」と題されています。
メディカル・ディテクション・ドッグズによって訓練された2頭の犬は、パーキンソン病患者とそうでない人々の皮脂(sebum)サンプルの違いを識別するよう教え込まれました。二重盲検試験において、研究者たちは最大80%の感度と最大98%の特異度という高い精度を示しました。さらに驚くべきことに、犬たちは他の疾患を併発している患者のサンプルからも、パーキンソン病の匂いを検出することができたのです。
犬たちは、パーキンソン病と診断された人々からの200以上の匂いサンプルと、健常者からの対照サンプルを用いて、数週間にわたる訓練を受けました。サンプルはスタンドに設置され、犬たちは陽性サンプルを正しく指示した
誰でも作れる感染症の検査薬?ウィーンとガーナの共同研究が拓く診断技術の未来
 感染症のパンデミックが起きたとき、誰もが迅速に検査を受けられる世界は実現可能なのでしょうか?特に、医療資源が限られた国々では、高価で冷蔵保存が必要な検査キットは大きな壁となってきました。しかし今、その常識を覆す画期的な技術が登場しました。常温で運べて、誰でも安価に作れる「オープンソース」の診断法です。この技術が、世界の健康格差をどう変えるのか、その可能性に迫ります。
広範な分子診断へのアクセスを確保する上でのボトルネックは、特に低・中所得国において、迅速なポイントオブケア検査に伴う高コストと物流の複雑さでした。今回、2025年7月14日にライフサイエンス・アライアンス誌(LSA: Life Science Alliance)に掲載された研究で概説された共同研究の取り組みは、凍結乾燥されたオープンソースの逆転写ループ介在性等温増幅法(RT-LAMP: reverse transcription loop-mediated isothermal amplification)アッセイを病原体検出のために開発することで、これらの課題に対処しました。この方法は、新型コロナウイルス(COVID-19)にうまく適用され、診断を世界的に、よりアクセスしやすく、手頃な価格にすることを目指しています。
このLSAのオープンアクセス論文のタイトルは、「A Lyophilized Open-Source RT-LAMP Assay for Molecular Diagnostics in Resource-Limited Settings(資源が限られた環境における分子診断のための凍結乾燥オープンソースRT-LAMP法)」です。この新しい研究では、オーストリア、ウィーンのウィーン・バイオセンターと、ガーナ、レゴンのガーナ大学にある西アフリカ感染症病原体細胞生物学センターの科学者たちが、逆転
感染症のパンデミックが起きたとき、誰もが迅速に検査を受けられる世界は実現可能なのでしょうか?特に、医療資源が限られた国々では、高価で冷蔵保存が必要な検査キットは大きな壁となってきました。しかし今、その常識を覆す画期的な技術が登場しました。常温で運べて、誰でも安価に作れる「オープンソース」の診断法です。この技術が、世界の健康格差をどう変えるのか、その可能性に迫ります。
広範な分子診断へのアクセスを確保する上でのボトルネックは、特に低・中所得国において、迅速なポイントオブケア検査に伴う高コストと物流の複雑さでした。今回、2025年7月14日にライフサイエンス・アライアンス誌(LSA: Life Science Alliance)に掲載された研究で概説された共同研究の取り組みは、凍結乾燥されたオープンソースの逆転写ループ介在性等温増幅法(RT-LAMP: reverse transcription loop-mediated isothermal amplification)アッセイを病原体検出のために開発することで、これらの課題に対処しました。この方法は、新型コロナウイルス(COVID-19)にうまく適用され、診断を世界的に、よりアクセスしやすく、手頃な価格にすることを目指しています。
このLSAのオープンアクセス論文のタイトルは、「A Lyophilized Open-Source RT-LAMP Assay for Molecular Diagnostics in Resource-Limited Settings(資源が限られた環境における分子診断のための凍結乾燥オープンソースRT-LAMP法)」です。この新しい研究では、オーストリア、ウィーンのウィーン・バイオセンターと、ガーナ、レゴンのガーナ大学にある西アフリカ感染症病原体細胞生物学センターの科学者たちが、逆転
初経年齢が将来の病気リスクを左右する?女性なら知っておきたい健康の新常識
 あなたが初めて生理(初経)を迎えたのは何歳でしたか?ほとんどの女性が覚えているであろうこの出来事が、実は、将来の健康を占う重要なサインかもしれない――。そんな驚きの研究結果が、ブラジルの大規模な調査から明らかになりました。初経が早すぎても、遅すぎても、将来の病気のリスクに関わってくるというのです。この記事では、あなたの過去の経験が未来の健康管理にどう繋がるのかを詳しく解説します。
2025年7月13日(日)にカリフォルニア州サンフランシスコで開催された内分泌学会の年次総会「ENDO 2025」で発表された研究によると、女性が初経を迎える年齢は、肥満、糖尿病、心臓病、生殖に関する問題といった疾患の長期的なリスクについて、貴重な手がかりを提供してくれる可能性があります。このブラジルの研究では、初経(女性が初めて月経を迎える年齢)が早い場合も遅い場合も、それぞれ異なる健康リスクと関連していることが明らかになりました。
初経を10歳未満で迎えた女性は、後年、肥満、高血圧、糖尿病、心臓の問題、そして子癇前症のような生殖に関する問題を発症する可能性が高くなりました。一方、15歳以降に初経を迎えた女性は、肥満になる可能性は低いものの、月経不順や特定の心臓疾患のリスクが高いことが分かりました。
「私たちは今、ブラジルの大規模な人口調査から、思春期が早い場合と遅い場合の両方が、長期的に異なる健康への影響を及ぼしうることを裏付けるエビデンスを得ました」と、研究著者であるブラジル、サンパウロ大学のフラビア・レゼンデ・ティナノ博士(Dr. Flávia Rezende Tinano)は述べています。「早発初経は複数の代謝性疾患や心臓の問題のリスクを高める一方で、遅発初経は肥満を防ぐかもしれませんが、特定の心臓や月経の問題を増加させる可能性があります。ほとんどの女性は自分の初経がいつ
あなたが初めて生理(初経)を迎えたのは何歳でしたか?ほとんどの女性が覚えているであろうこの出来事が、実は、将来の健康を占う重要なサインかもしれない――。そんな驚きの研究結果が、ブラジルの大規模な調査から明らかになりました。初経が早すぎても、遅すぎても、将来の病気のリスクに関わってくるというのです。この記事では、あなたの過去の経験が未来の健康管理にどう繋がるのかを詳しく解説します。
2025年7月13日(日)にカリフォルニア州サンフランシスコで開催された内分泌学会の年次総会「ENDO 2025」で発表された研究によると、女性が初経を迎える年齢は、肥満、糖尿病、心臓病、生殖に関する問題といった疾患の長期的なリスクについて、貴重な手がかりを提供してくれる可能性があります。このブラジルの研究では、初経(女性が初めて月経を迎える年齢)が早い場合も遅い場合も、それぞれ異なる健康リスクと関連していることが明らかになりました。
初経を10歳未満で迎えた女性は、後年、肥満、高血圧、糖尿病、心臓の問題、そして子癇前症のような生殖に関する問題を発症する可能性が高くなりました。一方、15歳以降に初経を迎えた女性は、肥満になる可能性は低いものの、月経不順や特定の心臓疾患のリスクが高いことが分かりました。
「私たちは今、ブラジルの大規模な人口調査から、思春期が早い場合と遅い場合の両方が、長期的に異なる健康への影響を及ぼしうることを裏付けるエビデンスを得ました」と、研究著者であるブラジル、サンパウロ大学のフラビア・レゼンデ・ティナノ博士(Dr. Flávia Rezende Tinano)は述べています。「早発初経は複数の代謝性疾患や心臓の問題のリスクを高める一方で、遅発初経は肥満を防ぐかもしれませんが、特定の心臓や月経の問題を増加させる可能性があります。ほとんどの女性は自分の初経がいつ
コオロギに寄生し、赤ちゃんを産むハエ?驚異の生態から補聴器技術まで
 歌でメスを呼ぶコオロギ。その美しい歌声は、自らの命を奪う恐ろしい寄生バエを呼び寄せているかもしれません。このヤドリバエは、ハエの世界では極めて珍しい「胎生」、つまり赤ちゃんを産むという驚きの繁殖方法を持っていました。学部生が主導した研究によって明らかになった、この小さな生物の驚異的な生態と、その発見がもたらす未来の科学技術への応用可能性に迫ります。
2025年7月10日にAnnals of the Entomological Society of America誌に掲載された新しい研究は、この特異なハエがどのように発生し、生きた子を産むのかについて、これまでで最も詳細な見解を提供しています。ハエの世界では珍しい現象です。セント・オラフ大学の学部生であるパーカー・ヘンダーソン氏(Parker Henderson ‘22)が主導したこの研究は、ヤドリバエの一種であるOrmia ochraceaの繁殖生物学に関する驚くべき洞察を明らかにしました。このハエは、超鋭敏な指向性聴覚を用いて歌うコオロギを見つけ出す能力で知られています。
チームは解剖、蛍光染色、顕微鏡観察を組み合わせ、メスのO. ochraceaが子宮のような構造の中で発生中の胚を保持し、完全に形成された幼虫として孵化するまで体内で栄養を与える様子を記録しました。これらの幼虫はその後、宿主であるコオロギの上に直接産み付けられ、体内に潜り込み、コオロギの体内で発生を完了させ、最終的に宿主を死に至らしめます。
この研究は、胚が子宮内で大幅に成長し、発生中に母親から栄養供給を受けている可能性が高いことを記述しており、これは腺栄養胎生として知られる繁殖様式です。また、この研究は部分的な単為生殖という驚くべき能力も明らかにしました。処女のメスから得られた未受精卵が、核分裂や初期のパターン形成を含む発生の初期段階を経る
歌でメスを呼ぶコオロギ。その美しい歌声は、自らの命を奪う恐ろしい寄生バエを呼び寄せているかもしれません。このヤドリバエは、ハエの世界では極めて珍しい「胎生」、つまり赤ちゃんを産むという驚きの繁殖方法を持っていました。学部生が主導した研究によって明らかになった、この小さな生物の驚異的な生態と、その発見がもたらす未来の科学技術への応用可能性に迫ります。
2025年7月10日にAnnals of the Entomological Society of America誌に掲載された新しい研究は、この特異なハエがどのように発生し、生きた子を産むのかについて、これまでで最も詳細な見解を提供しています。ハエの世界では珍しい現象です。セント・オラフ大学の学部生であるパーカー・ヘンダーソン氏(Parker Henderson ‘22)が主導したこの研究は、ヤドリバエの一種であるOrmia ochraceaの繁殖生物学に関する驚くべき洞察を明らかにしました。このハエは、超鋭敏な指向性聴覚を用いて歌うコオロギを見つけ出す能力で知られています。
チームは解剖、蛍光染色、顕微鏡観察を組み合わせ、メスのO. ochraceaが子宮のような構造の中で発生中の胚を保持し、完全に形成された幼虫として孵化するまで体内で栄養を与える様子を記録しました。これらの幼虫はその後、宿主であるコオロギの上に直接産み付けられ、体内に潜り込み、コオロギの体内で発生を完了させ、最終的に宿主を死に至らしめます。
この研究は、胚が子宮内で大幅に成長し、発生中に母親から栄養供給を受けている可能性が高いことを記述しており、これは腺栄養胎生として知られる繁殖様式です。また、この研究は部分的な単為生殖という驚くべき能力も明らかにしました。処女のメスから得られた未受精卵が、核分裂や初期のパターン形成を含む発生の初期段階を経る
神経幹細胞は脳だけではなかった!手足や肺にも存在、再生医療に新たな希望
 脳や脊髄を再生する鍵「神経幹細胞」。この重要な細胞は、これまで脳と脊髄という、厳重に守られた「聖域」にしか存在しないと考えられてきました。しかし、もしあなたの手足や肺といった、もっと身近な場所にも、この“万能細胞”が眠っているとしたら…?科学の常識を覆す、驚くべき発見が、再生医療に新たな扉を開こうとしています。
前例のない国際共同研究において、香港大学LKS医学部(HKUMed)の研究者たちは、マックス・プランク分子生物医学研究所との協力により、実験用マウスの中枢神経系の外に位置する、これまで知られていなかった新しいタイプの神経幹細胞を発見しました。これは、「神経幹細胞は脳と脊髄に限定される」という長年の定説に挑戦するものであり、神経疾患や外傷を治療する再生医療において、変革的な可能性を開くものです。この発見は『Nature Cell Biology』誌に掲載され、『Nature』誌によって過去1年間の「幹細胞・発生生物学の一年」コレクションにも選ばれました。2025年4月10日に発表されたこのオープンアクセスの論文タイトルは「Multipotent Neural Stem Cells Originating from Neuroepithelium Exist Outside the Mouse Central Nervous System(神経上皮に由来する多能性神経幹細胞はマウス中枢神経系の外に存在する)」です。
何十年もの間、科学者たちは、哺乳類の神経幹細胞(中枢神経系の発達に不可欠な、自己複製能と様々な細胞になる能力を持つ多能性細胞)は、中枢神経系の中にのみ存在すると信じてきました。しかし、HKUMed生物医科学系の研究助教であるハン・ドン博士(Han Dong, PhD)と、同教授でありInnoHKトランスレーショナル幹細胞生物学センターのマネージングデ
脳や脊髄を再生する鍵「神経幹細胞」。この重要な細胞は、これまで脳と脊髄という、厳重に守られた「聖域」にしか存在しないと考えられてきました。しかし、もしあなたの手足や肺といった、もっと身近な場所にも、この“万能細胞”が眠っているとしたら…?科学の常識を覆す、驚くべき発見が、再生医療に新たな扉を開こうとしています。
前例のない国際共同研究において、香港大学LKS医学部(HKUMed)の研究者たちは、マックス・プランク分子生物医学研究所との協力により、実験用マウスの中枢神経系の外に位置する、これまで知られていなかった新しいタイプの神経幹細胞を発見しました。これは、「神経幹細胞は脳と脊髄に限定される」という長年の定説に挑戦するものであり、神経疾患や外傷を治療する再生医療において、変革的な可能性を開くものです。この発見は『Nature Cell Biology』誌に掲載され、『Nature』誌によって過去1年間の「幹細胞・発生生物学の一年」コレクションにも選ばれました。2025年4月10日に発表されたこのオープンアクセスの論文タイトルは「Multipotent Neural Stem Cells Originating from Neuroepithelium Exist Outside the Mouse Central Nervous System(神経上皮に由来する多能性神経幹細胞はマウス中枢神経系の外に存在する)」です。
何十年もの間、科学者たちは、哺乳類の神経幹細胞(中枢神経系の発達に不可欠な、自己複製能と様々な細胞になる能力を持つ多能性細胞)は、中枢神経系の中にのみ存在すると信じてきました。しかし、HKUMed生物医科学系の研究助教であるハン・ドン博士(Han Dong, PhD)と、同教授でありInnoHKトランスレーショナル幹細胞生物学センターのマネージングデ
私たちの祖先はいつから感染症に苦しんでいた?6,500年前のDNAから探る病気の歴史
 近年の新型コロナウイルスのように、動物から人へとうつる感染症は、いつから私たちの脅威となったのでしょうか?その答えは、数千年前の私たちの祖先の骨や歯に刻まれていました。古代人のDNAを解析するという驚くべき手法で、人と動物との関わりがいかにして私たちの健康を永遠に変えてしまったのか、感染症の壮大な歴史を解き明かした最新の研究をご紹介します。
コペンハーゲン大学およびケンブリッジ大学の教授であるエスケ・ウィラースレフ教授(Eske Willerslev)が率いる研究チームは、ユーラシア大陸の先史時代の人骨から、214種類もの既知のヒト病原体の古代DNAを回収することに成功しました。この研究により、近年の新型コロナウイルスのように動物からヒトに感染する人獣共通感染症の最も古い証拠が約6,500年前に遡ること、そして約5,000年前にその感染がより広範囲に拡大したことなどが示されました。これは感染症の歴史に関するこれまでで最大規模の研究であり、2025年7月9日付の科学誌Natureに掲載されました。このオープンアクセスの論文のタイトルは「The Spatiotemporal Distribution of Human Pathogens in Ancient Eurasia(古代ユーラシアにおけるヒト病原体の時空間分布)」です。
研究者たちは、中には37,000年前にまで遡るものも含む、1,300人以上の先史時代の人々のDNAを分析しました。これらの古代の骨や歯は、細菌、ウイルス、寄生虫によって引き起こされる病気の発達について、他に類を見ない洞察をもたらしてくれました
この結果は、人類が家畜と密接に共存するようになったこと、そしてポントス草原からの牧畜民による大規模な移住が、これらの病気の拡大に決定的な役割を果たしたことを示唆しています。
「私たちは長い間、農耕
近年の新型コロナウイルスのように、動物から人へとうつる感染症は、いつから私たちの脅威となったのでしょうか?その答えは、数千年前の私たちの祖先の骨や歯に刻まれていました。古代人のDNAを解析するという驚くべき手法で、人と動物との関わりがいかにして私たちの健康を永遠に変えてしまったのか、感染症の壮大な歴史を解き明かした最新の研究をご紹介します。
コペンハーゲン大学およびケンブリッジ大学の教授であるエスケ・ウィラースレフ教授(Eske Willerslev)が率いる研究チームは、ユーラシア大陸の先史時代の人骨から、214種類もの既知のヒト病原体の古代DNAを回収することに成功しました。この研究により、近年の新型コロナウイルスのように動物からヒトに感染する人獣共通感染症の最も古い証拠が約6,500年前に遡ること、そして約5,000年前にその感染がより広範囲に拡大したことなどが示されました。これは感染症の歴史に関するこれまでで最大規模の研究であり、2025年7月9日付の科学誌Natureに掲載されました。このオープンアクセスの論文のタイトルは「The Spatiotemporal Distribution of Human Pathogens in Ancient Eurasia(古代ユーラシアにおけるヒト病原体の時空間分布)」です。
研究者たちは、中には37,000年前にまで遡るものも含む、1,300人以上の先史時代の人々のDNAを分析しました。これらの古代の骨や歯は、細菌、ウイルス、寄生虫によって引き起こされる病気の発達について、他に類を見ない洞察をもたらしてくれました
この結果は、人類が家畜と密接に共存するようになったこと、そしてポントス草原からの牧畜民による大規模な移住が、これらの病気の拡大に決定的な役割を果たしたことを示唆しています。
「私たちは長い間、農耕
あなたの脳は実年齢より若い?血液でわかる生物学的年齢と将来の病気リスク
 誕生日ケーキのろうそくの数は、あなたの本当の年齢を語ってはくれません。同窓会に行くと、ある人は若々しく、ある人は少し老けて見える、そんな経験はありませんか? 実は私たちには、暦の上の年齢とは別に、体の状態をより正確に示す「生物学的年齢」というものがあります。そして今、たった一滴の血液から、脳や心臓といった11もの臓器がそれぞれ「何歳」なのかを判定し、将来の健康リスクまで予測する画期的な技術が開発されました。この記事では、あなたの体の“本当の年齢”を解き明かす、未来の医療の姿に迫ります。
スタンフォード大学医学部で開発された血液検査の分析により、個人の体内にある11の異なる臓器系の「生物学的年齢」を判定し、健康への影響を予測できることが明らかになりました。
誕生日ケーキのろうそくは、物語のすべてを語ってくれるわけではありません。高校の同窓会に出席したことのある人なら誰でもわかるように、人によって老化のスピードは異なります。ケーキにろうそくを立てた人は、あなたの暦年齢を推測する必要はなかったでしょう。しかし研究によれば、私たちには「生物学的年齢」と呼ばれるものもあり、これは私たちの生理学的状態や、心臓疾患からアルツハイマー病といった加齢関連疾患を発症する可能性を示す、不可解ながらもより正確な指標です。私たちは皆、しわや目の下のたるみなど、特徴的な兆候を顔から読み取って、ほとんど無意識に人の実年齢を推測しています。しかし、その人の脳や動脈、腎臓が何歳なのかを知ることはまた別の話です。スタンフォード大学医学部の研究者による新しい研究によると、私たちの体内に収められた臓器もまた、それぞれ異なる速度で老化しているのです。
「私たちは、あなたの臓器の年齢を示す血液ベースの指標を開発しました」と、神経学・神経科学の教授であり、ウー・ツァイ神経科学研究所のナイト・イニシアチブ・フォ
誕生日ケーキのろうそくの数は、あなたの本当の年齢を語ってはくれません。同窓会に行くと、ある人は若々しく、ある人は少し老けて見える、そんな経験はありませんか? 実は私たちには、暦の上の年齢とは別に、体の状態をより正確に示す「生物学的年齢」というものがあります。そして今、たった一滴の血液から、脳や心臓といった11もの臓器がそれぞれ「何歳」なのかを判定し、将来の健康リスクまで予測する画期的な技術が開発されました。この記事では、あなたの体の“本当の年齢”を解き明かす、未来の医療の姿に迫ります。
スタンフォード大学医学部で開発された血液検査の分析により、個人の体内にある11の異なる臓器系の「生物学的年齢」を判定し、健康への影響を予測できることが明らかになりました。
誕生日ケーキのろうそくは、物語のすべてを語ってくれるわけではありません。高校の同窓会に出席したことのある人なら誰でもわかるように、人によって老化のスピードは異なります。ケーキにろうそくを立てた人は、あなたの暦年齢を推測する必要はなかったでしょう。しかし研究によれば、私たちには「生物学的年齢」と呼ばれるものもあり、これは私たちの生理学的状態や、心臓疾患からアルツハイマー病といった加齢関連疾患を発症する可能性を示す、不可解ながらもより正確な指標です。私たちは皆、しわや目の下のたるみなど、特徴的な兆候を顔から読み取って、ほとんど無意識に人の実年齢を推測しています。しかし、その人の脳や動脈、腎臓が何歳なのかを知ることはまた別の話です。スタンフォード大学医学部の研究者による新しい研究によると、私たちの体内に収められた臓器もまた、それぞれ異なる速度で老化しているのです。
「私たちは、あなたの臓器の年齢を示す血液ベースの指標を開発しました」と、神経学・神経科学の教授であり、ウー・ツァイ神経科学研究所のナイト・イニシアチブ・フォ
メッセンジャーだけではなかった!RNAの驚くべき機能と、その可能性を紐解く
 生命の設計図といえばDNAが主役と考えられてきました。しかし、その影で黙々と働く「RNA」が、実は生命現象のあらゆる場面で活躍する、驚くべき多機能プレーヤーであることが次々と明らかになっています。遺伝子情報の単なるメッセンジャーではなく、病気の発症から治療、さらには進化の謎に至るまで、その影響力は計り知れません。
かつてはDNAの指示通りにタンパク質を作る単なる作業員と見なされていたRNAは、その有名な親戚であるDNAの影から完全に抜け出しました。研究者たちが、低分子RNA、長鎖ノンコーディングRNA、低分子干渉RNA、piwi-interacting RNA、マイクロRNA、リボソームRNA、核小体低分子RNAなど、その無数の種類を発見するにつれて、RNAが遺伝子発現の調節から他の分子の活性化まで、様々な生化学的タスクの中心にあることも明らかにしてきました。DNAとリボソームの単なる仲介役どころか、RNAは実際には生物学において比類のない多様な形態と機能の多様性を備えています。
以下は、RNA科学の進歩におけるロックフェラー大学の科学者たちの重要な関与について、同大学が発表した記事です。著者はジョシュア・A・クリシュ氏(Joshua A. Krisch, JK)とジェン・ピンコウスキー氏(Jen Pinkowski, JP)で、記事は2024年12月11日に公開されました。
当初から、ロックフェラー大学の科学者たちは、私たちのRNAに対する理解を変革する上で重要な役割を果たしてきました。彼らの基礎的な発見は、細胞が環境シグナルに応答するためにRNAをどのように使用するかを説明し、その調節不全がどのように病気を引き起こすかを突き止め、以前は治療不可能だった疾患に対するRNAベースの治療法の基盤を築き、抗生物質耐性菌が可能な迅速な進化における役割を解明し、そして医薬
生命の設計図といえばDNAが主役と考えられてきました。しかし、その影で黙々と働く「RNA」が、実は生命現象のあらゆる場面で活躍する、驚くべき多機能プレーヤーであることが次々と明らかになっています。遺伝子情報の単なるメッセンジャーではなく、病気の発症から治療、さらには進化の謎に至るまで、その影響力は計り知れません。
かつてはDNAの指示通りにタンパク質を作る単なる作業員と見なされていたRNAは、その有名な親戚であるDNAの影から完全に抜け出しました。研究者たちが、低分子RNA、長鎖ノンコーディングRNA、低分子干渉RNA、piwi-interacting RNA、マイクロRNA、リボソームRNA、核小体低分子RNAなど、その無数の種類を発見するにつれて、RNAが遺伝子発現の調節から他の分子の活性化まで、様々な生化学的タスクの中心にあることも明らかにしてきました。DNAとリボソームの単なる仲介役どころか、RNAは実際には生物学において比類のない多様な形態と機能の多様性を備えています。
以下は、RNA科学の進歩におけるロックフェラー大学の科学者たちの重要な関与について、同大学が発表した記事です。著者はジョシュア・A・クリシュ氏(Joshua A. Krisch, JK)とジェン・ピンコウスキー氏(Jen Pinkowski, JP)で、記事は2024年12月11日に公開されました。
当初から、ロックフェラー大学の科学者たちは、私たちのRNAに対する理解を変革する上で重要な役割を果たしてきました。彼らの基礎的な発見は、細胞が環境シグナルに応答するためにRNAをどのように使用するかを説明し、その調節不全がどのように病気を引き起こすかを突き止め、以前は治療不可能だった疾患に対するRNAベースの治療法の基盤を築き、抗生物質耐性菌が可能な迅速な進化における役割を解明し、そして医薬
iPS細胞から神経を再生?人工誘導神経幹細胞による脳修復メカニズムが解明
 進行すると有効な治療法がなくなってしまう難病、多発性硬化症。この病気によって失われた神経機能を、自分の細胞から作り出した「神経幹細胞」で再生できるかもしれない――。そんな希望の光を示す画期的な研究成果が、英国の名門ケンブリッジ大学から発表されました。この記事では、難病治療の未来を塗り替える可能性を秘めた、幹細胞研究の最前線に迫ります。
ケンブリッジ大学の研究者らが主導した研究により、神経幹細胞移植が中枢神経系のミエリンを回復させる仕組みに光が当てられました。この発見は、神経幹細胞を基盤とした治療法が、慢性的な脱髄性疾患、特に進行性多発性硬化症の新たな治療法となる可能性を示唆しています。多発性硬化症は、体の免疫系が誤って中枢神経系を攻撃し、神経線維を保護する髄鞘(ミエリン)を破壊してしまう自己免疫疾患です。この損傷は、若年成人における神経障害の主な原因となっています。
MSの初期段階では、特定の細胞が新しいミエリンを生成することで、この損傷を部分的に修復する能力を持っています。しかし、病気が慢性的で進行性の段階に入ると、この再生能力は著しく低下します。この修復能力の低下が、さらなる神経細胞の損傷を招き、進行性MSの患者さんの障害を悪化させる一因となっています。
治療法に進歩は見られるものの、現在の治療法のほとんどは症状の管理に重点を置いており、損傷や神経変性を食い止めたり、回復させたりするまでには至っていません。このことは、MSがどのように進行するのかをより深く理解し、幹細胞技術がMS治療にどのように貢献できるかを探求する必要性を浮き彫りにしています。
このオープンアクセスの研究は、2025年7月7日付の学術誌Brainに掲載され、ケンブリッジ大学の科学者であるルカ・ペルゾッティ-ジャメッティ博士(Luca Peruzzotti-Jametti, MD, PhD)
進行すると有効な治療法がなくなってしまう難病、多発性硬化症。この病気によって失われた神経機能を、自分の細胞から作り出した「神経幹細胞」で再生できるかもしれない――。そんな希望の光を示す画期的な研究成果が、英国の名門ケンブリッジ大学から発表されました。この記事では、難病治療の未来を塗り替える可能性を秘めた、幹細胞研究の最前線に迫ります。
ケンブリッジ大学の研究者らが主導した研究により、神経幹細胞移植が中枢神経系のミエリンを回復させる仕組みに光が当てられました。この発見は、神経幹細胞を基盤とした治療法が、慢性的な脱髄性疾患、特に進行性多発性硬化症の新たな治療法となる可能性を示唆しています。多発性硬化症は、体の免疫系が誤って中枢神経系を攻撃し、神経線維を保護する髄鞘(ミエリン)を破壊してしまう自己免疫疾患です。この損傷は、若年成人における神経障害の主な原因となっています。
MSの初期段階では、特定の細胞が新しいミエリンを生成することで、この損傷を部分的に修復する能力を持っています。しかし、病気が慢性的で進行性の段階に入ると、この再生能力は著しく低下します。この修復能力の低下が、さらなる神経細胞の損傷を招き、進行性MSの患者さんの障害を悪化させる一因となっています。
治療法に進歩は見られるものの、現在の治療法のほとんどは症状の管理に重点を置いており、損傷や神経変性を食い止めたり、回復させたりするまでには至っていません。このことは、MSがどのように進行するのかをより深く理解し、幹細胞技術がMS治療にどのように貢献できるかを探求する必要性を浮き彫りにしています。
このオープンアクセスの研究は、2025年7月7日付の学術誌Brainに掲載され、ケンブリッジ大学の科学者であるルカ・ペルゾッティ-ジャメッティ博士(Luca Peruzzotti-Jametti, MD, PhD)
記憶力の鍵は「海馬」にあり!成人後も続く脳の成長メカニズムが解明される
 「大人の脳はもう成長しない」と考えていませんか?長年、科学者たちの間で議論されてきたこのテーマに、一つの答えを示す画期的な研究が発表されました。私たちの「記憶」を司る脳の重要な部分で、なんと80歳近くになっても新しい神経細胞が作られ続けていることが、最新の技術によって明らかになったのです。これは、脳の驚くべき適応能力と、未来の医療に新たな希望をもたらす発見かもしれません。
2025年7月3日に科学誌「Science」に掲載された研究は、脳の記憶中枢である海馬において、後期成人期に至るまで神経細胞が形成され続けるという、説得力のある新たな証拠を提示しました。スウェーデンのカロリンスカ研究所によるこの研究は、人間の脳の適応能力に関する、長年議論されてきた根源的な問いに答えを与えるものです。海馬は、学習や記憶に不可欠であり、感情の調節にも関わる脳領域です。2013年、カロリンスカ研究所のヨナス・フリーセン博士(Jonas Frisén, MD)の研究グループは、注目を集めた研究で、成人の海馬で新しい神経細胞が形成されうることを示しました。当時、研究チームは脳組織のDNAに含まれる炭素14のレベルを測定し、細胞がいつ形成されたかを特定することを可能にしました。
起源となる細胞の特定
しかし、この新しい神経細胞の形成、すなわち神経新生(neurogenesis)の規模や重要性については、まだ議論が続いていました。新しい神経細胞の前駆体となる神経前駆細胞が、実際に成人の体内に存在し、分裂しているという明確な証拠はなかったのです。
「私たちは今回、これらの起源となる細胞を特定することに成功し、成人脳の海馬でニューロンの形成が継続的に行われていることを確認しました」と、この研究を主導したカロリンスカ研究所 細胞・分子生物学部門の幹細胞研究教授であるフリーセン博士は述
「大人の脳はもう成長しない」と考えていませんか?長年、科学者たちの間で議論されてきたこのテーマに、一つの答えを示す画期的な研究が発表されました。私たちの「記憶」を司る脳の重要な部分で、なんと80歳近くになっても新しい神経細胞が作られ続けていることが、最新の技術によって明らかになったのです。これは、脳の驚くべき適応能力と、未来の医療に新たな希望をもたらす発見かもしれません。
2025年7月3日に科学誌「Science」に掲載された研究は、脳の記憶中枢である海馬において、後期成人期に至るまで神経細胞が形成され続けるという、説得力のある新たな証拠を提示しました。スウェーデンのカロリンスカ研究所によるこの研究は、人間の脳の適応能力に関する、長年議論されてきた根源的な問いに答えを与えるものです。海馬は、学習や記憶に不可欠であり、感情の調節にも関わる脳領域です。2013年、カロリンスカ研究所のヨナス・フリーセン博士(Jonas Frisén, MD)の研究グループは、注目を集めた研究で、成人の海馬で新しい神経細胞が形成されうることを示しました。当時、研究チームは脳組織のDNAに含まれる炭素14のレベルを測定し、細胞がいつ形成されたかを特定することを可能にしました。
起源となる細胞の特定
しかし、この新しい神経細胞の形成、すなわち神経新生(neurogenesis)の規模や重要性については、まだ議論が続いていました。新しい神経細胞の前駆体となる神経前駆細胞が、実際に成人の体内に存在し、分裂しているという明確な証拠はなかったのです。
「私たちは今回、これらの起源となる細胞を特定することに成功し、成人脳の海馬でニューロンの形成が継続的に行われていることを確認しました」と、この研究を主導したカロリンスカ研究所 細胞・分子生物学部門の幹細胞研究教授であるフリーセン博士は述
ゼブラフィッシュに学ぶ心臓再生の秘密:「眠っていた」胚性遺伝子の再活性化が鍵
 心筋梗塞などで一度傷つくと、人間の心臓が完全に元通りになることはありません。しかし、もし心臓が自ら再生する力を持っていたらどうでしょうか?そんな夢のような能力を持つ生物がいます。小さな魚、ゼブラフィッシュです。この度、カリフォルニア工科大学とカリフォルニア大学バークレー校の研究チームが、この魚の驚異的な心臓再生能力の秘密を解き明かし、将来の人間の心臓治療に繋がるかもしれない重要な手がかりを発見しました。
ゼブラフィッシュは、損傷後に心臓を再生・修復するという、驚くべき稀な能力を持っています。カリフォルニア工科大学(Caltech)とカリフォルニア大学バークレー校(UC Berkeley)による新しい研究は、この能力を制御する遺伝子の回路を特定し、心臓発作などの損傷後や先天性心疾患の場合に、いつか人間の心臓を修復する方法についての手がかりを提供しています。この研究は、Caltechのエドワード・B・ルイス生物学教授であり、ベックマン研究所所長であるマリアン・ブロナー博士(Marianne Bronner, PhD)と、UC Berkeleyの発達生物学者であるメーガン・マーティク博士(Megan Martik, PhD)の研究室による共同研究です。この研究を記述した論文は、2025年6月18日に「PNAS」誌に掲載されました。論文のタイトルは「Reactivation of an Embryonic Cardiac Neural Crest Transcriptional Profile During Zebrafish Heart Regeneration(ゼブラフィッシュの心臓再生時における胚性心臓神経堤転写プロファイルの再活性化)」です。
心臓は、筋肉細胞、神経細胞、血管細胞など、多くの異なる種類の細胞で構成されています。ゼブラフィッシュでは、これらの細胞の約1
心筋梗塞などで一度傷つくと、人間の心臓が完全に元通りになることはありません。しかし、もし心臓が自ら再生する力を持っていたらどうでしょうか?そんな夢のような能力を持つ生物がいます。小さな魚、ゼブラフィッシュです。この度、カリフォルニア工科大学とカリフォルニア大学バークレー校の研究チームが、この魚の驚異的な心臓再生能力の秘密を解き明かし、将来の人間の心臓治療に繋がるかもしれない重要な手がかりを発見しました。
ゼブラフィッシュは、損傷後に心臓を再生・修復するという、驚くべき稀な能力を持っています。カリフォルニア工科大学(Caltech)とカリフォルニア大学バークレー校(UC Berkeley)による新しい研究は、この能力を制御する遺伝子の回路を特定し、心臓発作などの損傷後や先天性心疾患の場合に、いつか人間の心臓を修復する方法についての手がかりを提供しています。この研究は、Caltechのエドワード・B・ルイス生物学教授であり、ベックマン研究所所長であるマリアン・ブロナー博士(Marianne Bronner, PhD)と、UC Berkeleyの発達生物学者であるメーガン・マーティク博士(Megan Martik, PhD)の研究室による共同研究です。この研究を記述した論文は、2025年6月18日に「PNAS」誌に掲載されました。論文のタイトルは「Reactivation of an Embryonic Cardiac Neural Crest Transcriptional Profile During Zebrafish Heart Regeneration(ゼブラフィッシュの心臓再生時における胚性心臓神経堤転写プロファイルの再活性化)」です。
心臓は、筋肉細胞、神経細胞、血管細胞など、多くの異なる種類の細胞で構成されています。ゼブラフィッシュでは、これらの細胞の約1
肺の線維化を食い止める!マクロファージ上のTREM2受容体をブロックする新戦略
 息切れがひどくなり、徐々に呼吸が困難になる進行性の病気、肺線維症。これまで有効な治療法が限られていましたが、この難病の進行を食い止める新たな鍵が見つかったかもしれません。私たちの体を守る免疫細胞「マクロファージ」の特定の働きを制御することで、肺の線維化を抑えるという画期的なアプローチが、アラバマ大学バーミンガム校の研究で示されました。
マクロファージを介した線維化の重要な制御因子としてTREM2が発見されたことにより、TREM2は肺線維症性疾患に対する有望な治療介入の標的となります。
肺マクロファージは、特発性肺線維症のような疾患において極めて重要な役割を果たします。肺には、微生物を殺し、死んだ細胞を除去し、免疫応答を刺激して体を守る白血球であるマクロファージが2種類存在します。一つは生まれつき存在する組織常在性マクロファージ、もう一つは損傷や感染に反応して短期間だけ肺に入る単球由来マクロファージです。近年、これらの単球由来肺胞マクロファージ(Mo-AMs)が、肺線維症の病態進行の主要な駆動因子であることが特定されました。しかし、その線維化を促進する挙動や肺での生存メカニズムは不明なままであり、臨床医は依然として有効な治療法を欠いています。
医学誌「Nature Communications」に掲載された研究で、ガン・リュー博士(Gang Liu, MD, PhD)、ファチュン・ツイ博士(Huachun Cui, PhD)、そして彼らのアラバマ大学バーミンガム校(UAB)の同僚たちは、Mo-AMs細胞上の細胞表面受容体タンパク質であるTREM2が、マクロファージを介した肺線維症の重要な制御因子であることを示しました。これにより、TREM2は有望な治療介入の標的となると、UAB医学部呼吸器・アレルギー・救命救急医学科の教授であるリュー博士は述べています。
「私
息切れがひどくなり、徐々に呼吸が困難になる進行性の病気、肺線維症。これまで有効な治療法が限られていましたが、この難病の進行を食い止める新たな鍵が見つかったかもしれません。私たちの体を守る免疫細胞「マクロファージ」の特定の働きを制御することで、肺の線維化を抑えるという画期的なアプローチが、アラバマ大学バーミンガム校の研究で示されました。
マクロファージを介した線維化の重要な制御因子としてTREM2が発見されたことにより、TREM2は肺線維症性疾患に対する有望な治療介入の標的となります。
肺マクロファージは、特発性肺線維症のような疾患において極めて重要な役割を果たします。肺には、微生物を殺し、死んだ細胞を除去し、免疫応答を刺激して体を守る白血球であるマクロファージが2種類存在します。一つは生まれつき存在する組織常在性マクロファージ、もう一つは損傷や感染に反応して短期間だけ肺に入る単球由来マクロファージです。近年、これらの単球由来肺胞マクロファージ(Mo-AMs)が、肺線維症の病態進行の主要な駆動因子であることが特定されました。しかし、その線維化を促進する挙動や肺での生存メカニズムは不明なままであり、臨床医は依然として有効な治療法を欠いています。
医学誌「Nature Communications」に掲載された研究で、ガン・リュー博士(Gang Liu, MD, PhD)、ファチュン・ツイ博士(Huachun Cui, PhD)、そして彼らのアラバマ大学バーミンガム校(UAB)の同僚たちは、Mo-AMs細胞上の細胞表面受容体タンパク質であるTREM2が、マクロファージを介した肺線維症の重要な制御因子であることを示しました。これにより、TREM2は有望な治療介入の標的となると、UAB医学部呼吸器・アレルギー・救命救急医学科の教授であるリュー博士は述べています。
「私
唾液が解き明かす2型糖尿病のリスク:AMY1遺伝子コピー数との関係
 ご飯やパンなどの炭水化物が好きな方にとって、少し気になるニュースかもしれません。私たちが普段、何気なく分泌している唾液。実はその中に含まれる「消化酵素」の量が、2型糖尿病のリスクと関連している可能性が、新たな研究によって示唆されました。この記事では、あなたの健康にも関わるかもしれない、唾液と遺伝子の興味深い関係について、分かりやすく解説していきます。
コーネル大学の新しい研究により、2型糖尿病と、デンプンを分解する唾液酵素を生成する遺伝子との関係が、さらに明確になりました。唾液アミラーゼをコードする遺伝子(AMY1)のコピー数が多い人ほど、唾液アミラーゼ酵素の産生量が多いことは以前から知られていました。2025年7月2日にPLOS One誌で発表された新しい論文は、AMY1遺伝子のコピー数が多いことが2型糖尿病に対する予防効果を持つ可能性があるという考えを裏付けています。ただし、この理論を証明するには、さらなる長期的な研究が必要です。このオープンアクセスの研究論文は「The Association Between Salivary Amylase Gene Copy Number and Enzyme Activity with Type 2 Diabetes Status(唾液アミラーゼの遺伝子コピー数および酵素活性と2型糖尿病の状態との関連)」と題されています。もし研究者たちが最終的にAMY1のコピー数と糖尿病との明確な関連性を証明できれば、生まれつきの遺伝子検査によって、個人の糖尿病へのかかりやすさを予測できるようになるかもしれません。
「もし生まれた日から糖尿病のリスクが高いと分かっていれば、日々の選択や人生の選択に早期に影響を与え、将来の発症を防ぐことができるかもしれません」と、コーネル大学農学・生命科学部の分子栄養学助教である筆頭著者のアンジェラ・プ
ご飯やパンなどの炭水化物が好きな方にとって、少し気になるニュースかもしれません。私たちが普段、何気なく分泌している唾液。実はその中に含まれる「消化酵素」の量が、2型糖尿病のリスクと関連している可能性が、新たな研究によって示唆されました。この記事では、あなたの健康にも関わるかもしれない、唾液と遺伝子の興味深い関係について、分かりやすく解説していきます。
コーネル大学の新しい研究により、2型糖尿病と、デンプンを分解する唾液酵素を生成する遺伝子との関係が、さらに明確になりました。唾液アミラーゼをコードする遺伝子(AMY1)のコピー数が多い人ほど、唾液アミラーゼ酵素の産生量が多いことは以前から知られていました。2025年7月2日にPLOS One誌で発表された新しい論文は、AMY1遺伝子のコピー数が多いことが2型糖尿病に対する予防効果を持つ可能性があるという考えを裏付けています。ただし、この理論を証明するには、さらなる長期的な研究が必要です。このオープンアクセスの研究論文は「The Association Between Salivary Amylase Gene Copy Number and Enzyme Activity with Type 2 Diabetes Status(唾液アミラーゼの遺伝子コピー数および酵素活性と2型糖尿病の状態との関連)」と題されています。もし研究者たちが最終的にAMY1のコピー数と糖尿病との明確な関連性を証明できれば、生まれつきの遺伝子検査によって、個人の糖尿病へのかかりやすさを予測できるようになるかもしれません。
「もし生まれた日から糖尿病のリスクが高いと分かっていれば、日々の選択や人生の選択に早期に影響を与え、将来の発症を防ぐことができるかもしれません」と、コーネル大学農学・生命科学部の分子栄養学助教である筆頭著者のアンジェラ・プ
脳細胞を光で操る!「青いロドプシン」が拓くオプトジェネティクスの未来
 グリーンランドの壮大な氷河、チベットの高山の万年雪…。美しくも過酷なこれらの極寒の地に、脳細胞の活動さえもコントロールできるかもしれない、魔法のような分子が眠っていました。偶然の発見から始まった、珍しい「青いタンパク質」の物語。それは、光で生命を操る未来の技術への扉を開く、驚くべき可能性を秘めていました。
極寒環境に適応した微生物由来の希少な青いタンパク質が、細胞の分子ON/OFFスイッチを設計するための原型となりうる
構造生物学者であるキリル・コバレフ博士(Kirill Kovalev, PhD)にとって、グリーンランドの壮大な氷河、チベット高山の万年雪、そしてフィンランドの恒久的に氷のように冷たい地下水は、単に冷たく美しいだけでなく、それ以上に重要なことに、脳細胞の活動を制御できる可能性を秘めた特異な分子の故郷なのです。EMBLハンブルクのシュナイダーグループおよびEMBL-EBIのベイトマングループに所属するEIPODポスドク研究員であるコバレフ博士は、生物学的な問題の解決に情熱を注ぐ物理学者です。彼は特に、水生微生物が太陽光をエネルギーとして利用することを可能にする、色彩豊かなタンパク質群であるロドプシンに夢中です。
「私の研究では、特異なロドプシンを探し、それらが何をしているのかを理解しようと試みています」とコバレフ博士は言います。「そのような分子は、私たちが恩恵を受けることのできる、未発見の機能を持っているかもしれません。」
一部のロドプシンは、細胞内の電気的活動を光で操作するスイッチとして機能するように、すでに改変されています。オプトジェネティクス(光遺伝学)と呼ばれるこの技術は、神経科学者が実験中に神経細胞の活動を選択的に制御するために使用しています。例えば、酵素活性といった他の能力を持つロドプシンは、光を用いて化学反応を制御するために使用
グリーンランドの壮大な氷河、チベットの高山の万年雪…。美しくも過酷なこれらの極寒の地に、脳細胞の活動さえもコントロールできるかもしれない、魔法のような分子が眠っていました。偶然の発見から始まった、珍しい「青いタンパク質」の物語。それは、光で生命を操る未来の技術への扉を開く、驚くべき可能性を秘めていました。
極寒環境に適応した微生物由来の希少な青いタンパク質が、細胞の分子ON/OFFスイッチを設計するための原型となりうる
構造生物学者であるキリル・コバレフ博士(Kirill Kovalev, PhD)にとって、グリーンランドの壮大な氷河、チベット高山の万年雪、そしてフィンランドの恒久的に氷のように冷たい地下水は、単に冷たく美しいだけでなく、それ以上に重要なことに、脳細胞の活動を制御できる可能性を秘めた特異な分子の故郷なのです。EMBLハンブルクのシュナイダーグループおよびEMBL-EBIのベイトマングループに所属するEIPODポスドク研究員であるコバレフ博士は、生物学的な問題の解決に情熱を注ぐ物理学者です。彼は特に、水生微生物が太陽光をエネルギーとして利用することを可能にする、色彩豊かなタンパク質群であるロドプシンに夢中です。
「私の研究では、特異なロドプシンを探し、それらが何をしているのかを理解しようと試みています」とコバレフ博士は言います。「そのような分子は、私たちが恩恵を受けることのできる、未発見の機能を持っているかもしれません。」
一部のロドプシンは、細胞内の電気的活動を光で操作するスイッチとして機能するように、すでに改変されています。オプトジェネティクス(光遺伝学)と呼ばれるこの技術は、神経科学者が実験中に神経細胞の活動を選択的に制御するために使用しています。例えば、酵素活性といった他の能力を持つロドプシンは、光を用いて化学反応を制御するために使用
遺伝子治療で失われた聴力が回復!先天性難聴の子どもと大人に希望の光
 失われた聴力を取り戻す――。これまで不可能と思われていたこの夢が、遺伝子治療によって現実のものになろうとしています。生まれつき耳が聞こえない、あるいは重度の聴覚障害を持つ人々にとって、まさに人生を変えるような朗報です。たった1回の注射で、子どもから大人まで、多くの人の世界に「音」が戻ってきました。この画期的な研究の最前線をご紹介します。
カロリンスカ研究所の研究者らが関与した新しい研究により、遺伝子治療が先天性難聴または重度の聴覚障害を持つ子どもと大人の聴力を改善できることが報告されました。10人の患者全員で聴力の改善が見られ、治療の忍容性も良好でした。この研究は中国の病院や大学と共同で行われ、科学雑誌『Nature Medicine』に掲載されました。
「これは難聴の遺伝子治療における大きな一歩であり、子どもたちと大人たちの人生を変える可能性のあるものです」と、スウェーデンのカロリンスカ研究所臨床科学・介入・技術部門のコンサルタント兼講師であり、本研究の責任著者の一人であるマオリ・デュアン医学博士(Maoli Duan, MD PhD)は述べています。
この研究には、中国の5つの病院にいる1歳から24歳までの10人の患者が参加しました。彼らは全員、OTOFと呼ばれる遺伝子の変異によって引き起こされる遺伝性の難聴または重度の聴覚障害を持っていました。これらの変異は、耳から脳へ聴覚信号を伝達する上で重要な役割を果たすオトフェリンというタンパク質の欠乏を引き起こします。
1ヶ月以内に効果が現れる
この遺伝子治療では、合成されたアデノ随伴ウイルスを用いて、機能を持つOTOF遺伝子の正常なコピーを内耳に送達します。これは、蝸牛の基部にある正円窓と呼ばれる膜を通して1回注射するだけで行われます。
遺伝子治療の効果は速やかに現れ、患者の大多数はわずか1ヶ月後
失われた聴力を取り戻す――。これまで不可能と思われていたこの夢が、遺伝子治療によって現実のものになろうとしています。生まれつき耳が聞こえない、あるいは重度の聴覚障害を持つ人々にとって、まさに人生を変えるような朗報です。たった1回の注射で、子どもから大人まで、多くの人の世界に「音」が戻ってきました。この画期的な研究の最前線をご紹介します。
カロリンスカ研究所の研究者らが関与した新しい研究により、遺伝子治療が先天性難聴または重度の聴覚障害を持つ子どもと大人の聴力を改善できることが報告されました。10人の患者全員で聴力の改善が見られ、治療の忍容性も良好でした。この研究は中国の病院や大学と共同で行われ、科学雑誌『Nature Medicine』に掲載されました。
「これは難聴の遺伝子治療における大きな一歩であり、子どもたちと大人たちの人生を変える可能性のあるものです」と、スウェーデンのカロリンスカ研究所臨床科学・介入・技術部門のコンサルタント兼講師であり、本研究の責任著者の一人であるマオリ・デュアン医学博士(Maoli Duan, MD PhD)は述べています。
この研究には、中国の5つの病院にいる1歳から24歳までの10人の患者が参加しました。彼らは全員、OTOFと呼ばれる遺伝子の変異によって引き起こされる遺伝性の難聴または重度の聴覚障害を持っていました。これらの変異は、耳から脳へ聴覚信号を伝達する上で重要な役割を果たすオトフェリンというタンパク質の欠乏を引き起こします。
1ヶ月以内に効果が現れる
この遺伝子治療では、合成されたアデノ随伴ウイルスを用いて、機能を持つOTOF遺伝子の正常なコピーを内耳に送達します。これは、蝸牛の基部にある正円窓と呼ばれる膜を通して1回注射するだけで行われます。
遺伝子治療の効果は速やかに現れ、患者の大多数はわずか1ヶ月後
未来の診断・治療を変えるか?ブリルアン顕微鏡が解き明かす細胞メカニクスの謎
 細胞の「硬さ」や「柔らかさ」。実は、がんや炎症といった病気の発症に深く関わっています。しかし、生きたままの細胞を傷つけずに、その“触り心地”を正確に知ることは、これまで非常に困難でした。この長年の壁を打ち破る、魔法のような顕微鏡がアイルランドに初上陸。光を使って細胞の力学を「見る」、その驚くべき技術とは?トリニティ・カレッジ・ダブリンに、アイルランド初で唯一となる「バイオブリルアン顕微鏡」が導入されました。これにより、研究者たちは炎症、がん、発生生物学、生物医用材料などの分野で大きな進歩を遂げることが期待されています。
細胞や組織の力学(メカニクス)は、病気、機能不全、そして再生を強力に制御する要因であり、その理解は生物医学研究者の大きな焦点となっています。しかし、既存の方法は侵襲的(対象を傷つける)であり、得られる情報にも限界がありました。しかし、この驚くべき新しいブリルアン顕微鏡は、非侵襲的な光を用いて、材料や生体組織の圧縮性、粘弾性、そして詳細な力学をマッピングし、定量化することができます。
これにより、研究者は生きたシステム(細胞や組織など)に干渉することなく、その機械的特性を評価できるようになり、システムとその経時的な変化をモニタリングすることが可能になります。この技術は、光の光子(フォトン)と、物質の機械的特性に影響される音響フォノン(音子)との相互作用の結果生じる光散乱に基づいています。
欧州研究会議とリサーチ・アイルランドの支援を受け、このブリルアン顕微鏡システムは、トリニティ大学工学部のマイケル・モナハン教授(Michael Monaghan)の研究室に設置されました。研究室は、トリニティ生物医科学研究所内にあるトリニティ生物医工学センターにあります。
「世界初の商用システムであるため、私たちはベンダーであるCellSense Technolo
細胞の「硬さ」や「柔らかさ」。実は、がんや炎症といった病気の発症に深く関わっています。しかし、生きたままの細胞を傷つけずに、その“触り心地”を正確に知ることは、これまで非常に困難でした。この長年の壁を打ち破る、魔法のような顕微鏡がアイルランドに初上陸。光を使って細胞の力学を「見る」、その驚くべき技術とは?トリニティ・カレッジ・ダブリンに、アイルランド初で唯一となる「バイオブリルアン顕微鏡」が導入されました。これにより、研究者たちは炎症、がん、発生生物学、生物医用材料などの分野で大きな進歩を遂げることが期待されています。
細胞や組織の力学(メカニクス)は、病気、機能不全、そして再生を強力に制御する要因であり、その理解は生物医学研究者の大きな焦点となっています。しかし、既存の方法は侵襲的(対象を傷つける)であり、得られる情報にも限界がありました。しかし、この驚くべき新しいブリルアン顕微鏡は、非侵襲的な光を用いて、材料や生体組織の圧縮性、粘弾性、そして詳細な力学をマッピングし、定量化することができます。
これにより、研究者は生きたシステム(細胞や組織など)に干渉することなく、その機械的特性を評価できるようになり、システムとその経時的な変化をモニタリングすることが可能になります。この技術は、光の光子(フォトン)と、物質の機械的特性に影響される音響フォノン(音子)との相互作用の結果生じる光散乱に基づいています。
欧州研究会議とリサーチ・アイルランドの支援を受け、このブリルアン顕微鏡システムは、トリニティ大学工学部のマイケル・モナハン教授(Michael Monaghan)の研究室に設置されました。研究室は、トリニティ生物医科学研究所内にあるトリニティ生物医工学センターにあります。
「世界初の商用システムであるため、私たちはベンダーであるCellSense Technolo
PCOSはなぜ遺伝する?母親から受け継がれる「エピジェネティックな記憶」の謎を解明
 なぜ、ある病気は家族で遺伝するのだろう?多くの女性を悩ませる「多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)」も、母親から娘へと受け継がれることが多い疾患の一つです。その長年の謎を解き明かすかもしれない、驚くべき研究成果が発表されました。母親から子へ、DNAだけではない「記憶」が受け継がれているとしたら…?最新の研究が、その正体に迫ります。
多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)の女性から得られた胚は、この疾患が家族内で多発する理由を説明しうる、特有の「エピジェネティックな記憶」を持っていることが新たな研究で判明
(フランス・パリ、2025年7月1日)本日、第41回欧州ヒト生殖医学会(ESHRE: European Society of Human Reproduction and Embryology)年次総会で発表された新しい研究により、多嚢胞性卵巣症候群の女性から得られた胚が、この疾患が家族内で多発する理由を説明しうる、特有の「エピジェネティックな記憶」を持っていることが明らかになりました[1]。
PCOSは、世界中の生殖可能年齢の女性の推定10人に1人が罹患する一般的なホルモン障害です[2]。不規則な月経周期、アンドロゲン(男性ホルモン)の過剰、そして卵巣に多数の嚢胞が存在することを特徴とします[3]。不妊症の主な原因として認識されていますが、その正確な原因や遺伝のメカニズムは未だ不明です[4]。チィエンシュー・シュ博士(Qianshu Zhu, PhD)が主導したこの研究では、不妊治療を受けているPCOS患者133人と非PCOSの不妊女性95人から得られた卵母細胞と着床前胚を分析しました。研究チームは、超低入力シーケンシング技術を用いて、遺伝子の活動とエピジェネティックな変化(DNAの塩基配列そのものを変えることなく、遺伝子の働きをオン・オフに制御する化学的な目印)の両方を解
なぜ、ある病気は家族で遺伝するのだろう?多くの女性を悩ませる「多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)」も、母親から娘へと受け継がれることが多い疾患の一つです。その長年の謎を解き明かすかもしれない、驚くべき研究成果が発表されました。母親から子へ、DNAだけではない「記憶」が受け継がれているとしたら…?最新の研究が、その正体に迫ります。
多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)の女性から得られた胚は、この疾患が家族内で多発する理由を説明しうる、特有の「エピジェネティックな記憶」を持っていることが新たな研究で判明
(フランス・パリ、2025年7月1日)本日、第41回欧州ヒト生殖医学会(ESHRE: European Society of Human Reproduction and Embryology)年次総会で発表された新しい研究により、多嚢胞性卵巣症候群の女性から得られた胚が、この疾患が家族内で多発する理由を説明しうる、特有の「エピジェネティックな記憶」を持っていることが明らかになりました[1]。
PCOSは、世界中の生殖可能年齢の女性の推定10人に1人が罹患する一般的なホルモン障害です[2]。不規則な月経周期、アンドロゲン(男性ホルモン)の過剰、そして卵巣に多数の嚢胞が存在することを特徴とします[3]。不妊症の主な原因として認識されていますが、その正確な原因や遺伝のメカニズムは未だ不明です[4]。チィエンシュー・シュ博士(Qianshu Zhu, PhD)が主導したこの研究では、不妊治療を受けているPCOS患者133人と非PCOSの不妊女性95人から得られた卵母細胞と着床前胚を分析しました。研究チームは、超低入力シーケンシング技術を用いて、遺伝子の活動とエピジェネティックな変化(DNAの塩基配列そのものを変えることなく、遺伝子の働きをオン・オフに制御する化学的な目印)の両方を解
遺伝子治療の「運び屋」問題を解決へ。DNAナノ粒子の細胞内動態解明に挑む
 まるで狙った住所に手紙を届けるように、体の中の特定の細胞にだけ薬を届ける――。このようなSFのような技術が、現実のものになろうとしています。その鍵を握るのが、「プログラム可能」なDNAナノ粒子。この革新的な研究を率いる若き化学者が、その功績を認められ、権威ある賞を受賞しました。未来の医療を塗り替える可能性を秘めた、小さな粒子の大きな挑戦に迫ります。
ケース・ウェスタン・リザーブ大学の化学者、「プログラム可能な」ナノ粒子で権威あるNSF CAREER賞を受賞
ケース・ウェスタン・リザーブ大学の化学者であるディヴィタ・マサー博士(Divita Mathur, PhD)が、合成DNAナノ粒子に関する研究で、米国科学財団(NSF: National Science Foundation)の教員早期キャリア開発プログラム(CAREER)賞を受賞しました。このナノ粒子は、遺伝子治療への応用が期待されています。
この助成金は、マサー博士が進めるナノ粒子の合成と、実験室環境でそれらが細胞内でどのように振る舞うかを研究する取り組みを支援するものです。彼女は、単一細胞への注入と顕微鏡を用いてナノ粒子を追跡し、個々の細胞内で時間と共に何が起こるかを観察する予定です。
CAREER賞は、NSFが「研究と教育における学術的な模範となり、所属する学部や組織の使命の進展を導くポテンシャルを持つ」若手教員に授与する、最も権威ある助成金と見なされています。文理学部の化学助教であるマサー博士は、今年CAREER賞を受賞したケース・ウェスタン・リザーブ大学の3人の教員のうちの一人です。
「この画期的な研究は、新たな救命治療につながる可能性のある基礎科学の素晴らしい一例です」と、同学部長のデイビッド・ガーデス氏(David Gerdes)は述べています。「CAREER賞の受賞は、彼女が私たちのキャ
まるで狙った住所に手紙を届けるように、体の中の特定の細胞にだけ薬を届ける――。このようなSFのような技術が、現実のものになろうとしています。その鍵を握るのが、「プログラム可能」なDNAナノ粒子。この革新的な研究を率いる若き化学者が、その功績を認められ、権威ある賞を受賞しました。未来の医療を塗り替える可能性を秘めた、小さな粒子の大きな挑戦に迫ります。
ケース・ウェスタン・リザーブ大学の化学者、「プログラム可能な」ナノ粒子で権威あるNSF CAREER賞を受賞
ケース・ウェスタン・リザーブ大学の化学者であるディヴィタ・マサー博士(Divita Mathur, PhD)が、合成DNAナノ粒子に関する研究で、米国科学財団(NSF: National Science Foundation)の教員早期キャリア開発プログラム(CAREER)賞を受賞しました。このナノ粒子は、遺伝子治療への応用が期待されています。
この助成金は、マサー博士が進めるナノ粒子の合成と、実験室環境でそれらが細胞内でどのように振る舞うかを研究する取り組みを支援するものです。彼女は、単一細胞への注入と顕微鏡を用いてナノ粒子を追跡し、個々の細胞内で時間と共に何が起こるかを観察する予定です。
CAREER賞は、NSFが「研究と教育における学術的な模範となり、所属する学部や組織の使命の進展を導くポテンシャルを持つ」若手教員に授与する、最も権威ある助成金と見なされています。文理学部の化学助教であるマサー博士は、今年CAREER賞を受賞したケース・ウェスタン・リザーブ大学の3人の教員のうちの一人です。
「この画期的な研究は、新たな救命治療につながる可能性のある基礎科学の素晴らしい一例です」と、同学部長のデイビッド・ガーデス氏(David Gerdes)は述べています。「CAREER賞の受賞は、彼女が私たちのキャ
失われた聴覚は取り戻せる?ゼブラフィッシュが解き明かす「感覚有毛細胞」再生の謎
 一度失うと二度と戻らない――。それが、私たちの聴覚を支える「感覚有毛細胞」の常識でした。しかし、もしこの細胞を再生できたら?魚やカエルが当たり前のように行っているこの「再生」の秘密を、ゼブラフィッシュという小さな熱帯魚が解き明かしてくれるかもしれません。ストワーズ医学研究所の最新研究が、失われた聴覚を取り戻す未来への扉を開く、驚くべき遺伝子の働きを突き止めました。
私たちヒトは、血液や腸の細胞のように定期的に特定の細胞を入れ替えることはできますが、体の他のほとんどの部分を自然に再生することはできません。例えば、内耳にある微小な感覚有毛細胞が損傷すると、その結果は永続的な難聴、聴力損失、あるいは平衡感覚の問題につながることがよくあります。対照的に、魚やカエル、ヒヨコなどの動物は、感覚有毛細胞をいとも簡単に再生します。
今回、ストワーズ医学研究所の科学者たちは、2つの異なる遺伝子がゼブラフィッシュの感覚細胞の再生をどのように導くかを特定しました。この発見は、ゼブラフィッシュにおける再生の仕組みについての私たちの理解を深め、ヒトを含む哺乳類の難聴や再生医療に関する将来の研究の指針となる可能性があります。「私たちのような哺乳類は、内耳の有毛細胞を再生することができません」と、本研究の上級著者であり責任著者でもあるストワーズ研究所の主任研究員、タチアナ・ピオトロフスキー博士(Tatjana Piotrowski, PhD)は述べています。「私たちは年をとったり、長期間の騒音にさらされたりすると、聴覚と平衡感覚を失っていきます。」
2025年7月14日にNature Communications誌に掲載されたピオトロフスキー研究室の新しい研究は、有毛細胞の再生を促進し、かつ幹細胞の安定した供給を維持するために、細胞分裂がどのように調節されているかを理解しようとするものです
一度失うと二度と戻らない――。それが、私たちの聴覚を支える「感覚有毛細胞」の常識でした。しかし、もしこの細胞を再生できたら?魚やカエルが当たり前のように行っているこの「再生」の秘密を、ゼブラフィッシュという小さな熱帯魚が解き明かしてくれるかもしれません。ストワーズ医学研究所の最新研究が、失われた聴覚を取り戻す未来への扉を開く、驚くべき遺伝子の働きを突き止めました。
私たちヒトは、血液や腸の細胞のように定期的に特定の細胞を入れ替えることはできますが、体の他のほとんどの部分を自然に再生することはできません。例えば、内耳にある微小な感覚有毛細胞が損傷すると、その結果は永続的な難聴、聴力損失、あるいは平衡感覚の問題につながることがよくあります。対照的に、魚やカエル、ヒヨコなどの動物は、感覚有毛細胞をいとも簡単に再生します。
今回、ストワーズ医学研究所の科学者たちは、2つの異なる遺伝子がゼブラフィッシュの感覚細胞の再生をどのように導くかを特定しました。この発見は、ゼブラフィッシュにおける再生の仕組みについての私たちの理解を深め、ヒトを含む哺乳類の難聴や再生医療に関する将来の研究の指針となる可能性があります。「私たちのような哺乳類は、内耳の有毛細胞を再生することができません」と、本研究の上級著者であり責任著者でもあるストワーズ研究所の主任研究員、タチアナ・ピオトロフスキー博士(Tatjana Piotrowski, PhD)は述べています。「私たちは年をとったり、長期間の騒音にさらされたりすると、聴覚と平衡感覚を失っていきます。」
2025年7月14日にNature Communications誌に掲載されたピオトロフスキー研究室の新しい研究は、有毛細胞の再生を促進し、かつ幹細胞の安定した供給を維持するために、細胞分裂がどのように調節されているかを理解しようとするものです
テストステロン値が低い男性に朗報!抗肥満薬が活力と生殖機能を取り戻す可能性
 最近話題の「痩せ薬」。実はこの薬、単に体重を減らすだけでなく、男性の活力を取り戻す鍵になるかもしれません。肥満や糖尿病に悩む男性でしばしば見られるテストステロンの低下は、疲労感や意欲減退の原因になることも。最新の研究で、抗肥満薬がこの低下したテストステロン値を劇的に改善させることが明らかになりました。体重管理と男性機能の向上、一石二鳥の可能性を秘めたこの研究に迫ります。
7月14日(月)にカリフォルニア州サンフランシスコで開催された内分泌学会の年次総会「ENDO 2025」で発表された新しい研究によると、抗肥満薬は肥満または2型糖尿病の男性のテストステロン値を大幅に上昇させ、健康状態を改善する可能性があります。テストステロンは、男性の性機能において重要な役割を果たすだけでなく、個人の骨量、脂肪分布、筋肉量、筋力、そして赤血球の産生にも影響を与えることがあります。体重の増加や2型糖尿病の有病率は、テストステロン値の低下としばしば関連しており、その結果、疲労感、性欲減退、生活の質の低下を引き起こします。
「生活習慣の改善や肥満外科手術による減量がテストステロン値を上昇させることはよく知られていますが、抗肥満薬がこれらのレベルに与える影響については、これまで広く研究されてきませんでした」と、ミズーリ州セントルイスにあるSSMヘルス・セントルイス大学病院の内分泌学フェローであるシェルシー・ポルティージョ・カナレス医師(Shellsea Portillo Canales, MD)は述べています。「私たちの研究は、一般的に処方されている抗肥満薬の使用によって、低いテストステロン値を回復させることができるという説得力のあるエビデンスを提供する、最初の研究の一つです。」
この仮説を検証するため、研究者らは、抗肥満薬であるセマグルチド、デュラグルチド、またはチルゼパチドで治療を受け
最近話題の「痩せ薬」。実はこの薬、単に体重を減らすだけでなく、男性の活力を取り戻す鍵になるかもしれません。肥満や糖尿病に悩む男性でしばしば見られるテストステロンの低下は、疲労感や意欲減退の原因になることも。最新の研究で、抗肥満薬がこの低下したテストステロン値を劇的に改善させることが明らかになりました。体重管理と男性機能の向上、一石二鳥の可能性を秘めたこの研究に迫ります。
7月14日(月)にカリフォルニア州サンフランシスコで開催された内分泌学会の年次総会「ENDO 2025」で発表された新しい研究によると、抗肥満薬は肥満または2型糖尿病の男性のテストステロン値を大幅に上昇させ、健康状態を改善する可能性があります。テストステロンは、男性の性機能において重要な役割を果たすだけでなく、個人の骨量、脂肪分布、筋肉量、筋力、そして赤血球の産生にも影響を与えることがあります。体重の増加や2型糖尿病の有病率は、テストステロン値の低下としばしば関連しており、その結果、疲労感、性欲減退、生活の質の低下を引き起こします。
「生活習慣の改善や肥満外科手術による減量がテストステロン値を上昇させることはよく知られていますが、抗肥満薬がこれらのレベルに与える影響については、これまで広く研究されてきませんでした」と、ミズーリ州セントルイスにあるSSMヘルス・セントルイス大学病院の内分泌学フェローであるシェルシー・ポルティージョ・カナレス医師(Shellsea Portillo Canales, MD)は述べています。「私たちの研究は、一般的に処方されている抗肥満薬の使用によって、低いテストステロン値を回復させることができるという説得力のあるエビデンスを提供する、最初の研究の一つです。」
この仮説を検証するため、研究者らは、抗肥満薬であるセマグルチド、デュラグルチド、またはチルゼパチドで治療を受け
寿命が15%延びる?老化を防ぐ「クローソー」タンパク質の驚くべき効果とは
 誰もが願う「健康で長生き」。その夢を叶える鍵となるかもしれない、驚きのタンパク質が発見されました。マウスでの実験では寿命を延ばすだけでなく、筋肉や骨、さらには脳の若々しさまで保つことが示されたのです。未来のアンチエイジング治療の主役となりうる「クローソー」タンパク質の秘密に迫ります。バルセロナ自治大学神経科学研究所(INc-UAB)が主導する国際研究チームは、マウスにおいてクローソータンパク質のレベルを高めることで寿命が延び、老化に伴う身体能力と認知機能の両方が改善することを示しました。
年を重ねるにつれて、筋肉や骨量が自然に減少し、身体が弱くなることで転倒や重傷のリスクが高まります。認知的にも、ニューロンは徐々に変性してつながりを失い、アルツハイマー病やパーキンソン病といった疾患がより一般的になります。社会の高齢化が着実に進む中で、これらの影響を軽減することは研究における主要な課題の一つです。今回、『Molecular Therapy』誌に2025年4月2日に掲載された論文(オンライン版は2025年2月22日)で、INc-UABのICREA研究者であるミゲル・チロン教授(Miguel Chillón)が率いる国際研究チームは、分泌型クローソータンパク質(s-KL)のレベルを上げることが、マウスの老化を改善することを示しました。研究チームは、若いマウスに遺伝子治療ベクターを投与し、体内の細胞がより多くのs-KLを分泌するようにしました。そして、マウスが生後24ヶ月(ヒトの約70歳に相当)になった時点で、この治療がマウスの筋肉、骨、そして認知機能の健康を改善したことを見出しました。このオープンアクセス論文のタイトルは「Long-Term Effects of s-KL Treatment in Wild-Type Mice: Enhancing Longevity,
誰もが願う「健康で長生き」。その夢を叶える鍵となるかもしれない、驚きのタンパク質が発見されました。マウスでの実験では寿命を延ばすだけでなく、筋肉や骨、さらには脳の若々しさまで保つことが示されたのです。未来のアンチエイジング治療の主役となりうる「クローソー」タンパク質の秘密に迫ります。バルセロナ自治大学神経科学研究所(INc-UAB)が主導する国際研究チームは、マウスにおいてクローソータンパク質のレベルを高めることで寿命が延び、老化に伴う身体能力と認知機能の両方が改善することを示しました。
年を重ねるにつれて、筋肉や骨量が自然に減少し、身体が弱くなることで転倒や重傷のリスクが高まります。認知的にも、ニューロンは徐々に変性してつながりを失い、アルツハイマー病やパーキンソン病といった疾患がより一般的になります。社会の高齢化が着実に進む中で、これらの影響を軽減することは研究における主要な課題の一つです。今回、『Molecular Therapy』誌に2025年4月2日に掲載された論文(オンライン版は2025年2月22日)で、INc-UABのICREA研究者であるミゲル・チロン教授(Miguel Chillón)が率いる国際研究チームは、分泌型クローソータンパク質(s-KL)のレベルを上げることが、マウスの老化を改善することを示しました。研究チームは、若いマウスに遺伝子治療ベクターを投与し、体内の細胞がより多くのs-KLを分泌するようにしました。そして、マウスが生後24ヶ月(ヒトの約70歳に相当)になった時点で、この治療がマウスの筋肉、骨、そして認知機能の健康を改善したことを見出しました。このオープンアクセス論文のタイトルは「Long-Term Effects of s-KL Treatment in Wild-Type Mice: Enhancing Longevity,
重症喘息の治療薬「生物学的製剤」の驚くべき効果とは?免疫細胞への長期的な影響を解明
 重症喘息の治療に革命をもたらした生物学的製剤。多くの患者さんの生活を劇的に改善してきたこの画期的な薬ですが、その効果の裏側で、私たちの免疫システムに一体何が起きているのでしょうか?最新の研究が、これまで知られていなかった驚くべき事実を明らかにしました。治療を続けているにもかかわらず、なぜか体内で増えてしまう「ある細胞」。この記事では、その謎に迫る研究成果をご紹介します。
生物学的製剤は、多くの重症喘息患者さんの生活の質を向上させてきました。しかし、スウェーデンのカロリンスカ研究所による新たな研究で、炎症を引き起こす力の強い一部の免疫細胞が、治療後も完全にはなくならないことが示されました。
生物学的製剤は、重症喘息の治療において重要なツールとなっています。「ほとんどの患者さんが症状をコントロールできるようになりましたが、これらの薬が免疫システムに具体的にどう影響するのかは、これまで詳しくわかっていませんでした」と、カロリンスカ大学病院の呼吸器内科コンサルタントであり、カロリンスカ研究所医学部の博士課程に在籍するヴァレンティナ・ヤシンスカ氏(Valentyna Yasinska)は語ります。科学雑誌『Allergy』に掲載された新しい研究で、カロリンスカ研究所の研究チームは、生物学的製剤で治療を受けている患者さんの免疫細胞に何が起こるかを調査しました。40人の患者さんから治療前と治療中に血液サンプルを採取して分析した結果、喘息の炎症に重要な役割を果たす特定の種類の免疫細胞が、治療中に消失するどころか、むしろ増加していることを発見したのです。
「この結果は、生物学的製剤が治療中にどれほど患者さんを助けているとしても、問題の根本原因には働きかけていない可能性を示唆しています」と、カロリンスカ研究所医学部組織免疫学の教授であるジェニー・ミョースベリ博士(Jenny Mj
重症喘息の治療に革命をもたらした生物学的製剤。多くの患者さんの生活を劇的に改善してきたこの画期的な薬ですが、その効果の裏側で、私たちの免疫システムに一体何が起きているのでしょうか?最新の研究が、これまで知られていなかった驚くべき事実を明らかにしました。治療を続けているにもかかわらず、なぜか体内で増えてしまう「ある細胞」。この記事では、その謎に迫る研究成果をご紹介します。
生物学的製剤は、多くの重症喘息患者さんの生活の質を向上させてきました。しかし、スウェーデンのカロリンスカ研究所による新たな研究で、炎症を引き起こす力の強い一部の免疫細胞が、治療後も完全にはなくならないことが示されました。
生物学的製剤は、重症喘息の治療において重要なツールとなっています。「ほとんどの患者さんが症状をコントロールできるようになりましたが、これらの薬が免疫システムに具体的にどう影響するのかは、これまで詳しくわかっていませんでした」と、カロリンスカ大学病院の呼吸器内科コンサルタントであり、カロリンスカ研究所医学部の博士課程に在籍するヴァレンティナ・ヤシンスカ氏(Valentyna Yasinska)は語ります。科学雑誌『Allergy』に掲載された新しい研究で、カロリンスカ研究所の研究チームは、生物学的製剤で治療を受けている患者さんの免疫細胞に何が起こるかを調査しました。40人の患者さんから治療前と治療中に血液サンプルを採取して分析した結果、喘息の炎症に重要な役割を果たす特定の種類の免疫細胞が、治療中に消失するどころか、むしろ増加していることを発見したのです。
「この結果は、生物学的製剤が治療中にどれほど患者さんを助けているとしても、問題の根本原因には働きかけていない可能性を示唆しています」と、カロリンスカ研究所医学部組織免疫学の教授であるジェニー・ミョースベリ博士(Jenny Mj
たった1枚の脳画像で将来の健康がわかる。加齢性疾患を予測する新たな老化時計
 高校の同窓会は、人によって老化の進み方がいかに違うかを痛感させてくれる場所かもしれません。年を重ねても、身体的にはつらつとし、頭脳明晰な人もいれば、予想よりずっと早くから身体の衰えや物忘れを感じ始める人もいます。もし、たった1枚の脳の画像で、あなたの「本当の老化スピード」が分かり、将来の病気まで予測できるとしたらどうでしょう?そんな夢のようなツールが、現実のものとなりました。
新しい老化時計、症状が現れる数年前に認知症や他の加齢性疾患のリスクを予測
「私たちが年をとるにつれて見せる老化の仕方は、太陽の周りを何周したか(=暦年齢)とはまったく異なります」と、デューク大学の心理学・神経科学教授であるアーマド・ハリリ博士(Ahmad Hariri, PhD)は語ります。この度、デューク大学、ハーバード大学、そしてニュージーランドのオタゴ大学の科学者たちは、ある人がどれだけ速く老化しているかを、まだ比較的健康なうちに知ることができるツールを開発しました。しかも、脳のスナップショットを見るだけで、誰でも無料で利用可能です。
このツールは、1回のMRI脳スキャンから、中年期における慢性疾患のリスクを推定できます。通常、これらの病気は何十年も後になって現れるものです。この情報を知ることで、健康を改善するための生活習慣や食生活の変更への動機付けになるかもしれません。
高齢者においては、このツールは症状が現れる数年前に認知症や他の加齢関連疾患を発症するかどうかを予測でき、病気の進行を遅らせるためのより良い機会を得られる可能性があります。
「このツールの本当にすごいところは、中年期に収集されたデータを使って人々がどれだけ速く老化しているかを捉えたことです」とハリリ博士は言います。「そしてそれが、はるかに高齢な人々の認知症の診断を予測するのに役立っているのです。」
この研究成果は
高校の同窓会は、人によって老化の進み方がいかに違うかを痛感させてくれる場所かもしれません。年を重ねても、身体的にはつらつとし、頭脳明晰な人もいれば、予想よりずっと早くから身体の衰えや物忘れを感じ始める人もいます。もし、たった1枚の脳の画像で、あなたの「本当の老化スピード」が分かり、将来の病気まで予測できるとしたらどうでしょう?そんな夢のようなツールが、現実のものとなりました。
新しい老化時計、症状が現れる数年前に認知症や他の加齢性疾患のリスクを予測
「私たちが年をとるにつれて見せる老化の仕方は、太陽の周りを何周したか(=暦年齢)とはまったく異なります」と、デューク大学の心理学・神経科学教授であるアーマド・ハリリ博士(Ahmad Hariri, PhD)は語ります。この度、デューク大学、ハーバード大学、そしてニュージーランドのオタゴ大学の科学者たちは、ある人がどれだけ速く老化しているかを、まだ比較的健康なうちに知ることができるツールを開発しました。しかも、脳のスナップショットを見るだけで、誰でも無料で利用可能です。
このツールは、1回のMRI脳スキャンから、中年期における慢性疾患のリスクを推定できます。通常、これらの病気は何十年も後になって現れるものです。この情報を知ることで、健康を改善するための生活習慣や食生活の変更への動機付けになるかもしれません。
高齢者においては、このツールは症状が現れる数年前に認知症や他の加齢関連疾患を発症するかどうかを予測でき、病気の進行を遅らせるためのより良い機会を得られる可能性があります。
「このツールの本当にすごいところは、中年期に収集されたデータを使って人々がどれだけ速く老化しているかを捉えたことです」とハリリ博士は言います。「そしてそれが、はるかに高齢な人々の認知症の診断を予測するのに役立っているのです。」
この研究成果は
マンモス復活も夢じゃない?壮大なゲノムプロジェクトが解き明かす生命の謎と未来
 地球に生きるすべての生き物の「設計図」、ゲノム。そのすべてを解読するという、まるでSFのような壮大なプロジェクトが今、現実のものとなろうとしています。この”現代版ノアの箱舟”ともいえる計画が、絶滅の危機に瀕した動物を救い、生命の進化の謎を解き明かす鍵となるかもしれません。この壮大な挑戦を率いる研究者たちが語る、未来への展望とは?
科学の多くは、地球上のあらゆる生命の設計図であるゲノムを解読することから始まります。このロードマップを手にすることで、科学者たちはヒトの言語の進化的ルーツをたどり、他の動物の知性をより深く理解し、さらにはケナガマンモスを絶滅から蘇らせようと試みることさえできるのです。しかし、これまで利用可能だったゲノムのほとんどは、誤りや欠落だらけで、研究を行き詰まらせることがしばしばありました。そこで登場したのが、地球上に存在する約7万種の脊椎動物すべての、ほぼ完璧なゲノムを構築することを目的とした野心的な取り組み、脊椎動物ゲノムプロジェクトです。ロックフェラー大学の言語の神経遺伝学研究室長であり、VGPの議長を務めるエーリッヒ・D・ジャーヴィス博士(Erich D. Jarvis, PhD)は、このようなデータベースが生物保全、進化生物学、そして基礎科学において変革的な進歩への道を開く未来を思い描いています。さらに野心的なことに、この取り組みは、地球上の全真核生物180万種の高品質ゲノムを解読するという、さらに壮大な挑戦「地球バイオゲノムプロジェクト(EBP: Earth BioGenome Project)」の着想源となり、今やその一部となっています。
脊椎動物の「目(もく)」を代表する数百種に焦点を当てたパイロットプロジェクトの成功に続き、ジャーヴィス博士、EBP議長のハリス・ルーウィン博士(Harris Lewin, PhD)らは現在、米国領内
地球に生きるすべての生き物の「設計図」、ゲノム。そのすべてを解読するという、まるでSFのような壮大なプロジェクトが今、現実のものとなろうとしています。この”現代版ノアの箱舟”ともいえる計画が、絶滅の危機に瀕した動物を救い、生命の進化の謎を解き明かす鍵となるかもしれません。この壮大な挑戦を率いる研究者たちが語る、未来への展望とは?
科学の多くは、地球上のあらゆる生命の設計図であるゲノムを解読することから始まります。このロードマップを手にすることで、科学者たちはヒトの言語の進化的ルーツをたどり、他の動物の知性をより深く理解し、さらにはケナガマンモスを絶滅から蘇らせようと試みることさえできるのです。しかし、これまで利用可能だったゲノムのほとんどは、誤りや欠落だらけで、研究を行き詰まらせることがしばしばありました。そこで登場したのが、地球上に存在する約7万種の脊椎動物すべての、ほぼ完璧なゲノムを構築することを目的とした野心的な取り組み、脊椎動物ゲノムプロジェクトです。ロックフェラー大学の言語の神経遺伝学研究室長であり、VGPの議長を務めるエーリッヒ・D・ジャーヴィス博士(Erich D. Jarvis, PhD)は、このようなデータベースが生物保全、進化生物学、そして基礎科学において変革的な進歩への道を開く未来を思い描いています。さらに野心的なことに、この取り組みは、地球上の全真核生物180万種の高品質ゲノムを解読するという、さらに壮大な挑戦「地球バイオゲノムプロジェクト(EBP: Earth BioGenome Project)」の着想源となり、今やその一部となっています。
脊椎動物の「目(もく)」を代表する数百種に焦点を当てたパイロットプロジェクトの成功に続き、ジャーヴィス博士、EBP議長のハリス・ルーウィン博士(Harris Lewin, PhD)らは現在、米国領内
遺伝子検査が第一選択へ!米国小児科学会の新指針で子どもの発達障害診断が変わる
 お子さんの発達に不安を感じるとき、その原因がなかなかわからず、長い間いくつもの病院を巡る「診断の旅(診断オデッセイ)」に疲弊してしまうご家族がいます。もし、その旅を終わらせるための「羅針盤」が、遺伝子検査によって手に入るとしたらどうでしょう?米国小児科学会が発表した新しい指針は、まさにそのような未来への扉を開くものです。そして今、遺伝子診断のトップランナーであるBaylor Genetics社が、その画期的な動きを強力に後押しすることを表明しました。
ガイダンスではまた、第二選択検査として、Baylor Genetics社独自の非標的メタボライトスクリーンであるGlobal MAPS®のような代謝評価の概要も示されています。
2025年6月26日、遺伝子検査の最前線に立つ主要な臨床診断ラボであるBaylor Genetics社は、全ゲノムシーケンシングおよび全エクソームシーケンシングを第一選択検査(として推奨する米国小児科学会の更新されたガイダンスへの支持を表明しました。Baylor Geneticsは長年にわたりこれらの検査の価値を認識しており、全般性発達遅延や知的障害を示す子どもたちの潜在的な遺伝的原因を小児科医が迅速に特定できるよう、包括的で体系化されたフレームワークを提供しています。この画期的な出来事は、遺伝学の専門家に支えられた小児科医が、患者とその家族のための臨床判断を導く、より早期で包括的な洞察にアクセスできることを意味し、より迅速な診断と改善された治療成果に向けた重要な一歩となります。
米国小気科学会の更新されたガイダンスではまた、GDD/IDを持つ子どもたちにおける第二選択(Tier 2)としての代謝評価の活用法も概説されています。これに沿って、Baylor Geneticsは血漿アミノ酸分析や尿中有機酸分析などの標準的な代謝検査を提供していま
お子さんの発達に不安を感じるとき、その原因がなかなかわからず、長い間いくつもの病院を巡る「診断の旅(診断オデッセイ)」に疲弊してしまうご家族がいます。もし、その旅を終わらせるための「羅針盤」が、遺伝子検査によって手に入るとしたらどうでしょう?米国小児科学会が発表した新しい指針は、まさにそのような未来への扉を開くものです。そして今、遺伝子診断のトップランナーであるBaylor Genetics社が、その画期的な動きを強力に後押しすることを表明しました。
ガイダンスではまた、第二選択検査として、Baylor Genetics社独自の非標的メタボライトスクリーンであるGlobal MAPS®のような代謝評価の概要も示されています。
2025年6月26日、遺伝子検査の最前線に立つ主要な臨床診断ラボであるBaylor Genetics社は、全ゲノムシーケンシングおよび全エクソームシーケンシングを第一選択検査(として推奨する米国小児科学会の更新されたガイダンスへの支持を表明しました。Baylor Geneticsは長年にわたりこれらの検査の価値を認識しており、全般性発達遅延や知的障害を示す子どもたちの潜在的な遺伝的原因を小児科医が迅速に特定できるよう、包括的で体系化されたフレームワークを提供しています。この画期的な出来事は、遺伝学の専門家に支えられた小児科医が、患者とその家族のための臨床判断を導く、より早期で包括的な洞察にアクセスできることを意味し、より迅速な診断と改善された治療成果に向けた重要な一歩となります。
米国小気科学会の更新されたガイダンスではまた、GDD/IDを持つ子どもたちにおける第二選択(Tier 2)としての代謝評価の活用法も概説されています。これに沿って、Baylor Geneticsは血漿アミノ酸分析や尿中有機酸分析などの標準的な代謝検査を提供していま
AIによる細胞シミュレーションの精度を競う世界的挑戦
 AIは、画像生成や自動運転だけでなく、今や生命の根源的な謎そのものに挑戦しています。もし、コンピュータ上で細胞の振る舞いを完璧にシミュレーションできたとしたら、創薬や病気の解明はどれほど加速するでしょうか?その夢の実現に向け、米国の研究機関Arc Instituteが優勝賞金10万ドル相当をかけたAIコンペティションを開始しました。世界中の頭脳が、生命の「仮想モデル」構築に挑みます。これは、かつてタンパク質の構造予測に革命を起こしたコンペティションの再来となるかもしれません。
Arc Instituteが主催し、NVIDIA、10x Genomics、そしてUltima Genomicsが協賛するこのコンペティションは、AIによる生物学のモデリングの進歩を加速させることに焦点を当てています。参加者は、細胞における単一遺伝子摂動(single gene perturbations: 単一の遺伝子への意図的な変化)の影響を予測するモデルを作成します。優勝賞金10万ドル相当のこのチャレンジは、高品質なデータセットの作成を奨励し、仮想細胞モデリングのための標準化されたベンチマークの確立を支援するArcの取り組みの一環です。
本日(2025年6月26日)発行の学術雑誌『Cell』に掲載された解説記事で、Arcの研究者らは、この独立非営利団体初の「Virtual Cell Challenge」を発表しました。これは、細胞が遺伝的摂動にどのように応答するかを最もよく予測する機械学習モデルに、10万ドル相当の優勝賞金を授与する公開コンペティションです。Arcは、人工知能と生物学の接点における進歩を促進するため、特に高品質なデータセットの作成を加速させ、AIモデルが細胞の挙動をどれだけうまくシミュレートできるかを評価するための厳格な基準についての議論を喚起するために、このコンペティ
AIは、画像生成や自動運転だけでなく、今や生命の根源的な謎そのものに挑戦しています。もし、コンピュータ上で細胞の振る舞いを完璧にシミュレーションできたとしたら、創薬や病気の解明はどれほど加速するでしょうか?その夢の実現に向け、米国の研究機関Arc Instituteが優勝賞金10万ドル相当をかけたAIコンペティションを開始しました。世界中の頭脳が、生命の「仮想モデル」構築に挑みます。これは、かつてタンパク質の構造予測に革命を起こしたコンペティションの再来となるかもしれません。
Arc Instituteが主催し、NVIDIA、10x Genomics、そしてUltima Genomicsが協賛するこのコンペティションは、AIによる生物学のモデリングの進歩を加速させることに焦点を当てています。参加者は、細胞における単一遺伝子摂動(single gene perturbations: 単一の遺伝子への意図的な変化)の影響を予測するモデルを作成します。優勝賞金10万ドル相当のこのチャレンジは、高品質なデータセットの作成を奨励し、仮想細胞モデリングのための標準化されたベンチマークの確立を支援するArcの取り組みの一環です。
本日(2025年6月26日)発行の学術雑誌『Cell』に掲載された解説記事で、Arcの研究者らは、この独立非営利団体初の「Virtual Cell Challenge」を発表しました。これは、細胞が遺伝的摂動にどのように応答するかを最もよく予測する機械学習モデルに、10万ドル相当の優勝賞金を授与する公開コンペティションです。Arcは、人工知能と生物学の接点における進歩を促進するため、特に高品質なデータセットの作成を加速させ、AIモデルが細胞の挙動をどれだけうまくシミュレートできるかを評価するための厳格な基準についての議論を喚起するために、このコンペティ
細胞内に未知の小器官「ヘミフソソーム」を発見!遺伝病治療に新たな光
 私たちの体を構成する無数の細胞。その中には、生命活動を支えるための様々な「小器官(オルガネラ)」が存在します。もし、その生物の教科書に載っているリストに、まだ誰も知らない新しい小器官が加わるとしたら、ワクワクしませんか?最近、バージニア大学(UVA)と米国国立衛生研究所(NIH)の科学者たちが、まさにそのような大発見をしました。この小さな新発見の小器官は、深刻な遺伝病の治療法開発に向けた、大きなブレークスルーになるかもしれません。
私たちの細胞内部でこれまで知られていなかったオルガネラ(細胞小器官)が発見されたことにより、深刻な遺伝性疾患に対する新たな治療法への道が開かれる可能性があります。バージニア大学(UVA)医学部と米国国立衛生研究所(NIH)の発見者らによって「ヘミフソソーム」と名付けられたこのオルガネラは、特殊な構造の一種です。科学者たちによると、この小さなオルガネラは、私たちの細胞が重要な積み荷を自身の中で分類、リサイクル、そして廃棄するのを助けるという大きな役割を担っています。この新しい発見は、これらの必須のハウスキーピング機能(細胞内のお掃除機能)を妨げる遺伝的疾患で何がうまくいかないのかを、科学者がより良く理解するのに役立つ可能性があります。
「これは、細胞内における新しいリサイクルセンターを発見するようなものです」と、UVAの分子生理学・生物物理学部門の研究者であるセハム・エブラヒム博士(Seham Ebrahim, PhD)は述べています。「私たちは、ヘミフソソームが細胞の物質の梱包や処理方法を管理するのを助けていると考えており、これがうまくいかないと、体内の多くのシステムに影響を及ぼす疾患の一因となる可能性があります。」
そのような疾患の一つに、白皮症、視力障害、肺疾患、血液凝固の問題などを引き起こす可能性のある、まれな遺伝性疾患であるヘ
私たちの体を構成する無数の細胞。その中には、生命活動を支えるための様々な「小器官(オルガネラ)」が存在します。もし、その生物の教科書に載っているリストに、まだ誰も知らない新しい小器官が加わるとしたら、ワクワクしませんか?最近、バージニア大学(UVA)と米国国立衛生研究所(NIH)の科学者たちが、まさにそのような大発見をしました。この小さな新発見の小器官は、深刻な遺伝病の治療法開発に向けた、大きなブレークスルーになるかもしれません。
私たちの細胞内部でこれまで知られていなかったオルガネラ(細胞小器官)が発見されたことにより、深刻な遺伝性疾患に対する新たな治療法への道が開かれる可能性があります。バージニア大学(UVA)医学部と米国国立衛生研究所(NIH)の発見者らによって「ヘミフソソーム」と名付けられたこのオルガネラは、特殊な構造の一種です。科学者たちによると、この小さなオルガネラは、私たちの細胞が重要な積み荷を自身の中で分類、リサイクル、そして廃棄するのを助けるという大きな役割を担っています。この新しい発見は、これらの必須のハウスキーピング機能(細胞内のお掃除機能)を妨げる遺伝的疾患で何がうまくいかないのかを、科学者がより良く理解するのに役立つ可能性があります。
「これは、細胞内における新しいリサイクルセンターを発見するようなものです」と、UVAの分子生理学・生物物理学部門の研究者であるセハム・エブラヒム博士(Seham Ebrahim, PhD)は述べています。「私たちは、ヘミフソソームが細胞の物質の梱包や処理方法を管理するのを助けていると考えており、これがうまくいかないと、体内の多くのシステムに影響を及ぼす疾患の一因となる可能性があります。」
そのような疾患の一つに、白皮症、視力障害、肺疾患、血液凝固の問題などを引き起こす可能性のある、まれな遺伝性疾患であるヘ
自閉症と心臓病の意外な繋がりを発見!鍵は細胞の「繊毛」にあった
 脳の発達障害である「自閉症」と、心臓の病気である「先天性心疾患」。一見すると全く関係ないように思えるこの二つの状態が、なぜか同じ子どもに併発することがあります。この長年の謎を解く鍵が、私たちの体のほぼすべての細胞に生えている、目に見えないほど小さな「毛」にあることがわかりました。カリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF)の研究チームによるこの発見は、自閉症のリスクを早期に発見し、より適切な支援につなげるための、全く新しい道筋を示してくれるかもしれません。
自閉症スペクトラム障害は、世界の約100人に1人の子どもが罹患する複雑な神経発達障害です。早期に診断ができれば、発達を促し生活の質を向上させるためのタイムリーな介入が可能になります。科学者たちはこれまでに200以上の自閉症関連遺伝子を特定してきましたが、遺伝情報に基づいて自閉症の発症リスクを予測することは容易ではありません。
自閉症は、心臓の構造、成長、機能に影響を及ぼす先天性心疾患と併発することがあります。先天性心疾患は新生児期に容易に特定できるため、その診断は自閉症を発症するリスクが高い子どもをより早期に特定するのに役立つ可能性があります。科学者たちは、それぞれ脳と心臓の発達に影響を与えるこの二つの状態が、なぜ同時に起こるのかを解明しようと試みてきました。
この度、米国のカリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF)に所属するヘレン・ウィルゼー医学博士(Helen Willsey, MD)が率いる科学者チームは、ほぼすべての細胞の表面に見られる繊毛(cilia)と呼ばれる微細な毛のような構造が、自閉症と先天性心疾患の共通の生物学的基盤となっていることを発見しました。これにより、私たちは自閉症発症のリスクがある子どもたちの早期予測に一歩近づくことになります。この研究は、2025年6月24日付の学術雑誌
脳の発達障害である「自閉症」と、心臓の病気である「先天性心疾患」。一見すると全く関係ないように思えるこの二つの状態が、なぜか同じ子どもに併発することがあります。この長年の謎を解く鍵が、私たちの体のほぼすべての細胞に生えている、目に見えないほど小さな「毛」にあることがわかりました。カリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF)の研究チームによるこの発見は、自閉症のリスクを早期に発見し、より適切な支援につなげるための、全く新しい道筋を示してくれるかもしれません。
自閉症スペクトラム障害は、世界の約100人に1人の子どもが罹患する複雑な神経発達障害です。早期に診断ができれば、発達を促し生活の質を向上させるためのタイムリーな介入が可能になります。科学者たちはこれまでに200以上の自閉症関連遺伝子を特定してきましたが、遺伝情報に基づいて自閉症の発症リスクを予測することは容易ではありません。
自閉症は、心臓の構造、成長、機能に影響を及ぼす先天性心疾患と併発することがあります。先天性心疾患は新生児期に容易に特定できるため、その診断は自閉症を発症するリスクが高い子どもをより早期に特定するのに役立つ可能性があります。科学者たちは、それぞれ脳と心臓の発達に影響を与えるこの二つの状態が、なぜ同時に起こるのかを解明しようと試みてきました。
この度、米国のカリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF)に所属するヘレン・ウィルゼー医学博士(Helen Willsey, MD)が率いる科学者チームは、ほぼすべての細胞の表面に見られる繊毛(cilia)と呼ばれる微細な毛のような構造が、自閉症と先天性心疾患の共通の生物学的基盤となっていることを発見しました。これにより、私たちは自閉症発症のリスクがある子どもたちの早期予測に一歩近づくことになります。この研究は、2025年6月24日付の学術雑誌
アルツハイマー病を遅らせる「奇跡の遺伝子変異」、その仕組みを解明!
 アルツハイマー病という、未だ多くの謎に包まれた病気の進行を、劇的に遅らせることが知られている希少な遺伝子変異があります。なぜこの「クライストチャーチ変異」と呼ばれる特別な遺伝子を持つ人は、病魔から強く守られるのでしょうか?その驚くべきメカニズムの一端が、ワイル・コーネル医科大学の研究チームによる最新の研究で明らかになりました。鍵を握っていたのは、私たちの脳を守る「免疫細胞」と、その「炎症シグナル」を巧みにコントロールする力でした。この発見は、アルツハイマー病の新たな治療戦略への道を切り開くかもしれません。
本記事では、この画期的な研究の詳細と、将来の治療法への期待について詳しく解説します。
ワイル・コーネル医科大学の研究者らが主導した前臨床研究によると、アルツハイマー病の発症を遅らせる希少な遺伝子変異は、脳に存在する免疫細胞の炎症シグナルを抑制することによって、その効果を発揮することが明らかになりました。この発見は、脳の炎症がアルツハイマー病のような神経変性疾患の主要な原因であり、これらの疾患の重要な治療標的となりうるという証拠をさらに強固にするものです。
2025年6月23日に『Immunity』誌で発表されたこの研究で、研究者らは「クライストチャーチ変異」として知られるAPOE3-R136S変異の効果を検証しました。この変異は、遺伝性の早期発症型アルツハイマー病を遅らせることが最近発見されたものです。ワイル・コーネル医科大学の科学者たちは、この変異がcGAS-STING経路を阻害することを示しました。cGAS-STING経路は、アルツハイマー病や他の神経変性疾患で異常に活性化している自然免疫のシグナル伝達カスケードです。
研究者らは、薬剤のような阻害剤を用いてcGAS-STING経路を薬理学的にブロックすると、前臨床モデルにおいて、この変異が持つ重要な保
アルツハイマー病という、未だ多くの謎に包まれた病気の進行を、劇的に遅らせることが知られている希少な遺伝子変異があります。なぜこの「クライストチャーチ変異」と呼ばれる特別な遺伝子を持つ人は、病魔から強く守られるのでしょうか?その驚くべきメカニズムの一端が、ワイル・コーネル医科大学の研究チームによる最新の研究で明らかになりました。鍵を握っていたのは、私たちの脳を守る「免疫細胞」と、その「炎症シグナル」を巧みにコントロールする力でした。この発見は、アルツハイマー病の新たな治療戦略への道を切り開くかもしれません。
本記事では、この画期的な研究の詳細と、将来の治療法への期待について詳しく解説します。
ワイル・コーネル医科大学の研究者らが主導した前臨床研究によると、アルツハイマー病の発症を遅らせる希少な遺伝子変異は、脳に存在する免疫細胞の炎症シグナルを抑制することによって、その効果を発揮することが明らかになりました。この発見は、脳の炎症がアルツハイマー病のような神経変性疾患の主要な原因であり、これらの疾患の重要な治療標的となりうるという証拠をさらに強固にするものです。
2025年6月23日に『Immunity』誌で発表されたこの研究で、研究者らは「クライストチャーチ変異」として知られるAPOE3-R136S変異の効果を検証しました。この変異は、遺伝性の早期発症型アルツハイマー病を遅らせることが最近発見されたものです。ワイル・コーネル医科大学の科学者たちは、この変異がcGAS-STING経路を阻害することを示しました。cGAS-STING経路は、アルツハイマー病や他の神経変性疾患で異常に活性化している自然免疫のシグナル伝達カスケードです。
研究者らは、薬剤のような阻害剤を用いてcGAS-STING経路を薬理学的にブロックすると、前臨床モデルにおいて、この変異が持つ重要な保
ビール酵母が「創薬工場」に!大環状ペプチドの新薬開発を加速する新技術
 パンやビール作りに欠かせない、あの小さな「酵母」。もし、この身近な微生物が、がんなどの難病を治療する未来の薬を生み出す「超小型工場」になるとしたら、どうでしょう?イタリアの研究チームが、まさにそんな夢のような技術を開発しました。数十億もの酵母を使って、新薬の候補をわずか数時間で見つけ出すこの画期的な方法は、創薬の世界に「グリーン革命」をもたらすかもしれません。
カ・フォスカリ大学ヴェネツィアの科学者たちは、日本、中国、スイス、イタリアの研究者と協力し、現代医療でますます利用されている大環状ペプチドという分子を大量に生産し、迅速に分析する革新的な方法を開発しました。2025年6月25日に『Nature Communications』誌で発表されたこの研究は、おなじみのビール酵母を活用し、これらの微小な生物をそれぞれが治療応用の可能性を秘めたユニークなペプチドを作り出すことができる、数十億もの小型蛍光工場に変えるものです。このオープンアクセスの論文タイトルは「Screening Macrocyclic Peptide Libraries by Yeast Display Allows Control of Selection Process and Affinity Ranking(酵母ディスプレイによる大環状ペプチドライブラリーのスクリーニングは選択プロセスと親和性ランキングの制御を可能にする)」です。
大環状ペプチドは、精密な標的化、安定性、安全性を兼ね備え、従来の医薬品よりも副作用が少ないことから、有望な医薬品とされています。しかし、これらのペプチドを発見し、試験するための従来の方法は、しばしば複雑で制御が難しく、時間がかかり、環境にも優しくありませんでした。
これらの限界を克服するため、研究者たちは一般的なビール酵母の細胞を操作し、個々に異なる大環状ペプチドを
パンやビール作りに欠かせない、あの小さな「酵母」。もし、この身近な微生物が、がんなどの難病を治療する未来の薬を生み出す「超小型工場」になるとしたら、どうでしょう?イタリアの研究チームが、まさにそんな夢のような技術を開発しました。数十億もの酵母を使って、新薬の候補をわずか数時間で見つけ出すこの画期的な方法は、創薬の世界に「グリーン革命」をもたらすかもしれません。
カ・フォスカリ大学ヴェネツィアの科学者たちは、日本、中国、スイス、イタリアの研究者と協力し、現代医療でますます利用されている大環状ペプチドという分子を大量に生産し、迅速に分析する革新的な方法を開発しました。2025年6月25日に『Nature Communications』誌で発表されたこの研究は、おなじみのビール酵母を活用し、これらの微小な生物をそれぞれが治療応用の可能性を秘めたユニークなペプチドを作り出すことができる、数十億もの小型蛍光工場に変えるものです。このオープンアクセスの論文タイトルは「Screening Macrocyclic Peptide Libraries by Yeast Display Allows Control of Selection Process and Affinity Ranking(酵母ディスプレイによる大環状ペプチドライブラリーのスクリーニングは選択プロセスと親和性ランキングの制御を可能にする)」です。
大環状ペプチドは、精密な標的化、安定性、安全性を兼ね備え、従来の医薬品よりも副作用が少ないことから、有望な医薬品とされています。しかし、これらのペプチドを発見し、試験するための従来の方法は、しばしば複雑で制御が難しく、時間がかかり、環境にも優しくありませんでした。
これらの限界を克服するため、研究者たちは一般的なビール酵母の細胞を操作し、個々に異なる大環状ペプチドを
失明原因「加齢黄斑変性」に新展開!コレステロール代謝の改善が鍵
 50歳を過ぎると誰もが気になる目の衰え。その中でも失明の大きな原因となる「加齢黄斑変性」。この病気の進行を食い止める鍵が、私たちの血液中を流れる「コレステロール」の代謝にあったとしたらどうでしょう?マウスとヒトの血漿サンプルを用いた最新の研究が、目の病気と心臓病を結びつける意外なメカニズムを解き明かし、全く新しい治療法への道を切り開きました。失明という深刻な事態を防ぐための、希望の光となるかもしれません。
セントルイス・ワシントン大学医学部(Washington University School of Medicine in St. Louis)の新しい研究により、50歳以上の人々の失明の主因である加齢黄斑変性の進行を遅らせる、あるいは阻止する可能性のある方法が特定されました。ワシントン大学医学部の研究者とその国際共同研究者らは、この種の視力喪失にコレステロール代謝の問題が関与していることを突き止めました。これは、加齢とともに悪化する加齢黄斑変性と心血管疾患との関連性を説明するのに役立つ可能性があります。
ヒトの血漿サンプルと加齢黄斑変性のマウスモデルを用いて特定されたこの新しい発見は、血中のアポリポタンパク質Mと呼ばれる分子の量を増やすことで、目や他の臓器の細胞損傷につながるコレステロール処理の問題が修正されることを示唆しています。ApoMを増加させる様々な方法は、加齢黄斑変性や、同様の機能不全に陥ったコレステロール処理によって引き起こされる一部の心不全に対する、新しい治療戦略となる可能性があります。この研究は、2025年6月24日に科学雑誌『Nature Communications』に掲載されました。このオープンアクセスの論文タイトルは「Apolipoprotein M Attenuates Age-Related Macular Degeneration
50歳を過ぎると誰もが気になる目の衰え。その中でも失明の大きな原因となる「加齢黄斑変性」。この病気の進行を食い止める鍵が、私たちの血液中を流れる「コレステロール」の代謝にあったとしたらどうでしょう?マウスとヒトの血漿サンプルを用いた最新の研究が、目の病気と心臓病を結びつける意外なメカニズムを解き明かし、全く新しい治療法への道を切り開きました。失明という深刻な事態を防ぐための、希望の光となるかもしれません。
セントルイス・ワシントン大学医学部(Washington University School of Medicine in St. Louis)の新しい研究により、50歳以上の人々の失明の主因である加齢黄斑変性の進行を遅らせる、あるいは阻止する可能性のある方法が特定されました。ワシントン大学医学部の研究者とその国際共同研究者らは、この種の視力喪失にコレステロール代謝の問題が関与していることを突き止めました。これは、加齢とともに悪化する加齢黄斑変性と心血管疾患との関連性を説明するのに役立つ可能性があります。
ヒトの血漿サンプルと加齢黄斑変性のマウスモデルを用いて特定されたこの新しい発見は、血中のアポリポタンパク質Mと呼ばれる分子の量を増やすことで、目や他の臓器の細胞損傷につながるコレステロール処理の問題が修正されることを示唆しています。ApoMを増加させる様々な方法は、加齢黄斑変性や、同様の機能不全に陥ったコレステロール処理によって引き起こされる一部の心不全に対する、新しい治療戦略となる可能性があります。この研究は、2025年6月24日に科学雑誌『Nature Communications』に掲載されました。このオープンアクセスの論文タイトルは「Apolipoprotein M Attenuates Age-Related Macular Degeneration
高周波から低周波まで対応!フクロウに学ぶ次世代の広帯域騒音吸収材
 夜の森のハンター、フクロウ。彼らが獲物に全く気づかれずに、驚くほど静かに空を飛べる秘密は何だと思いますか?その答えは、彼らの特別な皮膚と羽毛に隠されていました。音を吸収するこの自然界の叡智にヒントを得て、科学者たちが私たちの生活を悩ませる「騒音」を劇的に減らす、画期的な新素材を開発しました。このフクロウに学んだ新技術は、自動車から工場の機械音まで、様々な騒音問題への新たな解決策となるかもしれません。
フクロウが飛ぶ姿を見たことがあっても、その羽音を聞いたことはほとんどないでしょう。それは、彼らの皮膚と羽毛が高周波から低周波までの飛行音を吸収し、音を減衰させるからです。この自然の防音効果に着想を得て、2025年5月28日に『ACS Applied Materials & Interfaces』誌で発表を行った研究者たちは、フクロウの羽と皮膚の内部構造を模倣し、騒音公害を軽減する二層構造のエアロゲルを開発しました。この新しい素材は、自動車や製造工場などで交通騒音や産業騒音を低減するために利用できる可能性があります。この論文のタイトルは「Owl-Inspired Coupled Structure Nanofiber-Based Aerogels for Broadband Noise Reduction(フクロウに着想を得た連結構造を持つナノファイバーベースのエアロゲルによる広帯域騒音低減)」です。
騒音公害は単なる不快なものではありません。過度の騒音は難聴を引き起こす可能性があり、心血管疾患や2型糖尿病などの健康状態を悪化させることもあります。騒音源を取り除くことが不可能な場合、防音材がその音を和らげるのに役立ちます。しかし、従来の材料は、ブレーキのきしむような高周波音か、自動車エンジンのような低いうなり音のどちらかしか吸収できません。これは、エンジニアが
夜の森のハンター、フクロウ。彼らが獲物に全く気づかれずに、驚くほど静かに空を飛べる秘密は何だと思いますか?その答えは、彼らの特別な皮膚と羽毛に隠されていました。音を吸収するこの自然界の叡智にヒントを得て、科学者たちが私たちの生活を悩ませる「騒音」を劇的に減らす、画期的な新素材を開発しました。このフクロウに学んだ新技術は、自動車から工場の機械音まで、様々な騒音問題への新たな解決策となるかもしれません。
フクロウが飛ぶ姿を見たことがあっても、その羽音を聞いたことはほとんどないでしょう。それは、彼らの皮膚と羽毛が高周波から低周波までの飛行音を吸収し、音を減衰させるからです。この自然の防音効果に着想を得て、2025年5月28日に『ACS Applied Materials & Interfaces』誌で発表を行った研究者たちは、フクロウの羽と皮膚の内部構造を模倣し、騒音公害を軽減する二層構造のエアロゲルを開発しました。この新しい素材は、自動車や製造工場などで交通騒音や産業騒音を低減するために利用できる可能性があります。この論文のタイトルは「Owl-Inspired Coupled Structure Nanofiber-Based Aerogels for Broadband Noise Reduction(フクロウに着想を得た連結構造を持つナノファイバーベースのエアロゲルによる広帯域騒音低減)」です。
騒音公害は単なる不快なものではありません。過度の騒音は難聴を引き起こす可能性があり、心血管疾患や2型糖尿病などの健康状態を悪化させることもあります。騒音源を取り除くことが不可能な場合、防音材がその音を和らげるのに役立ちます。しかし、従来の材料は、ブレーキのきしむような高周波音か、自動車エンジンのような低いうなり音のどちらかしか吸収できません。これは、エンジニアが
AIが細胞の未来を予測!画期的な「仮想細胞モデル STATE」が創薬を変える
 私たちの体の中では、免疫細胞、幹細胞、そして時にはがん細胞といった、多種多様な細胞たちがまるで個性豊かな役者のように、日々異なる役割を演じています。しかし驚くべきことに、その脚本、つまり設計図であるゲノムは、ほぼ全ての細胞で同じなのです。では、なぜこれほど多様な細胞が生まれるのでしょうか?その答えは、設計図の「使い方」、すなわちどの遺伝子をオンにし、どの遺伝子をオフにするかという「遺伝子発現」の違いにあります。
そして今、AIがその複雑な使い方を解読し、細胞の未来を予測する「仮想細胞モデル」が登場しました。これは、創薬研究に革命をもたらす可能性を秘めた、大きな一歩です。
ヒトの体は細胞のモザイクです。免疫細胞は感染と戦うために炎症を活性化させ、幹細胞は多様な組織に分化し、がん細胞は制御シグナルを回避して無限に分裂します。これらの驚くべき違いにもかかわらず、ヒトの各細胞は(ほぼ)同じゲノムを持っています。細胞の個性は、DNAの違いだけでなく、むしろ各細胞がそのDNAを「どのように」使うかによって生じます。言い換えれば、細胞の特性は、時間とともに遺伝子が「オン」や「オフ」に切り替わる遺伝子発現のバリエーションから生まれるのです。
細胞の遺伝子発現パターンは、ゲノムから転写されるRNA分子によって表され、細胞の種類だけでなく、その「細胞の状態」をも決定します。細胞の遺伝子発現の変化を追うことで、健康な状態から炎症状態、そしてがん化した状態へとどのように移行するかがわかります。化学的または遺伝的な摂動(perturbation: 意図的な変化)を与えた細胞と与えていない細胞のRNA転写産物を測定することで、細胞の状態の鍵を握る遺伝子発現パターンがどのように変化するかを予測できるAIモデルを訓練することが可能です。このようなモデルは、これまで遭遇したことのない摂動に対する応
私たちの体の中では、免疫細胞、幹細胞、そして時にはがん細胞といった、多種多様な細胞たちがまるで個性豊かな役者のように、日々異なる役割を演じています。しかし驚くべきことに、その脚本、つまり設計図であるゲノムは、ほぼ全ての細胞で同じなのです。では、なぜこれほど多様な細胞が生まれるのでしょうか?その答えは、設計図の「使い方」、すなわちどの遺伝子をオンにし、どの遺伝子をオフにするかという「遺伝子発現」の違いにあります。
そして今、AIがその複雑な使い方を解読し、細胞の未来を予測する「仮想細胞モデル」が登場しました。これは、創薬研究に革命をもたらす可能性を秘めた、大きな一歩です。
ヒトの体は細胞のモザイクです。免疫細胞は感染と戦うために炎症を活性化させ、幹細胞は多様な組織に分化し、がん細胞は制御シグナルを回避して無限に分裂します。これらの驚くべき違いにもかかわらず、ヒトの各細胞は(ほぼ)同じゲノムを持っています。細胞の個性は、DNAの違いだけでなく、むしろ各細胞がそのDNAを「どのように」使うかによって生じます。言い換えれば、細胞の特性は、時間とともに遺伝子が「オン」や「オフ」に切り替わる遺伝子発現のバリエーションから生まれるのです。
細胞の遺伝子発現パターンは、ゲノムから転写されるRNA分子によって表され、細胞の種類だけでなく、その「細胞の状態」をも決定します。細胞の遺伝子発現の変化を追うことで、健康な状態から炎症状態、そしてがん化した状態へとどのように移行するかがわかります。化学的または遺伝的な摂動(perturbation: 意図的な変化)を与えた細胞と与えていない細胞のRNA転写産物を測定することで、細胞の状態の鍵を握る遺伝子発現パターンがどのように変化するかを予測できるAIモデルを訓練することが可能です。このようなモデルは、これまで遭遇したことのない摂動に対する応
脳の謎に迫る!小脳シナプスの「設計図」を世界で初めて解明
 私たちが何気なく行っている歩行や、バランスを取るといった複雑な動き、そして学習や記憶といった高度な思考。これらはすべて、脳の中にある「小脳」という部分で、無数の神経細胞が情報をやり取りすることで成り立っています。その情報の受け渡し場所である「シナプス」は、まさに生命活動の根幹をなす極めて重要な接続点です。
もし、この超微細な接続点の「設計図」を、分子レベルで詳細に覗き見ることができたとしたらどうでしょう?
この度、科学者たちは最先端の技術を駆使して、その偉業を成し遂げました。脳科学における長年の謎であった小脳シナプスの構造が初めて明らかになり、将来の医療に新たな光を当てる可能性がでてきました。
科学者たちはクライオ電子顕微鏡法を用いて、脳の小脳にある神経細胞をつなぐ重要な受容体の構造と形状を、世界で初めて明らかにしました。脳幹の後ろに位置する小脳は、運動の協調、平衡感覚、認知といった機能において極めて重要な役割を果たしています。2025年6月23日に科学雑誌『Nature』誌で発表されたこの研究は、怪我や遺伝子変異によってこれらの構造が破壊された際に、それらを修復する治療法の開発につながる可能性のある新しい知見を提供するものです。影響を受ける運動能力には、座る、立つ、歩く、走る、跳ぶといった動作や、学習・記憶が含まれます。この論文のタイトルは「Gating and Noelin Clustering of Native Ca2+-Permeable AMPA Receptors(天然のCa2+透過性AMPA受容体のゲーティングとノエリンによるクラスタリング)」です。
オレゴン健康科学大学(OHSU)の科学者たちによるこの発見は、直ちに新薬や治療法に結びつくものではありませんが、人間の健康を向上させるために何十年にもわたって維持されてきた、米国の医学研究への取り組
私たちが何気なく行っている歩行や、バランスを取るといった複雑な動き、そして学習や記憶といった高度な思考。これらはすべて、脳の中にある「小脳」という部分で、無数の神経細胞が情報をやり取りすることで成り立っています。その情報の受け渡し場所である「シナプス」は、まさに生命活動の根幹をなす極めて重要な接続点です。
もし、この超微細な接続点の「設計図」を、分子レベルで詳細に覗き見ることができたとしたらどうでしょう?
この度、科学者たちは最先端の技術を駆使して、その偉業を成し遂げました。脳科学における長年の謎であった小脳シナプスの構造が初めて明らかになり、将来の医療に新たな光を当てる可能性がでてきました。
科学者たちはクライオ電子顕微鏡法を用いて、脳の小脳にある神経細胞をつなぐ重要な受容体の構造と形状を、世界で初めて明らかにしました。脳幹の後ろに位置する小脳は、運動の協調、平衡感覚、認知といった機能において極めて重要な役割を果たしています。2025年6月23日に科学雑誌『Nature』誌で発表されたこの研究は、怪我や遺伝子変異によってこれらの構造が破壊された際に、それらを修復する治療法の開発につながる可能性のある新しい知見を提供するものです。影響を受ける運動能力には、座る、立つ、歩く、走る、跳ぶといった動作や、学習・記憶が含まれます。この論文のタイトルは「Gating and Noelin Clustering of Native Ca2+-Permeable AMPA Receptors(天然のCa2+透過性AMPA受容体のゲーティングとノエリンによるクラスタリング)」です。
オレゴン健康科学大学(OHSU)の科学者たちによるこの発見は、直ちに新薬や治療法に結びつくものではありませんが、人間の健康を向上させるために何十年にもわたって維持されてきた、米国の医学研究への取り組
生命の基本設計図「細胞周期」を操る、ヒト特有の新しい遺伝子を発見
 私たちの体が毎日を健康に過ごすため、体内では一日におよそ3,300億回もの細胞分裂が繰り返されています。この生命活動の根幹をなすのが「細胞周期」と呼ばれる、太古のバクテリアの時代から受け継がれてきた生命の基本ルールです。その原理は「細胞の中身を2倍にして、2つの娘細胞に分裂する」というシンプルなもの。しかし、私たちヒトのような複雑な生物では、この細胞周期はより高度で精巧なものへと進化してきました。ここで一つの疑問が浮かび上がります。それは「進化の過程で比較的最近になって登場した遺伝子は、この生命の根源的なプロセスを制御する上で、どのような役割を果たしているのだろうか?」というものです。
この深遠な問いに、スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)の研究チームが挑み、驚くべき事実を突き止めました。
スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)のディディエ・トロノ医学博士(Didier Trono, MD)のグループに所属する二人の科学者、ロマン・フォレー(Romain Forey)とシリル・プルバー(Cyril Pulver)が、この問題の解明に乗り出しました。彼らは細胞周期生物学とゲノミクスを組み合わせ、細胞分裂の過程で遺伝子の働きがどのように変化するのかを調査しました。同僚のアレックス・レデラー(Alex Lederer)と協力し、ヒトの細胞周期における遺伝子活性の詳細なアトラスを作成しました。このアトラスは現在、研究者や一般の人々にも公開されています。研究そのものは、2025年6月23日に『Cell Genomics』誌で発表されました。このオープンアクセスの論文タイトルは「Evolutionarily Recent Transcription Factors Partake in Human Cell Cycle Regulation(進化的に新しい転写因子がヒ
私たちの体が毎日を健康に過ごすため、体内では一日におよそ3,300億回もの細胞分裂が繰り返されています。この生命活動の根幹をなすのが「細胞周期」と呼ばれる、太古のバクテリアの時代から受け継がれてきた生命の基本ルールです。その原理は「細胞の中身を2倍にして、2つの娘細胞に分裂する」というシンプルなもの。しかし、私たちヒトのような複雑な生物では、この細胞周期はより高度で精巧なものへと進化してきました。ここで一つの疑問が浮かび上がります。それは「進化の過程で比較的最近になって登場した遺伝子は、この生命の根源的なプロセスを制御する上で、どのような役割を果たしているのだろうか?」というものです。
この深遠な問いに、スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)の研究チームが挑み、驚くべき事実を突き止めました。
スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)のディディエ・トロノ医学博士(Didier Trono, MD)のグループに所属する二人の科学者、ロマン・フォレー(Romain Forey)とシリル・プルバー(Cyril Pulver)が、この問題の解明に乗り出しました。彼らは細胞周期生物学とゲノミクスを組み合わせ、細胞分裂の過程で遺伝子の働きがどのように変化するのかを調査しました。同僚のアレックス・レデラー(Alex Lederer)と協力し、ヒトの細胞周期における遺伝子活性の詳細なアトラスを作成しました。このアトラスは現在、研究者や一般の人々にも公開されています。研究そのものは、2025年6月23日に『Cell Genomics』誌で発表されました。このオープンアクセスの論文タイトルは「Evolutionarily Recent Transcription Factors Partake in Human Cell Cycle Regulation(進化的に新しい転写因子がヒ
Life Science News from Around the Globe
Edited by Michael D. O'Neill

バイオクイックニュースは、サイエンスライターとして30年以上の豊富な経験があるマイケルD. オニールによって発行されている独立系科学ニュースメディアです。世界中のバイオニュース(生命科学・医学研究の動向)をタイムリーにお届けします。バイオクイックニュースは、現在160カ国以上に読者がおり、2010年から6年連続で米国APEX Award for Publication Excellenceを受賞しました。
BioQuick is a trademark of Michael D. O'Neill