アプタマーでバイオセンサー開発:抗体と比較し多くのメリット - Novaptech
Novaptech社は、常に最前線で革新的なソリューションを提供するために、Switching…
この製品について詳しく知る
 私たちの細胞は、まるで宅配便のように、目に見えないほど小さなカプセルを使って互いにメッセージや物質を送り合っています。この小さなカプセルが、腎臓にたくさんの袋(嚢胞)ができて機能が損なわれてしまう遺伝性の難病、「多発性嚢胞腎」の進行に深く関わっていることが分かってきました。ラトガース大学の研究チームは、この“細胞の宅配便”の中身と行き先を追跡する画期的な「目印」を開発し、病気の謎を解き明かす重要な手がかりを発見しました。ラトガース大学が主導した革新的な細胞追跡ツールの発見は、一般的な遺伝性腎疾患である常染色体優性多発性嚢胞腎に対する新しい治療法を生み出す可能性があります。
多発性嚢胞腎は、老廃物を除去する臓器である腎臓が嚢胞によって破壊される一般的な遺伝性疾患で、現在のところ透析や移植が唯一の治療法となっています。世界中で1,240万人以上が、この病気の優性遺伝型(AD-PKD)に苦しんでいます。この度、ラトガース大学の遺伝学者たちが、この病気がどのように進行するのかについての新たな詳細を解明し、新しい治療法への扉を開く可能性のある発見をしました。
2025年4月3日に学術誌「Nature Communications」で発表された研究で、ラトガース大学芸術科学部遺伝学科の研究助教であるインナ・ニコンノロワ氏(Inna Nikonorova)と共同研究者たちは、細胞外小胞によって運ばれる物質を特定し追跡する新しい方法について報告しました。EVは細胞から放出される微小なコミュニケーションツールで、癌や神経変性疾患、そしてPKDのような腎疾患の発症において重要な役割を果たしています。このオープンアクセスの論文は、「ポリシスチンは線虫において繊毛の細胞外小胞の特定のサブタイプに積み荷を動員する(Polycystins Recruit Cargo to Distinct
私たちの細胞は、まるで宅配便のように、目に見えないほど小さなカプセルを使って互いにメッセージや物質を送り合っています。この小さなカプセルが、腎臓にたくさんの袋(嚢胞)ができて機能が損なわれてしまう遺伝性の難病、「多発性嚢胞腎」の進行に深く関わっていることが分かってきました。ラトガース大学の研究チームは、この“細胞の宅配便”の中身と行き先を追跡する画期的な「目印」を開発し、病気の謎を解き明かす重要な手がかりを発見しました。ラトガース大学が主導した革新的な細胞追跡ツールの発見は、一般的な遺伝性腎疾患である常染色体優性多発性嚢胞腎に対する新しい治療法を生み出す可能性があります。
多発性嚢胞腎は、老廃物を除去する臓器である腎臓が嚢胞によって破壊される一般的な遺伝性疾患で、現在のところ透析や移植が唯一の治療法となっています。世界中で1,240万人以上が、この病気の優性遺伝型(AD-PKD)に苦しんでいます。この度、ラトガース大学の遺伝学者たちが、この病気がどのように進行するのかについての新たな詳細を解明し、新しい治療法への扉を開く可能性のある発見をしました。
2025年4月3日に学術誌「Nature Communications」で発表された研究で、ラトガース大学芸術科学部遺伝学科の研究助教であるインナ・ニコンノロワ氏(Inna Nikonorova)と共同研究者たちは、細胞外小胞によって運ばれる物質を特定し追跡する新しい方法について報告しました。EVは細胞から放出される微小なコミュニケーションツールで、癌や神経変性疾患、そしてPKDのような腎疾患の発症において重要な役割を果たしています。このオープンアクセスの論文は、「ポリシスチンは線虫において繊毛の細胞外小胞の特定のサブタイプに積み荷を動員する(Polycystins Recruit Cargo to Distinct
 薬が効かない「スーパー耐性菌」。この静かなる脅威は、数十年後にはがんによる死亡者数を超えるとも言われ、世界的な健康課題となっています。「敵の敵は味方」という発想で、細菌を攻撃するウイルス(ファージ)を使った治療法が期待されていますが、細菌も巧みにウイルスから身を守る術を持っています。スウェーデンの研究チームが、その賢い防御システムの謎を解き明かし、耐性菌との戦いに新たな光を当てました。抗生物質耐性は、数十年以内にがんによる死亡率を上回る可能性のある、世界的な健康課題です。スウェーデンのウメオ大学の研究者たちは、新しい研究で、耐性の出現が、細菌がウイルスの感染から身を守るための防御機構を構築する仕組みの中で理解できることを示しました。それは、攻撃してくるウイルスの増殖能力を妨害する細菌内の遺伝子に関するものです。
この研究成果は、2025年2月22日に「Nature Communications」誌に掲載されました。このオープンアクセスの論文タイトルは、「ファージの相同組換え酵素を標的とするファージ寄生体が抗ウイルス免疫を提供する(Phage Parasites Targeting Phage Homologous Recombinases Provide Antiviral Immunity)」です。
「抗生物質耐性への鍵の一つは、ウイルスを使って細菌を殺すことかもしれませんが、細菌がウイルスから身を守るために用いるシステムは(編集者注:CRISPRを除き)知られていません。これらのシステムを理解することは、将来的に重篤な感染症を治療できるよう、その防御をいかに打ち破るかという研究への道を開きます」と、ウメオ大学の助教であり、本研究の筆頭著者であるイグナシオ・ミル・サンチス博士(Ignacio Mir-Sanchis, DVM, PhD)は述べています。
ウメオ
薬が効かない「スーパー耐性菌」。この静かなる脅威は、数十年後にはがんによる死亡者数を超えるとも言われ、世界的な健康課題となっています。「敵の敵は味方」という発想で、細菌を攻撃するウイルス(ファージ)を使った治療法が期待されていますが、細菌も巧みにウイルスから身を守る術を持っています。スウェーデンの研究チームが、その賢い防御システムの謎を解き明かし、耐性菌との戦いに新たな光を当てました。抗生物質耐性は、数十年以内にがんによる死亡率を上回る可能性のある、世界的な健康課題です。スウェーデンのウメオ大学の研究者たちは、新しい研究で、耐性の出現が、細菌がウイルスの感染から身を守るための防御機構を構築する仕組みの中で理解できることを示しました。それは、攻撃してくるウイルスの増殖能力を妨害する細菌内の遺伝子に関するものです。
この研究成果は、2025年2月22日に「Nature Communications」誌に掲載されました。このオープンアクセスの論文タイトルは、「ファージの相同組換え酵素を標的とするファージ寄生体が抗ウイルス免疫を提供する(Phage Parasites Targeting Phage Homologous Recombinases Provide Antiviral Immunity)」です。
「抗生物質耐性への鍵の一つは、ウイルスを使って細菌を殺すことかもしれませんが、細菌がウイルスから身を守るために用いるシステムは(編集者注:CRISPRを除き)知られていません。これらのシステムを理解することは、将来的に重篤な感染症を治療できるよう、その防御をいかに打ち破るかという研究への道を開きます」と、ウメオ大学の助教であり、本研究の筆頭著者であるイグナシオ・ミル・サンチス博士(Ignacio Mir-Sanchis, DVM, PhD)は述べています。
ウメオ
 パーキンソン病の発症リスクには、まだ解明されていない謎が多く残されています。なぜ同じ遺伝的リスクを持っていても、病気を発症する人としない人がいるのでしょうか?この長年の疑問に、最先端のゲノム編集技術が光を当てました。ノースウェスタン大学の研究チームが、CRISPR干渉法という画期的な技術を用いてヒトゲノムの全遺伝子を探索。その結果、パーキンソン病のリスクに関わる新たな遺伝子群と細胞内の仕組みを発見し、これまで未知であった治療薬の標的を突き止めました。この発見は、パーキンソン病や関連する神経変性疾患の治療に、新たな道を切り開くものとして期待されています。
CRISPR技術でパーキンソン病の新たな遺伝子を発見
パーキンソン病(PD)研究における長年の謎の一つは、PDのリスクを高める病原性遺伝子変異を持つ人の中でも、発症する人としない人がいる理由でした。これまでは、追加の遺伝的要因が関与している可能性が示唆されていました。
この疑問に答えるため、ノースウェスタン大学医学部の新しい研究では、CRISPR干渉法と呼ばれる最新技術を用いて、ヒトゲノムの全遺伝子を体系的に調査しました。その結果、科学者たちはパーキンソン病のリスクに寄与する新たな遺伝子群を特定し、これまで手つかずだった創薬標的への扉を開きました。
パーキンソン病はアルツハイマー病に次いで2番目に多い神経変性疾患であり、世界で1000万人以上の人々がこの病と共に生活しています。
この研究は2025年4月10日付の科学誌「Science」に掲載され、論文タイトルは「Commander複合体はリソソーム機能を調節し、パーキンソン病リスクに関与する(Commander Complex Regulates Lysosomal Function and Is Implicated in Parkinson’s Di
パーキンソン病の発症リスクには、まだ解明されていない謎が多く残されています。なぜ同じ遺伝的リスクを持っていても、病気を発症する人としない人がいるのでしょうか?この長年の疑問に、最先端のゲノム編集技術が光を当てました。ノースウェスタン大学の研究チームが、CRISPR干渉法という画期的な技術を用いてヒトゲノムの全遺伝子を探索。その結果、パーキンソン病のリスクに関わる新たな遺伝子群と細胞内の仕組みを発見し、これまで未知であった治療薬の標的を突き止めました。この発見は、パーキンソン病や関連する神経変性疾患の治療に、新たな道を切り開くものとして期待されています。
CRISPR技術でパーキンソン病の新たな遺伝子を発見
パーキンソン病(PD)研究における長年の謎の一つは、PDのリスクを高める病原性遺伝子変異を持つ人の中でも、発症する人としない人がいる理由でした。これまでは、追加の遺伝的要因が関与している可能性が示唆されていました。
この疑問に答えるため、ノースウェスタン大学医学部の新しい研究では、CRISPR干渉法と呼ばれる最新技術を用いて、ヒトゲノムの全遺伝子を体系的に調査しました。その結果、科学者たちはパーキンソン病のリスクに寄与する新たな遺伝子群を特定し、これまで手つかずだった創薬標的への扉を開きました。
パーキンソン病はアルツハイマー病に次いで2番目に多い神経変性疾患であり、世界で1000万人以上の人々がこの病と共に生活しています。
この研究は2025年4月10日付の科学誌「Science」に掲載され、論文タイトルは「Commander複合体はリソソーム機能を調節し、パーキンソン病リスクに関与する(Commander Complex Regulates Lysosomal Function and Is Implicated in Parkinson’s Di
 私たちの体の中には、病気の芽を摘み取り、健康を守るために常にパトロールしている頼もしい存在がいます。それが「免疫細胞」です。もし、この免疫細胞の能力を最大限に引き出し、癌や難病の兆候を超早期に発見し、さらには治療まで行えるとしたらどうでしょうか?そんな未来の医療を実現するため、ある壮大な研究プロジェクトが始動しました。その最前線に立つ9人の新たな研究者が選出されたというニュースをお届けします。2025年4月3日、チャン・ザッカーバーグ・バイオハブ・ニューヨークは、才能あふれる研究者のリストに、新たに9名のインベスティゲーター(研究者)が加わったことを発表しました。
コロンビア大学、ロックフェラー大学、イェール大学から参加する研究者たちによる8つのプロジェクトは、免疫細胞を利用し、バイオエンジニアリング技術を駆使して、神経変性疾患や進行性の癌を含む幅広い加齢関連疾患の早期発見、予防、治療を目指すというCZ Biohub NYのミッションに焦点を当てています。採択されたプロジェクトは、合成生物学を活用して現在の免疫細胞療法の限界に取り組んだり、モデルを用いて健康時および疾患時における細胞ネットワークや組織の適応に関する洞察を得るなど、様々な革新的戦略を支援するものです。
「私たちの協力的な研究者コミュニティに、これらの新しいインベスティゲーターを迎えることができ、大変嬉しく思います」と、CZ Biohub NYのプレジデントであり、コロンビア大学バゲロス医科大学院の化学・システム生物学分野でクライド&ヘレン・ウー記念教授を務めるアンドレア・カリファノ博士(Andrea Califano, PhD)は語ります。「彼らは、私たちの免疫細胞が持つ本来の能力を利用して、体内の異常を非常に早い段階で検知し、修復するという複雑な課題に私たちが取り組む中で参加してくれます。彼らの貢献
私たちの体の中には、病気の芽を摘み取り、健康を守るために常にパトロールしている頼もしい存在がいます。それが「免疫細胞」です。もし、この免疫細胞の能力を最大限に引き出し、癌や難病の兆候を超早期に発見し、さらには治療まで行えるとしたらどうでしょうか?そんな未来の医療を実現するため、ある壮大な研究プロジェクトが始動しました。その最前線に立つ9人の新たな研究者が選出されたというニュースをお届けします。2025年4月3日、チャン・ザッカーバーグ・バイオハブ・ニューヨークは、才能あふれる研究者のリストに、新たに9名のインベスティゲーター(研究者)が加わったことを発表しました。
コロンビア大学、ロックフェラー大学、イェール大学から参加する研究者たちによる8つのプロジェクトは、免疫細胞を利用し、バイオエンジニアリング技術を駆使して、神経変性疾患や進行性の癌を含む幅広い加齢関連疾患の早期発見、予防、治療を目指すというCZ Biohub NYのミッションに焦点を当てています。採択されたプロジェクトは、合成生物学を活用して現在の免疫細胞療法の限界に取り組んだり、モデルを用いて健康時および疾患時における細胞ネットワークや組織の適応に関する洞察を得るなど、様々な革新的戦略を支援するものです。
「私たちの協力的な研究者コミュニティに、これらの新しいインベスティゲーターを迎えることができ、大変嬉しく思います」と、CZ Biohub NYのプレジデントであり、コロンビア大学バゲロス医科大学院の化学・システム生物学分野でクライド&ヘレン・ウー記念教授を務めるアンドレア・カリファノ博士(Andrea Califano, PhD)は語ります。「彼らは、私たちの免疫細胞が持つ本来の能力を利用して、体内の異常を非常に早い段階で検知し、修復するという複雑な課題に私たちが取り組む中で参加してくれます。彼らの貢献
 まるで魔法のように、細胞が音楽に合わせてダンスする――。そんな光景が、未来の医療を大きく変えるかもしれません。これは、音の力で細胞を自在に操り、新薬の開発や一人ひとりに最適な治療法を見つけ出す「個別化医療」を劇的に加速させる可能性を秘めた、画期的な新技術です。ブリストル大学から生まれた一社のスタートアップ企業が開発した、この驚きのコンセプトをご紹介します。ブリストル大学のスピンアウト企業のエンジニアたちが、細胞に触れることなく移動させることができる新しい技術を開発しました。これにより、これまで研究室の大きな装置を必要としていた重要な作業が、実験台の上に置けるベンチトップデバイスで行えるようになります。この発明は、新薬の発見を加速させ、クリニックでの個別化医療スクリーニングを可能にするかもしれません。
この画期的なコンセプトは、2025年4月3日、スタートアップ企業ImpulsonicsのCEOであるルーク・コックス博士(Luke Cox, PhD)によって、科学誌「Science」に掲載された記事の中で初めて公開されました。この記事で彼は、ブリストル大学の学生からCEOになるまでの道のりを語っています。この記事は、「Bioinnovation Institute and Science Prize for Innovation」の受賞エッセイです。
全ての新薬の背景には、患者に試される前に、科学者たちがペトリ皿で細胞を培養し、それをテストするために費やした何千時間もの時間があります。2025年現在でも、これは依然として手作業が多く、自動化が困難なプロセスであり、高価で時に信頼性に欠けるプロセスにつながっています。その結果、命を救う新しい薬を臨床で使用できる段階まで開発することがより困難になっています。
この新技術は、音波を使って細胞を移動させ、その様子はまるで細胞
まるで魔法のように、細胞が音楽に合わせてダンスする――。そんな光景が、未来の医療を大きく変えるかもしれません。これは、音の力で細胞を自在に操り、新薬の開発や一人ひとりに最適な治療法を見つけ出す「個別化医療」を劇的に加速させる可能性を秘めた、画期的な新技術です。ブリストル大学から生まれた一社のスタートアップ企業が開発した、この驚きのコンセプトをご紹介します。ブリストル大学のスピンアウト企業のエンジニアたちが、細胞に触れることなく移動させることができる新しい技術を開発しました。これにより、これまで研究室の大きな装置を必要としていた重要な作業が、実験台の上に置けるベンチトップデバイスで行えるようになります。この発明は、新薬の発見を加速させ、クリニックでの個別化医療スクリーニングを可能にするかもしれません。
この画期的なコンセプトは、2025年4月3日、スタートアップ企業ImpulsonicsのCEOであるルーク・コックス博士(Luke Cox, PhD)によって、科学誌「Science」に掲載された記事の中で初めて公開されました。この記事で彼は、ブリストル大学の学生からCEOになるまでの道のりを語っています。この記事は、「Bioinnovation Institute and Science Prize for Innovation」の受賞エッセイです。
全ての新薬の背景には、患者に試される前に、科学者たちがペトリ皿で細胞を培養し、それをテストするために費やした何千時間もの時間があります。2025年現在でも、これは依然として手作業が多く、自動化が困難なプロセスであり、高価で時に信頼性に欠けるプロセスにつながっています。その結果、命を救う新しい薬を臨床で使用できる段階まで開発することがより困難になっています。
この新技術は、音波を使って細胞を移動させ、その様子はまるで細胞
 私たちの体の中にある「大腸」が、まるで「小腸」のように生まれ変わるかもしれない――そんな驚きの研究が発表されました。もしこれが実現すれば、手術で小腸の大部分を失い、栄養をうまく吸収できなくなる難病「短腸症候群」に苦しむ人々にとって、大きな希望の光となる可能性があります。ワイル・コーネル医科大学の研究チームが、たった一つの遺伝子を操作するという画期的なアプローチで、この難題に挑みました。単一の遺伝子の働きを止めることで、大腸の一部が、栄養を吸収する小腸のように機能するよう再プログラムされることが明らかになりました。ワイル・コーネル医科大学の研究者たちは、前臨床研究において、この技術が小腸の大部分を摘出した際に生じる栄養失調を回復させることを示しました。この実証の成功は、同様の戦略が短腸症候群の治療に利用できる可能性を示唆しています。
短腸症候群は、慢性的な炎症、癌、外傷、または先天性の疾患に対処するための手術後に小腸がほとんど残らない場合に発生しうる、生命を脅かす疾患です。小腸は消化器系における主要な栄養吸収器官であるのに対し、大腸(結腸)は主に水分を吸収するため、短腸症候群の患者は全ての栄養を静脈注射で摂取する必要がある場合もあります。
2025年4月3日に医学誌「Gastroenterology」に掲載された新しい研究で、研究者たちは短腸症候群の前臨床モデルにおいて、大腸の遺伝子SATB2を削除すると、上行結腸の細胞がそのアイデンティティを小腸様の細胞に変化させ、栄養吸収を回復させ、体重減少を逆転させることを示しました。この論文のタイトルは、「回腸の特性を持つように大腸を再構築し短腸症候群を治療する(Remodeling the Colon with Ileal Properties to Treat Short Bowel Syndrome)」です。
「私た
私たちの体の中にある「大腸」が、まるで「小腸」のように生まれ変わるかもしれない――そんな驚きの研究が発表されました。もしこれが実現すれば、手術で小腸の大部分を失い、栄養をうまく吸収できなくなる難病「短腸症候群」に苦しむ人々にとって、大きな希望の光となる可能性があります。ワイル・コーネル医科大学の研究チームが、たった一つの遺伝子を操作するという画期的なアプローチで、この難題に挑みました。単一の遺伝子の働きを止めることで、大腸の一部が、栄養を吸収する小腸のように機能するよう再プログラムされることが明らかになりました。ワイル・コーネル医科大学の研究者たちは、前臨床研究において、この技術が小腸の大部分を摘出した際に生じる栄養失調を回復させることを示しました。この実証の成功は、同様の戦略が短腸症候群の治療に利用できる可能性を示唆しています。
短腸症候群は、慢性的な炎症、癌、外傷、または先天性の疾患に対処するための手術後に小腸がほとんど残らない場合に発生しうる、生命を脅かす疾患です。小腸は消化器系における主要な栄養吸収器官であるのに対し、大腸(結腸)は主に水分を吸収するため、短腸症候群の患者は全ての栄養を静脈注射で摂取する必要がある場合もあります。
2025年4月3日に医学誌「Gastroenterology」に掲載された新しい研究で、研究者たちは短腸症候群の前臨床モデルにおいて、大腸の遺伝子SATB2を削除すると、上行結腸の細胞がそのアイデンティティを小腸様の細胞に変化させ、栄養吸収を回復させ、体重減少を逆転させることを示しました。この論文のタイトルは、「回腸の特性を持つように大腸を再構築し短腸症候群を治療する(Remodeling the Colon with Ileal Properties to Treat Short Bowel Syndrome)」です。
「私た
 失われた聴覚や視覚が、いつか取り戻せるようになるかもしれません。そんな未来を期待させる画期的な研究成果が発表されました。耳と目の細胞を再生させるための鍵を、全く同じ遺伝子が握っているかもしれないのです。南カリフォルニア大学(USC)の研究チームがマウスを用いた最新の研究で突き止めた、この驚くべき発見についてご紹介します。この研究は、USCステムセル研究所のクセニア・グネデワ博士(Ksenia Gnedeva, PhD)の研究室から、科学アカデミー紀要(PNAS)で発表されました。「感覚受容体の再生には、傷害に応答して前駆細胞が増殖することが不可欠ですが、哺乳類の内耳と網膜ではこのプロセスが阻害されています。この阻害に関わる遺伝子を理解することで、患者さんの聴覚や視覚を回復させる取り組みを前進させることができます」と、グネデワ博士は語ります。博士は、USCティナ・アンド・リック・カルーソ耳鼻咽喉科・頭頸部外科、およびケック医科大学院の幹細胞生物学・再生医療学科の助教を務めています。
本研究では、筆頭著者であるグネデワ研究室のエヴァ・ジャハンシル氏(Eva Jahanshir)とフアン・リャマス氏(Juan Llamas)が、ヒポ経路と呼ばれる相互作用する遺伝子群に着目しました。この経路は、細胞に「増殖停止」を命じる信号として機能し、胎児の発生段階で耳の細胞増殖を抑制することが、同研究室の過去の研究で示されています。今回の実験で科学者たちは、このヒポ経路が、成体マウスの耳と目で損傷した感覚受容容体の再生も抑制していることを明らかにしました。
研究チームは、ヒポ経路の重要なタンパク質であるLats1/2の働きを抑えるために、以前研究室で開発した実験的な化合物を使用しました。この薬剤様化合物をペトリ皿で作用させると、支持細胞として知られる前駆細胞が、平衡感覚を助ける内耳の感
失われた聴覚や視覚が、いつか取り戻せるようになるかもしれません。そんな未来を期待させる画期的な研究成果が発表されました。耳と目の細胞を再生させるための鍵を、全く同じ遺伝子が握っているかもしれないのです。南カリフォルニア大学(USC)の研究チームがマウスを用いた最新の研究で突き止めた、この驚くべき発見についてご紹介します。この研究は、USCステムセル研究所のクセニア・グネデワ博士(Ksenia Gnedeva, PhD)の研究室から、科学アカデミー紀要(PNAS)で発表されました。「感覚受容体の再生には、傷害に応答して前駆細胞が増殖することが不可欠ですが、哺乳類の内耳と網膜ではこのプロセスが阻害されています。この阻害に関わる遺伝子を理解することで、患者さんの聴覚や視覚を回復させる取り組みを前進させることができます」と、グネデワ博士は語ります。博士は、USCティナ・アンド・リック・カルーソ耳鼻咽喉科・頭頸部外科、およびケック医科大学院の幹細胞生物学・再生医療学科の助教を務めています。
本研究では、筆頭著者であるグネデワ研究室のエヴァ・ジャハンシル氏(Eva Jahanshir)とフアン・リャマス氏(Juan Llamas)が、ヒポ経路と呼ばれる相互作用する遺伝子群に着目しました。この経路は、細胞に「増殖停止」を命じる信号として機能し、胎児の発生段階で耳の細胞増殖を抑制することが、同研究室の過去の研究で示されています。今回の実験で科学者たちは、このヒポ経路が、成体マウスの耳と目で損傷した感覚受容容体の再生も抑制していることを明らかにしました。
研究チームは、ヒポ経路の重要なタンパク質であるLats1/2の働きを抑えるために、以前研究室で開発した実験的な化合物を使用しました。この薬剤様化合物をペトリ皿で作用させると、支持細胞として知られる前駆細胞が、平衡感覚を助ける内耳の感
 HIVと共に生きる日々から、解放される日は来るのでしょうか?過去40年間の懸命な研究にもかかわらず、一度感染したヒト免疫不全ウイルスを体内から完全に消し去る治療法はまだ見つかっていません。しかし、希望の光が見えてきました。最新の臨床試験で、特殊な抗体を使った治療法が、毎日の服薬なしに長期間ウイルスを抑え込む可能性が示されたのです。これは、HIV治療における「寛解」という新たな目標達成に向けた、大きな一歩となるかもしれません。この記事では、その画期的な研究の最前線に迫ります。
過去40年間が私たちにHIVについて何かを教えてくれたとすれば、それは期待を調整することです。ウイルスの制御において多大な進歩があったにもかかわらず、一度定着したHIVを完全に根絶できる治療法はまだありません。しかし、最近の臨床試験からの有望な結果は、広域中和抗体療法(bNAbs: broadly neutralizing antibodies)が次善の策を達成できる可能性を示唆しています。ロックフェラー大学、インペリアル・カレッジ・ロンドン、およびオックスフォード大学(RIO試験: RIO collaboration)が主導する共同研究であるこの試験のデータは、最近レトロウイルス・日和見感染症会議で発表されました。その結果は、毎日の抗レトロウイルス療法の代わりに2種類のbNAbsの治療を一度だけ受けた参加者のほとんどが、最大20週間ウイルスを検出不能なレベルに維持できたことを示唆しています。抑制を維持した参加者には、20週目以降に2回目のbNAbs投与を受ける選択肢が与えられました。
研究者たちが参加者の追跡を続ける中で、この後者のグループはさらに有望な結果を示しました。48週目には参加者の半数が依然として検出不能であり、最後の治療から約1年後の72週目になっても3分の1がその状態を維持し
HIVと共に生きる日々から、解放される日は来るのでしょうか?過去40年間の懸命な研究にもかかわらず、一度感染したヒト免疫不全ウイルスを体内から完全に消し去る治療法はまだ見つかっていません。しかし、希望の光が見えてきました。最新の臨床試験で、特殊な抗体を使った治療法が、毎日の服薬なしに長期間ウイルスを抑え込む可能性が示されたのです。これは、HIV治療における「寛解」という新たな目標達成に向けた、大きな一歩となるかもしれません。この記事では、その画期的な研究の最前線に迫ります。
過去40年間が私たちにHIVについて何かを教えてくれたとすれば、それは期待を調整することです。ウイルスの制御において多大な進歩があったにもかかわらず、一度定着したHIVを完全に根絶できる治療法はまだありません。しかし、最近の臨床試験からの有望な結果は、広域中和抗体療法(bNAbs: broadly neutralizing antibodies)が次善の策を達成できる可能性を示唆しています。ロックフェラー大学、インペリアル・カレッジ・ロンドン、およびオックスフォード大学(RIO試験: RIO collaboration)が主導する共同研究であるこの試験のデータは、最近レトロウイルス・日和見感染症会議で発表されました。その結果は、毎日の抗レトロウイルス療法の代わりに2種類のbNAbsの治療を一度だけ受けた参加者のほとんどが、最大20週間ウイルスを検出不能なレベルに維持できたことを示唆しています。抑制を維持した参加者には、20週目以降に2回目のbNAbs投与を受ける選択肢が与えられました。
研究者たちが参加者の追跡を続ける中で、この後者のグループはさらに有望な結果を示しました。48週目には参加者の半数が依然として検出不能であり、最後の治療から約1年後の72週目になっても3分の1がその状態を維持し
 夜空を覆い尽くす数千、数万のコウモリの群れ。洞窟から一斉に飛び立つその様は壮観ですが、なぜあれほどの密集状態で互いに衝突しないのでしょうか?この長年の謎は、科学者たちにとって「カクテルパーティーナイトメア」――騒がしい中で特定の声を聞き取れない状況――にも似た難問でした。しかし、最新の研究が、コウモリたちが音の洪水の中で巧みに進路を見つけ出し、衝突を回避する驚くべき戦略を明らかにしました。彼らが夜空を安全に飛び回るための、洗練された「空の交通ルール」に迫ります。
アヤ・ゴールドシュタイン氏(Aya Goldshtein)、オメル・マザール氏(Omer Mazar)、そしてヨッシー・ヨーベル氏(Yossi Yovel)は、コウモリの洞窟の外で幾夜も過ごしてきました。それでも、数千匹のコウモリが洞窟から噴き出し、夜の闇へと羽ばたいていく光景、時には液体のように見えるほどの高密度で飛び交う様に、科学者たちは毎回驚嘆させられます。しかし最近まで、コウモリ生物学者たちは、彼らが見ていなかったことによってさらに困惑していました。「コウモリは互いに衝突しません」と、マックス・プランク動物行動研究所のゴールドシュタイン氏は言います。「時には数十万匹のコウモリがすべて小さな開口部から飛び出すコロニーでさえもです。」
「悪夢の」カクテルパーティー
コウモリが採餌のために洞窟から押し出すように飛び出す際、毎晩どのようにして致命的な衝突を避けているのかは、科学的な謎でした。多くのコウモリは主に反響定位(エコーロケーション)によって世界を認識しています。彼らはコールを発し、反射したエコーを聞くことで、周囲の状況を「見る」ことができるのです。しかし、多くのコウモリが同時に反響定位を行うと、例えばコロニー全体が数分のうちに洞窟から出現するような場合、他のコウモリのコールが、彼らが必要とす
夜空を覆い尽くす数千、数万のコウモリの群れ。洞窟から一斉に飛び立つその様は壮観ですが、なぜあれほどの密集状態で互いに衝突しないのでしょうか?この長年の謎は、科学者たちにとって「カクテルパーティーナイトメア」――騒がしい中で特定の声を聞き取れない状況――にも似た難問でした。しかし、最新の研究が、コウモリたちが音の洪水の中で巧みに進路を見つけ出し、衝突を回避する驚くべき戦略を明らかにしました。彼らが夜空を安全に飛び回るための、洗練された「空の交通ルール」に迫ります。
アヤ・ゴールドシュタイン氏(Aya Goldshtein)、オメル・マザール氏(Omer Mazar)、そしてヨッシー・ヨーベル氏(Yossi Yovel)は、コウモリの洞窟の外で幾夜も過ごしてきました。それでも、数千匹のコウモリが洞窟から噴き出し、夜の闇へと羽ばたいていく光景、時には液体のように見えるほどの高密度で飛び交う様に、科学者たちは毎回驚嘆させられます。しかし最近まで、コウモリ生物学者たちは、彼らが見ていなかったことによってさらに困惑していました。「コウモリは互いに衝突しません」と、マックス・プランク動物行動研究所のゴールドシュタイン氏は言います。「時には数十万匹のコウモリがすべて小さな開口部から飛び出すコロニーでさえもです。」
「悪夢の」カクテルパーティー
コウモリが採餌のために洞窟から押し出すように飛び出す際、毎晩どのようにして致命的な衝突を避けているのかは、科学的な謎でした。多くのコウモリは主に反響定位(エコーロケーション)によって世界を認識しています。彼らはコールを発し、反射したエコーを聞くことで、周囲の状況を「見る」ことができるのです。しかし、多くのコウモリが同時に反響定位を行うと、例えばコロニー全体が数分のうちに洞窟から出現するような場合、他のコウモリのコールが、彼らが必要とす
 ふるえや動きにくさに悩まされるパーキンソン病。その根本的な原因はいまだ謎に包まれていますが、私たちの細胞がエネルギーを生み出す基本的な仕組み「解糖系」に、病解明の新たな鍵が隠されているかもしれません。中国の研究チームが、血液中の遺伝子情報を解析することで、パーキンソン病と解糖系の深い関わりを突き止めました。この記事では、病気の早期発見や新しい治療法開発につながる可能性を秘めた、この画期的な研究の最前線に迫ります。
パーキンソン病は、世界中で運動機能および認知機能に著しい影響を与える慢性的かつ進行性の神経変性疾患です。主な症状には、ふるえ、筋肉のこわばり、運動緩慢(ブラジキネジア)、バランス障害などがあります。集中的な研究にもかかわらず、正確な原因や進行メカニズムは依然として不明であり、効果的な診断と治療を妨げています。近年の研究では、グルコースを利用可能なエネルギーに変換するために不可欠な基本的な代謝経路である解糖系に注目が集まっています。2025年2月15日に『Heliyon』誌に掲載された画期的な研究論文「Glycolytic Pathways: The Hidden Regulators in Parkinson’s Disease(解糖系経路:パーキンソン病における隠れた制御因子)」において、中国の石河子大学の科学者たちは、パーキンソン病における解糖系の潜在的な役割について説得力のある証拠を提示しました。
解糖系関連バイオマーカーの特定
研究者たちは、高度なバイオインフォマティクス技術を用いて、パーキンソン病患者と健常対照者の血液サンプルにおける遺伝子発現を解析しました。Gene Expression Omnibus(GEO)データベースのデータセットを調べることにより、チームは解糖系関連遺伝子の発現における重大な混乱を突き止めました。彼らの解析
ふるえや動きにくさに悩まされるパーキンソン病。その根本的な原因はいまだ謎に包まれていますが、私たちの細胞がエネルギーを生み出す基本的な仕組み「解糖系」に、病解明の新たな鍵が隠されているかもしれません。中国の研究チームが、血液中の遺伝子情報を解析することで、パーキンソン病と解糖系の深い関わりを突き止めました。この記事では、病気の早期発見や新しい治療法開発につながる可能性を秘めた、この画期的な研究の最前線に迫ります。
パーキンソン病は、世界中で運動機能および認知機能に著しい影響を与える慢性的かつ進行性の神経変性疾患です。主な症状には、ふるえ、筋肉のこわばり、運動緩慢(ブラジキネジア)、バランス障害などがあります。集中的な研究にもかかわらず、正確な原因や進行メカニズムは依然として不明であり、効果的な診断と治療を妨げています。近年の研究では、グルコースを利用可能なエネルギーに変換するために不可欠な基本的な代謝経路である解糖系に注目が集まっています。2025年2月15日に『Heliyon』誌に掲載された画期的な研究論文「Glycolytic Pathways: The Hidden Regulators in Parkinson’s Disease(解糖系経路:パーキンソン病における隠れた制御因子)」において、中国の石河子大学の科学者たちは、パーキンソン病における解糖系の潜在的な役割について説得力のある証拠を提示しました。
解糖系関連バイオマーカーの特定
研究者たちは、高度なバイオインフォマティクス技術を用いて、パーキンソン病患者と健常対照者の血液サンプルにおける遺伝子発現を解析しました。Gene Expression Omnibus(GEO)データベースのデータセットを調べることにより、チームは解糖系関連遺伝子の発現における重大な混乱を突き止めました。彼らの解析
 ゲノム科学の未来を照らす新たなリーダーシップが、ニューヨークで始動します。2025年3月27日、ニューヨークゲノムセンター(NYGC: New York Genome Center)は、ゲノミクスとエピジェネティクスの分野で世界的に名高いビン・レン博士(Bing Ren, PhD)を、新しい科学ディレクター兼最高経営責任者(CEO)として迎えると発表しました。この重要な人事は、大規模な慈善的支援と相まって、ゲノム研究の進展と、その成果を医療現場へとつなげる動きを一層加速させることが期待されます。レン博士がNYGC、そしてコロンビア大学と共にどのような革新を推進していくのか、その詳細とビジョンに迫ります。
レン博士はまた、コロンビア大学の遺伝学・発生学部門、生化学・分子生物物理学部門、システム生物学部門の教授、そしてバゲロス医学校内のロイ&ダイアナ・バゲロス基礎生物医学科学研究所の副所長にも就任します。レン博士は、遺伝子発現を制御する調節プロセスに焦点を当てたゲノミクスおよびエピジェネティクスの先駆的な研究で名高く、その業績は、遺伝情報が研究者によってどのように解釈されるか、そして遺伝子活性が発生や疾患の病態を通じてどのように調節されるかについての私たちの理解を深めてきました。彼の貢献は、精密医療からがん、神経疾患研究に至るまで、多岐にわたる分野に影響を与えています。
「私たちは、ビンをニューヨークゲノムセンターと、より広範なニューヨークの科学コミュニティに迎えることを嬉しく思います」と、NYGCの名誉科学ディレクターであり共同設立者であるトム・マニアティス博士(Tom Maniatis, PhD)は述べています。「ビンのゲノム科学への画期的な貢献は、ヒトの発生に関わる調節メカニズムと、それらがヒトの疾患でどのように変化するかについての私たちの理解に大きな進歩をもたら
ゲノム科学の未来を照らす新たなリーダーシップが、ニューヨークで始動します。2025年3月27日、ニューヨークゲノムセンター(NYGC: New York Genome Center)は、ゲノミクスとエピジェネティクスの分野で世界的に名高いビン・レン博士(Bing Ren, PhD)を、新しい科学ディレクター兼最高経営責任者(CEO)として迎えると発表しました。この重要な人事は、大規模な慈善的支援と相まって、ゲノム研究の進展と、その成果を医療現場へとつなげる動きを一層加速させることが期待されます。レン博士がNYGC、そしてコロンビア大学と共にどのような革新を推進していくのか、その詳細とビジョンに迫ります。
レン博士はまた、コロンビア大学の遺伝学・発生学部門、生化学・分子生物物理学部門、システム生物学部門の教授、そしてバゲロス医学校内のロイ&ダイアナ・バゲロス基礎生物医学科学研究所の副所長にも就任します。レン博士は、遺伝子発現を制御する調節プロセスに焦点を当てたゲノミクスおよびエピジェネティクスの先駆的な研究で名高く、その業績は、遺伝情報が研究者によってどのように解釈されるか、そして遺伝子活性が発生や疾患の病態を通じてどのように調節されるかについての私たちの理解を深めてきました。彼の貢献は、精密医療からがん、神経疾患研究に至るまで、多岐にわたる分野に影響を与えています。
「私たちは、ビンをニューヨークゲノムセンターと、より広範なニューヨークの科学コミュニティに迎えることを嬉しく思います」と、NYGCの名誉科学ディレクターであり共同設立者であるトム・マニアティス博士(Tom Maniatis, PhD)は述べています。「ビンのゲノム科学への画期的な貢献は、ヒトの発生に関わる調節メカニズムと、それらがヒトの疾患でどのように変化するかについての私たちの理解に大きな進歩をもたら
 必死なメスの鳥たちにとっては切実な叫びです。なぜ一部の鳥だけが、縄張りを荒らす侵入者に猛烈に攻撃的になるのでしょうか?その謎を解く鍵は、意外な「住宅事情」にありました。デューク大学生物学助教のサラ・リプシャッツ博士(Sara Lipshutz, PhD)が率いる国際研究チームは、木の洞などの穴の中にしか巣を作れないメスの鳥が、巣作りの場所にそのような制約がない鳥よりもはるかに攻撃的であることを発見しました。「二次的な穴利用営巣性鳥類」と呼ばれるこれらの種は、木の幹や柵の柱、岩の露頭などに既存の穴を見つけて巣を作ります。「彼女たちは自分で穴を掘ることはできず、どこにでも巣を作れるわけではありません」とリプシャッツ博士は説明します。「木の穴を見つけなければならず、それが彼女たちが繁殖できる唯一の方法なのです。」
これらの特殊なニーズ、そして自分たちでは穴を作らないという事実は、良い巣を見つけたメスにとって、それが守るべき貴重な資源であることを意味します。そして彼女たちは、くちばしと爪、そしてかなりの量の怒りの鳴き声で、実際にそれを守るのです。
リプシャッツ博士の連邦政府資金によるチームは、ツバメ、アメリカムシクイ、スズメ、ツグミ、ミソサザイの5つの科の鳥に注目し、各科から近縁な2種(一方は二次的な穴利用営巣性の鳥、もう一方はそうでない鳥)を対象としました。研究者たちは、それぞれの種に対応する剥製と、その鳴き声を再生するBluetoothスピーカーを巣の近くに戦略的に配置し、住人である鳥がどのように反応するかを観察しました。
他の多くの形質と同様に、攻撃性も家系に由来し、鳥の進化の系統樹のある枝では他の枝よりも顕著に見られると予想されるかもしれません。しかし、リプシャッツ博士と彼女のチームが発見したのは、攻撃性が家系よりも巣作りの戦略にはるかに強く関連しているということ
必死なメスの鳥たちにとっては切実な叫びです。なぜ一部の鳥だけが、縄張りを荒らす侵入者に猛烈に攻撃的になるのでしょうか?その謎を解く鍵は、意外な「住宅事情」にありました。デューク大学生物学助教のサラ・リプシャッツ博士(Sara Lipshutz, PhD)が率いる国際研究チームは、木の洞などの穴の中にしか巣を作れないメスの鳥が、巣作りの場所にそのような制約がない鳥よりもはるかに攻撃的であることを発見しました。「二次的な穴利用営巣性鳥類」と呼ばれるこれらの種は、木の幹や柵の柱、岩の露頭などに既存の穴を見つけて巣を作ります。「彼女たちは自分で穴を掘ることはできず、どこにでも巣を作れるわけではありません」とリプシャッツ博士は説明します。「木の穴を見つけなければならず、それが彼女たちが繁殖できる唯一の方法なのです。」
これらの特殊なニーズ、そして自分たちでは穴を作らないという事実は、良い巣を見つけたメスにとって、それが守るべき貴重な資源であることを意味します。そして彼女たちは、くちばしと爪、そしてかなりの量の怒りの鳴き声で、実際にそれを守るのです。
リプシャッツ博士の連邦政府資金によるチームは、ツバメ、アメリカムシクイ、スズメ、ツグミ、ミソサザイの5つの科の鳥に注目し、各科から近縁な2種(一方は二次的な穴利用営巣性の鳥、もう一方はそうでない鳥)を対象としました。研究者たちは、それぞれの種に対応する剥製と、その鳴き声を再生するBluetoothスピーカーを巣の近くに戦略的に配置し、住人である鳥がどのように反応するかを観察しました。
他の多くの形質と同様に、攻撃性も家系に由来し、鳥の進化の系統樹のある枝では他の枝よりも顕著に見られると予想されるかもしれません。しかし、リプシャッツ博士と彼女のチームが発見したのは、攻撃性が家系よりも巣作りの戦略にはるかに強く関連しているということ
 糖尿病による足の切断、そんな未来はもう見たくない。そんな切実な願いに応えるべく、シンガポールで画期的な治療法が開発されたかもしれません。なかなか治らない糖尿病性の傷は、世界中で多くの人々を苦しめており、深刻な場合には手足の切断に至ることもあります。この大きな課題に対し、シンガポール国立大学の研究者たちが、傷の治りを早める画期的な二つの「マイクロニードル技術」を開発しました。私たちの体にもともと備わっている治癒力を高め、同時に厄介な炎症を取り除くという、この新しいアプローチは、一体どのようなものなのでしょうか?この記事では、その驚くべき技術の詳細と、未来の医療にもたらす可能性に迫ります。
糖尿病性の創傷は、しばしば切断につながる深刻な合併症を引き起こします。これらの慢性で治癒しない創傷は、持続的な炎症を特徴とし、世界人口の6%以上が罹患しています。シンガポールでは、治癒しない糖尿病性の創傷が原因で、毎日約4件の下肢切断手術が行われています。シンガポールにおける糖尿病性創傷に焦点を当てたある研究では、2017年における患者一人当たりの切断関連の医療費総額は23,000ドルと推定されました。この国内外で極めて重要な課題に取り組むため、シンガポール国立大学(NUS)の研究者たちは、成長因子と呼ばれるタンパク質の機能を維持し、望ましくない炎症性化合物を除去することによって、前臨床モデルで糖尿病性創傷治癒を加速する有効性を示した2つのマイクロニードル技術を開発しました。
これら2つの新規技術は、シンガポール国立大学デザイン工学部生体医工学科および健康革新技術研究所のアンディ・テイ助教授(Assistant Professor Andy Tay)が率いる科学者チームによって開発されました。「成長因子は、主要な細胞機能を調節するため、創傷治癒に重要です。しかし、糖尿病性の創傷では
糖尿病による足の切断、そんな未来はもう見たくない。そんな切実な願いに応えるべく、シンガポールで画期的な治療法が開発されたかもしれません。なかなか治らない糖尿病性の傷は、世界中で多くの人々を苦しめており、深刻な場合には手足の切断に至ることもあります。この大きな課題に対し、シンガポール国立大学の研究者たちが、傷の治りを早める画期的な二つの「マイクロニードル技術」を開発しました。私たちの体にもともと備わっている治癒力を高め、同時に厄介な炎症を取り除くという、この新しいアプローチは、一体どのようなものなのでしょうか?この記事では、その驚くべき技術の詳細と、未来の医療にもたらす可能性に迫ります。
糖尿病性の創傷は、しばしば切断につながる深刻な合併症を引き起こします。これらの慢性で治癒しない創傷は、持続的な炎症を特徴とし、世界人口の6%以上が罹患しています。シンガポールでは、治癒しない糖尿病性の創傷が原因で、毎日約4件の下肢切断手術が行われています。シンガポールにおける糖尿病性創傷に焦点を当てたある研究では、2017年における患者一人当たりの切断関連の医療費総額は23,000ドルと推定されました。この国内外で極めて重要な課題に取り組むため、シンガポール国立大学(NUS)の研究者たちは、成長因子と呼ばれるタンパク質の機能を維持し、望ましくない炎症性化合物を除去することによって、前臨床モデルで糖尿病性創傷治癒を加速する有効性を示した2つのマイクロニードル技術を開発しました。
これら2つの新規技術は、シンガポール国立大学デザイン工学部生体医工学科および健康革新技術研究所のアンディ・テイ助教授(Assistant Professor Andy Tay)が率いる科学者チームによって開発されました。「成長因子は、主要な細胞機能を調節するため、創傷治癒に重要です。しかし、糖尿病性の創傷では
 カリッと香ばしく、栄養もたっぷり。私たちの食卓を彩るピスタチオですが、その未来がちょっぴり心配なことをご存知でしたか?気候変動の影響を受けやすいピスタチオ栽培を持続可能にし、さらにはもっと美味しく、もっと栄養豊かにするための鍵が、ついに見つかったかもしれません。カリフォルニア大学デービス校の研究チームが、ピスタチオの遺伝情報を詳細に解読し、その秘密に迫りました。カリフォルニア州は全米のピスタチオの99%を生産し、州内で約30億ドルの経済価値を生み出しています。しかし、ピスタチオはそのDNAの高品質なマップが不足していたこともあり、これまで十分な研究がされてきませんでした。カリフォルニア大学デービス校の研究者らはこの度、ピスタチオの最も包括的なゲノム配列を作成し、これにより植物育種家はより優れた、おそらくはより栄養価の高い品種を作り出すことが可能になります。
彼らはまた、ピスタチオのナッツがどのように発達するかの詳細も明らかにし、これは農家が作物をより持続可能な形で管理するのに役立ちます。New Phytologist誌が2025年3月20日にこの研究を発表しました。このオープンアクセスの論文タイトルは「In a Nutshell: Pistachio Genome and Kernel Development(ナッツシェルの中:ピスタチオのゲノムと仁の発達)」です。
科学者たちは以前にもピスタチオのDNA配列を解読していましたが、共同責任著者である植物科学科の助教、J. グレイ・モンロー博士(J. Grey Monroe, PhD)は、この新しい遺伝子地図ははるかに詳細で正確であると述べています。「新しい参照ゲノムの精度の向上は、風景の手描きの地図からGoogle Earthの衛星画像に移行するようなものです」と彼は語りました。モンロー博士と研究チームは、カリフォル
カリッと香ばしく、栄養もたっぷり。私たちの食卓を彩るピスタチオですが、その未来がちょっぴり心配なことをご存知でしたか?気候変動の影響を受けやすいピスタチオ栽培を持続可能にし、さらにはもっと美味しく、もっと栄養豊かにするための鍵が、ついに見つかったかもしれません。カリフォルニア大学デービス校の研究チームが、ピスタチオの遺伝情報を詳細に解読し、その秘密に迫りました。カリフォルニア州は全米のピスタチオの99%を生産し、州内で約30億ドルの経済価値を生み出しています。しかし、ピスタチオはそのDNAの高品質なマップが不足していたこともあり、これまで十分な研究がされてきませんでした。カリフォルニア大学デービス校の研究者らはこの度、ピスタチオの最も包括的なゲノム配列を作成し、これにより植物育種家はより優れた、おそらくはより栄養価の高い品種を作り出すことが可能になります。
彼らはまた、ピスタチオのナッツがどのように発達するかの詳細も明らかにし、これは農家が作物をより持続可能な形で管理するのに役立ちます。New Phytologist誌が2025年3月20日にこの研究を発表しました。このオープンアクセスの論文タイトルは「In a Nutshell: Pistachio Genome and Kernel Development(ナッツシェルの中:ピスタチオのゲノムと仁の発達)」です。
科学者たちは以前にもピスタチオのDNA配列を解読していましたが、共同責任著者である植物科学科の助教、J. グレイ・モンロー博士(J. Grey Monroe, PhD)は、この新しい遺伝子地図ははるかに詳細で正確であると述べています。「新しい参照ゲノムの精度の向上は、風景の手描きの地図からGoogle Earthの衛星画像に移行するようなものです」と彼は語りました。モンロー博士と研究チームは、カリフォル
 私たちの体の設計図であるDNA。その形は「二重らせん」だと、誰もが学んできたはずです。しかし、もしDNAがらせん以外の形をとることがあり、それが病気の原因や進化の鍵を握っているとしたら…? 最新のゲノム解読技術が、これまで謎に包まれてきたDNAの「もう一つの顔」を明らかにし始めています。研究者たちは、最近公開されたヒト、チンパンジー、ボノボ、ゴリラ、そして2種のオランウータンのテロメア・ツー・テロメアゲノムを用いて、二重らせん以外の構造を形成しうるDNA配列の位置を予測しました。
特定のDNA配列は、標準的な二重らせん以外の構造を形成することがあります。これらの代替的なDNA立体構造は非B型DNAと呼ばれ、細胞プロセスやゲノム進化の調節因子として関与が指摘されてきましたが、そのDNAは反復性が高い傾向があり、最近まで配列を確実に読み取って組み立てることを困難にしていました。今回、ペンシルベニア州立大学の生物学者たちが率いる研究チームが、大型類人猿における非B型DNA構造の位置を包括的に予測しました。これは、遺伝性疾患やがんへの関与が知られているこれらの構造の機能と進化を理解するための第一歩であるとチームは述べています。この研究は、反復DNAに関連する塩基配列決定とアセンブリの困難を克服し、ゲノムに残っていたギャップを埋めた、新しく利用可能になったヒトや他の大型類人猿のテロメア・ツー・テロメア(T2T)、すなわち末端から末端までの完全なゲノムに依存しています。この研究を記述した論文は、非B型DNAが新たに解読されたゲノム領域に豊富に存在することを示し、新たな機能の可能性を示唆するもので、2025年4月24日付の学術誌Nucleic Acids Researchに掲載されました。このオープンアクセスの論文タイトルは、「Non-Canonical DNA in Human
私たちの体の設計図であるDNA。その形は「二重らせん」だと、誰もが学んできたはずです。しかし、もしDNAがらせん以外の形をとることがあり、それが病気の原因や進化の鍵を握っているとしたら…? 最新のゲノム解読技術が、これまで謎に包まれてきたDNAの「もう一つの顔」を明らかにし始めています。研究者たちは、最近公開されたヒト、チンパンジー、ボノボ、ゴリラ、そして2種のオランウータンのテロメア・ツー・テロメアゲノムを用いて、二重らせん以外の構造を形成しうるDNA配列の位置を予測しました。
特定のDNA配列は、標準的な二重らせん以外の構造を形成することがあります。これらの代替的なDNA立体構造は非B型DNAと呼ばれ、細胞プロセスやゲノム進化の調節因子として関与が指摘されてきましたが、そのDNAは反復性が高い傾向があり、最近まで配列を確実に読み取って組み立てることを困難にしていました。今回、ペンシルベニア州立大学の生物学者たちが率いる研究チームが、大型類人猿における非B型DNA構造の位置を包括的に予測しました。これは、遺伝性疾患やがんへの関与が知られているこれらの構造の機能と進化を理解するための第一歩であるとチームは述べています。この研究は、反復DNAに関連する塩基配列決定とアセンブリの困難を克服し、ゲノムに残っていたギャップを埋めた、新しく利用可能になったヒトや他の大型類人猿のテロメア・ツー・テロメア(T2T)、すなわち末端から末端までの完全なゲノムに依存しています。この研究を記述した論文は、非B型DNAが新たに解読されたゲノム領域に豊富に存在することを示し、新たな機能の可能性を示唆するもので、2025年4月24日付の学術誌Nucleic Acids Researchに掲載されました。このオープンアクセスの論文タイトルは、「Non-Canonical DNA in Human
 院内感染などで問題となる手強い細菌、クロストリディオイデス・ディフィシル(C. diff)。この菌が、なんと他の腸内細菌にとっては「毒」となる物質を、自身の「栄養」に変えて生き延びる驚きの戦略を持っていたことが明らかになりました!私たちの食卓にものぼるブロッコリーなどの野菜に含まれる可能性のあるこの物質と、C. diffのしたたかな関係とは?感染メカニズムの新たな理解と、未来の治療法につながるかもしれない最新の研究成果を、わかりやすくご紹介します。医療関連感染性下痢の最も一般的な原因菌であるクロストリディオイデス・ディフィシル(C. diff: Clostridioides difficile)は、ヒトの腸内常在菌を殺す化合物を生存と増殖に利用し、感染した腸内で競争上の優位性を獲得できることが明らかになりました。ヴァンダービルト大学医療センター(VUMC: Vanderbilt University Medical Center)の研究者チームは、C. diffが、ブロッコリーなどの食品に含まれる可能性のある有毒な化合物「4-チオウラシル」を利用可能な栄養素に変換する仕組みを発見しました。
2025年3月25日に学術誌「Cell Host & Microbe」に掲載された彼らの発見は、C. diff感染の分子的要因の理解を深め、新たな治療戦略を示唆するものです。この論文のタイトルは「A Thiouracil Desulfurase Protects Clostridioides difficile RNA from 4-Thiouracil Incorporation, Providing a Competitive Advantage in the Gut(チオウラシル脱硫酵素はクロストリディオイデス・ディフィシルのRNAを4-チオウラシル取り込みから保護し
院内感染などで問題となる手強い細菌、クロストリディオイデス・ディフィシル(C. diff)。この菌が、なんと他の腸内細菌にとっては「毒」となる物質を、自身の「栄養」に変えて生き延びる驚きの戦略を持っていたことが明らかになりました!私たちの食卓にものぼるブロッコリーなどの野菜に含まれる可能性のあるこの物質と、C. diffのしたたかな関係とは?感染メカニズムの新たな理解と、未来の治療法につながるかもしれない最新の研究成果を、わかりやすくご紹介します。医療関連感染性下痢の最も一般的な原因菌であるクロストリディオイデス・ディフィシル(C. diff: Clostridioides difficile)は、ヒトの腸内常在菌を殺す化合物を生存と増殖に利用し、感染した腸内で競争上の優位性を獲得できることが明らかになりました。ヴァンダービルト大学医療センター(VUMC: Vanderbilt University Medical Center)の研究者チームは、C. diffが、ブロッコリーなどの食品に含まれる可能性のある有毒な化合物「4-チオウラシル」を利用可能な栄養素に変換する仕組みを発見しました。
2025年3月25日に学術誌「Cell Host & Microbe」に掲載された彼らの発見は、C. diff感染の分子的要因の理解を深め、新たな治療戦略を示唆するものです。この論文のタイトルは「A Thiouracil Desulfurase Protects Clostridioides difficile RNA from 4-Thiouracil Incorporation, Providing a Competitive Advantage in the Gut(チオウラシル脱硫酵素はクロストリディオイデス・ディフィシルのRNAを4-チオウラシル取り込みから保護し
 美食の代名詞、フォアグラ。そのとろけるような舌触りと濃厚な風味は多くの人々を魅了しますが、伝統的な生産方法が動物福祉の観点から議論を呼んでいることも事実です。もし、あの贅沢な味わいを、動物たちにもっと優しい方法で実現できるとしたら?この記事では、科学者たちが強制給餌に頼らず、本物と見紛うフォアグラを創り出す画期的なレシピを開発し、特許を取得したニュースをお届けします。美食と倫理の両立を目指す、注目の研究に迫ります。
フォアグラは、アヒルやガチョウの肝臓から作られるユニークな珍味です。その風味は好みが分かれることもありますが、バターのように濃厚で脂質の多いこの料理は、世界の多くの地域で珍重される贅沢な一品です。フォアグラが通常の家禽の肝臓と異なるのは、その高い脂肪含有量のおかげであり、これは伝統的にアヒルやガチョウに通常の餌以上の量を与える強制給餌によって達成されてきました。
研究者であるトーマス・ヴィルギス氏(Thomas Vilgis)はフォアグラを愛好していますが、この料理をもっと倫理的に楽しむ方法はないかと考えました。AIP出版発行の学術誌「フィジックス・オブ・フルイズ」で、ヴィルギス氏はマックス・プランク高分子研究所および南デンマーク大学の共同研究者たちと共に、強制給餌なしでこの美味な料理を再現するプロセスを開発しました。このオープンアクセスの論文は2025年3月25日に公開され、タイトルは「Foie Gras Pâté Without Force-Feeding(強制給餌なしのフォアグラパテ)」です。
「フォアグラをより手軽にし、動物福祉にも配慮したものにすることは長年の夢でした」とヴィルギス氏は語ります。「この強制給餌という慣行を終わらせる、あるいは少なくとも減らすことは良いことです。」
ヴィルギス氏と彼のチームにとって、フォアグラに外部の材料や添加
美食の代名詞、フォアグラ。そのとろけるような舌触りと濃厚な風味は多くの人々を魅了しますが、伝統的な生産方法が動物福祉の観点から議論を呼んでいることも事実です。もし、あの贅沢な味わいを、動物たちにもっと優しい方法で実現できるとしたら?この記事では、科学者たちが強制給餌に頼らず、本物と見紛うフォアグラを創り出す画期的なレシピを開発し、特許を取得したニュースをお届けします。美食と倫理の両立を目指す、注目の研究に迫ります。
フォアグラは、アヒルやガチョウの肝臓から作られるユニークな珍味です。その風味は好みが分かれることもありますが、バターのように濃厚で脂質の多いこの料理は、世界の多くの地域で珍重される贅沢な一品です。フォアグラが通常の家禽の肝臓と異なるのは、その高い脂肪含有量のおかげであり、これは伝統的にアヒルやガチョウに通常の餌以上の量を与える強制給餌によって達成されてきました。
研究者であるトーマス・ヴィルギス氏(Thomas Vilgis)はフォアグラを愛好していますが、この料理をもっと倫理的に楽しむ方法はないかと考えました。AIP出版発行の学術誌「フィジックス・オブ・フルイズ」で、ヴィルギス氏はマックス・プランク高分子研究所および南デンマーク大学の共同研究者たちと共に、強制給餌なしでこの美味な料理を再現するプロセスを開発しました。このオープンアクセスの論文は2025年3月25日に公開され、タイトルは「Foie Gras Pâté Without Force-Feeding(強制給餌なしのフォアグラパテ)」です。
「フォアグラをより手軽にし、動物福祉にも配慮したものにすることは長年の夢でした」とヴィルギス氏は語ります。「この強制給餌という慣行を終わらせる、あるいは少なくとも減らすことは良いことです。」
ヴィルギス氏と彼のチームにとって、フォアグラに外部の材料や添加
 いつもの食事が、実はこころの元気と深く関わっているかもしれません。最近の研究で、しょっぱいものが大好きなあなたの食生活が、知らず知らずのうちに「うつ」の引き金となる特定のタンパク質を増やしている可能性が浮かび上がってきました。この記事では、塩分の摂りすぎと心の病の意外な関係、そしてそこから見える新しい予防法や治療法への希望の光を、やさしく解き明かしていきます。免疫学の専門誌「Journal of Immunology」に発表された新しい研究で、高塩分食が、インターロイキン17Aと呼ばれるタンパク質の産生を促進することによって、マウスにうつ病様症状を引き起こすことが明らかになりました。このタンパク質は、以前からヒトの臨床研究においてもうつ病の一因として特定されていました。
「この研究は、減塩などの食事介入が精神疾患の予防策となることを支持するものです。また、IL-17Aを標的とした新しいうつ病治療戦略への道を開くものでもあります」と、この研究を主導した南京医科大学の研究者、シャオジュン・チェン博士(Xiaojun Chen, PhD)は述べています。「これらの知見が、塩分摂取ガイドラインに関する議論を促進することを期待しています」とチェン博士は語りました。
研究チームはまた、高塩分食を与えられたマウスにおいて、ガンマデルタT細胞と呼ばれる免疫細胞の一種がIL-17Aの重要な供給源であり、IL-17A産生細胞の約40%を占めることを特定しました。γδT細胞を除去すると、高塩分食誘発性のうつ様症状が大幅に軽減され、別の治療法の可能性も示されました。
高塩分摂取は西洋型の食事ではごく一般的で、ファストフードには家庭料理の100倍もの塩分が含まれていることも珍しくありません。高塩分食は、心血管疾患、自己免疫疾患、神経発達特性の多様性に関連する疾患と関連しており、すでに
いつもの食事が、実はこころの元気と深く関わっているかもしれません。最近の研究で、しょっぱいものが大好きなあなたの食生活が、知らず知らずのうちに「うつ」の引き金となる特定のタンパク質を増やしている可能性が浮かび上がってきました。この記事では、塩分の摂りすぎと心の病の意外な関係、そしてそこから見える新しい予防法や治療法への希望の光を、やさしく解き明かしていきます。免疫学の専門誌「Journal of Immunology」に発表された新しい研究で、高塩分食が、インターロイキン17Aと呼ばれるタンパク質の産生を促進することによって、マウスにうつ病様症状を引き起こすことが明らかになりました。このタンパク質は、以前からヒトの臨床研究においてもうつ病の一因として特定されていました。
「この研究は、減塩などの食事介入が精神疾患の予防策となることを支持するものです。また、IL-17Aを標的とした新しいうつ病治療戦略への道を開くものでもあります」と、この研究を主導した南京医科大学の研究者、シャオジュン・チェン博士(Xiaojun Chen, PhD)は述べています。「これらの知見が、塩分摂取ガイドラインに関する議論を促進することを期待しています」とチェン博士は語りました。
研究チームはまた、高塩分食を与えられたマウスにおいて、ガンマデルタT細胞と呼ばれる免疫細胞の一種がIL-17Aの重要な供給源であり、IL-17A産生細胞の約40%を占めることを特定しました。γδT細胞を除去すると、高塩分食誘発性のうつ様症状が大幅に軽減され、別の治療法の可能性も示されました。
高塩分摂取は西洋型の食事ではごく一般的で、ファストフードには家庭料理の100倍もの塩分が含まれていることも珍しくありません。高塩分食は、心血管疾患、自己免疫疾患、神経発達特性の多様性に関連する疾患と関連しており、すでに
 これまで手の施しようがなかった「治療抵抗性てんかん」。その影に隠れていた微細な脳の変化を、ついに捉える光明が差し込んできました!超強力なMRIスキャナーの限界を打ち破る新技術が、手術による根治への道を切り開き、多くの患者さんに希望をもたらそうとしています。この記事では、ケンブリッジ大学とパリ・サクレー大学の研究チームが開発した画期的な画像診断法と、それによって人生が大きく変わった一人の女性の物語をご紹介します。超強力なMRIスキャナーが、治療抵抗性てんかんの原因となる患者さんの脳内の微細な差異を特定できる新技術が登場しました。このアプローチを用いた最初の研究では、英国ケンブリッジのアデンブルック病院の医師たちが、患者さんに根治手術を提案することを可能にしました。
これまで、7テスラ(7T)MRIスキャナーは(先行する3Tスキャナーの2倍以上の強度である7テスラの磁場を使用して動作するためそう呼ばれています)、脳の重要な部分で信号のブラックアウトに悩まされてきました。しかし、医学雑誌「Epilepsia」に2025年3月20日付で発表された研究において、ケンブリッジとパリの研究者チームは、この課題を克服する画期的な技術を導入しました。このオープンアクセスの論文タイトルは「Parallel Transmit 7T MRI for Adult Epilepsy Pre-Surgical Evaluation(成人てんかんの術前評価のための並列送信7T MRI)」です。
英国では約36万人が、脳の一部から発作が広がる焦点てんかんとして知られる症状を抱えています。これらの人々の3分の1は、薬物療法にもかかわらず持続的な発作があり、その状態を根治できる唯一の治療法は手術です。てんかん発作は、入院理由の第6位を占めています。
外科医がこの手術を行うためには、発作の原因となって
これまで手の施しようがなかった「治療抵抗性てんかん」。その影に隠れていた微細な脳の変化を、ついに捉える光明が差し込んできました!超強力なMRIスキャナーの限界を打ち破る新技術が、手術による根治への道を切り開き、多くの患者さんに希望をもたらそうとしています。この記事では、ケンブリッジ大学とパリ・サクレー大学の研究チームが開発した画期的な画像診断法と、それによって人生が大きく変わった一人の女性の物語をご紹介します。超強力なMRIスキャナーが、治療抵抗性てんかんの原因となる患者さんの脳内の微細な差異を特定できる新技術が登場しました。このアプローチを用いた最初の研究では、英国ケンブリッジのアデンブルック病院の医師たちが、患者さんに根治手術を提案することを可能にしました。
これまで、7テスラ(7T)MRIスキャナーは(先行する3Tスキャナーの2倍以上の強度である7テスラの磁場を使用して動作するためそう呼ばれています)、脳の重要な部分で信号のブラックアウトに悩まされてきました。しかし、医学雑誌「Epilepsia」に2025年3月20日付で発表された研究において、ケンブリッジとパリの研究者チームは、この課題を克服する画期的な技術を導入しました。このオープンアクセスの論文タイトルは「Parallel Transmit 7T MRI for Adult Epilepsy Pre-Surgical Evaluation(成人てんかんの術前評価のための並列送信7T MRI)」です。
英国では約36万人が、脳の一部から発作が広がる焦点てんかんとして知られる症状を抱えています。これらの人々の3分の1は、薬物療法にもかかわらず持続的な発作があり、その状態を根治できる唯一の治療法は手術です。てんかん発作は、入院理由の第6位を占めています。
外科医がこの手術を行うためには、発作の原因となって
 注射の回数が減り、針も細くなる――そんな夢のような薬物投与法が、もうすぐ現実になるかもしれません。マサチューセッツ工科大学(MIT)のエンジニアたちが、薬の小さな結晶を注射することで、皮下で薬剤が長期間安定して放出される「薬剤貯蔵庫(デポ)」を作り出す新しい技術を開発しました。これにより、避妊薬やヒト免疫不全ウイルス(HIV)感染症などの治療薬を、より少ない苦痛で、数ヶ月から数年にわたって届けられるようになるかもしれません。このアプローチは、より細い針とより少ない注射回数で、避妊薬やヒト免疫不全ウイルス感染症などの疾患治療薬の長期的な投与に新たな選択肢をもたらす可能性があります。
MITのエンジニアたちは、特定の薬剤をより少ない痛みで高用量投与する新しい方法を考案しました。それは、薬剤を微小な結晶の懸濁液として注射するというものです。皮下に注入されると、結晶は集合して数ヶ月から数年間持続する可能性のある薬剤の「デポ剤」を形成し、頻繁な薬剤注射の必要性をなくします。このアプローチは、長期作用型の避妊薬や、長期間にわたって投与する必要がある他の薬剤の送達に有用である可能性があります。薬剤は注射前に懸濁液中に分散されているため、患者にとってより許容しやすい細い針を通して投与することができます。
「私たちは、細い針を通して、非常によく制御された持続的な送達が、おそらく数ヶ月、さらには数年間可能であることを示しました」と、MITの機械工学准教授であり、ブリガム・アンド・ウィメンズ病院(BWH: Brigham and Women’s Hospital)の消化器専門医、ブロード研究所のアソシエイトメンバーであり、この研究のシニアオーサーであるジョバンニ・トラバーソ博士(Giovanni Traverso, PhD)は述べています。トラバーソ博士は、ジョンズ・ホプキンス大学のバー
注射の回数が減り、針も細くなる――そんな夢のような薬物投与法が、もうすぐ現実になるかもしれません。マサチューセッツ工科大学(MIT)のエンジニアたちが、薬の小さな結晶を注射することで、皮下で薬剤が長期間安定して放出される「薬剤貯蔵庫(デポ)」を作り出す新しい技術を開発しました。これにより、避妊薬やヒト免疫不全ウイルス(HIV)感染症などの治療薬を、より少ない苦痛で、数ヶ月から数年にわたって届けられるようになるかもしれません。このアプローチは、より細い針とより少ない注射回数で、避妊薬やヒト免疫不全ウイルス感染症などの疾患治療薬の長期的な投与に新たな選択肢をもたらす可能性があります。
MITのエンジニアたちは、特定の薬剤をより少ない痛みで高用量投与する新しい方法を考案しました。それは、薬剤を微小な結晶の懸濁液として注射するというものです。皮下に注入されると、結晶は集合して数ヶ月から数年間持続する可能性のある薬剤の「デポ剤」を形成し、頻繁な薬剤注射の必要性をなくします。このアプローチは、長期作用型の避妊薬や、長期間にわたって投与する必要がある他の薬剤の送達に有用である可能性があります。薬剤は注射前に懸濁液中に分散されているため、患者にとってより許容しやすい細い針を通して投与することができます。
「私たちは、細い針を通して、非常によく制御された持続的な送達が、おそらく数ヶ月、さらには数年間可能であることを示しました」と、MITの機械工学准教授であり、ブリガム・アンド・ウィメンズ病院(BWH: Brigham and Women’s Hospital)の消化器専門医、ブロード研究所のアソシエイトメンバーであり、この研究のシニアオーサーであるジョバンニ・トラバーソ博士(Giovanni Traverso, PhD)は述べています。トラバーソ博士は、ジョンズ・ホプキンス大学のバー
 まるで魔法のように、たった一つの細胞がリズミカルに動き出し、生命の形が紡ぎ出されていく――そんな神秘的なプロセスの一端を、光を使って自在にコントロールできるとしたらどうでしょう?マサチューセッツ工科大学(MIT)の科学者たちが、光をスイッチにして細胞の初期段階の「ダンス」を操る画期的な方法を開発しました。この技術は、将来、傷ついた組織を修復したり、必要な場所に正確に薬を届けたりする、まったく新しい医療への道を開くかもしれません。この研究は、創傷治癒や薬物送達のための、光で活性化する合成細胞の設計を可能にするかもしれません。
生命は、単一の細胞の動きとともに形作られます。特定のタンパク質や酵素からのシグナルに応答して、細胞は動き始め、振動し、収縮を引き起こし、くびれ、最終的には分裂に至ります。娘細胞が世代を超えてそれに続くと、それらは成長し、分化し、最終的には完全に形成された生物へと配置されます。今回、マサチューセッツ工科大学の科学者たちは、光を使って、単一細胞が発生の最も初期の段階でどのように揺れ動き、移動するかを制御しました。研究チームは、科学者が細胞の成長と発生を理解するための古典的なモデルとして長年使用してきた生物であるヒトデが産生する卵細胞の動きを研究しました。研究者たちは、ヒトデ卵細胞内で一連の動きを引き起こす重要な酵素に焦点を当てました。彼らは、同じ酵素の光感受性バージョンを遺伝子操作で設計し、それを卵細胞に注入し、その後、異なる光のパターンで細胞を刺激しました。
その結果、光が酵素を効果的に活性化し、それが細胞を予測可能なパターンで揺れ動かすことを発見しました。例えば、科学者たちは、照射する光のパターンに応じて、細胞に小さなくびれや広範囲な収縮を示させることができました。細胞の周りの特定の部分に光を当てることで、細胞の形を円形から四角形に引き伸ばす
まるで魔法のように、たった一つの細胞がリズミカルに動き出し、生命の形が紡ぎ出されていく――そんな神秘的なプロセスの一端を、光を使って自在にコントロールできるとしたらどうでしょう?マサチューセッツ工科大学(MIT)の科学者たちが、光をスイッチにして細胞の初期段階の「ダンス」を操る画期的な方法を開発しました。この技術は、将来、傷ついた組織を修復したり、必要な場所に正確に薬を届けたりする、まったく新しい医療への道を開くかもしれません。この研究は、創傷治癒や薬物送達のための、光で活性化する合成細胞の設計を可能にするかもしれません。
生命は、単一の細胞の動きとともに形作られます。特定のタンパク質や酵素からのシグナルに応答して、細胞は動き始め、振動し、収縮を引き起こし、くびれ、最終的には分裂に至ります。娘細胞が世代を超えてそれに続くと、それらは成長し、分化し、最終的には完全に形成された生物へと配置されます。今回、マサチューセッツ工科大学の科学者たちは、光を使って、単一細胞が発生の最も初期の段階でどのように揺れ動き、移動するかを制御しました。研究チームは、科学者が細胞の成長と発生を理解するための古典的なモデルとして長年使用してきた生物であるヒトデが産生する卵細胞の動きを研究しました。研究者たちは、ヒトデ卵細胞内で一連の動きを引き起こす重要な酵素に焦点を当てました。彼らは、同じ酵素の光感受性バージョンを遺伝子操作で設計し、それを卵細胞に注入し、その後、異なる光のパターンで細胞を刺激しました。
その結果、光が酵素を効果的に活性化し、それが細胞を予測可能なパターンで揺れ動かすことを発見しました。例えば、科学者たちは、照射する光のパターンに応じて、細胞に小さなくびれや広範囲な収縮を示させることができました。細胞の周りの特定の部分に光を当てることで、細胞の形を円形から四角形に引き伸ばす
 空を覆い尽くし、農作物に壊滅的な被害をもたらすバッタの大群。その圧倒的な光景は自然の驚異であると同時に、長年、人類を悩ませてきた脅威でもあります。彼らは一体どのようにして、あれほど巨大な群れを形成し、統率された動きで移動するのでしょうか?この長年の謎に、新たな光を当てる研究が登場しました。従来の定説を覆すかもしれないその新理論は、バッタの被害を食い止めるための画期的な戦略につながるかもしれません。2025年2月27日にScience誌に掲載された新しい研究が、自然界で最も見事で、しかし破壊的な現象の一つである、共に移動する巨大なバッタの群れについての私たちの理解を塗り替えようとしています。テキサスA&M大学農学生命科学部昆虫学科の摂政教授であり、チャールズ・R・パレンシア記念講座(綿花昆虫学)の保持者であるグレッグ・ソード博士(Greg Sword, PhD)を含む研究チームは、動物の集団において無秩序から秩序がどのように生まれるのかという長年の理論に異議を唱えています。
ソード博士は、マックス・プランク動物行動研究所およびドイツ・コンスタンツ大学集団行動高等研究センターの研究者チームと共に、最近「The Behavioral Mechanisms Governing Collective Motion in Swarming Locusts(群れをなすバッタの集団運動を支配する行動メカニズム)」と題する研究を発表しました。この研究は、バッタはこれまで信じられていたような同期した集団運動ではなく、非協調的なリーダー追従行動のような形で移動することを提案しています。この記事には、サイエンス誌に「Virtual Reality Rewrites Rules of the Swarm(バーチャルリアリティが群れのルールを書き換える)と題されたパースペクティブ論文も掲
空を覆い尽くし、農作物に壊滅的な被害をもたらすバッタの大群。その圧倒的な光景は自然の驚異であると同時に、長年、人類を悩ませてきた脅威でもあります。彼らは一体どのようにして、あれほど巨大な群れを形成し、統率された動きで移動するのでしょうか?この長年の謎に、新たな光を当てる研究が登場しました。従来の定説を覆すかもしれないその新理論は、バッタの被害を食い止めるための画期的な戦略につながるかもしれません。2025年2月27日にScience誌に掲載された新しい研究が、自然界で最も見事で、しかし破壊的な現象の一つである、共に移動する巨大なバッタの群れについての私たちの理解を塗り替えようとしています。テキサスA&M大学農学生命科学部昆虫学科の摂政教授であり、チャールズ・R・パレンシア記念講座(綿花昆虫学)の保持者であるグレッグ・ソード博士(Greg Sword, PhD)を含む研究チームは、動物の集団において無秩序から秩序がどのように生まれるのかという長年の理論に異議を唱えています。
ソード博士は、マックス・プランク動物行動研究所およびドイツ・コンスタンツ大学集団行動高等研究センターの研究者チームと共に、最近「The Behavioral Mechanisms Governing Collective Motion in Swarming Locusts(群れをなすバッタの集団運動を支配する行動メカニズム)」と題する研究を発表しました。この研究は、バッタはこれまで信じられていたような同期した集団運動ではなく、非協調的なリーダー追従行動のような形で移動することを提案しています。この記事には、サイエンス誌に「Virtual Reality Rewrites Rules of the Swarm(バーチャルリアリティが群れのルールを書き換える)と題されたパースペクティブ論文も掲
 「お腹がいっぱい!」と感じさせてくれる満腹感。この大切な感覚を操る脳内物質が、実は私たち人間だけでなく、なんとヒトデにも共通して存在し、5億年以上も前から食欲をコントロールしてきたかもしれないとしたら、驚きませんか?このほど、ロンドン大学クイーンメアリー校の生物学者チームが、食欲を抑える働きを持つ神経ホルモン「ボンベシン」の驚くべき進化のルーツを解明しました。この発見は、私たちの食欲メカニズムの起源を深く理解する上で、新たな扉を開くものです。ロンドン大学クイーンメアリー校の生物学研究チームは、ヒトの食欲を制御する神経ホルモンが、5億年以上前に遡る古い進化的起源を持つことを発見しました。この研究成果は、科学雑誌PNASに掲載され、この満腹感を引き起こす分子、ボンベシンとして知られるものが、ヒトや他の脊椎動物だけでなく、ヒトデやその近縁の海洋生物にも存在することを明らかにしています。
ボンベシンは小さなペプチドで、私たちが十分に食べたことを知らせることで空腹感を調節する上で重要な役割を果たしています。しかし、その物語は人間や哺乳類から始まるわけではありません。新しい研究は、ボンベシン様神経ホルモンが、地球上で最初の脊椎動物が進化するずっと前から動物の食欲を制御してきたことを示しています。
「ボンベシン」という名前は、1971年にこのペプチドが初めて皮膚から単離されたヨーロッパ原産のヒキガエルの一種であるファイヤーベリード・トード(Bombina bombina)(写真参照)に由来します。哺乳類にボンベシンを注射すると、食事量が減少し、食事の間隔が長くなることがわかりました。このことから科学者たちは、脳や腸で生成されるボンベシン様神経ホルモンが、食物摂取を制御する体の自然なシステムの一部であると考えるようになりました。さらに、オゼンピックのような体重減少を誘発する薬剤と
「お腹がいっぱい!」と感じさせてくれる満腹感。この大切な感覚を操る脳内物質が、実は私たち人間だけでなく、なんとヒトデにも共通して存在し、5億年以上も前から食欲をコントロールしてきたかもしれないとしたら、驚きませんか?このほど、ロンドン大学クイーンメアリー校の生物学者チームが、食欲を抑える働きを持つ神経ホルモン「ボンベシン」の驚くべき進化のルーツを解明しました。この発見は、私たちの食欲メカニズムの起源を深く理解する上で、新たな扉を開くものです。ロンドン大学クイーンメアリー校の生物学研究チームは、ヒトの食欲を制御する神経ホルモンが、5億年以上前に遡る古い進化的起源を持つことを発見しました。この研究成果は、科学雑誌PNASに掲載され、この満腹感を引き起こす分子、ボンベシンとして知られるものが、ヒトや他の脊椎動物だけでなく、ヒトデやその近縁の海洋生物にも存在することを明らかにしています。
ボンベシンは小さなペプチドで、私たちが十分に食べたことを知らせることで空腹感を調節する上で重要な役割を果たしています。しかし、その物語は人間や哺乳類から始まるわけではありません。新しい研究は、ボンベシン様神経ホルモンが、地球上で最初の脊椎動物が進化するずっと前から動物の食欲を制御してきたことを示しています。
「ボンベシン」という名前は、1971年にこのペプチドが初めて皮膚から単離されたヨーロッパ原産のヒキガエルの一種であるファイヤーベリード・トード(Bombina bombina)(写真参照)に由来します。哺乳類にボンベシンを注射すると、食事量が減少し、食事の間隔が長くなることがわかりました。このことから科学者たちは、脳や腸で生成されるボンベシン様神経ホルモンが、食物摂取を制御する体の自然なシステムの一部であると考えるようになりました。さらに、オゼンピックのような体重減少を誘発する薬剤と
 私たちの体の中では、無数の細胞が絶えず動き、生命という壮大なシンフォニーを奏でています。しかし、その複雑でダイナミックな姿を、私たちはまだ断片的にしか見ることができません。もし、この生命の営みを映画のように、隅々まで鮮明に観察できるとしたらどうでしょうか?そんな夢のような技術を開発するため、ある巨大プロジェクトが始動しました。2つのトップクラス研究所を統合し、イメージング技術に革命を起こすという、壮大な挑戦をご紹介します。CZバイオハブ・サンフランシスコとCZイメージング研究所が統合し、スコット・フレイザー博士(Dr. Scott Fraser)のリーダーシップのもと、人間の生物学に関する全く新しい洞察を提供する新規イメージング技術を開発します。
チャン・ザッカーバーグ・イニシアチブ(CZI: Chan Zuckerberg Initiative)は、科学者が生きた細胞や生命体を観察、測定、理解する方法を変革する、画期的なイメージング技術を開発するという新たなグランドチャレンジ(壮大な挑戦)を発表しました。CZIの2つの強力な研究所、CZバイオハブ・サンフランシスコとCZ先端生物イメージング研究所は、それぞれの相補的な専門知識を活用し、生命科学イメージング研究の分野で比類のない新しいバイオハブを形成します。両チームは、CZI本部に隣接するカリフォルニア州レッドウッドシティの新しいサイエンスキャンパスに集結します。「これらの研究所は、生物学的発見における重要な時期に、それぞれの補完的な強みを活かしています。適切な技術的・科学的専門知識の組み合わせが、脳や免疫系のような複雑なシステムの隠された動態を解明し、それらがどのように機能するかを完全に理解するための新しいツールを生み出すことができる時なのです」と、CZIの共同創設者兼共同CEOであるプリシラ・チャン氏(Prisci
私たちの体の中では、無数の細胞が絶えず動き、生命という壮大なシンフォニーを奏でています。しかし、その複雑でダイナミックな姿を、私たちはまだ断片的にしか見ることができません。もし、この生命の営みを映画のように、隅々まで鮮明に観察できるとしたらどうでしょうか?そんな夢のような技術を開発するため、ある巨大プロジェクトが始動しました。2つのトップクラス研究所を統合し、イメージング技術に革命を起こすという、壮大な挑戦をご紹介します。CZバイオハブ・サンフランシスコとCZイメージング研究所が統合し、スコット・フレイザー博士(Dr. Scott Fraser)のリーダーシップのもと、人間の生物学に関する全く新しい洞察を提供する新規イメージング技術を開発します。
チャン・ザッカーバーグ・イニシアチブ(CZI: Chan Zuckerberg Initiative)は、科学者が生きた細胞や生命体を観察、測定、理解する方法を変革する、画期的なイメージング技術を開発するという新たなグランドチャレンジ(壮大な挑戦)を発表しました。CZIの2つの強力な研究所、CZバイオハブ・サンフランシスコとCZ先端生物イメージング研究所は、それぞれの相補的な専門知識を活用し、生命科学イメージング研究の分野で比類のない新しいバイオハブを形成します。両チームは、CZI本部に隣接するカリフォルニア州レッドウッドシティの新しいサイエンスキャンパスに集結します。「これらの研究所は、生物学的発見における重要な時期に、それぞれの補完的な強みを活かしています。適切な技術的・科学的専門知識の組み合わせが、脳や免疫系のような複雑なシステムの隠された動態を解明し、それらがどのように機能するかを完全に理解するための新しいツールを生み出すことができる時なのです」と、CZIの共同創設者兼共同CEOであるプリシラ・チャン氏(Prisci
 地球温暖化やエネルギー問題が深刻化する現代、その解決のヒントが、実は何十億年も前の地球に隠されているかもしれません。マサチューセッツ工科大学(MIT)のある化学者は、生命が誕生したばかりの原始の地球で細胞が使っていた「古代の酵素」に注目しています。これらの酵素は、金属原子のクラスターを巧みに利用し、現代の私たちが直面するエネルギー問題や環境問題に対する、全く新しい解決策を秘めている可能性があるのです。一体、太古の酵素からどのような未来が拓けるのでしょうか?細胞が困難な反応を実行するために用いる酵素を研究することで、マサチューセッツ工科大学(MIT)の化学者であるダニエル・スース博士(Daniel Suess, PhD)は、地球規模のエネルギー課題に対する新たな解決策を見つけ出すことを目指しています。
地球の気候危機への解決策を見出すために、MITの准教授であるスース博士は、地球の古代の過去に目を向けています。生命進化の初期において、細胞は、ある原子から別の原子へ電子を移動させるような反応を行う能力を獲得しました。これらの反応は、細胞が炭素含有化合物や窒素含有化合物を構築するのを助け、金属原子のクラスターを持つ特殊な酵素に依存しています。これらの酵素がどのように機能するのかをより深く理解することで、スース博士は最終的に、大気中から炭素を回収したり、代替燃料の開発を可能にしたりするのに役立つ、基本的な化学反応を行う新しい方法を考案したいと考えています。
「私たちは、社会が単に膨大な量の還元型炭素、つまり化石燃料に依存し、それを酸素を使って燃焼させるだけではないように、社会を再構築する方法を見つけなければなりません」と彼は言います。「私たちが行っているのは、酸素や光合成が登場する最大10億年前まで遡り、炭素燃焼に依存しないプロセスの根底にある化学原理を特定できるかどうか
地球温暖化やエネルギー問題が深刻化する現代、その解決のヒントが、実は何十億年も前の地球に隠されているかもしれません。マサチューセッツ工科大学(MIT)のある化学者は、生命が誕生したばかりの原始の地球で細胞が使っていた「古代の酵素」に注目しています。これらの酵素は、金属原子のクラスターを巧みに利用し、現代の私たちが直面するエネルギー問題や環境問題に対する、全く新しい解決策を秘めている可能性があるのです。一体、太古の酵素からどのような未来が拓けるのでしょうか?細胞が困難な反応を実行するために用いる酵素を研究することで、マサチューセッツ工科大学(MIT)の化学者であるダニエル・スース博士(Daniel Suess, PhD)は、地球規模のエネルギー課題に対する新たな解決策を見つけ出すことを目指しています。
地球の気候危機への解決策を見出すために、MITの准教授であるスース博士は、地球の古代の過去に目を向けています。生命進化の初期において、細胞は、ある原子から別の原子へ電子を移動させるような反応を行う能力を獲得しました。これらの反応は、細胞が炭素含有化合物や窒素含有化合物を構築するのを助け、金属原子のクラスターを持つ特殊な酵素に依存しています。これらの酵素がどのように機能するのかをより深く理解することで、スース博士は最終的に、大気中から炭素を回収したり、代替燃料の開発を可能にしたりするのに役立つ、基本的な化学反応を行う新しい方法を考案したいと考えています。
「私たちは、社会が単に膨大な量の還元型炭素、つまり化石燃料に依存し、それを酸素を使って燃焼させるだけではないように、社会を再構築する方法を見つけなければなりません」と彼は言います。「私たちが行っているのは、酸素や光合成が登場する最大10億年前まで遡り、炭素燃焼に依存しないプロセスの根底にある化学原理を特定できるかどうか
 ワクチンが私たちの体を病気から守る力は、どれだけ長く、どれだけ質の高い「抗体」を作り出せるかにかかっています。この重要な抗体を生み出すB細胞は、ワクチンや病原体に反応すると、まるでギャンブルのように自らの遺伝子を次々と変異させ、最強の抗体を見つけ出そうとします。しかし、この変異は諸刃の剣。抗体の能力を高めることもあれば、逆に機能しないものに変えてしまうことの方がずっと多いのです。では、どうやってB細胞はこの難関を乗り越え、優れた抗体を効率よく生み出しているのでしょうか?最新の研究が、B細胞が「大当たり」の変異を無駄にしないための、驚くべき戦略を明らかにしました。
ワクチンの効果が持続し、高い親和性を持つ抗体を産生できるかどうかは、非常に繊細なバランスにかかっています。ワクチンや病原体にさらされると、B細胞は防御機構を洗練させるために奔走し、最も効果的な抗体を産生することを期待して急速に変異を繰り返します。しかし、このプロセスの各段階は遺伝的なサイコロを振るようなものです。全ての変異は親和性を向上させる可能性を秘めていますが、それよりもはるかに多くの場合は、機能的な抗体を劣化させたり破壊したりします。高親和性B細胞は、どのようにしてこの不利な状況を克服しているのでしょうか?新しい研究は、B細胞が成功した変異を戦略的に「貯蓄」することで、良い変異を失うリスクを回避していることを示唆しています。2025年3月19日にNature誌に掲載された論文「Regulated Somatic Hypermutation Enhances Antibody Affinity Maturation(制御された体細胞超変異は抗体親和性成熟を強化する)」で説明されているように、成功した高親和性B細胞は、変異のリスクを低減する特別な条件下で増殖することができます。このメカニズムを実験室で捉え
ワクチンが私たちの体を病気から守る力は、どれだけ長く、どれだけ質の高い「抗体」を作り出せるかにかかっています。この重要な抗体を生み出すB細胞は、ワクチンや病原体に反応すると、まるでギャンブルのように自らの遺伝子を次々と変異させ、最強の抗体を見つけ出そうとします。しかし、この変異は諸刃の剣。抗体の能力を高めることもあれば、逆に機能しないものに変えてしまうことの方がずっと多いのです。では、どうやってB細胞はこの難関を乗り越え、優れた抗体を効率よく生み出しているのでしょうか?最新の研究が、B細胞が「大当たり」の変異を無駄にしないための、驚くべき戦略を明らかにしました。
ワクチンの効果が持続し、高い親和性を持つ抗体を産生できるかどうかは、非常に繊細なバランスにかかっています。ワクチンや病原体にさらされると、B細胞は防御機構を洗練させるために奔走し、最も効果的な抗体を産生することを期待して急速に変異を繰り返します。しかし、このプロセスの各段階は遺伝的なサイコロを振るようなものです。全ての変異は親和性を向上させる可能性を秘めていますが、それよりもはるかに多くの場合は、機能的な抗体を劣化させたり破壊したりします。高親和性B細胞は、どのようにしてこの不利な状況を克服しているのでしょうか?新しい研究は、B細胞が成功した変異を戦略的に「貯蓄」することで、良い変異を失うリスクを回避していることを示唆しています。2025年3月19日にNature誌に掲載された論文「Regulated Somatic Hypermutation Enhances Antibody Affinity Maturation(制御された体細胞超変異は抗体親和性成熟を強化する)」で説明されているように、成功した高親和性B細胞は、変異のリスクを低減する特別な条件下で増殖することができます。このメカニズムを実験室で捉え
 アスガルド古細菌:生命の起源の謎を解き明かす「失われた環」か?
私たちの体の細胞、そして動物や植物の細胞がどのようにして生まれたのか、その起源は生命科学における大きな謎の一つです。10年前にはその存在すら知られていなかった微生物「アスガルド古細菌」が、この謎を解き明かす鍵を握っているかもしれません。深海の熱水噴出孔近くで発見されたこの小さな生命体は、私たち真核生物と、より原始的な古細菌とをつなぐ「失われた環(ミッシングリンク)」である可能性を秘めているのです。この発見は、生命の系統樹を書き換えるかもしれないほど衝撃的なものでした。この記事では、アスガルド古細菌の驚くべき特徴と、それが私たちのルーツ解明にどのように貢献するのか、最新の研究成果とともにご紹介します。
10年前、アスガルド古細菌が存在することを知る人はいませんでした。しかし2015年、深海堆積物を調査していた研究者たちが、未知の新しい微生物の存在を示す遺伝子の断片を発見しました。研究者たちはコンピューターの助けを借りて、これらの断片をパズルのピースのように組み立て、全ゲノムを解読しました。その時初めて、彼らはこれまで知られていなかった古細菌のグループを扱っていることに気づいたのです。細菌と同様に、古細菌も単細胞生物です。しかし、遺伝的には、特に細胞の外被や代謝プロセスに関して、この2つのドメイン間には大きな違いがあります。さらなる探索の結果、微生物学者たちは対応する生物を特定し、それらを記述し、独立した古細菌のサブグループとしてアスガルド古細菌と分類しました。その名前は、北欧神話の神々の住まう天上の世界から取られ、ノルウェーとスヴァールバル諸島の間にある大西洋中央海嶺のブラックスモーカー「ロキの城」の近くで最初に発見されたことに由来します。
実際、アスガルド古細菌は研究にとって天からの贈り物のようでした
アスガルド古細菌:生命の起源の謎を解き明かす「失われた環」か?
私たちの体の細胞、そして動物や植物の細胞がどのようにして生まれたのか、その起源は生命科学における大きな謎の一つです。10年前にはその存在すら知られていなかった微生物「アスガルド古細菌」が、この謎を解き明かす鍵を握っているかもしれません。深海の熱水噴出孔近くで発見されたこの小さな生命体は、私たち真核生物と、より原始的な古細菌とをつなぐ「失われた環(ミッシングリンク)」である可能性を秘めているのです。この発見は、生命の系統樹を書き換えるかもしれないほど衝撃的なものでした。この記事では、アスガルド古細菌の驚くべき特徴と、それが私たちのルーツ解明にどのように貢献するのか、最新の研究成果とともにご紹介します。
10年前、アスガルド古細菌が存在することを知る人はいませんでした。しかし2015年、深海堆積物を調査していた研究者たちが、未知の新しい微生物の存在を示す遺伝子の断片を発見しました。研究者たちはコンピューターの助けを借りて、これらの断片をパズルのピースのように組み立て、全ゲノムを解読しました。その時初めて、彼らはこれまで知られていなかった古細菌のグループを扱っていることに気づいたのです。細菌と同様に、古細菌も単細胞生物です。しかし、遺伝的には、特に細胞の外被や代謝プロセスに関して、この2つのドメイン間には大きな違いがあります。さらなる探索の結果、微生物学者たちは対応する生物を特定し、それらを記述し、独立した古細菌のサブグループとしてアスガルド古細菌と分類しました。その名前は、北欧神話の神々の住まう天上の世界から取られ、ノルウェーとスヴァールバル諸島の間にある大西洋中央海嶺のブラックスモーカー「ロキの城」の近くで最初に発見されたことに由来します。
実際、アスガルド古細菌は研究にとって天からの贈り物のようでした
 光が拓く創薬の未来:新開発の化学反応が医薬品開発を加速する!
新しい薬が私たちの手元に届くまでには、複雑で長い道のりがあります。その中でも、薬の「設計図」とも言える化学物質を効率よく、そして正確に作り出すことは非常に重要です。もし、光の力を借りて、これまで難しかった薬のタネを簡単に、そしてクリーンに作れるとしたらどうでしょう?インディアナ大学と武漢大学の研究チームが、まさにそんな夢のような新しい化学反応を開発しました。この技術は、パーキンソン病やがん治療薬など、多くの医薬品開発を加速させるかもしれません。この記事では、光が化学の未来を照らす、この画期的な研究について詳しくご紹介します。
インディアナ大学と中国の武漢大学の研究者たちは、医薬品化合物、すなわち薬物が体とどのように相互作用するかに影響を与える化学構造の基本骨格の開発を効率化できる可能性を秘めた、画期的な化学プロセスを発表しました。彼らの研究は、2025年3月6日に科学雑誌Chemに掲載され、医薬品化学において重要な役割を果たす化学物質群であるテトラヒドロイソキノリンを効率的に生成する新しい光駆動反応について詳述しています。この論文のタイトルは「An Unconventional Photochemical Tetrahydroisoquinoline Synthesis from Sulfonylimines and Alkenes(スルホニルイミンとアルケンからの非従来型光化学的テトラヒドロイソキノリン合成)」です。
テトラヒドロイソキノリンは、パーキンソン病、心血管疾患などを対象とした治療法の基盤として機能します。これらの化合物は、鎮痛剤や高血圧治療薬などの医薬品や、特定の植物や海洋生物などの天然資源にも一般的に見られます。
従来、化学者たちはこれらの分子を合成するために、確立されてはいるものの
光が拓く創薬の未来:新開発の化学反応が医薬品開発を加速する!
新しい薬が私たちの手元に届くまでには、複雑で長い道のりがあります。その中でも、薬の「設計図」とも言える化学物質を効率よく、そして正確に作り出すことは非常に重要です。もし、光の力を借りて、これまで難しかった薬のタネを簡単に、そしてクリーンに作れるとしたらどうでしょう?インディアナ大学と武漢大学の研究チームが、まさにそんな夢のような新しい化学反応を開発しました。この技術は、パーキンソン病やがん治療薬など、多くの医薬品開発を加速させるかもしれません。この記事では、光が化学の未来を照らす、この画期的な研究について詳しくご紹介します。
インディアナ大学と中国の武漢大学の研究者たちは、医薬品化合物、すなわち薬物が体とどのように相互作用するかに影響を与える化学構造の基本骨格の開発を効率化できる可能性を秘めた、画期的な化学プロセスを発表しました。彼らの研究は、2025年3月6日に科学雑誌Chemに掲載され、医薬品化学において重要な役割を果たす化学物質群であるテトラヒドロイソキノリンを効率的に生成する新しい光駆動反応について詳述しています。この論文のタイトルは「An Unconventional Photochemical Tetrahydroisoquinoline Synthesis from Sulfonylimines and Alkenes(スルホニルイミンとアルケンからの非従来型光化学的テトラヒドロイソキノリン合成)」です。
テトラヒドロイソキノリンは、パーキンソン病、心血管疾患などを対象とした治療法の基盤として機能します。これらの化合物は、鎮痛剤や高血圧治療薬などの医薬品や、特定の植物や海洋生物などの天然資源にも一般的に見られます。
従来、化学者たちはこれらの分子を合成するために、確立されてはいるものの
 私たちの体は、未知の病原体と戦うために、驚くほど巧妙な免疫システムを備えています。その最前線で活躍するのが「抗体」ですが、この抗体がどのようにしてこれほど迅速かつ正確に作り出されるのか、長い間謎に包まれていました。特に、リンパ節内に存在する「胚中心」という微小な構造は、まるで高速進化マシンのように抗体を改良し続ける場所です。しかし、急速な進化には通常、質の低下という代償が伴うはず。では、胚中心はどのようにして、この矛盾を乗り越えているのでしょうか?最新の研究が、ついにその驚くべき秘密の一端を明らかにしました。それは、増殖のスピードを優先する際には変異を一時的に抑制するという、巧みな戦略だったのです。
胚中心は、高速で進化する機械のようなものです。リンパ節にある小さな集合体である胚中心は、変異と増殖を通じて抗体を洗練させ、最終的にはさまざまな病原体を抑制するように適応した高親和性B細胞を産生します。しかし、急速な進化には代償が伴うはずです。ほとんどの変異は有害であるため、細胞分裂のたびに絶え間ない変異が起こり、それが抑制されない増殖と組み合わさると、大惨事を招くはずです。B細胞がどのようにして、これほど迅速に変異し、かつ同時に改善していくのかは、長年の謎でした。今回、先進的なイメージング技術により、胚中心の秘密兵器が明らかになりました。それは、急速な増殖中に変異を抑制する能力です。この組み込まれた安全装置により、胚中心は抗体の品質を損なうことなく、成功したクローンを大量生産できるのです。この発見は、2025年3月19日にネイチャー誌に掲載された論文「Transient Silencing of Hypermutation Preserves B Cell Affinity During Clonal Bursting(クローン増殖中の超変異の一時的サイレンシングはB細
私たちの体は、未知の病原体と戦うために、驚くほど巧妙な免疫システムを備えています。その最前線で活躍するのが「抗体」ですが、この抗体がどのようにしてこれほど迅速かつ正確に作り出されるのか、長い間謎に包まれていました。特に、リンパ節内に存在する「胚中心」という微小な構造は、まるで高速進化マシンのように抗体を改良し続ける場所です。しかし、急速な進化には通常、質の低下という代償が伴うはず。では、胚中心はどのようにして、この矛盾を乗り越えているのでしょうか?最新の研究が、ついにその驚くべき秘密の一端を明らかにしました。それは、増殖のスピードを優先する際には変異を一時的に抑制するという、巧みな戦略だったのです。
胚中心は、高速で進化する機械のようなものです。リンパ節にある小さな集合体である胚中心は、変異と増殖を通じて抗体を洗練させ、最終的にはさまざまな病原体を抑制するように適応した高親和性B細胞を産生します。しかし、急速な進化には代償が伴うはずです。ほとんどの変異は有害であるため、細胞分裂のたびに絶え間ない変異が起こり、それが抑制されない増殖と組み合わさると、大惨事を招くはずです。B細胞がどのようにして、これほど迅速に変異し、かつ同時に改善していくのかは、長年の謎でした。今回、先進的なイメージング技術により、胚中心の秘密兵器が明らかになりました。それは、急速な増殖中に変異を抑制する能力です。この組み込まれた安全装置により、胚中心は抗体の品質を損なうことなく、成功したクローンを大量生産できるのです。この発見は、2025年3月19日にネイチャー誌に掲載された論文「Transient Silencing of Hypermutation Preserves B Cell Affinity During Clonal Bursting(クローン増殖中の超変異の一時的サイレンシングはB細
 あの驚異的なスタミナはどこから来るのか?競馬場のヒーロー、馬たちの強靭な持久力の裏には、巧妙な遺伝子のからくりが隠されていました。最新の研究が、彼らがエネルギーを効率よく生み出し、同時に細胞へのダメージを防ぐという、まさに「一石二鳥」のメカニズムを解き明かしたのです。この発見は、私たち人間の健康や病気の治療法開発にも新たな視点をもたらすかもしれません。馬の進化が織りなす生命の神秘に、一緒に迫ってみましょう。
研究者たちは、馬の並外れた持久力の背後にある秘密を明らかにしました。それは、細胞の酸化ストレスから保護しつつエネルギー産生を促進する、KEAP1遺伝子の変異です。この発見は、自然界で最も強力なアスリートの一種を形作ってきたユニークな進化的適応に光を当てるものであり、ヒト医学への潜在的な示唆も持っています。また、これまで主にウイルスに限定されると考えられていた戦略である、新規終止コドンのリコーディングが、脊椎動物の適応を促進しうることも示しています。その速さと持久力で古くから珍重されてきた馬は、特にその大きな体格を考えると、並外れた持久走ランナーとする驚くべき生理学的適応を備えています。酸素を取り込み、輸送し、利用する能力は広く並外れていると認識されており、最大酸素摂取量(VO2max: maximal oxygen consumption)はエリートのヒトアスリートの2倍以上です。馬の骨格筋におけるミトコンドリアの高密度な集中は、これらの偉業を可能にするためにエネルギー産生を高めますが、同時に活性酸素種(ROS: reactive oxygen species)の産生も促進し、重大な組織損傷や細胞機能不全を引き起こす可能性があります。馬がその並外れたミトコンドリア活性によって引き起こされる酸化ストレスを管理するために進化させてきた分子的メカニズムは、依然として不明
あの驚異的なスタミナはどこから来るのか?競馬場のヒーロー、馬たちの強靭な持久力の裏には、巧妙な遺伝子のからくりが隠されていました。最新の研究が、彼らがエネルギーを効率よく生み出し、同時に細胞へのダメージを防ぐという、まさに「一石二鳥」のメカニズムを解き明かしたのです。この発見は、私たち人間の健康や病気の治療法開発にも新たな視点をもたらすかもしれません。馬の進化が織りなす生命の神秘に、一緒に迫ってみましょう。
研究者たちは、馬の並外れた持久力の背後にある秘密を明らかにしました。それは、細胞の酸化ストレスから保護しつつエネルギー産生を促進する、KEAP1遺伝子の変異です。この発見は、自然界で最も強力なアスリートの一種を形作ってきたユニークな進化的適応に光を当てるものであり、ヒト医学への潜在的な示唆も持っています。また、これまで主にウイルスに限定されると考えられていた戦略である、新規終止コドンのリコーディングが、脊椎動物の適応を促進しうることも示しています。その速さと持久力で古くから珍重されてきた馬は、特にその大きな体格を考えると、並外れた持久走ランナーとする驚くべき生理学的適応を備えています。酸素を取り込み、輸送し、利用する能力は広く並外れていると認識されており、最大酸素摂取量(VO2max: maximal oxygen consumption)はエリートのヒトアスリートの2倍以上です。馬の骨格筋におけるミトコンドリアの高密度な集中は、これらの偉業を可能にするためにエネルギー産生を高めますが、同時に活性酸素種(ROS: reactive oxygen species)の産生も促進し、重大な組織損傷や細胞機能不全を引き起こす可能性があります。馬がその並外れたミトコンドリア活性によって引き起こされる酸化ストレスを管理するために進化させてきた分子的メカニズムは、依然として不明
 空を優雅に舞う鳥の羽。その複雑で美しい構造は、一体どこから来たのでしょうか?最新の研究が、その起源をなんと太古の恐竜にまで遡り、進化の謎の一端を解き明かそうとしています。スイス、ジュネーブ大学の研究チームが、ニワトリの胚を使った巧みな実験で、羽毛発生の「スイッチ」を操作。まるでタイムトラベルのように、恐竜がまとっていたかもしれない「最初の羽毛」の姿を垣間見ることに成功したのです。羽毛は、動物界で最も複雑な皮膚付属器の一つです。その進化の起源は広く議論されてきましたが、古生物学的な発見や発生生物学の研究は、羽毛がプロトフェザーとして知られる単純な構造から進化したことを示唆しています。これらの単一の管状フィラメントで構成される原始的な構造は、約2億年前に特定の恐竜に出現しました。古生物学者たちは、約2億4千万年前の恐竜と翼竜(膜状の翼を持つ最初の飛行脊椎動物)の共通祖先に、さらに早くから存在していた可能性について議論を続けています。
プロトフェザーは単純な円筒状のフィラメントです。それらは、羽枝や小羽枝がないこと、そして基部にある陥入構造である羽包がないことによって、現代の羽毛とは異なります。プロトフェザーの出現は、羽毛進化における最初の重要なステップを示したと考えられ、当初は断熱や装飾を提供し、その後、自然選択のもとで徐々に改変され、飛行を可能にするより複雑な構造を生み出しました。
ジュネーブ大学科学部遺伝学進化発生学研究室の教授であるミシェル・ミリンコビッチ博士(Michel Milinkovitch, PhD)の研究室では、ソニック・ヘッジホッグ(Shh: Sonic Hedgehog)経路のような分子シグナル伝達経路(細胞内および細胞間でメッセージを伝達するコミュニケーションシステム)が、現代の脊椎動物における鱗、毛、羽毛の胚発生において果たす役割を研究していま
空を優雅に舞う鳥の羽。その複雑で美しい構造は、一体どこから来たのでしょうか?最新の研究が、その起源をなんと太古の恐竜にまで遡り、進化の謎の一端を解き明かそうとしています。スイス、ジュネーブ大学の研究チームが、ニワトリの胚を使った巧みな実験で、羽毛発生の「スイッチ」を操作。まるでタイムトラベルのように、恐竜がまとっていたかもしれない「最初の羽毛」の姿を垣間見ることに成功したのです。羽毛は、動物界で最も複雑な皮膚付属器の一つです。その進化の起源は広く議論されてきましたが、古生物学的な発見や発生生物学の研究は、羽毛がプロトフェザーとして知られる単純な構造から進化したことを示唆しています。これらの単一の管状フィラメントで構成される原始的な構造は、約2億年前に特定の恐竜に出現しました。古生物学者たちは、約2億4千万年前の恐竜と翼竜(膜状の翼を持つ最初の飛行脊椎動物)の共通祖先に、さらに早くから存在していた可能性について議論を続けています。
プロトフェザーは単純な円筒状のフィラメントです。それらは、羽枝や小羽枝がないこと、そして基部にある陥入構造である羽包がないことによって、現代の羽毛とは異なります。プロトフェザーの出現は、羽毛進化における最初の重要なステップを示したと考えられ、当初は断熱や装飾を提供し、その後、自然選択のもとで徐々に改変され、飛行を可能にするより複雑な構造を生み出しました。
ジュネーブ大学科学部遺伝学進化発生学研究室の教授であるミシェル・ミリンコビッチ博士(Michel Milinkovitch, PhD)の研究室では、ソニック・ヘッジホッグ(Shh: Sonic Hedgehog)経路のような分子シグナル伝達経路(細胞内および細胞間でメッセージを伝達するコミュニケーションシステム)が、現代の脊椎動物における鱗、毛、羽毛の胚発生において果たす役割を研究していま
 自分を守るはずの免疫システムが、誤って自身の体を攻撃してしまう自己免疫疾患。米国だけでも1500万人以上が罹患していると推定され、多くの人々を苦しめています。これまで、免疫システムが「誤報」を発するきっかけは分かっていましたが、実際に攻撃部隊を「出動」させてしまう詳細なメカニズムは謎に包まれていました。しかしこのほど、その謎を解き明かすかもしれない重要なタンパク質が発見されました。この発見は、新たな治療法開発への大きな一歩となるかもしれません。ワシントン大学医学部とペンシルベニア大学ペレルマン医学部の科学者たちが共同研究者らと共に、免疫活動、そして過剰な免疫活動を引き起こす鍵となる構成要素を特定しました。
研究チームは、細胞内で感染と戦う分子の放出を促進するタンパク質を同定しました。このタンパク質は、これまで免疫系における役割が疑われていなかったもので、数々の深刻な消耗性疾患の根底にある過剰な免疫応答を防ぐ治療法の潜在的な標的となります。彼らの論文は、2025年2月12日に『Cell』誌のオンライン版に掲載されました。論文のタイトルは「ArfGAP2 Promotes STING Proton Channel Activity, Cytokine Transit, and Autoinflammation(ArfGAP2はSTINGプロトンチャネル活性、サイトカイン輸送、および自己炎症を促進する)」です。
この研究チームは、ペンシルベニア大学コルター自己免疫センターのメンバーであり、リウマチ学・微生物学の准教授であるジョナサン・マイナー医学博士(Jonathan Miner, MD, PhD)と、ワシントン大学医学部細胞生物学・生理学部門の助教であるデイビッド・カスト博士(David Kast, PhD)が共同で率いており、SAVI(STING-associated
自分を守るはずの免疫システムが、誤って自身の体を攻撃してしまう自己免疫疾患。米国だけでも1500万人以上が罹患していると推定され、多くの人々を苦しめています。これまで、免疫システムが「誤報」を発するきっかけは分かっていましたが、実際に攻撃部隊を「出動」させてしまう詳細なメカニズムは謎に包まれていました。しかしこのほど、その謎を解き明かすかもしれない重要なタンパク質が発見されました。この発見は、新たな治療法開発への大きな一歩となるかもしれません。ワシントン大学医学部とペンシルベニア大学ペレルマン医学部の科学者たちが共同研究者らと共に、免疫活動、そして過剰な免疫活動を引き起こす鍵となる構成要素を特定しました。
研究チームは、細胞内で感染と戦う分子の放出を促進するタンパク質を同定しました。このタンパク質は、これまで免疫系における役割が疑われていなかったもので、数々の深刻な消耗性疾患の根底にある過剰な免疫応答を防ぐ治療法の潜在的な標的となります。彼らの論文は、2025年2月12日に『Cell』誌のオンライン版に掲載されました。論文のタイトルは「ArfGAP2 Promotes STING Proton Channel Activity, Cytokine Transit, and Autoinflammation(ArfGAP2はSTINGプロトンチャネル活性、サイトカイン輸送、および自己炎症を促進する)」です。
この研究チームは、ペンシルベニア大学コルター自己免疫センターのメンバーであり、リウマチ学・微生物学の准教授であるジョナサン・マイナー医学博士(Jonathan Miner, MD, PhD)と、ワシントン大学医学部細胞生物学・生理学部門の助教であるデイビッド・カスト博士(David Kast, PhD)が共同で率いており、SAVI(STING-associated
 畑の野菜や庭の花々が、ある日突然モザイク模様に…。これは、多くの植物を脅かすキュウリモザイクウイルス(CMV)の仕業かもしれません。この厄介なウイルスに対し、これまで有効な対策は限られていましたが、ついに希望の光が見えてきました。ドイツの研究チームが、植物自身の免疫力を巧みに利用する、新しいリボ核酸ベースの薬剤を開発。実験では驚くべき効果を示しており、農業や園芸の未来を大きく変える可能性を秘めています。新しいRNAベースの有効成分が、農業や園芸で最も一般的なウイルスであるキュウリモザイクウイルスから植物を確実に保護することが明らかになりました。
この薬剤は、マルティン・ルター大学ハレ・ヴィッテンベルク校の研究者らによって開発されたものです。この有効成分は広範囲な効果を持ち、一連のRNA分子が植物の免疫システムをサポートしてウイルスと戦います。研究チームが2025年3月24日にNucleic Acids Research誌で報告したところによると、実験室での実験では、高いウイルス量に感染させたにもかかわらず、処理された植物の80~100パーセントが生き残りました。彼らの論文は同誌によって「ブレイクスルー論文」に選ばれています。研究者らは現在、このアイデアを実験室から実用へと移すための研究に取り組んでいます。このオープンアクセスのNAR論文のタイトルは「A New Level of RNA-Based Plant Protection: dsRNAs Designed from Functionally Characterized siRNAs Highly Effective Against Cucumber mosaic Virus(RNAベースの植物保護の新境地:機能的に特性評価されたsiRNAから設計された、キュウリモザイクウイルスに対して極めて効果的なdsRNA
畑の野菜や庭の花々が、ある日突然モザイク模様に…。これは、多くの植物を脅かすキュウリモザイクウイルス(CMV)の仕業かもしれません。この厄介なウイルスに対し、これまで有効な対策は限られていましたが、ついに希望の光が見えてきました。ドイツの研究チームが、植物自身の免疫力を巧みに利用する、新しいリボ核酸ベースの薬剤を開発。実験では驚くべき効果を示しており、農業や園芸の未来を大きく変える可能性を秘めています。新しいRNAベースの有効成分が、農業や園芸で最も一般的なウイルスであるキュウリモザイクウイルスから植物を確実に保護することが明らかになりました。
この薬剤は、マルティン・ルター大学ハレ・ヴィッテンベルク校の研究者らによって開発されたものです。この有効成分は広範囲な効果を持ち、一連のRNA分子が植物の免疫システムをサポートしてウイルスと戦います。研究チームが2025年3月24日にNucleic Acids Research誌で報告したところによると、実験室での実験では、高いウイルス量に感染させたにもかかわらず、処理された植物の80~100パーセントが生き残りました。彼らの論文は同誌によって「ブレイクスルー論文」に選ばれています。研究者らは現在、このアイデアを実験室から実用へと移すための研究に取り組んでいます。このオープンアクセスのNAR論文のタイトルは「A New Level of RNA-Based Plant Protection: dsRNAs Designed from Functionally Characterized siRNAs Highly Effective Against Cucumber mosaic Virus(RNAベースの植物保護の新境地:機能的に特性評価されたsiRNAから設計された、キュウリモザイクウイルスに対して極めて効果的なdsRNA
 脳卒中後のリハビリ、それは多くの患者さんにとって長く険しい道のりです。「もっと効果的な方法はないのだろうか…?」そんな切実な願いに応えるかもしれない、画期的な研究成果が発表されました。なんと、飲むだけでリハビリテーションと同様の効果をもたらす可能性を秘めた薬剤が、動物実験でその効果を示したというのです。カリフォルニア大学ロサンゼルス校ヘルス(UCLA Health)の研究チームが、脳卒中後の運動機能回復における新たな希望の扉を開きました。UCLA Healthの研究者とその共同研究者による新しい研究で、ヒトでの研究に続き、モデルマウスにおいて脳卒中後の身体的リハビリテーションの効果を完全に再現する初めての薬剤であると研究者らが述べる物質が発見されました。
この研究結果は、2025年3月15日にNature Communications誌に掲載され、リハビリテーションが脳に与える影響のメカニズムに関する研究から導き出された2つの薬剤候補を検証し、そのうちの1つがマウスモデルにおいて脳卒中後の運動制御の顕著な回復をもたらしたことを報告しています。
脳卒中は、ほとんどの患者さんがその影響から完全には回復しないため、成人の障害の主な原因となっています。現在、脳卒中回復の分野には有効な治療薬がなく、患者さんは身体的なリハビリテーションに頼らざるを得ませんが、その効果は限定的であるとされてきました。このオープンアクセスの論文は「Parvalbumin Interneurons Regulate Rehabilitation-Induced Functional Recovery After Stroke and Identify a Rehabilitation Drug(パルブアルブミン介在ニューロンは脳卒中後のリハビリテーションによる機能回復を制御し、リハビリテーション薬を
脳卒中後のリハビリ、それは多くの患者さんにとって長く険しい道のりです。「もっと効果的な方法はないのだろうか…?」そんな切実な願いに応えるかもしれない、画期的な研究成果が発表されました。なんと、飲むだけでリハビリテーションと同様の効果をもたらす可能性を秘めた薬剤が、動物実験でその効果を示したというのです。カリフォルニア大学ロサンゼルス校ヘルス(UCLA Health)の研究チームが、脳卒中後の運動機能回復における新たな希望の扉を開きました。UCLA Healthの研究者とその共同研究者による新しい研究で、ヒトでの研究に続き、モデルマウスにおいて脳卒中後の身体的リハビリテーションの効果を完全に再現する初めての薬剤であると研究者らが述べる物質が発見されました。
この研究結果は、2025年3月15日にNature Communications誌に掲載され、リハビリテーションが脳に与える影響のメカニズムに関する研究から導き出された2つの薬剤候補を検証し、そのうちの1つがマウスモデルにおいて脳卒中後の運動制御の顕著な回復をもたらしたことを報告しています。
脳卒中は、ほとんどの患者さんがその影響から完全には回復しないため、成人の障害の主な原因となっています。現在、脳卒中回復の分野には有効な治療薬がなく、患者さんは身体的なリハビリテーションに頼らざるを得ませんが、その効果は限定的であるとされてきました。このオープンアクセスの論文は「Parvalbumin Interneurons Regulate Rehabilitation-Induced Functional Recovery After Stroke and Identify a Rehabilitation Drug(パルブアルブミン介在ニューロンは脳卒中後のリハビリテーションによる機能回復を制御し、リハビリテーション薬を
 「飼料の女王」と称され、世界の畜産を支える重要な作物アルファルファ。しかし、その複雑な遺伝的背景は長年、品種改良の大きな壁となっていました。このほど、科学者たちが画期的な染色体識別システムを開発し、アルファルファの遺伝子の謎に迫る大きな一歩を踏み出しました。このブレークスルーは、より優れたアルファルファ品種の開発を加速し、持続可能な農業への貢献が期待されます。最近の研究で、科学者たちは、世界で最も経済的に重要な飼料作物の一つであるアルファルファのための革新的な染色体識別システムを開発しました。先進的なオリゴ蛍光in situハイブリダイゼーションバーコード技術を活用し、研究者たちはアルファルファの全染色体のマッピングと識別に成功し、異数性や大きなセグメント欠失といった予期せぬ染色体異常を発見しました。この飛躍的進歩は、分子細胞遺伝学を強化するだけでなく、同質四倍体アルファルファの遺伝的安定性と進化のパターンに光を当て、より正確で効率的な育種戦略への道を開くものです。
アルファルファは、家畜栄養と持続可能な農業において極めて重要な役割を担っています。しかし、その同質四倍体ゲノムに由来する遺伝的な複雑さ(染色体が小さく非常に均一であること)は、長らく分子細胞遺伝学的研究にとって課題となってきました。蛍光in situハイブリダイゼーション(FISH)のような従来の染色体識別法は、特異性と効率の面で限界があり、多倍数体種における個々の染色体を区別することを困難にしていました。その結果、詳細な核型解析やアルファルファの染色体進化に関する洞察は得られにくいままであり、その遺伝的構造を解読するための革新的なツールの緊急の必要性が浮き彫りになっていました。
2024年9月20日、石河子大学と中国科学院の研究チームは、『Horticulture Research』誌に先駆的な研究
「飼料の女王」と称され、世界の畜産を支える重要な作物アルファルファ。しかし、その複雑な遺伝的背景は長年、品種改良の大きな壁となっていました。このほど、科学者たちが画期的な染色体識別システムを開発し、アルファルファの遺伝子の謎に迫る大きな一歩を踏み出しました。このブレークスルーは、より優れたアルファルファ品種の開発を加速し、持続可能な農業への貢献が期待されます。最近の研究で、科学者たちは、世界で最も経済的に重要な飼料作物の一つであるアルファルファのための革新的な染色体識別システムを開発しました。先進的なオリゴ蛍光in situハイブリダイゼーションバーコード技術を活用し、研究者たちはアルファルファの全染色体のマッピングと識別に成功し、異数性や大きなセグメント欠失といった予期せぬ染色体異常を発見しました。この飛躍的進歩は、分子細胞遺伝学を強化するだけでなく、同質四倍体アルファルファの遺伝的安定性と進化のパターンに光を当て、より正確で効率的な育種戦略への道を開くものです。
アルファルファは、家畜栄養と持続可能な農業において極めて重要な役割を担っています。しかし、その同質四倍体ゲノムに由来する遺伝的な複雑さ(染色体が小さく非常に均一であること)は、長らく分子細胞遺伝学的研究にとって課題となってきました。蛍光in situハイブリダイゼーション(FISH)のような従来の染色体識別法は、特異性と効率の面で限界があり、多倍数体種における個々の染色体を区別することを困難にしていました。その結果、詳細な核型解析やアルファルファの染色体進化に関する洞察は得られにくいままであり、その遺伝的構造を解読するための革新的なツールの緊急の必要性が浮き彫りになっていました。
2024年9月20日、石河子大学と中国科学院の研究チームは、『Horticulture Research』誌に先駆的な研究
 私たちの良きパートナーである犬たちが持つ、驚異的な嗅覚。彼らはどのようにして、人間には感知できない微かな匂いをも嗅ぎ分けるのでしょうか?この長年の謎に迫る画期的な研究が、イスラエルのバルイラン大学から発表されました。最新の光学技術を駆使し、犬の脳活動をリアルタイムで捉えることで、彼らの嗅覚世界の秘密が少しずつ明らかになってきています。この成果は、将来的には法執行や医療、さらには災害救助といった幅広い分野で、犬たちの能力を最大限に活かす新たな道を開くかもしれません。
犬が匂いを検出する際の脳活動を調査したこの先駆的な研究は、彼らの驚くべき嗅覚能力に関する重要な洞察を明らかにしました。イスラエルのバルイラン大学の研究者たちは、犬が異なる匂いを識別する方法において重要な役割を果たす3つの主要な脳領域、すなわち嗅球、海馬、扁桃体の活動を遠隔で感知できる光学センサーを開発しました。このブレークスルーは、犬の嗅覚認知を人間が理解できるように解釈・翻訳できる、小型で非侵襲的なデバイスの開発につながる可能性があります。
この研究では、科学者たちはレーザー技術と高解像度カメラを用いた最先端の検出構造システムを利用し、4つの異なる犬種の脳活動をリアルタイムで捉えました。これらの犬は、ニンニク、メントール、アルコール、マリファナという4つの異なる匂い刺激にさらされました。その後、データは機械学習アルゴリズムを用いて分析され、扁桃体が匂いの識別に重要な役割を果たしていることが明らかになり、匂い処理の感情的側面および記憶関連側面が浮き彫りになりました。
「この発見は、犬が匂いを処理し反応する方法において扁桃体が極めて重要であり、特定の匂いが明確な感情的反応や記憶反応を引き起こすことを示しています。そして私たちは、この領域における彼らの脳活動を光学的に検出することができます」と、バルイラ
私たちの良きパートナーである犬たちが持つ、驚異的な嗅覚。彼らはどのようにして、人間には感知できない微かな匂いをも嗅ぎ分けるのでしょうか?この長年の謎に迫る画期的な研究が、イスラエルのバルイラン大学から発表されました。最新の光学技術を駆使し、犬の脳活動をリアルタイムで捉えることで、彼らの嗅覚世界の秘密が少しずつ明らかになってきています。この成果は、将来的には法執行や医療、さらには災害救助といった幅広い分野で、犬たちの能力を最大限に活かす新たな道を開くかもしれません。
犬が匂いを検出する際の脳活動を調査したこの先駆的な研究は、彼らの驚くべき嗅覚能力に関する重要な洞察を明らかにしました。イスラエルのバルイラン大学の研究者たちは、犬が異なる匂いを識別する方法において重要な役割を果たす3つの主要な脳領域、すなわち嗅球、海馬、扁桃体の活動を遠隔で感知できる光学センサーを開発しました。このブレークスルーは、犬の嗅覚認知を人間が理解できるように解釈・翻訳できる、小型で非侵襲的なデバイスの開発につながる可能性があります。
この研究では、科学者たちはレーザー技術と高解像度カメラを用いた最先端の検出構造システムを利用し、4つの異なる犬種の脳活動をリアルタイムで捉えました。これらの犬は、ニンニク、メントール、アルコール、マリファナという4つの異なる匂い刺激にさらされました。その後、データは機械学習アルゴリズムを用いて分析され、扁桃体が匂いの識別に重要な役割を果たしていることが明らかになり、匂い処理の感情的側面および記憶関連側面が浮き彫りになりました。
「この発見は、犬が匂いを処理し反応する方法において扁桃体が極めて重要であり、特定の匂いが明確な感情的反応や記憶反応を引き起こすことを示しています。そして私たちは、この領域における彼らの脳活動を光学的に検出することができます」と、バルイラ
 空を舞う鳥たちと、かつて地上を闊歩した恐竜。一見かけ離れた存在に思えるかもしれませんが、実は現代の鳥類は恐竜の生き残りとも言える近縁な関係にあります。ニワトリやダチョウのような二本足で直立歩行する飛べない鳥や、鋭い爪と優れた視力を持つワシやタカのような捕食性の鳥の特徴を見ると、『ジュラシック・パーク』で有名なヴェロキラプトルのような小型獣脚類恐竜との類似点は驚くほどです。では、彼らはどのようにして、あの多種多様な姿へと進化を遂げたのでしょうか?その鍵の一つが「脳の大型化」にあるようです。最新の研究は、3Dモデリング技術を駆使し、大きな脳が鳥の顎の筋肉や関節の仕組みに驚くべき変化を引き起こし、柔軟な採餌システム、ひいては現代の鳥類の繁栄につながったことを明らかにしました。
この新しい研究は、シカゴ大学とミズーリ大学の研究者によるもので、現代の鳥類がどのようにしてその特徴的なくちばしを動かし、食事をし、生息環境を探索するようになったのか、その力学的な変化が示されています。これらの適応が、今日私たちが見る驚くほど多様な翼を持つ生き物へと進化するのを助けたのです。
「柔軟な」頭蓋の利点
現代の鳥類は、ヘビや魚類といった他の動物と同様に、哺乳類、カメ、あるいは鳥類以外の恐竜のように顎や口蓋が硬く固定されていません。この研究の筆頭著者であるシカゴ大学統合生物学の大学院生、アレック・ウィルケン氏(Alec Wilken)は、このような柔軟な頭蓋を「『グラグラする』とも言える」と表現しています。彼によれば、この特徴があるために、各パーツがどのように連携して機能するのかを理解することが一層難しくなるとのことです。
「そこに関節があるからといって、それがどのように動くのかが分かるとは限りません」とウィルケン氏は述べています。「ですから、筋肉が関節をどのように引っ張るのか
空を舞う鳥たちと、かつて地上を闊歩した恐竜。一見かけ離れた存在に思えるかもしれませんが、実は現代の鳥類は恐竜の生き残りとも言える近縁な関係にあります。ニワトリやダチョウのような二本足で直立歩行する飛べない鳥や、鋭い爪と優れた視力を持つワシやタカのような捕食性の鳥の特徴を見ると、『ジュラシック・パーク』で有名なヴェロキラプトルのような小型獣脚類恐竜との類似点は驚くほどです。では、彼らはどのようにして、あの多種多様な姿へと進化を遂げたのでしょうか?その鍵の一つが「脳の大型化」にあるようです。最新の研究は、3Dモデリング技術を駆使し、大きな脳が鳥の顎の筋肉や関節の仕組みに驚くべき変化を引き起こし、柔軟な採餌システム、ひいては現代の鳥類の繁栄につながったことを明らかにしました。
この新しい研究は、シカゴ大学とミズーリ大学の研究者によるもので、現代の鳥類がどのようにしてその特徴的なくちばしを動かし、食事をし、生息環境を探索するようになったのか、その力学的な変化が示されています。これらの適応が、今日私たちが見る驚くほど多様な翼を持つ生き物へと進化するのを助けたのです。
「柔軟な」頭蓋の利点
現代の鳥類は、ヘビや魚類といった他の動物と同様に、哺乳類、カメ、あるいは鳥類以外の恐竜のように顎や口蓋が硬く固定されていません。この研究の筆頭著者であるシカゴ大学統合生物学の大学院生、アレック・ウィルケン氏(Alec Wilken)は、このような柔軟な頭蓋を「『グラグラする』とも言える」と表現しています。彼によれば、この特徴があるために、各パーツがどのように連携して機能するのかを理解することが一層難しくなるとのことです。
「そこに関節があるからといって、それがどのように動くのかが分かるとは限りません」とウィルケン氏は述べています。「ですから、筋肉が関節をどのように引っ張るのか
 脳は、私たちが世界をどう認識し、どう学ぶのか、その驚くべき仕組みを内に秘めています。この「心と脳の迷宮」を、鋭い洞察と美しい言葉で探求し続けるフランスの碩学、スタニスラス・ドゥアンヌ博士(Stanislas Dehaene, PhD)。赤ちゃんがいかにして数を理解するのか、映画を見ているときの脳内では何が起きているのか、そして学習の驚くべき原動力とは――。ドゥアンヌ博士は、複雑な脳科学の世界を、まるで魅力的な物語のように、私たち一般読者にも分かりやすく、そして感動的に描き出してきました。その卓越した科学コミュニケーション能力が高く評価され、この度、科学的探求と美しい文章表現を融合させた科学者に贈られる栄誉ある「ルイス・トーマス科学著述賞(Lewis Thomas Prize for Writing about Science)」を受賞することになりました。
2025年3月17日にロックフェラー大学で授賞式が行われるこの賞は、かつて医師であり、科学者、そして名エッセイストでもあったルイス・トーマス氏(Lewis Thomas)の名を冠し、科学の魅力を広く伝える著者を称えるものです。
選考委員長であるジェシー・H・オーシュベル氏(Jesse H. Ausubel)は、「スタン・ドゥアンヌは、驚きこそが学習の原動力である、つまり驚きなくして学習なし、と説得力をもって論じています」と述べています。「彼の著書は、赤ちゃんがどのように計算するのか、映画を見ているときの脳はどのように振る舞うのか、シナプスがいかに学習の『キノコ』であるかといった驚きに満ちており、偉大な教師がいかに書くかを見事に示しています」。
著書『脳はいかに学ぶか――学習の神経科学と教育の未来』(原題:How We Learn)の中で、ドゥアンヌ博士は自身の実験を記録し、脳が推論、抽象的概念、体系的ルール
脳は、私たちが世界をどう認識し、どう学ぶのか、その驚くべき仕組みを内に秘めています。この「心と脳の迷宮」を、鋭い洞察と美しい言葉で探求し続けるフランスの碩学、スタニスラス・ドゥアンヌ博士(Stanislas Dehaene, PhD)。赤ちゃんがいかにして数を理解するのか、映画を見ているときの脳内では何が起きているのか、そして学習の驚くべき原動力とは――。ドゥアンヌ博士は、複雑な脳科学の世界を、まるで魅力的な物語のように、私たち一般読者にも分かりやすく、そして感動的に描き出してきました。その卓越した科学コミュニケーション能力が高く評価され、この度、科学的探求と美しい文章表現を融合させた科学者に贈られる栄誉ある「ルイス・トーマス科学著述賞(Lewis Thomas Prize for Writing about Science)」を受賞することになりました。
2025年3月17日にロックフェラー大学で授賞式が行われるこの賞は、かつて医師であり、科学者、そして名エッセイストでもあったルイス・トーマス氏(Lewis Thomas)の名を冠し、科学の魅力を広く伝える著者を称えるものです。
選考委員長であるジェシー・H・オーシュベル氏(Jesse H. Ausubel)は、「スタン・ドゥアンヌは、驚きこそが学習の原動力である、つまり驚きなくして学習なし、と説得力をもって論じています」と述べています。「彼の著書は、赤ちゃんがどのように計算するのか、映画を見ているときの脳はどのように振る舞うのか、シナプスがいかに学習の『キノコ』であるかといった驚きに満ちており、偉大な教師がいかに書くかを見事に示しています」。
著書『脳はいかに学ぶか――学習の神経科学と教育の未来』(原題:How We Learn)の中で、ドゥアンヌ博士は自身の実験を記録し、脳が推論、抽象的概念、体系的ルール
 ギャラリーに足を踏み入れると、壁に広がる複雑なパターン。それはまるで科学シンポジウムで目にするような精密なイメージかもしれません。しかし、これは実はある芸術家の作品なのです。ドイツ出身のマルチメディアアーティスト、マクシミリアン・プルファー氏(Maximilian Pruefer)が織りなす、動物たちの見えない世界の物語へとご案内しましょう。38歳のプルファー氏は、長年にわたり動物たちの目に見えない動きを捉え、その不可視の世界を可視化してきました。革新的な技法を駆使し、動物たちの一瞬の相互作用、最近では特にアリの行動の痕跡を記録し、それらを印象的な視覚的構成作品へと昇華させています。
自然界に隠された物語を解き明かしたいという探求心が、彼をロックフェラー大学へと導きました。そこで彼は、アーティスト・イン・レジデンスとして社会進化・行動学研究室に6週間滞在しました。この研究室を率いるのは、スタンレー S. & シドニー R. シューマン准教授であるダニエル・クロナウアー博士(Daniel Kronauer, PhD)です。クロナウアー博士は、アリをモデルとして、遺伝子や神経回路からコロニー全体の相互作用に至るまで、複雑な昆虫社会の進化と社会行動の制御メカニズムを研究しています。共通の友人を介して出会った二人ですが、クロナウアー博士はすぐにプルファー氏の作品との共通点を見出しました。
「プルファー氏の作品を初めて見たとき、私たちの研究室で行っている行動追跡のデータと驚くほど似ていることに衝撃を受けました」とクロナウアー博士は語ります。「私たちは異なる問いを立てていますが、集団行動がどのようにパターンを生み出すかという点では、二人とも関心を持っています。」
アリ社会の解読
クロナウアー博士の研究室は、クローンレイダーアントという種のアリを専門としてい
ギャラリーに足を踏み入れると、壁に広がる複雑なパターン。それはまるで科学シンポジウムで目にするような精密なイメージかもしれません。しかし、これは実はある芸術家の作品なのです。ドイツ出身のマルチメディアアーティスト、マクシミリアン・プルファー氏(Maximilian Pruefer)が織りなす、動物たちの見えない世界の物語へとご案内しましょう。38歳のプルファー氏は、長年にわたり動物たちの目に見えない動きを捉え、その不可視の世界を可視化してきました。革新的な技法を駆使し、動物たちの一瞬の相互作用、最近では特にアリの行動の痕跡を記録し、それらを印象的な視覚的構成作品へと昇華させています。
自然界に隠された物語を解き明かしたいという探求心が、彼をロックフェラー大学へと導きました。そこで彼は、アーティスト・イン・レジデンスとして社会進化・行動学研究室に6週間滞在しました。この研究室を率いるのは、スタンレー S. & シドニー R. シューマン准教授であるダニエル・クロナウアー博士(Daniel Kronauer, PhD)です。クロナウアー博士は、アリをモデルとして、遺伝子や神経回路からコロニー全体の相互作用に至るまで、複雑な昆虫社会の進化と社会行動の制御メカニズムを研究しています。共通の友人を介して出会った二人ですが、クロナウアー博士はすぐにプルファー氏の作品との共通点を見出しました。
「プルファー氏の作品を初めて見たとき、私たちの研究室で行っている行動追跡のデータと驚くほど似ていることに衝撃を受けました」とクロナウアー博士は語ります。「私たちは異なる問いを立てていますが、集団行動がどのようにパターンを生み出すかという点では、二人とも関心を持っています。」
アリ社会の解読
クロナウアー博士の研究室は、クローンレイダーアントという種のアリを専門としてい
 病原体は、私たちの免疫システムから逃れるため、まるでカメレオンのように細胞表面の「顔」を巧みに変える「抗原多様性」という驚くべき能力を持っています。この巧妙な変装術のせいで、一度作られた抗体が効かなくなり、感染症の治療やワクチン開発は困難を極めます。特に、アフリカ睡眠病などを引き起こすトリパノソーマという寄生虫は、この変装術の「名人」として知られています。彼らがどのようにして、どの「顔」に次々と変えていくのか、その順番の秘密は長年謎に包まれていました。しかしこの度、ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン(LMU)とヘルムホルツ・ミュンヘンの研究チームが、最先端のシングルセルRNAシーケンシング技術を駆使し、ついにそのメカニズムの一端を解明。次にどの抗原が現れるかを予測する道筋をつけたのです。2025年3月12日に科学誌「Nature」で発表されたこの成果は、トリパノソーマだけでなく、多くの病原体に対する新たな治療薬開発に繋がる画期的な一歩となるかもしれません。
論文タイトルは「Genomic Determinants of Antigen Expression Hierarchy in African Trypanosomes(アフリカトリパノソーマにおける抗原発現階層のゲノム決定因子)」です。研究を率いた物理学者のマリア・コロメ-タッチ博士(Maria Colomé-Tatché, PhD)と生化学者のニコライ・シーゲル博士(Nicolai Siegel, PhD)は、この発見が病原体との戦いに新たな武器をもたらすと期待しています。
「抗原多様性は、進化的に遠縁の広範囲な病原体で見られます」と、LMU生物医学センターの分子寄生虫学研究グループのリーダー(獣医学部実験寄生虫学講座長)であるシーゲル博士は付け加えます。
2025年3月12日に科学誌「Nature
病原体は、私たちの免疫システムから逃れるため、まるでカメレオンのように細胞表面の「顔」を巧みに変える「抗原多様性」という驚くべき能力を持っています。この巧妙な変装術のせいで、一度作られた抗体が効かなくなり、感染症の治療やワクチン開発は困難を極めます。特に、アフリカ睡眠病などを引き起こすトリパノソーマという寄生虫は、この変装術の「名人」として知られています。彼らがどのようにして、どの「顔」に次々と変えていくのか、その順番の秘密は長年謎に包まれていました。しかしこの度、ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン(LMU)とヘルムホルツ・ミュンヘンの研究チームが、最先端のシングルセルRNAシーケンシング技術を駆使し、ついにそのメカニズムの一端を解明。次にどの抗原が現れるかを予測する道筋をつけたのです。2025年3月12日に科学誌「Nature」で発表されたこの成果は、トリパノソーマだけでなく、多くの病原体に対する新たな治療薬開発に繋がる画期的な一歩となるかもしれません。
論文タイトルは「Genomic Determinants of Antigen Expression Hierarchy in African Trypanosomes(アフリカトリパノソーマにおける抗原発現階層のゲノム決定因子)」です。研究を率いた物理学者のマリア・コロメ-タッチ博士(Maria Colomé-Tatché, PhD)と生化学者のニコライ・シーゲル博士(Nicolai Siegel, PhD)は、この発見が病原体との戦いに新たな武器をもたらすと期待しています。
「抗原多様性は、進化的に遠縁の広範囲な病原体で見られます」と、LMU生物医学センターの分子寄生虫学研究グループのリーダー(獣医学部実験寄生虫学講座長)であるシーゲル博士は付け加えます。
2025年3月12日に科学誌「Nature
 私たちの目には見えないけれど、動物たちにとっては「見える世界」があるとしたら? ミシガン大学の研究チームが、人間には感知できない「紫外線の色(UVカラー: ultraviolet (UV) color)」の秘密に、ヘビを通じて迫りました。鳥や蝶が紫外線を巧みに利用することは知られていましたが、ヘビのような「地味」と見られがちな生き物もまた、生存のためにこの見えざる色を駆使していたのです。驚くべきことに、ヘビの紫外線色は、求愛よりもむしろ捕食者から身を隠すカモフラージュに役立っている可能性が示唆されました。この発見は、私たちが普段目にしている動物たちの姿が、実はほんの一面でしかないことを教えてくれます。2024年6月18日に「[Nature Communications」誌で発表されたこの研究は、人間中心の色彩感覚を見直し、動物たちの真のコミュニケーションや生存戦略を理解する上で、新たな視点を与えてくれるでしょう。
論文タイトルは「Ecological Drivers of Ultraviolet Colour Evolution in Snakes(ヘビにおける紫外線色進化の生態学的駆動要因)」です。研究の共著者であり、ミシガン大学(U-M)生態学・進化学科の博士課程の学生であるヘイリー・クロウェル氏(Hayley Crowell)は、この紫外線色がヘビの進化の系統樹全体に広く分布し、捕食者回避に重要な役割を果たしていると指摘しています。
「紫外線色に関する研究の多くは、鳥や花、蝶のように、私たちが伝統的に明るくカラフルだと考えている系で行われています。しかし、これらの色彩研究の多くは、人間の色彩認識によって大きく偏っています」とクロウェル氏は言います。
「これらの研究は主に、交配や生殖システム、例えば、昆虫を受粉に必要な花の部分へと導くのに役立つ花の紫外線『蜜標
私たちの目には見えないけれど、動物たちにとっては「見える世界」があるとしたら? ミシガン大学の研究チームが、人間には感知できない「紫外線の色(UVカラー: ultraviolet (UV) color)」の秘密に、ヘビを通じて迫りました。鳥や蝶が紫外線を巧みに利用することは知られていましたが、ヘビのような「地味」と見られがちな生き物もまた、生存のためにこの見えざる色を駆使していたのです。驚くべきことに、ヘビの紫外線色は、求愛よりもむしろ捕食者から身を隠すカモフラージュに役立っている可能性が示唆されました。この発見は、私たちが普段目にしている動物たちの姿が、実はほんの一面でしかないことを教えてくれます。2024年6月18日に「[Nature Communications」誌で発表されたこの研究は、人間中心の色彩感覚を見直し、動物たちの真のコミュニケーションや生存戦略を理解する上で、新たな視点を与えてくれるでしょう。
論文タイトルは「Ecological Drivers of Ultraviolet Colour Evolution in Snakes(ヘビにおける紫外線色進化の生態学的駆動要因)」です。研究の共著者であり、ミシガン大学(U-M)生態学・進化学科の博士課程の学生であるヘイリー・クロウェル氏(Hayley Crowell)は、この紫外線色がヘビの進化の系統樹全体に広く分布し、捕食者回避に重要な役割を果たしていると指摘しています。
「紫外線色に関する研究の多くは、鳥や花、蝶のように、私たちが伝統的に明るくカラフルだと考えている系で行われています。しかし、これらの色彩研究の多くは、人間の色彩認識によって大きく偏っています」とクロウェル氏は言います。
「これらの研究は主に、交配や生殖システム、例えば、昆虫を受粉に必要な花の部分へと導くのに役立つ花の紫外線『蜜標
 もし自分の皮膚細胞が、失われた神経細胞の代わりになれるとしたら?そんな再生医療の夢を大きく前進させる画期的な技術が、マサチューセッツ工科大学(MIT)で生まれました。これまで細胞の種類を変えるには、iPS細胞のような「万能細胞」を経由する必要がありましたが、MITの研究チームは、皮膚細胞から直接、神経細胞へと「ワープ」させるかのような新たな手法を開発。しかも、マウス実験では、1つの皮膚細胞から10個以上のニューロンを作り出すという驚異的な効率を達成しました。この「ダイレクトコンバージョン」技術がヒト細胞にも応用できれば、脊髄損傷やALSといった難病に苦しむ患者さんのための運動ニューロンを大量に供給できる道が開けるかもしれません。2025年3月13日に「Cell Systems」誌で発表されたこの研究は、細胞置換療法の未来を明るく照らしています。
「私たちは、これらの細胞が細胞置換療法の実行可能な候補となりうるかどうかという問いを発することができるほどの収率に到達できました。そうなってほしいと願っています。このような種類の再プログラミング技術が私たちをそこへ導いてくれるのです」と、MITのW. M. ケック生物医学工学・化学工学キャリア開発教授であるケイティ・ギャロウェイ博士(Katie Galloway, PhD)は述べています。
これらの細胞を治療法として開発するための第一歩として、研究者らは運動ニューロンを生成し、それらをマウスの脳に移植したところ、宿主組織と統合することを示しました。
ギャロウェイ博士は、この新しい方法を記述した2つの論文の責任著者であり、MITの大学院生であるネイサン・ワン氏(Nathan Wang)が両論文の筆頭著者です。
皮膚からニューロンへ
約20年前、日本の科学者たちは、4つの転写因子を皮膚細胞に導入することで、それら
もし自分の皮膚細胞が、失われた神経細胞の代わりになれるとしたら?そんな再生医療の夢を大きく前進させる画期的な技術が、マサチューセッツ工科大学(MIT)で生まれました。これまで細胞の種類を変えるには、iPS細胞のような「万能細胞」を経由する必要がありましたが、MITの研究チームは、皮膚細胞から直接、神経細胞へと「ワープ」させるかのような新たな手法を開発。しかも、マウス実験では、1つの皮膚細胞から10個以上のニューロンを作り出すという驚異的な効率を達成しました。この「ダイレクトコンバージョン」技術がヒト細胞にも応用できれば、脊髄損傷やALSといった難病に苦しむ患者さんのための運動ニューロンを大量に供給できる道が開けるかもしれません。2025年3月13日に「Cell Systems」誌で発表されたこの研究は、細胞置換療法の未来を明るく照らしています。
「私たちは、これらの細胞が細胞置換療法の実行可能な候補となりうるかどうかという問いを発することができるほどの収率に到達できました。そうなってほしいと願っています。このような種類の再プログラミング技術が私たちをそこへ導いてくれるのです」と、MITのW. M. ケック生物医学工学・化学工学キャリア開発教授であるケイティ・ギャロウェイ博士(Katie Galloway, PhD)は述べています。
これらの細胞を治療法として開発するための第一歩として、研究者らは運動ニューロンを生成し、それらをマウスの脳に移植したところ、宿主組織と統合することを示しました。
ギャロウェイ博士は、この新しい方法を記述した2つの論文の責任著者であり、MITの大学院生であるネイサン・ワン氏(Nathan Wang)が両論文の筆頭著者です。
皮膚からニューロンへ
約20年前、日本の科学者たちは、4つの転写因子を皮膚細胞に導入することで、それら
 私たちの体の中で、歳とともに増え続け、まるで「ゾンビ」のように居座っては悪さをする細胞がいることをご存知ですか?これらは「老化細胞」と呼ばれ、分裂をやめた後も体内に残り、周囲に炎症を引き起こす物質をまき散らします。この慢性的な炎症こそが、多くの加齢関連疾患の引き金になると考えられています。この「体内の火種」を消し止める鍵を、サンフォード・バーナム・プレビス医学研究所の研究チームが発見しました。そのヒーローは、細胞のがん化を防ぐ「門番」としても知られるDNA修復タンパク質「p53」。p53が、老化細胞による炎症を抑え、さらにはその原因となる細胞内の「ゴミ(損傷DNAの断片)」の発生も防ぐというのです。2025年3月5日に「Nature Communications」誌で発表されたこの研究は、p53をターゲットにした新しい老化予防・治療戦略への道を開くかもしれません。
論文タイトルは「p53 Enhances DNA Repair and Suppresses Cytoplasmic Chromatin Fragments and Inflammation in Senescent Cells(p53は老化細胞におけるDNA修復を強化し細胞質クロマチン断片と炎症を抑制する)」です。研究を率いたサンフォード・バーナム・プレビス医学研究所(Sanford Burnham Prebys)のがんゲノム・エピジェネティクスプログラムのディレクター兼教授であるピーター・アダムス博士(Peter Adams, PhD)は、老化細胞の炎症プログラムが健康長寿の大きな障害となっていると指摘しています。
この炎症プログラムを「実行している」細胞は、老化関連分泌現象(SASP: senescence-associated secretory phenotype)を示すと考えられています。炎症
私たちの体の中で、歳とともに増え続け、まるで「ゾンビ」のように居座っては悪さをする細胞がいることをご存知ですか?これらは「老化細胞」と呼ばれ、分裂をやめた後も体内に残り、周囲に炎症を引き起こす物質をまき散らします。この慢性的な炎症こそが、多くの加齢関連疾患の引き金になると考えられています。この「体内の火種」を消し止める鍵を、サンフォード・バーナム・プレビス医学研究所の研究チームが発見しました。そのヒーローは、細胞のがん化を防ぐ「門番」としても知られるDNA修復タンパク質「p53」。p53が、老化細胞による炎症を抑え、さらにはその原因となる細胞内の「ゴミ(損傷DNAの断片)」の発生も防ぐというのです。2025年3月5日に「Nature Communications」誌で発表されたこの研究は、p53をターゲットにした新しい老化予防・治療戦略への道を開くかもしれません。
論文タイトルは「p53 Enhances DNA Repair and Suppresses Cytoplasmic Chromatin Fragments and Inflammation in Senescent Cells(p53は老化細胞におけるDNA修復を強化し細胞質クロマチン断片と炎症を抑制する)」です。研究を率いたサンフォード・バーナム・プレビス医学研究所(Sanford Burnham Prebys)のがんゲノム・エピジェネティクスプログラムのディレクター兼教授であるピーター・アダムス博士(Peter Adams, PhD)は、老化細胞の炎症プログラムが健康長寿の大きな障害となっていると指摘しています。
この炎症プログラムを「実行している」細胞は、老化関連分泌現象(SASP: senescence-associated secretory phenotype)を示すと考えられています。炎症
 体内に埋め込んだセンサーが、24時間健康を見守ってくれる――そんなSFのような未来が、もうすぐそこまで来ているかもしれません。しかし、この「体内見守りセンサー」実用化には、大きな壁がありました。センサー表面に細菌や細胞が付着して邪魔をする「バイオファウリング」と、体がセンサーを異物とみなして攻撃する「異物反応」です。これらの問題が、センサーの寿命を縮め、正確な測定を妨げてきました。この長年の課題に、ハーバード大学ウィス研究所の研究チームが画期的な解決策を提示しました。彼らが開発したのは、センサーを「汚れ」や「体の攻撃」から守りつつ、長期間安定して機能させることを可能にする特殊なコーティング技術。まるでセンサーに「透明な鎧」を着せるようなこの技術は、糖尿病患者さんの血糖値モニターはもちろん、脳の状態やがん治療の効果判定など、幅広い医療分野での応用が期待されています。2025年3月6日に学術誌「Biosensors」で発表されたこの研究は、個別化医療やデジタルヘルスの未来を大きく前進させるかもしれません。
論文タイトルは「An Antimicrobial and Antifibrotic Coating for Implantable Biosensors(埋め込み型バイオセンサーのための抗菌・抗線維化コーティング)」です。
この課題の克服は、慢性疾患や自己免疫疾患患者のより長期的な状態モニタリング、既存治療や臨床試験中の新薬に対する患者の反応評価、脳を含む多くの臓器における生理学的・病理学的シグナルの測定といった、多くの臨床診断および研究応用への道を開くことになります。
この新しいコーティング技術は、埋め込み型およびウェアラブルバイオセンサーの寿命を大幅に延ばしつつ、その電気信号活性を維持します。これにより、体内のさまざまな生体液中のアナライトを、潜在的には数週間
体内に埋め込んだセンサーが、24時間健康を見守ってくれる――そんなSFのような未来が、もうすぐそこまで来ているかもしれません。しかし、この「体内見守りセンサー」実用化には、大きな壁がありました。センサー表面に細菌や細胞が付着して邪魔をする「バイオファウリング」と、体がセンサーを異物とみなして攻撃する「異物反応」です。これらの問題が、センサーの寿命を縮め、正確な測定を妨げてきました。この長年の課題に、ハーバード大学ウィス研究所の研究チームが画期的な解決策を提示しました。彼らが開発したのは、センサーを「汚れ」や「体の攻撃」から守りつつ、長期間安定して機能させることを可能にする特殊なコーティング技術。まるでセンサーに「透明な鎧」を着せるようなこの技術は、糖尿病患者さんの血糖値モニターはもちろん、脳の状態やがん治療の効果判定など、幅広い医療分野での応用が期待されています。2025年3月6日に学術誌「Biosensors」で発表されたこの研究は、個別化医療やデジタルヘルスの未来を大きく前進させるかもしれません。
論文タイトルは「An Antimicrobial and Antifibrotic Coating for Implantable Biosensors(埋め込み型バイオセンサーのための抗菌・抗線維化コーティング)」です。
この課題の克服は、慢性疾患や自己免疫疾患患者のより長期的な状態モニタリング、既存治療や臨床試験中の新薬に対する患者の反応評価、脳を含む多くの臓器における生理学的・病理学的シグナルの測定といった、多くの臨床診断および研究応用への道を開くことになります。
この新しいコーティング技術は、埋め込み型およびウェアラブルバイオセンサーの寿命を大幅に延ばしつつ、その電気信号活性を維持します。これにより、体内のさまざまな生体液中のアナライトを、潜在的には数週間
 パーキンソン病――その名は、多くの人々に不安と困難をもたらす進行性の神経変性疾患として知られています。根本的な治療法がいまだ見つからない中、オーストラリアの研究機関から、この難病との闘いに光明を投じる画期的な発見が報告されました。ウォルター・アンド・イライザ・ホール医学研究所(WEHI: Walter and Eliza Hall Institute)の科学者たちが、パーキンソン病の発症に深く関わる「PINK1」というタンパク質の「働く姿」を、世界で初めて捉えることに成功したのです。このタンパク質は、細胞内のエネルギー工場であるミトコンドリアが傷ついたときに重要な役割を果たしますが、その詳細なメカニズムは20年以上も謎に包まれていました。今回、その構造とスイッチが入る瞬間が明らかになったことで、PINK1を標的とした新しい治療薬開発への道が大きく開かれると期待されています。2025年3月13日に科学誌「Science」で発表されたこの成果は、パーキンソン病治療の新たな夜明けを告げるものかもしれません。論文タイトルは「Structure of Human PINK1 at a Mitochondrial TOM-VDAC Array(ミトコンドリアTOM-VDACアレイにおけるヒトPINK1の構造)」です。
研究成果のポイント
WEHIの研究者たちが、世界で初めてヒトPINK1の姿とその活性化の仕組みを発見しました。
PINK1は、アルツハイマー病に次いで2番目に多い神経変性疾患であるパーキンソン病に関連するタンパク質です。パーキンソン病には根治治療法がありません。
「Science」誌に掲載されたこの発見は、パーキンソン病との戦いにおける大きな前進であり、病気の進行を止める薬剤探索を加速させることが期待されます。
パーキンソン病は潜行性に進行し、診断までに数
パーキンソン病――その名は、多くの人々に不安と困難をもたらす進行性の神経変性疾患として知られています。根本的な治療法がいまだ見つからない中、オーストラリアの研究機関から、この難病との闘いに光明を投じる画期的な発見が報告されました。ウォルター・アンド・イライザ・ホール医学研究所(WEHI: Walter and Eliza Hall Institute)の科学者たちが、パーキンソン病の発症に深く関わる「PINK1」というタンパク質の「働く姿」を、世界で初めて捉えることに成功したのです。このタンパク質は、細胞内のエネルギー工場であるミトコンドリアが傷ついたときに重要な役割を果たしますが、その詳細なメカニズムは20年以上も謎に包まれていました。今回、その構造とスイッチが入る瞬間が明らかになったことで、PINK1を標的とした新しい治療薬開発への道が大きく開かれると期待されています。2025年3月13日に科学誌「Science」で発表されたこの成果は、パーキンソン病治療の新たな夜明けを告げるものかもしれません。論文タイトルは「Structure of Human PINK1 at a Mitochondrial TOM-VDAC Array(ミトコンドリアTOM-VDACアレイにおけるヒトPINK1の構造)」です。
研究成果のポイント
WEHIの研究者たちが、世界で初めてヒトPINK1の姿とその活性化の仕組みを発見しました。
PINK1は、アルツハイマー病に次いで2番目に多い神経変性疾患であるパーキンソン病に関連するタンパク質です。パーキンソン病には根治治療法がありません。
「Science」誌に掲載されたこの発見は、パーキンソン病との戦いにおける大きな前進であり、病気の進行を止める薬剤探索を加速させることが期待されます。
パーキンソン病は潜行性に進行し、診断までに数
 なぜか女性の方がよく効く痛み止めがある。なぜ閉経後に慢性痛が増える女性がいるのか――。これらの長年の疑問に光を当てるかもしれない、画期的な発見がありました。答えの鍵を握っていたのは、私たちの体にもともと備わっている「免疫細胞」と「女性ホルモン」の、これまで誰も知らなかった意外な連携プレーだったのです。カリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF)の研究チームが、痛みを感じる仕組みの常識を覆すかもしれない、新しいメカニズムを解き明かしました。科学者たちは、免疫細胞を介して作用する新しいメカニズムを発見し、慢性痛を治療するための異なる方法を示唆しました。UCSFの研究者たちによる新しい研究で、女性ホルモンが脊髄の近くにある免疫細胞にオピオイド(体内で作られる鎮痛物質)を産生させることで、痛みを抑制できることが明らかになりました。
これにより、痛み信号が脳に到達する前に阻止されます。この発見は、慢性痛に対する新しい治療法の開発に役立つ可能性があります。また、一部の鎮痛剤が男性よりも女性によく効く理由や、閉経後の女性がより多くの痛みを経験する理由を説明できるかもしれません。この研究は、炎症を軽減する能力で知られる制御性T細胞の全く新しい役割を明らかにしました。
「これらの細胞に、エストロゲンとプロゲステロンによって引き起こされる性別に依存した影響があり、それが免疫機能とは全く関係がないという事実は、非常に珍しいです」と、博士研究員のエロラ・ミダヴェーヌ博士(Elora Midavaine, PhD)は述べています。彼女は、アメリカ国立衛生研究所(NIH)から一部資金提供を受けたこの研究の筆頭著者です。この研究は2025年4月3日に科学誌「Science」に掲載されました。論文のタイトルは、「髄膜の制御性T細胞はメスマウスの侵害受容を抑制する(Meningeal Regul
なぜか女性の方がよく効く痛み止めがある。なぜ閉経後に慢性痛が増える女性がいるのか――。これらの長年の疑問に光を当てるかもしれない、画期的な発見がありました。答えの鍵を握っていたのは、私たちの体にもともと備わっている「免疫細胞」と「女性ホルモン」の、これまで誰も知らなかった意外な連携プレーだったのです。カリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF)の研究チームが、痛みを感じる仕組みの常識を覆すかもしれない、新しいメカニズムを解き明かしました。科学者たちは、免疫細胞を介して作用する新しいメカニズムを発見し、慢性痛を治療するための異なる方法を示唆しました。UCSFの研究者たちによる新しい研究で、女性ホルモンが脊髄の近くにある免疫細胞にオピオイド(体内で作られる鎮痛物質)を産生させることで、痛みを抑制できることが明らかになりました。
これにより、痛み信号が脳に到達する前に阻止されます。この発見は、慢性痛に対する新しい治療法の開発に役立つ可能性があります。また、一部の鎮痛剤が男性よりも女性によく効く理由や、閉経後の女性がより多くの痛みを経験する理由を説明できるかもしれません。この研究は、炎症を軽減する能力で知られる制御性T細胞の全く新しい役割を明らかにしました。
「これらの細胞に、エストロゲンとプロゲステロンによって引き起こされる性別に依存した影響があり、それが免疫機能とは全く関係がないという事実は、非常に珍しいです」と、博士研究員のエロラ・ミダヴェーヌ博士(Elora Midavaine, PhD)は述べています。彼女は、アメリカ国立衛生研究所(NIH)から一部資金提供を受けたこの研究の筆頭著者です。この研究は2025年4月3日に科学誌「Science」に掲載されました。論文のタイトルは、「髄膜の制御性T細胞はメスマウスの侵害受容を抑制する(Meningeal Regul
 B型肝炎ウイルス――この小さな侵略者は、世界で3億人もの人々の肝臓に静かに、しかし確実に感染を広げ、時には肝硬変や肝がんといった深刻な病気を引き起こします。ワクチンや治療薬は存在するものの、HBVが細胞の中でどのようにして生き続け、悪さをするのか、その巧妙な「隠れ蓑戦略」の全貌は長年謎に包まれていました。しかし、ついにその一端が明らかになりました。ロックフェラー大学などの共同研究チームが、HBVがまるで宿主の細胞核を「乗っ取る」かのように、自身の遺伝子を活性化させる驚くべきメカニズムを発見したのです。さらに興味深いことに、このウイルスの企みを阻止する鍵が、既存の抗がん剤候補薬にあるかもしれないというのです。2025年2月20日に権威ある科学誌「Cell」に掲載されたこの研究は、B型肝炎治療に新たな光を当てるかもしれません。論文タイトルは「A Nucleosome Switch Primes Hepatitis B Virus Infection(ヌクレオソームスイッチがB型肝炎ウイルス感染を準備する)」です。
「私たちは、HBV遺伝子制御のメカニズムに関する重要な詳細だけでなく、HBVに対する新しい治療ツールへの有望な道筋も発見できたことを大変嬉しく思います」と、ロックフェラー大学ゲノム構造・動態研究室長のヴィヴィアナ・I・リスカ 博士(Viviana I. Risca, PhD)は述べています。
鶏が先か、卵が先かの問題
B型肝炎感染は、生物学的なパラドックスを抱えています。研究によると、宿主細胞は、ウイルスタンパク質HBx(エイチビーエックス)によって宿主の防御が打ち消されない限り、ウイルスの遺伝子発現を停止させます。しかし、そのHBxタンパク質は、ウイルスの遺伝子発現なしには産生できません。これはまさに鶏が先か卵が先かの問題であり――HBxは自身を作り
B型肝炎ウイルス――この小さな侵略者は、世界で3億人もの人々の肝臓に静かに、しかし確実に感染を広げ、時には肝硬変や肝がんといった深刻な病気を引き起こします。ワクチンや治療薬は存在するものの、HBVが細胞の中でどのようにして生き続け、悪さをするのか、その巧妙な「隠れ蓑戦略」の全貌は長年謎に包まれていました。しかし、ついにその一端が明らかになりました。ロックフェラー大学などの共同研究チームが、HBVがまるで宿主の細胞核を「乗っ取る」かのように、自身の遺伝子を活性化させる驚くべきメカニズムを発見したのです。さらに興味深いことに、このウイルスの企みを阻止する鍵が、既存の抗がん剤候補薬にあるかもしれないというのです。2025年2月20日に権威ある科学誌「Cell」に掲載されたこの研究は、B型肝炎治療に新たな光を当てるかもしれません。論文タイトルは「A Nucleosome Switch Primes Hepatitis B Virus Infection(ヌクレオソームスイッチがB型肝炎ウイルス感染を準備する)」です。
「私たちは、HBV遺伝子制御のメカニズムに関する重要な詳細だけでなく、HBVに対する新しい治療ツールへの有望な道筋も発見できたことを大変嬉しく思います」と、ロックフェラー大学ゲノム構造・動態研究室長のヴィヴィアナ・I・リスカ 博士(Viviana I. Risca, PhD)は述べています。
鶏が先か、卵が先かの問題
B型肝炎感染は、生物学的なパラドックスを抱えています。研究によると、宿主細胞は、ウイルスタンパク質HBx(エイチビーエックス)によって宿主の防御が打ち消されない限り、ウイルスの遺伝子発現を停止させます。しかし、そのHBxタンパク質は、ウイルスの遺伝子発現なしには産生できません。これはまさに鶏が先か卵が先かの問題であり――HBxは自身を作り
 いまだ世界中で猛威を振るう感染症、結核。その病原菌である結核菌は、咳やくしゃみによって空気中に放出された後、どのようにして過酷な環境を生き延び、次の人へと感染を広げていくのでしょうか? この「空中サバイバル術」の謎を解き明かすことは、結核の「感染の鎖」を断ち切る上で極めて重要です。マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究チームが、この長年の疑問に迫る画期的な発見をしました。彼らは、結核菌が空中を漂う際に生存に不可欠となる一群の「サバイバル遺伝子」を特定。これらの遺伝子の多くは、これまで病気を引き起こす上では重要ではないと考えられていましたが、実は空気中での生存、つまり「感染力」にこそ深く関わっていたのです。この発見は、結核菌の弱点を突き、感染拡大そのものを防ぐ新しい治療薬開発への道を開くかもしれません。
2025年3月7日に「米国科学アカデミー紀要(Proceedings of the National Academy of Sciences)」で発表されたこの研究は、結核との戦いに新たな光を当てるものです。論文タイトルは「Candidate Transmission Survival Genome of Mycobacterium tuberculosis(結核菌の伝播生存候補ゲノム)」です。
「病原体が空気中を循環する際に、これらの急激な変化をどのように生き延びるかという点で、私たちは空気感染に対して盲点を持っていました」と、MITの流体病原体伝播研究室長であり、土木環境工学および機械工学の准教授、そしてMIT医療工学・科学研究所のコアファカルティメンバーでもあるリディア・ブロイバ(Lydia Bourouiba)博士は述べています。「今、私たちはこれらの遺伝子を通じて、結核菌が自身を守るためにどのようなツールを使っているのか、その手がかりを得ました」。
「も
いまだ世界中で猛威を振るう感染症、結核。その病原菌である結核菌は、咳やくしゃみによって空気中に放出された後、どのようにして過酷な環境を生き延び、次の人へと感染を広げていくのでしょうか? この「空中サバイバル術」の謎を解き明かすことは、結核の「感染の鎖」を断ち切る上で極めて重要です。マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究チームが、この長年の疑問に迫る画期的な発見をしました。彼らは、結核菌が空中を漂う際に生存に不可欠となる一群の「サバイバル遺伝子」を特定。これらの遺伝子の多くは、これまで病気を引き起こす上では重要ではないと考えられていましたが、実は空気中での生存、つまり「感染力」にこそ深く関わっていたのです。この発見は、結核菌の弱点を突き、感染拡大そのものを防ぐ新しい治療薬開発への道を開くかもしれません。
2025年3月7日に「米国科学アカデミー紀要(Proceedings of the National Academy of Sciences)」で発表されたこの研究は、結核との戦いに新たな光を当てるものです。論文タイトルは「Candidate Transmission Survival Genome of Mycobacterium tuberculosis(結核菌の伝播生存候補ゲノム)」です。
「病原体が空気中を循環する際に、これらの急激な変化をどのように生き延びるかという点で、私たちは空気感染に対して盲点を持っていました」と、MITの流体病原体伝播研究室長であり、土木環境工学および機械工学の准教授、そしてMIT医療工学・科学研究所のコアファカルティメンバーでもあるリディア・ブロイバ(Lydia Bourouiba)博士は述べています。「今、私たちはこれらの遺伝子を通じて、結核菌が自身を守るためにどのようなツールを使っているのか、その手がかりを得ました」。
「も
 いつものレタスが、まるでスーパーフードに変身?そんな夢のような話が、遺伝子編集技術の力で現実になるかもしれません。ヘブライ大学エルサレム校の研究チームが、人気の野菜レタスの栄養価を劇的に向上させることに成功しました。彼らは、最先端のCRISPR遺伝子編集技術を駆使し、レタスが本来持つ遺伝子をわずかに調整するだけで、視力や免疫に重要なβ-カロテン(プロビタミンA: provitamin A)を2.7倍、目の健康を守るゼアキサンチンを大幅に、そして美肌や風邪予防に欠かせないアスコルビン酸(ビタミンC)をなんと6.9倍にも増やすことに成功したのです。しかも、見た目や味、育ち方は従来のレタスと変わらないというから驚きです。この「次世代レタス」は、世界中で問題となっている「隠れ飢餓」と呼ばれる微量栄養素の不足を解消する切り札となるかもしれません。
2025年3月3日に「Plant Biotechnology Journal article」誌に掲載されたこの研究は、アレクサンダー・ヴァインシュタイン教授(Alexander Vainstein)が主導し、単一の栄養素ではなく複数の栄養価を同時に高めるという画期的なアプローチで達成されました。論文タイトルは「Combined Enhancement of Ascorbic Acid, β-carotene and Zeaxanthin in Gene-Edited Lettuce(遺伝子編集レタスにおけるアスコルビン酸、β-カロテン、ゼアキサンチンの複合的増強)」です。
CRISPRは、DNAを編集するための強力かつ精密なツールです。外来DNAを導入する従来の遺伝子組換え(GMO: genetic modification)技術とは異なり、CRISPRは科学者が植物自身の遺伝コード内で標的を定めた変更を行うことを可能にします。こ
いつものレタスが、まるでスーパーフードに変身?そんな夢のような話が、遺伝子編集技術の力で現実になるかもしれません。ヘブライ大学エルサレム校の研究チームが、人気の野菜レタスの栄養価を劇的に向上させることに成功しました。彼らは、最先端のCRISPR遺伝子編集技術を駆使し、レタスが本来持つ遺伝子をわずかに調整するだけで、視力や免疫に重要なβ-カロテン(プロビタミンA: provitamin A)を2.7倍、目の健康を守るゼアキサンチンを大幅に、そして美肌や風邪予防に欠かせないアスコルビン酸(ビタミンC)をなんと6.9倍にも増やすことに成功したのです。しかも、見た目や味、育ち方は従来のレタスと変わらないというから驚きです。この「次世代レタス」は、世界中で問題となっている「隠れ飢餓」と呼ばれる微量栄養素の不足を解消する切り札となるかもしれません。
2025年3月3日に「Plant Biotechnology Journal article」誌に掲載されたこの研究は、アレクサンダー・ヴァインシュタイン教授(Alexander Vainstein)が主導し、単一の栄養素ではなく複数の栄養価を同時に高めるという画期的なアプローチで達成されました。論文タイトルは「Combined Enhancement of Ascorbic Acid, β-carotene and Zeaxanthin in Gene-Edited Lettuce(遺伝子編集レタスにおけるアスコルビン酸、β-カロテン、ゼアキサンチンの複合的増強)」です。
CRISPRは、DNAを編集するための強力かつ精密なツールです。外来DNAを導入する従来の遺伝子組換え(GMO: genetic modification)技術とは異なり、CRISPRは科学者が植物自身の遺伝コード内で標的を定めた変更を行うことを可能にします。こ
 ついつい愛犬におやつをあげすぎてしまう…でも、もしかしたらその「食いしん坊」な性格、遺伝子が関係しているかもしれません。そして驚くべきことに、その遺伝子は私たち人間の肥満にも深く関わっている可能性があるのです。ケンブリッジ大学の研究チームが、人気犬種ラブラドール・レトリバーの肥満と遺伝子の関係を調査した結果、肥満に強く関連する「DENND1B(デンディーワンビー)」という遺伝子を発見しました。この遺伝子は人間にも存在し、やはり肥満との関連が示唆されています。DENND1B遺伝子は、脳内で食欲やエネルギー消費をコントロールする重要な経路に影響を与えることが判明。つまり、犬の肥満研究が、人間の肥満メカニズム解明の大きな手がかりとなるかもしれないのです。
2025年3月6日に科学誌「Science」に掲載されたこの研究は、種を超えた肥満の謎に迫る興味深い内容となっています。論文タイトルは「Canine Genome-Wide Association Study Identifies DENND1B As an Obesity Gene in Dogs and Humans(イヌのゲノムワイド関連解析によりDENND1Bをイヌとヒトにおける肥満遺伝子として同定)」です。
「これらの遺伝子は、体重減少薬の直接的な標的としてはすぐに明らかになるものではありません。なぜなら、これらは体内の他の重要な生物学的プロセスを制御しており、干渉すべきではないからです。しかし、この結果は、食欲と体重を制御する上で基本的な脳の経路の重要性を強調しています」と、ケンブリッジ大学生理学・発生・神経科学科のアリス・マクレラン博士(Alyce McClellan, PhD)は述べています。彼女はこの報告書の共同筆頭著者です。DENND1Bは、体内のエネルギーバランスを調節する役割を担う脳の経路であるレ
ついつい愛犬におやつをあげすぎてしまう…でも、もしかしたらその「食いしん坊」な性格、遺伝子が関係しているかもしれません。そして驚くべきことに、その遺伝子は私たち人間の肥満にも深く関わっている可能性があるのです。ケンブリッジ大学の研究チームが、人気犬種ラブラドール・レトリバーの肥満と遺伝子の関係を調査した結果、肥満に強く関連する「DENND1B(デンディーワンビー)」という遺伝子を発見しました。この遺伝子は人間にも存在し、やはり肥満との関連が示唆されています。DENND1B遺伝子は、脳内で食欲やエネルギー消費をコントロールする重要な経路に影響を与えることが判明。つまり、犬の肥満研究が、人間の肥満メカニズム解明の大きな手がかりとなるかもしれないのです。
2025年3月6日に科学誌「Science」に掲載されたこの研究は、種を超えた肥満の謎に迫る興味深い内容となっています。論文タイトルは「Canine Genome-Wide Association Study Identifies DENND1B As an Obesity Gene in Dogs and Humans(イヌのゲノムワイド関連解析によりDENND1Bをイヌとヒトにおける肥満遺伝子として同定)」です。
「これらの遺伝子は、体重減少薬の直接的な標的としてはすぐに明らかになるものではありません。なぜなら、これらは体内の他の重要な生物学的プロセスを制御しており、干渉すべきではないからです。しかし、この結果は、食欲と体重を制御する上で基本的な脳の経路の重要性を強調しています」と、ケンブリッジ大学生理学・発生・神経科学科のアリス・マクレラン博士(Alyce McClellan, PhD)は述べています。彼女はこの報告書の共同筆頭著者です。DENND1Bは、体内のエネルギーバランスを調節する役割を担う脳の経路であるレ
 生命の設計図「ゲノム」を自在に編集する技術は、病気の治療から新品種の開発まで、私たちの未来を大きく変える可能性を秘めています。その代表格であるCRISPR技術に続き、新たな「ゲノム編集のスター候補」が登場しました。マサチューセッツ工科大学(MIT)とブロード研究所の科学者たちが、自然界の広大な遺伝情報の中から、古代のウイルスなどが持つユニークなDNA改変システム「TIGRシステム」を発見したのです。このTIGRシステムは、RNAを道しるべにDNAの特定の部分を狙い撃ちし、様々な操作を加えることができる「プログラム可能なタンパク質」。CRISPRよりもコンパクトで、部品交換のように機能を組み合わせやすいモジュール構造を持つため、治療応用へのハードルが低いと期待されています。2025年2月27日に科学誌「Science」で発表されたこの発見は、ゲノム編集ツールボックスに強力な新メンバーを加えることになるかもしれません。
論文タイトルは「TIGR-Tas: A Family of Modular RNA-Guided DNA-Targeting Systems in Prokaryotes and Their Viruses(TIGR-Tas:原核生物とそのウイルスにおけるモジュール型RNA誘導DNA標的化システムのファミリー)」です。研究を率いたMITのフェン・チャン博士(Feng Zhang, PhD)は、このシステムの多機能性と応用の広さに大きな期待を寄せています。特に、TIGRシステムを構成するTIGR関連(Tas)タンパク質は、RNAガイドと結合する部分とDNAを切断する部分などが独立しており、まるでレゴブロックのように機能を組み替えられるため、ツール開発を加速させる可能性があります。
「自然は実に素晴らしいものです」と、マクガヴァン研究所およびハワード・ヒュー
生命の設計図「ゲノム」を自在に編集する技術は、病気の治療から新品種の開発まで、私たちの未来を大きく変える可能性を秘めています。その代表格であるCRISPR技術に続き、新たな「ゲノム編集のスター候補」が登場しました。マサチューセッツ工科大学(MIT)とブロード研究所の科学者たちが、自然界の広大な遺伝情報の中から、古代のウイルスなどが持つユニークなDNA改変システム「TIGRシステム」を発見したのです。このTIGRシステムは、RNAを道しるべにDNAの特定の部分を狙い撃ちし、様々な操作を加えることができる「プログラム可能なタンパク質」。CRISPRよりもコンパクトで、部品交換のように機能を組み合わせやすいモジュール構造を持つため、治療応用へのハードルが低いと期待されています。2025年2月27日に科学誌「Science」で発表されたこの発見は、ゲノム編集ツールボックスに強力な新メンバーを加えることになるかもしれません。
論文タイトルは「TIGR-Tas: A Family of Modular RNA-Guided DNA-Targeting Systems in Prokaryotes and Their Viruses(TIGR-Tas:原核生物とそのウイルスにおけるモジュール型RNA誘導DNA標的化システムのファミリー)」です。研究を率いたMITのフェン・チャン博士(Feng Zhang, PhD)は、このシステムの多機能性と応用の広さに大きな期待を寄せています。特に、TIGRシステムを構成するTIGR関連(Tas)タンパク質は、RNAガイドと結合する部分とDNAを切断する部分などが独立しており、まるでレゴブロックのように機能を組み替えられるため、ツール開発を加速させる可能性があります。
「自然は実に素晴らしいものです」と、マクガヴァン研究所およびハワード・ヒュー
 ストレス社会と言われる現代。同じ困難に直面しても、心が折れてしまう人と、しなやかに乗り越える人がいます。この「心の強さ(レジリエンス)」の違いは、一体どこから来るのでしょうか?カナダの研究チームが、その謎を解く鍵の一つを脳の中で見つけました。それは、脳を外部の有害物質から守る「血液脳関門」に存在する「カンナビノイド受容体1型(CB1: cannabinoid receptor type 1)」というタンパク質。なんと、このCB1受容体が、ストレスによる心の不調を防ぐ「門番」のような役割を果たしている可能性があるというのです。2025年2月27日に「Nature Neuroscience」誌で発表されたこの研究は、ストレスによる不安や抑うつ症状の新たな予防・治療法開発につながるかもしれません。
論文タイトルは「Astrocytic Cannabinoid Receptor 1 Promotes Resilience by Dampening Stress-Induced Blood–Brain Barrier Alterations(アストロサイトのカンナビノイド受容体1はストレス誘発性の血液脳関門変化を抑制することでレジリエンスを促進する)」です。研究リーダーであるラヴァル大学のキャロライン・メナール教授(Caroline Ménard)によると、慢性的なストレスはこの血液脳関門の機能を弱らせ、炎症を引き起こす物質の侵入を許し、結果として心の不調につながるといいます。
CB1受容体はニューロンに豊富に存在しますが、脳の血管とニューロン間のコミュニケーションを可能にする星形の細胞であるアストロサイトにも見られます。「アストロサイトは関門の不可欠な構成要素です」とメナール教授は説明します。「ストレスに強いマウスは、抑うつ様行動を示すマウスやストレスにさらされていないマウ
ストレス社会と言われる現代。同じ困難に直面しても、心が折れてしまう人と、しなやかに乗り越える人がいます。この「心の強さ(レジリエンス)」の違いは、一体どこから来るのでしょうか?カナダの研究チームが、その謎を解く鍵の一つを脳の中で見つけました。それは、脳を外部の有害物質から守る「血液脳関門」に存在する「カンナビノイド受容体1型(CB1: cannabinoid receptor type 1)」というタンパク質。なんと、このCB1受容体が、ストレスによる心の不調を防ぐ「門番」のような役割を果たしている可能性があるというのです。2025年2月27日に「Nature Neuroscience」誌で発表されたこの研究は、ストレスによる不安や抑うつ症状の新たな予防・治療法開発につながるかもしれません。
論文タイトルは「Astrocytic Cannabinoid Receptor 1 Promotes Resilience by Dampening Stress-Induced Blood–Brain Barrier Alterations(アストロサイトのカンナビノイド受容体1はストレス誘発性の血液脳関門変化を抑制することでレジリエンスを促進する)」です。研究リーダーであるラヴァル大学のキャロライン・メナール教授(Caroline Ménard)によると、慢性的なストレスはこの血液脳関門の機能を弱らせ、炎症を引き起こす物質の侵入を許し、結果として心の不調につながるといいます。
CB1受容体はニューロンに豊富に存在しますが、脳の血管とニューロン間のコミュニケーションを可能にする星形の細胞であるアストロサイトにも見られます。「アストロサイトは関門の不可欠な構成要素です」とメナール教授は説明します。「ストレスに強いマウスは、抑うつ様行動を示すマウスやストレスにさらされていないマウ
 失われた視力を取り戻す――そんな願いを叶えるかもしれない「視細胞補充療法」。実験室で育てた視細胞(光受容細胞: photoreceptors)を移植するこの治療法は、網膜の病気で光を失った人々に希望を与えています。しかし、ヒトの細胞を使った治療法の開発には、動物実験での安全性の確認が不可欠です。ところが、ヒトの細胞は他の動物では拒絶されてしまうため、十分な検証が難しいという壁がありました。このジレンマを打ち破るため、ウィスコンシン大学マディソン校とモーグリッジ研究所の研究チームが、ヒトとよく似た網膜構造を持つ「ブタ」に注目。世界で初めて、ブタの幹細胞から実験室で「ミニ網膜(網膜オルガノイド: retinal organoids)」を作り出すことに成功しました。この「ブタ版ミニ網膜」は、ヒトの視細胞治療研究を大きく前進させ、将来的には失明治療の新たな道を切り開くかもしれません。
2025年3月6日に「Stem Cell Reports」誌で発表されたこの画期的な研究について、詳しく見ていきましょう。論文タイトルは「Robust Generation of Photoreceptor-Dominant Retinal Organoids from Porcine Induced Pluripotent Stem Cells(ブタ人工多能性幹細胞からの視細胞優位な網膜オルガノイドの頑健な作製)」です。研究を率いたウィスコンシン大学マディソン校マクファーソン眼研究所所長であり、眼科・視覚科学の教授でもあるデイビッド・ガム 医学博士(David Gamm, MD PhD)は、ブタのモデルがヒト治療薬開発の鍵となると期待を寄せています。
「ブタの網膜オルガノイドが作製されたのはこれが初めてです」と、ガム研究室の大学院生であり、本研究の筆頭著者であるキム・エドワーズ氏(Kim E
失われた視力を取り戻す――そんな願いを叶えるかもしれない「視細胞補充療法」。実験室で育てた視細胞(光受容細胞: photoreceptors)を移植するこの治療法は、網膜の病気で光を失った人々に希望を与えています。しかし、ヒトの細胞を使った治療法の開発には、動物実験での安全性の確認が不可欠です。ところが、ヒトの細胞は他の動物では拒絶されてしまうため、十分な検証が難しいという壁がありました。このジレンマを打ち破るため、ウィスコンシン大学マディソン校とモーグリッジ研究所の研究チームが、ヒトとよく似た網膜構造を持つ「ブタ」に注目。世界で初めて、ブタの幹細胞から実験室で「ミニ網膜(網膜オルガノイド: retinal organoids)」を作り出すことに成功しました。この「ブタ版ミニ網膜」は、ヒトの視細胞治療研究を大きく前進させ、将来的には失明治療の新たな道を切り開くかもしれません。
2025年3月6日に「Stem Cell Reports」誌で発表されたこの画期的な研究について、詳しく見ていきましょう。論文タイトルは「Robust Generation of Photoreceptor-Dominant Retinal Organoids from Porcine Induced Pluripotent Stem Cells(ブタ人工多能性幹細胞からの視細胞優位な網膜オルガノイドの頑健な作製)」です。研究を率いたウィスコンシン大学マディソン校マクファーソン眼研究所所長であり、眼科・視覚科学の教授でもあるデイビッド・ガム 医学博士(David Gamm, MD PhD)は、ブタのモデルがヒト治療薬開発の鍵となると期待を寄せています。
「ブタの網膜オルガノイドが作製されたのはこれが初めてです」と、ガム研究室の大学院生であり、本研究の筆頭著者であるキム・エドワーズ氏(Kim E
 「統合失調症」と聞くと、どんなイメージを持つでしょうか?実はこの病気、一人ひとり症状の現れ方が大きく異なり、まるで「万華鏡」のようです。ある人は幻覚に、ある人は思考の混乱に悩まされるなど、その複雑さが長年、治療の難しさにもつながっていました。「統合失調症は一つではない、多くの顔を持つ」。そんな考え方のもと、スイスの研究者たちが、世界規模の脳画像データを用いて、この症状の多様性が脳の「形」の違いとしてどのように現れるのかを明らかにしました。この発見は、画一的な治療から、一人ひとりの脳の特徴に合わせた「オーダーメイド治療」への道を開くかもしれません。
2025年2月26日に「American Journal of Psychiatry」誌に掲載されたこの研究は、チューリッヒ大学精神科病院のヴォルフガング・オムラー医学博士(Wolfgang Omlor, MD , PhD)らが主導し、論文タイトルは「Estimating Multimodal Structural Brain Variability in Schizophrenia Spectrum Disorders: A Worldwide ENIGMA Study(統合失調症スペクトラム障害におけるマルチモーダルな脳構造の多様性の推定:世界規模のENIGMA研究)」と題されています。研究チームは、それぞれの脳のタイプに最適な治療法を見つける精密医療(プレシジョン・メディシン)の実現には、脳の個人差と共通性の両面からのアプローチが不可欠だと強調しています。
患者の脳構造に関する包括的な国際研究
国際的な多施設共同研究において、オムラー博士とチューリッヒ大学の研究チームは、統合失調症患者の脳構造の多様性を調査しました。すなわち、どの脳ネットワークが高い個別性を示し、どの脳ネットワークが高い類似性を示すのか、とい
「統合失調症」と聞くと、どんなイメージを持つでしょうか?実はこの病気、一人ひとり症状の現れ方が大きく異なり、まるで「万華鏡」のようです。ある人は幻覚に、ある人は思考の混乱に悩まされるなど、その複雑さが長年、治療の難しさにもつながっていました。「統合失調症は一つではない、多くの顔を持つ」。そんな考え方のもと、スイスの研究者たちが、世界規模の脳画像データを用いて、この症状の多様性が脳の「形」の違いとしてどのように現れるのかを明らかにしました。この発見は、画一的な治療から、一人ひとりの脳の特徴に合わせた「オーダーメイド治療」への道を開くかもしれません。
2025年2月26日に「American Journal of Psychiatry」誌に掲載されたこの研究は、チューリッヒ大学精神科病院のヴォルフガング・オムラー医学博士(Wolfgang Omlor, MD , PhD)らが主導し、論文タイトルは「Estimating Multimodal Structural Brain Variability in Schizophrenia Spectrum Disorders: A Worldwide ENIGMA Study(統合失調症スペクトラム障害におけるマルチモーダルな脳構造の多様性の推定:世界規模のENIGMA研究)」と題されています。研究チームは、それぞれの脳のタイプに最適な治療法を見つける精密医療(プレシジョン・メディシン)の実現には、脳の個人差と共通性の両面からのアプローチが不可欠だと強調しています。
患者の脳構造に関する包括的な国際研究
国際的な多施設共同研究において、オムラー博士とチューリッヒ大学の研究チームは、統合失調症患者の脳構造の多様性を調査しました。すなわち、どの脳ネットワークが高い個別性を示し、どの脳ネットワークが高い類似性を示すのか、とい
 「体全体の健康」とは言うけれど、実は私たちの心臓や肺、肝臓といった臓器は、それぞれ独自のペースで歳を重ねているようです。そして驚くべきことに、その「臓器の年齢」を血液一滴から読み解き、将来の病気のリスクを予測する技術が現実のものとなりつつあります。ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL)を中心とする研究チームが発表した最新の研究では、特定の臓器の老化が、その臓器だけでなく全身のさまざまな病気、例えば肺がんや心臓病、さらには認知症のリスクとも関連していることが明らかになりました。これは、未来の健康診断のあり方を大きく変え、よりパーソナルな病気予防への道を開くかもしれません。2025年3月に「The Lancet Digital Health」誌に掲載されたこの研究について、詳しく見ていきましょう。
論文タイトルは「Proteomic Organ-Specific Ageing Signatures and 20-Year Risk of Age-Related Diseases: The Whitehall II Observational Cohort Study(プロテオミクスによる臓器特異的な老化シグネチャーと加齢関連疾患の20年リスク:ホワイトホールII観察コホート研究)」です。
筆頭著者であるUCL脳科学部のミカ・キヴィマキ教授(Mika Kivimaki)は、「私たちの臓器は統合されたシステムとして機能していますが、それぞれ異なる速度で老化することがあります。特定の臓器の老化は、数多くの加齢関連疾患の一因となる可能性があるため、健康のあらゆる側面に気を配ることが重要です」と述べています。
「私たちは、迅速かつ簡単な血液検査で、特定の臓器が予想よりも早く老化しているかどうかを特定できることを見出しました。将来、このような血液検査が多くの病気の予防に重要
「体全体の健康」とは言うけれど、実は私たちの心臓や肺、肝臓といった臓器は、それぞれ独自のペースで歳を重ねているようです。そして驚くべきことに、その「臓器の年齢」を血液一滴から読み解き、将来の病気のリスクを予測する技術が現実のものとなりつつあります。ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL)を中心とする研究チームが発表した最新の研究では、特定の臓器の老化が、その臓器だけでなく全身のさまざまな病気、例えば肺がんや心臓病、さらには認知症のリスクとも関連していることが明らかになりました。これは、未来の健康診断のあり方を大きく変え、よりパーソナルな病気予防への道を開くかもしれません。2025年3月に「The Lancet Digital Health」誌に掲載されたこの研究について、詳しく見ていきましょう。
論文タイトルは「Proteomic Organ-Specific Ageing Signatures and 20-Year Risk of Age-Related Diseases: The Whitehall II Observational Cohort Study(プロテオミクスによる臓器特異的な老化シグネチャーと加齢関連疾患の20年リスク:ホワイトホールII観察コホート研究)」です。
筆頭著者であるUCL脳科学部のミカ・キヴィマキ教授(Mika Kivimaki)は、「私たちの臓器は統合されたシステムとして機能していますが、それぞれ異なる速度で老化することがあります。特定の臓器の老化は、数多くの加齢関連疾患の一因となる可能性があるため、健康のあらゆる側面に気を配ることが重要です」と述べています。
「私たちは、迅速かつ簡単な血液検査で、特定の臓器が予想よりも早く老化しているかどうかを特定できることを見出しました。将来、このような血液検査が多くの病気の予防に重要
 言葉や学習の困難などを引き起こす遺伝性の自閉症スペクトラム障害、脆弱X症候群。この長年多くの人々を苦しめてきた病気に対し、光明が差し込むかもしれません。マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究者たちが、20年以上にわたる探求の末、脳内の特定の「スイッチ」を操作することで、この病気の症状を改善する新たな方法を発見しました。まるで複雑なパズルのピースがはまるように、過去の研究成果と結びついたこの発見は、脳内のタンパク質合成のバランスを整え、神経細胞の働きを正常化させる可能性を秘めています。2025年2月20日にthe journal Nature Physics誌で発表されたこの研究は、NMDA受容体(NMDA receptors)と呼ばれる脳の重要な受容体の特定の部品(サブユニット)に注目。
この部品の働きを高めることで、脆弱X症候群モデルマウスの脳内で過剰になっていたタンパク質の大量生産を抑え、神経活動やけいれんの起こりやすさといった症状を改善することに成功しました。このオープンアクセス論文のタイトルは「Non-Ionotropic Signaling Through the NMDA Receptor Glun2b Carboxy-Terminal Domain Drives Dendritic Spine Plasticity and Reverses Fragile X Phenotypes(NMDA受容体GluN2Bカルボキシ末端ドメインを介した非イオンチャネル型シグナル伝達は樹状突起スパインの可塑性を駆動し脆弱X症候群の表現型を回復させる)」です。
研究の背景
「この研究で最も満足していることの一つは、パズルのピースがこれまでの研究成果と実に見事に合致したことです」と、本研究の責任著者であり、MIT脳・認知科学科のピカワープロフェッサーであるマーク
言葉や学習の困難などを引き起こす遺伝性の自閉症スペクトラム障害、脆弱X症候群。この長年多くの人々を苦しめてきた病気に対し、光明が差し込むかもしれません。マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究者たちが、20年以上にわたる探求の末、脳内の特定の「スイッチ」を操作することで、この病気の症状を改善する新たな方法を発見しました。まるで複雑なパズルのピースがはまるように、過去の研究成果と結びついたこの発見は、脳内のタンパク質合成のバランスを整え、神経細胞の働きを正常化させる可能性を秘めています。2025年2月20日にthe journal Nature Physics誌で発表されたこの研究は、NMDA受容体(NMDA receptors)と呼ばれる脳の重要な受容体の特定の部品(サブユニット)に注目。
この部品の働きを高めることで、脆弱X症候群モデルマウスの脳内で過剰になっていたタンパク質の大量生産を抑え、神経活動やけいれんの起こりやすさといった症状を改善することに成功しました。このオープンアクセス論文のタイトルは「Non-Ionotropic Signaling Through the NMDA Receptor Glun2b Carboxy-Terminal Domain Drives Dendritic Spine Plasticity and Reverses Fragile X Phenotypes(NMDA受容体GluN2Bカルボキシ末端ドメインを介した非イオンチャネル型シグナル伝達は樹状突起スパインの可塑性を駆動し脆弱X症候群の表現型を回復させる)」です。
研究の背景
「この研究で最も満足していることの一つは、パズルのピースがこれまでの研究成果と実に見事に合致したことです」と、本研究の責任著者であり、MIT脳・認知科学科のピカワープロフェッサーであるマーク
 文字を読むのが難しい、書くのが苦手…もしかしたら、それは「ディスレクシア」かもしれません。しかし、この学習障害の「顔」は一つではなく、その定義も長年、専門家の間でも揺れ動いてきました。その結果、支援が必要な子供たちが適切なサポートを受けられなかったり、地域によって対応に差が出たりする「ディスレクシア格差」とも呼べる状況が生まれています。この見過ごせない問題に、英国の研究チームが一石を投じました。「まず、ディスレクシアとは何か、その共通理解から始めよう」。国際的な専門家たちの知恵を結集し、より正確で包括的な新しい定義を打ち立てたのです。この新たな定義が、ディスレクシアに悩む多くの人々とその家族にとって、より良い未来を切り開く第一歩となるかもしれません。バーミンガム大学などが参加したこの研究は、2025年2月25日発行の学術誌「The Journal of Child Psychology and The open-access article」に掲載されました。論文タイトルは「Toward a Consensus on Dyslexia: Findings from a Delphi Study(ディスレクシアに関するコンセンサスに向けて:デルファイ調査の結果)」です。
研究を主導したバーミンガム大学の教育心理学教授であるジュリア・キャロル氏(Julia Carroll)は、「2009年のローズ・レビュー以来、ディスレクシアを定義する新たな試みはなされていませんでした。このレビューは定義を提供し、ディスレクシアを特定し支援するための専門教員の必要性を主張しました。ローズ定義は実践に大きな影響を与えたものの、過去15年間にわたって批判を集め、普遍的に受け入れられているわけではありません」と述べています。
「これに加えて、イングランド、ウェールズ、北アイルランドでは、デ
文字を読むのが難しい、書くのが苦手…もしかしたら、それは「ディスレクシア」かもしれません。しかし、この学習障害の「顔」は一つではなく、その定義も長年、専門家の間でも揺れ動いてきました。その結果、支援が必要な子供たちが適切なサポートを受けられなかったり、地域によって対応に差が出たりする「ディスレクシア格差」とも呼べる状況が生まれています。この見過ごせない問題に、英国の研究チームが一石を投じました。「まず、ディスレクシアとは何か、その共通理解から始めよう」。国際的な専門家たちの知恵を結集し、より正確で包括的な新しい定義を打ち立てたのです。この新たな定義が、ディスレクシアに悩む多くの人々とその家族にとって、より良い未来を切り開く第一歩となるかもしれません。バーミンガム大学などが参加したこの研究は、2025年2月25日発行の学術誌「The Journal of Child Psychology and The open-access article」に掲載されました。論文タイトルは「Toward a Consensus on Dyslexia: Findings from a Delphi Study(ディスレクシアに関するコンセンサスに向けて:デルファイ調査の結果)」です。
研究を主導したバーミンガム大学の教育心理学教授であるジュリア・キャロル氏(Julia Carroll)は、「2009年のローズ・レビュー以来、ディスレクシアを定義する新たな試みはなされていませんでした。このレビューは定義を提供し、ディスレクシアを特定し支援するための専門教員の必要性を主張しました。ローズ定義は実践に大きな影響を与えたものの、過去15年間にわたって批判を集め、普遍的に受け入れられているわけではありません」と述べています。
「これに加えて、イングランド、ウェールズ、北アイルランドでは、デ
 「食べても食べても満腹にならない」「ダイエットしてもなかなか痩せない」――その原因は、あなたの体が「満腹ホルモン」の声を無視しているからかもしれません。世界中で深刻な問題となっている肥満。その大部分に関わっているのが、食欲を抑えるホルモン「レプチン」が効かなくなる「レプチン抵抗性」という状態です。なぜレプチンが効かなくなるのか? この長年の謎に、ロックフェラー大学の研究チームが光を当てました。彼らは、レプチン抵抗性の背後にある脳内のメカニズムを解明し、さらに驚くべきことに、古くから知られる薬剤「ラパマイシン」が、マウス実験でこの抵抗性を打ち破り、レプチンの働きを復活させることを発見したのです。これは、肥満治療の新たな突破口となるかもしれません。2025年3月4日に「Cell Metabolism」誌で発表されたこの研究は、レプチン発見から30年以上経て、その真の力を解き放つ可能性を示唆しています。論文タイトルは「A Cellular and Molecular Basis of Leptin Resistance(レプチン抵抗性の細胞および分子的基盤)」です。
「私たちの研究以前は、食事誘発性肥満マウスにおける肥満の原因は不明であり、レプチン抵抗性がどのように発症し、どのように覆すことができるのかという理解において、決定的なギャップが残っていました」と、共同筆頭著者であり、フリードマン研究室の大学院生であるボーウェン・タン氏(Bowen Tan)は述べています。
「ジェフリー・M・フリードマン博士(Jeffrey M. Friedman, PhD)が1994年にこの強力なホルモンを発見したにもかかわらず、肥満患者のほとんどがレプチンに対する抵抗性を獲得しているため、人々が体重を減らすのを助けるというその完全な可能性は実現されていませんでした」と、共同筆頭著者であり、
「食べても食べても満腹にならない」「ダイエットしてもなかなか痩せない」――その原因は、あなたの体が「満腹ホルモン」の声を無視しているからかもしれません。世界中で深刻な問題となっている肥満。その大部分に関わっているのが、食欲を抑えるホルモン「レプチン」が効かなくなる「レプチン抵抗性」という状態です。なぜレプチンが効かなくなるのか? この長年の謎に、ロックフェラー大学の研究チームが光を当てました。彼らは、レプチン抵抗性の背後にある脳内のメカニズムを解明し、さらに驚くべきことに、古くから知られる薬剤「ラパマイシン」が、マウス実験でこの抵抗性を打ち破り、レプチンの働きを復活させることを発見したのです。これは、肥満治療の新たな突破口となるかもしれません。2025年3月4日に「Cell Metabolism」誌で発表されたこの研究は、レプチン発見から30年以上経て、その真の力を解き放つ可能性を示唆しています。論文タイトルは「A Cellular and Molecular Basis of Leptin Resistance(レプチン抵抗性の細胞および分子的基盤)」です。
「私たちの研究以前は、食事誘発性肥満マウスにおける肥満の原因は不明であり、レプチン抵抗性がどのように発症し、どのように覆すことができるのかという理解において、決定的なギャップが残っていました」と、共同筆頭著者であり、フリードマン研究室の大学院生であるボーウェン・タン氏(Bowen Tan)は述べています。
「ジェフリー・M・フリードマン博士(Jeffrey M. Friedman, PhD)が1994年にこの強力なホルモンを発見したにもかかわらず、肥満患者のほとんどがレプチンに対する抵抗性を獲得しているため、人々が体重を減らすのを助けるというその完全な可能性は実現されていませんでした」と、共同筆頭著者であり、
 生まれたときから、世界は光と闇だけ――。そんな過酷な運命を背負った4人の幼い子供たちに、希望の光が差し込みました。英国の研究チームが開発した画期的な遺伝子治療により、子供たちは失われた視力を取り戻し、人生を大きく変えるほどの喜びを手にしています。この治療は、特定の遺伝子の欠陥によって引き起こされる重度の網膜の病気に苦しむ子供たちにとって、まさに奇跡とも言える進歩です。手術後、ある少年は踊りだし、数ヶ月後にはお気に入りの車を見分けられるようになったといいます。この記事では、不可能を可能にした遺伝子治療の最前線と、それによって開かれる未来の可能性に迫ります。
この治療は、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL)眼科研究所とムーアフィールズ眼科病院が、メイヤGTx社(MeiraGTx)の支援を受けて実施したものです。子供たちは、AIPL1遺伝子の希少な遺伝的欠損により、生まれつき重度の視覚障害を抱えていました。この網膜ジストロフィーの一種である状態は、光と闇を区別する程度の視力しか持たずに生まれてくることを意味します。遺伝子の欠陥により網膜細胞が機能不全に陥り死滅するため、影響を受けた子供たちは出生時から法的に失明と認定されます。この新しい治療法は、網膜細胞がより良く機能し、より長く生存できるように設計されています。UCLの科学者たちによって開発されたこの手法は、鍵穴手術を通じて目の奥にある網膜に正常な遺伝子のコピーを注入するというものです。これらのコピーは無害なウイルスに内包されており、網膜細胞に浸透して欠陥のある遺伝子を置き換えることができます。
この状態は非常に稀であり、最初に特定された子供たちは海外の子供たちでした。潜在的な安全性の問題を軽減するため、最初の4人の子供たちは片目のみにこの新しい治療を受けました。4人全員が、治療を受けた目でその後3~4年にわ
生まれたときから、世界は光と闇だけ――。そんな過酷な運命を背負った4人の幼い子供たちに、希望の光が差し込みました。英国の研究チームが開発した画期的な遺伝子治療により、子供たちは失われた視力を取り戻し、人生を大きく変えるほどの喜びを手にしています。この治療は、特定の遺伝子の欠陥によって引き起こされる重度の網膜の病気に苦しむ子供たちにとって、まさに奇跡とも言える進歩です。手術後、ある少年は踊りだし、数ヶ月後にはお気に入りの車を見分けられるようになったといいます。この記事では、不可能を可能にした遺伝子治療の最前線と、それによって開かれる未来の可能性に迫ります。
この治療は、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL)眼科研究所とムーアフィールズ眼科病院が、メイヤGTx社(MeiraGTx)の支援を受けて実施したものです。子供たちは、AIPL1遺伝子の希少な遺伝的欠損により、生まれつき重度の視覚障害を抱えていました。この網膜ジストロフィーの一種である状態は、光と闇を区別する程度の視力しか持たずに生まれてくることを意味します。遺伝子の欠陥により網膜細胞が機能不全に陥り死滅するため、影響を受けた子供たちは出生時から法的に失明と認定されます。この新しい治療法は、網膜細胞がより良く機能し、より長く生存できるように設計されています。UCLの科学者たちによって開発されたこの手法は、鍵穴手術を通じて目の奥にある網膜に正常な遺伝子のコピーを注入するというものです。これらのコピーは無害なウイルスに内包されており、網膜細胞に浸透して欠陥のある遺伝子を置き換えることができます。
この状態は非常に稀であり、最初に特定された子供たちは海外の子供たちでした。潜在的な安全性の問題を軽減するため、最初の4人の子供たちは片目のみにこの新しい治療を受けました。4人全員が、治療を受けた目でその後3~4年にわ
 アルツハイマー病との闘いに、新たな希望の光が見えてきました。かつては診断も難しく、進行を止める手立ても限られていたこの病に対し、近年、検査法や治療法の開発が驚くべき速さで進んでいます。その最前線に立つ企業の一つが、アルツパス社(ALZpath Inc.)です。同社が開発した画期的な抗体は、血液一滴からアルツハイマー病の兆候を高精度かつ高感度に捉えることを可能にし、「診断の民主化」という大きな目標を掲げています。これは、高価で負担の大きかった従来の検査法に代わり、より多くの人々が早期に、そして手軽に検査を受けられる未来を意味します。この記事では、アルツハイマー病診断の新たな標準を目指すアルツパス社の挑戦と、その技術がもたらす可能性に迫ります。
アルツパス社は、血液によるアルツハイマー病の早期発見とモニタリングにおいてクラス最高レベルと確信する抗体を開発しました。この抗体は、確立されたアルツハイマー病バイオマーカーであるリン酸化タウ217(p-Tau217: phospho-Tau217)を標的としており、非常に高精度かつ高感度です。アルツパス社のp-Tau217抗体を用いた血液検査は、現在の標準的な検査法である陽電子放出断層撮影(PET: positron emission tomography)スキャンや脳脊髄液(CSF: cerebrospinal fluid)検査と比較して、比較的安価で、侵襲性が低く、実施が簡便で、大規模な実施にも容易に対応できると考えられています。アルツパス社のp-Tau217抗体を利用した、より広く利用可能で手頃な価格の血液検査の可能性は、早期診断とスクリーニングの支援にもつながるかもしれません。
2050年までに世界の認知症の罹患者数は約1億5000万人に達すると推定されており、アルツハイマー病がその最も一般的な形態です。現在の罹患者数と
アルツハイマー病との闘いに、新たな希望の光が見えてきました。かつては診断も難しく、進行を止める手立ても限られていたこの病に対し、近年、検査法や治療法の開発が驚くべき速さで進んでいます。その最前線に立つ企業の一つが、アルツパス社(ALZpath Inc.)です。同社が開発した画期的な抗体は、血液一滴からアルツハイマー病の兆候を高精度かつ高感度に捉えることを可能にし、「診断の民主化」という大きな目標を掲げています。これは、高価で負担の大きかった従来の検査法に代わり、より多くの人々が早期に、そして手軽に検査を受けられる未来を意味します。この記事では、アルツハイマー病診断の新たな標準を目指すアルツパス社の挑戦と、その技術がもたらす可能性に迫ります。
アルツパス社は、血液によるアルツハイマー病の早期発見とモニタリングにおいてクラス最高レベルと確信する抗体を開発しました。この抗体は、確立されたアルツハイマー病バイオマーカーであるリン酸化タウ217(p-Tau217: phospho-Tau217)を標的としており、非常に高精度かつ高感度です。アルツパス社のp-Tau217抗体を用いた血液検査は、現在の標準的な検査法である陽電子放出断層撮影(PET: positron emission tomography)スキャンや脳脊髄液(CSF: cerebrospinal fluid)検査と比較して、比較的安価で、侵襲性が低く、実施が簡便で、大規模な実施にも容易に対応できると考えられています。アルツパス社のp-Tau217抗体を利用した、より広く利用可能で手頃な価格の血液検査の可能性は、早期診断とスクリーニングの支援にもつながるかもしれません。
2050年までに世界の認知症の罹患者数は約1億5000万人に達すると推定されており、アルツハイマー病がその最も一般的な形態です。現在の罹患者数と
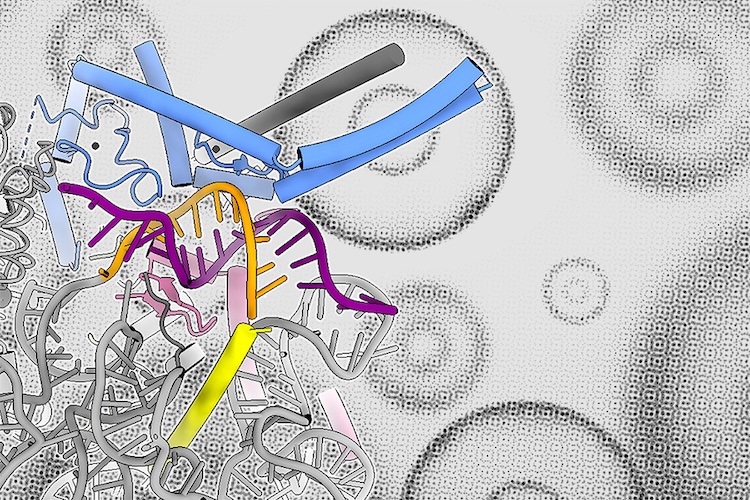 生命の設計図、遺伝子。その情報が正しく使われるためには、細胞内で日々行われている「RNAスプライシング」という巧妙な“編集作業”が欠かせません。この作業では、遺伝情報が写し取られたメッセンジャーRNAから不要な部分(イントロン)が切り取られ、必要な部分だけが精密につなぎ合わされます。この重要なプロセスを司るのが「スプライソソーム」という巨大な分子機械です。今回、マサチューセッツ工科大学(MIT)の生物学者たちは、このスプライソソームの働きをさらに精密に制御する、これまで知られていなかった新たな調節メカニズムを発見しました。驚くべきことに、この仕組みはヒトの遺伝子の約半数に関与し、動物から植物に至るまで広く存在しているというのです。この発見は、生命の基本的な仕組みであるRNAスプライシングが、私たちの想像以上に複雑で洗練されたものであることを示しています。
「ヒトのようなより複雑な生物におけるスプライシングは、酵母のような一部のモデル生物におけるスプライシングよりも複雑です。これは非常に保存された分子的プロセスであるにもかかわらずです。ヒトのスプライソソームには、特定のイントロンをより効率的に処理するための『付加機能』のようなものがあります。このようなシステムの利点の一つは、より複雑なタイプの遺伝子調節を可能にすることかもしれません」と、MITの大学院生であり、この研究の筆頭著者であるコナー・ケニー氏(Connor Kenny)は述べています。
MITの生物学のアンカス・アンド・ヘレン・ウィタカー記念教授であるクリストファー・バージ博士(Christopher Burge, PhD)が、この研究の責任著者です。この研究は2025年2月20日に「ネイチャー・コミュニケーションズ」誌に掲載されました。このオープンアクセス論文のタイトルは「LUC7 Proteins Def
生命の設計図、遺伝子。その情報が正しく使われるためには、細胞内で日々行われている「RNAスプライシング」という巧妙な“編集作業”が欠かせません。この作業では、遺伝情報が写し取られたメッセンジャーRNAから不要な部分(イントロン)が切り取られ、必要な部分だけが精密につなぎ合わされます。この重要なプロセスを司るのが「スプライソソーム」という巨大な分子機械です。今回、マサチューセッツ工科大学(MIT)の生物学者たちは、このスプライソソームの働きをさらに精密に制御する、これまで知られていなかった新たな調節メカニズムを発見しました。驚くべきことに、この仕組みはヒトの遺伝子の約半数に関与し、動物から植物に至るまで広く存在しているというのです。この発見は、生命の基本的な仕組みであるRNAスプライシングが、私たちの想像以上に複雑で洗練されたものであることを示しています。
「ヒトのようなより複雑な生物におけるスプライシングは、酵母のような一部のモデル生物におけるスプライシングよりも複雑です。これは非常に保存された分子的プロセスであるにもかかわらずです。ヒトのスプライソソームには、特定のイントロンをより効率的に処理するための『付加機能』のようなものがあります。このようなシステムの利点の一つは、より複雑なタイプの遺伝子調節を可能にすることかもしれません」と、MITの大学院生であり、この研究の筆頭著者であるコナー・ケニー氏(Connor Kenny)は述べています。
MITの生物学のアンカス・アンド・ヘレン・ウィタカー記念教授であるクリストファー・バージ博士(Christopher Burge, PhD)が、この研究の責任著者です。この研究は2025年2月20日に「ネイチャー・コミュニケーションズ」誌に掲載されました。このオープンアクセス論文のタイトルは「LUC7 Proteins Def
 細胞という小さな宇宙で、生命活動を支える無数の働き者、タンパク質。その機能は「形」だけでなく、細胞内の「居場所」によっても大きく左右されることがわかってきました。まるで都市のように区画化された細胞内で、タンパク質が適切な場所に配置されなければ、その能力を十分に発揮できません。しかし、この「タンパク質の住所録」を予測することは、これまで非常に困難な課題でした。そんな中、ホワイトヘッド研究所とマサチューセッツ工科大学(MIT)の研究者たちが、タンパク質の「アミノ酸コード」からその細胞内局在を高精度に予測し、さらには特定の場所に集まる新しいタンパク質を設計までできる画期的なAIモデル「ProtGPS」を開発しました。これは、病気の理解や治療法開発に新たな道を開く可能性を秘めています。
細胞内は、生物学の教科書でおなじみの細胞小器官(オルガネラ)に加え、特定の分子を集めて共同作業を行わせる、膜のないダイナミックな区画も多数存在します。あるタンパク質がどこに局在し、何と一緒にいるかを知ることは、そのタンパク質の役割や、健康な細胞あるいは病気の細胞における働きをより深く理解する上で役立ちますが、これまではこの情報を系統的に予測する方法がありませんでした。
一方、タンパク質の構造は半世紀以上にわたって研究され、その集大成として人工知能ツールであるAlphaFoldが登場しました。AlphaFoldは、タンパク質のアミノ酸配列からタンパク質の構造を予測できます。AlphaFoldや同様のモデルは、研究において広く利用されるツールとなっています。
タンパク質には、決まった構造に折りたたまれないアミノ酸領域も含まれており、これらの領域はタンパク質が細胞内のダイナミックな区画に加わるのを助ける上で重要です。ホワイトヘッド研究所のメンバーであるリチャード・ヤング氏(Richard
細胞という小さな宇宙で、生命活動を支える無数の働き者、タンパク質。その機能は「形」だけでなく、細胞内の「居場所」によっても大きく左右されることがわかってきました。まるで都市のように区画化された細胞内で、タンパク質が適切な場所に配置されなければ、その能力を十分に発揮できません。しかし、この「タンパク質の住所録」を予測することは、これまで非常に困難な課題でした。そんな中、ホワイトヘッド研究所とマサチューセッツ工科大学(MIT)の研究者たちが、タンパク質の「アミノ酸コード」からその細胞内局在を高精度に予測し、さらには特定の場所に集まる新しいタンパク質を設計までできる画期的なAIモデル「ProtGPS」を開発しました。これは、病気の理解や治療法開発に新たな道を開く可能性を秘めています。
細胞内は、生物学の教科書でおなじみの細胞小器官(オルガネラ)に加え、特定の分子を集めて共同作業を行わせる、膜のないダイナミックな区画も多数存在します。あるタンパク質がどこに局在し、何と一緒にいるかを知ることは、そのタンパク質の役割や、健康な細胞あるいは病気の細胞における働きをより深く理解する上で役立ちますが、これまではこの情報を系統的に予測する方法がありませんでした。
一方、タンパク質の構造は半世紀以上にわたって研究され、その集大成として人工知能ツールであるAlphaFoldが登場しました。AlphaFoldは、タンパク質のアミノ酸配列からタンパク質の構造を予測できます。AlphaFoldや同様のモデルは、研究において広く利用されるツールとなっています。
タンパク質には、決まった構造に折りたたまれないアミノ酸領域も含まれており、これらの領域はタンパク質が細胞内のダイナミックな区画に加わるのを助ける上で重要です。ホワイトヘッド研究所のメンバーであるリチャード・ヤング氏(Richard
 大きな怪我や病気で皮膚や筋肉などの軟らかい組織が傷ついたとき、その修復は簡単ではありません。特に、糖尿病などによる慢性的な傷は治りにくく、高齢化社会でますます増えることが心配されています。そんな中、期待されているのが、細胞を植え付けた特殊な「布」を移植して組織の再生を促す治療法です。しかし、これまでの「布」は、私たちの体のようにしなやかに伸び縮みすることが苦手でした。無理に伸びると、せっかく植え付けた細胞が死んでしまい、治療の妨げになることも…。この大きな壁を打ち破るため、マサチューセッツ工科大学(MIT)リンカーン研究所とMITの研究者たちが、まるで人間の皮膚や筋肉のように「縮んだり折りたたまれたりして」動き、細胞にも優しい新しい「生体吸収性の布地」の開発に取り組んでいます。この「魔法の布」が、傷ついた組織を優しく包み込み、細胞を育てながら自然に体に吸収されていく、そんな未来の治療法が見えてきました。
有望な治療法の一つとして、生きた細胞を付着させた生体適合性材料(マイクロティッシュ: microtissue)を傷に移植する方法が注目されています。この材料は、幹細胞や他の前駆細胞が傷ついた組織へと成長し、修復を助けるための「足場」となります。しかし、現在の足場材料作製技術には、繰り返し起こる課題がありました。人間の組織は独特な動きや屈曲をしますが、従来の軟質材料ではこれを再現するのが難しく、足場が伸びると、埋め込まれた細胞も伸びてしまい、しばしば細胞死を引き起こしてしまうのです。死んだ細胞は治癒プロセスを妨げ、体内で意図しない免疫応答を引き起こす可能性もあります。
「人体には、実際には伸びるのではなく、縮んだり折りたたまれたりする階層構造があります」と、MITリンカーン研究所機械工学グループの研究者であるスティーブ・ギルマー博士(Steven Gillmer,
大きな怪我や病気で皮膚や筋肉などの軟らかい組織が傷ついたとき、その修復は簡単ではありません。特に、糖尿病などによる慢性的な傷は治りにくく、高齢化社会でますます増えることが心配されています。そんな中、期待されているのが、細胞を植え付けた特殊な「布」を移植して組織の再生を促す治療法です。しかし、これまでの「布」は、私たちの体のようにしなやかに伸び縮みすることが苦手でした。無理に伸びると、せっかく植え付けた細胞が死んでしまい、治療の妨げになることも…。この大きな壁を打ち破るため、マサチューセッツ工科大学(MIT)リンカーン研究所とMITの研究者たちが、まるで人間の皮膚や筋肉のように「縮んだり折りたたまれたりして」動き、細胞にも優しい新しい「生体吸収性の布地」の開発に取り組んでいます。この「魔法の布」が、傷ついた組織を優しく包み込み、細胞を育てながら自然に体に吸収されていく、そんな未来の治療法が見えてきました。
有望な治療法の一つとして、生きた細胞を付着させた生体適合性材料(マイクロティッシュ: microtissue)を傷に移植する方法が注目されています。この材料は、幹細胞や他の前駆細胞が傷ついた組織へと成長し、修復を助けるための「足場」となります。しかし、現在の足場材料作製技術には、繰り返し起こる課題がありました。人間の組織は独特な動きや屈曲をしますが、従来の軟質材料ではこれを再現するのが難しく、足場が伸びると、埋め込まれた細胞も伸びてしまい、しばしば細胞死を引き起こしてしまうのです。死んだ細胞は治癒プロセスを妨げ、体内で意図しない免疫応答を引き起こす可能性もあります。
「人体には、実際には伸びるのではなく、縮んだり折りたたまれたりする階層構造があります」と、MITリンカーン研究所機械工学グループの研究者であるスティーブ・ギルマー博士(Steven Gillmer,
 「今度こそタバコをやめたい!」そう思って禁煙治療薬を試したけれど、期待したほどの効果がなかった…そんな経験はありませんか? もしかしたら、その理由はあなたの「遺伝子」にあるのかもしれません。人気の禁煙治療薬「バレニクリン」は、多くの人の禁煙を助けてきましたが、すべての人に同じように効くわけではありませんでした。この長年の疑問に、イギリスの研究者たちが新たな光を当てました。レスター大学の研究チームは、個人のDNAの違いがバレニクリンの効果にどう関わっているのか、その手がかりを発見したのです。この発見は、より個人に合わせた効果的な禁煙治療法の開発につながるかもしれません。
バレニクリンは間もなく、英国の国民保健サービス(acronym: NHS, National Health Service)を通じて再び喫煙者に提供される予定です。この薬は脳内の特定の受容体に作用し、喫煙による満足感を抑え、渇望感を軽減します。今回の研究では、国際的なチームが電子カルテを活用し、バレニクリンによる禁煙の成否と遺伝子の関連を調査する方法を編み出しました。
この方法は、英国ミッドランズ地方のレスターシャーおよびラトランドに住む人々で、EXCEED(健康、環境、DNAのための拡張コホート)研究(acronym: EXCEED, Extended Cohort for E-health, Environment and DNA)に参加している人々の診療記録に適用されました。また、この方法は、遺伝子データも収集している他の国内外のコホート研究でも実施されました。
これまでで最大規模となるこの種の研究で、研究チームは遺伝子解析を行い、個人の遺伝暗号の違いがバレニクリン治療の成功率の違いを説明できるかどうかを調査しました。
2025年1月10日にNicotine and Tobacco R
「今度こそタバコをやめたい!」そう思って禁煙治療薬を試したけれど、期待したほどの効果がなかった…そんな経験はありませんか? もしかしたら、その理由はあなたの「遺伝子」にあるのかもしれません。人気の禁煙治療薬「バレニクリン」は、多くの人の禁煙を助けてきましたが、すべての人に同じように効くわけではありませんでした。この長年の疑問に、イギリスの研究者たちが新たな光を当てました。レスター大学の研究チームは、個人のDNAの違いがバレニクリンの効果にどう関わっているのか、その手がかりを発見したのです。この発見は、より個人に合わせた効果的な禁煙治療法の開発につながるかもしれません。
バレニクリンは間もなく、英国の国民保健サービス(acronym: NHS, National Health Service)を通じて再び喫煙者に提供される予定です。この薬は脳内の特定の受容体に作用し、喫煙による満足感を抑え、渇望感を軽減します。今回の研究では、国際的なチームが電子カルテを活用し、バレニクリンによる禁煙の成否と遺伝子の関連を調査する方法を編み出しました。
この方法は、英国ミッドランズ地方のレスターシャーおよびラトランドに住む人々で、EXCEED(健康、環境、DNAのための拡張コホート)研究(acronym: EXCEED, Extended Cohort for E-health, Environment and DNA)に参加している人々の診療記録に適用されました。また、この方法は、遺伝子データも収集している他の国内外のコホート研究でも実施されました。
これまでで最大規模となるこの種の研究で、研究チームは遺伝子解析を行い、個人の遺伝暗号の違いがバレニクリン治療の成功率の違いを説明できるかどうかを調査しました。
2025年1月10日にNicotine and Tobacco R
 忍び寄るアルツハイマー病の不安。しかし、もし一滴の血液で、もっと早く、もっと正確にその兆候を捉えられるとしたら? そんな未来を現実にするかもしれない画期的な研究成果が発表されました。アルツハイマー病(AD)診断のための血液バイオマーカー開発をリードするニューロコードUSA社(Neurocode USA Inc)が、2025年1月28日、注目のリン酸化タウ217(pTau217)血液検査法の比較研究結果を公開しました。特に同社が米国で唯一臨床提供するALZpathアッセイは、病気の超初期段階での優れた診断精度を示し、アルツハイマー病診断の新たな地平を切り開く可能性を秘めています。pTau217はアルツハイマー病のアミロイド病理に関連する重要なバイオマーカーであり、この高精度な血液検査は、診断を大きく変えるものと期待されています。ニューロコード社は、このALZpath pTau217アッセイを臨床用自社開発検査(LDT: laboratory developed test)として提供しています。
この研究では、両アッセイがAD検出において確かな臨床性能を示すことが強調されています。しかし、調査結果からは、ALZpathアッセイが、特に効果的な介入のために早期発見が極めて重要な病気の進行初期段階において、より優れた診断精度を提供することが明らかになりました。
ニューロコード社のCSOであるハンス・フリックマン博士(Hans Frykman)は、「アルツハイマー病の早期かつ正確な診断は、患者さんの予後を改善するための基礎となります」と述べています。「この研究は、ニューロコード社のALZpath pTau217アッセイの卓越した能力と、アルツハイマー病診断を変革する上でのその役割を明確に示しています」。
2025年1月16日に「アルツハイマーズ&デメンティア:診断、評価、疾
忍び寄るアルツハイマー病の不安。しかし、もし一滴の血液で、もっと早く、もっと正確にその兆候を捉えられるとしたら? そんな未来を現実にするかもしれない画期的な研究成果が発表されました。アルツハイマー病(AD)診断のための血液バイオマーカー開発をリードするニューロコードUSA社(Neurocode USA Inc)が、2025年1月28日、注目のリン酸化タウ217(pTau217)血液検査法の比較研究結果を公開しました。特に同社が米国で唯一臨床提供するALZpathアッセイは、病気の超初期段階での優れた診断精度を示し、アルツハイマー病診断の新たな地平を切り開く可能性を秘めています。pTau217はアルツハイマー病のアミロイド病理に関連する重要なバイオマーカーであり、この高精度な血液検査は、診断を大きく変えるものと期待されています。ニューロコード社は、このALZpath pTau217アッセイを臨床用自社開発検査(LDT: laboratory developed test)として提供しています。
この研究では、両アッセイがAD検出において確かな臨床性能を示すことが強調されています。しかし、調査結果からは、ALZpathアッセイが、特に効果的な介入のために早期発見が極めて重要な病気の進行初期段階において、より優れた診断精度を提供することが明らかになりました。
ニューロコード社のCSOであるハンス・フリックマン博士(Hans Frykman)は、「アルツハイマー病の早期かつ正確な診断は、患者さんの予後を改善するための基礎となります」と述べています。「この研究は、ニューロコード社のALZpath pTau217アッセイの卓越した能力と、アルツハイマー病診断を変革する上でのその役割を明確に示しています」。
2025年1月16日に「アルツハイマーズ&デメンティア:診断、評価、疾
 映画「ファインディング・ニモ」でお馴染みのカクレクマノミとイソギンチャク。毒を持つ触手の中でなぜカクレクマノミだけが安全に暮らせるのか、不思議に思ったことはありませんか?この100年来の謎がついに解き明かされました!沖縄科学技術大学院大学(OIST)の研究チームが、カクレクマノミが持つ驚くべき「秘密のバリア」の正体を突き止めたのです。彼らがいかにしてイソギンチャクの「ハグ」を無害化しているのか、その巧妙な生存戦略に迫ります。
カクレクマノミ(アネモネフィッシュ)とイソギンチャクの共同生活は、共生の最も広く知られた例の一つです。研究者たちは、アネモネフィッシュがイソギンチャクの毒のある触手に刺されることなく安全に生活できる仕組みを理解する上で画期的な進歩を遂げ、一世紀にわたる謎を解明しました。沖縄科学技術大学院大学(OIST)の科学者たちと国際的な共同研究者たちは、アネモネフィッシュ(カクレクマノミ)が、宿主であるイソギンチャクの刺胞細胞(nematocysts (stinging cells))の放出を引き起こさないように、皮膚粘液中のシアル酸のレベルを非常に低く維持するように進化してきたことを発見しました。研究者たちは、イソギンチャク自身も自己を刺すことを避けるためか、自身の粘液中にこれらの糖化合物を持たないことを見出しました。彼らの発見は、BMC Biology誌に掲載され、アネモネフィッシュが宿主と類似した保護戦略を用いている可能性を示唆しています。2025年2月15日に公開されたオープンアクセス論文のタイトルは「Anemonefish Use Sialic Acid Metabolism As Trojan Horse to Avoid Giant Sea Anemone Stinging(アネモネフィッシュは巨大イソギンチャクの刺胞を回避するためにシアル酸代
映画「ファインディング・ニモ」でお馴染みのカクレクマノミとイソギンチャク。毒を持つ触手の中でなぜカクレクマノミだけが安全に暮らせるのか、不思議に思ったことはありませんか?この100年来の謎がついに解き明かされました!沖縄科学技術大学院大学(OIST)の研究チームが、カクレクマノミが持つ驚くべき「秘密のバリア」の正体を突き止めたのです。彼らがいかにしてイソギンチャクの「ハグ」を無害化しているのか、その巧妙な生存戦略に迫ります。
カクレクマノミ(アネモネフィッシュ)とイソギンチャクの共同生活は、共生の最も広く知られた例の一つです。研究者たちは、アネモネフィッシュがイソギンチャクの毒のある触手に刺されることなく安全に生活できる仕組みを理解する上で画期的な進歩を遂げ、一世紀にわたる謎を解明しました。沖縄科学技術大学院大学(OIST)の科学者たちと国際的な共同研究者たちは、アネモネフィッシュ(カクレクマノミ)が、宿主であるイソギンチャクの刺胞細胞(nematocysts (stinging cells))の放出を引き起こさないように、皮膚粘液中のシアル酸のレベルを非常に低く維持するように進化してきたことを発見しました。研究者たちは、イソギンチャク自身も自己を刺すことを避けるためか、自身の粘液中にこれらの糖化合物を持たないことを見出しました。彼らの発見は、BMC Biology誌に掲載され、アネモネフィッシュが宿主と類似した保護戦略を用いている可能性を示唆しています。2025年2月15日に公開されたオープンアクセス論文のタイトルは「Anemonefish Use Sialic Acid Metabolism As Trojan Horse to Avoid Giant Sea Anemone Stinging(アネモネフィッシュは巨大イソギンチャクの刺胞を回避するためにシアル酸代
 私たちヒトが、他の動物と一線を画す「言葉」。その起源は、いまだ多くの謎に包まれています。夕焼けの美しさを語り、遠い水源への道を教え合う複雑なコミュニケーションは、本当にホモ・サピエンスだけの特権なのでしょうか? 近年、私たちの「言葉」の進化に光を当てるかもしれない、あるタンパク質の「ヒト特有のカタチ」が注目されています。ロックフェラー大学の研究チームが、このタンパク質の謎に迫り、マウスを使った実験で驚くべき結果を得ました。もしかしたら、この小さな違いが、私たちが言葉を獲得する上で大きな一歩となったのかもしれません。2025年2月18日にNature Communications誌で発表された、ロックフェラー大学のロバート・B・ダーネル(Robert B. Darnell)医学博士の研究室によるこの画期的な研究は、神経発達に重要な役割を果たす脳内RNA結合タンパク質(acronym: RNA binding protein)「NOVA1」のヒト特異的な変異体に焦点を当てています。研究チームがこのヒト型NOVA1をマウスに導入したところ、マウスたちの「会話」に変化が現れたのです。
この研究論文のタイトルは「A Humanized NOVA1 Splicing Factor Alters Mouse Vocal Communications(ヒト化NOVA1スプライシング因子はマウスの発声コミュニケーションを変化させる)」です。この研究では、このNOVA1の変異体が、私たちの祖先と交配し、現代人のゲノムにもその痕跡を残している古代型人類であるネアンデルタール人やデニソワ人には見られないことも確認されました。
分子神経腫瘍学研究室を率いるダーネル博士は、「この遺伝子は、初期現生人類における広範な進化的変化の一部であり、話し言葉の古代の起源を示唆しています」と述べています。
私たちヒトが、他の動物と一線を画す「言葉」。その起源は、いまだ多くの謎に包まれています。夕焼けの美しさを語り、遠い水源への道を教え合う複雑なコミュニケーションは、本当にホモ・サピエンスだけの特権なのでしょうか? 近年、私たちの「言葉」の進化に光を当てるかもしれない、あるタンパク質の「ヒト特有のカタチ」が注目されています。ロックフェラー大学の研究チームが、このタンパク質の謎に迫り、マウスを使った実験で驚くべき結果を得ました。もしかしたら、この小さな違いが、私たちが言葉を獲得する上で大きな一歩となったのかもしれません。2025年2月18日にNature Communications誌で発表された、ロックフェラー大学のロバート・B・ダーネル(Robert B. Darnell)医学博士の研究室によるこの画期的な研究は、神経発達に重要な役割を果たす脳内RNA結合タンパク質(acronym: RNA binding protein)「NOVA1」のヒト特異的な変異体に焦点を当てています。研究チームがこのヒト型NOVA1をマウスに導入したところ、マウスたちの「会話」に変化が現れたのです。
この研究論文のタイトルは「A Humanized NOVA1 Splicing Factor Alters Mouse Vocal Communications(ヒト化NOVA1スプライシング因子はマウスの発声コミュニケーションを変化させる)」です。この研究では、このNOVA1の変異体が、私たちの祖先と交配し、現代人のゲノムにもその痕跡を残している古代型人類であるネアンデルタール人やデニソワ人には見られないことも確認されました。
分子神経腫瘍学研究室を率いるダーネル博士は、「この遺伝子は、初期現生人類における広範な進化的変化の一部であり、話し言葉の古代の起源を示唆しています」と述べています。
 「最近、小さい文字が見えにくくなった…」多くの人が経験する視力の変化。でも、なぜ同じように歳を重ねても、目の老化の進み具合には個人差があるのでしょうか?もしかしたら、その答えはあなたの遺伝子にあるかもしれません。さらに、目の老化具合を調べることで、アルツハイマー病のような脳の病気のリスクまで予測できるとしたら…?ジャクソン研究所(JAX)の最新研究が、そんな未来への扉を開くかもしれません。マウスを使った画期的な研究から見えてきた、目の老化と遺伝、そして脳の健康との驚くべきつながりをご紹介します。
視力の変化は避けられない老化の一部ですが、なぜ一部の人々は加齢に伴う眼疾患にかかりやすく、また、なぜ一部の人々は他の人々よりも深刻な衰えを経験するのでしょうか?ジャクソン研究所(The Jackson Laboratory (JAX))からの新しい研究は、遺伝子が目の老化に重要な役割を果たしており、異なる遺伝的背景が網膜老化に異なる形で影響を与えることを明らかにしています。Molecular Neurodegeneration誌に掲載されたこの研究は、人間に見られる遺伝的多様性を模倣した9系統のマウスの網膜における遺伝子とタンパク質の加齢に伴う変化を調査しました。全てのマウスが予想される老化の兆候を示しましたが、これらの変化の重症度と性質は9系統間で著しく異なりました。2025年1月20日に公開されたオープンアクセス論文のタイトルは「Genetic Context Modulates Aging and Degeneration in the Murine Retina(遺伝的背景はマウス網膜における老化と変性を調節する)」です。
目の老化をモデル化するためのより正確なアプローチ
従来、網膜老化と疾患の研究は、遺伝的に同一なマウスの単一系統に依存しており、遺伝的変
「最近、小さい文字が見えにくくなった…」多くの人が経験する視力の変化。でも、なぜ同じように歳を重ねても、目の老化の進み具合には個人差があるのでしょうか?もしかしたら、その答えはあなたの遺伝子にあるかもしれません。さらに、目の老化具合を調べることで、アルツハイマー病のような脳の病気のリスクまで予測できるとしたら…?ジャクソン研究所(JAX)の最新研究が、そんな未来への扉を開くかもしれません。マウスを使った画期的な研究から見えてきた、目の老化と遺伝、そして脳の健康との驚くべきつながりをご紹介します。
視力の変化は避けられない老化の一部ですが、なぜ一部の人々は加齢に伴う眼疾患にかかりやすく、また、なぜ一部の人々は他の人々よりも深刻な衰えを経験するのでしょうか?ジャクソン研究所(The Jackson Laboratory (JAX))からの新しい研究は、遺伝子が目の老化に重要な役割を果たしており、異なる遺伝的背景が網膜老化に異なる形で影響を与えることを明らかにしています。Molecular Neurodegeneration誌に掲載されたこの研究は、人間に見られる遺伝的多様性を模倣した9系統のマウスの網膜における遺伝子とタンパク質の加齢に伴う変化を調査しました。全てのマウスが予想される老化の兆候を示しましたが、これらの変化の重症度と性質は9系統間で著しく異なりました。2025年1月20日に公開されたオープンアクセス論文のタイトルは「Genetic Context Modulates Aging and Degeneration in the Murine Retina(遺伝的背景はマウス網膜における老化と変性を調節する)」です。
目の老化をモデル化するためのより正確なアプローチ
従来、網膜老化と疾患の研究は、遺伝的に同一なマウスの単一系統に依存しており、遺伝的変
 海のハンター、イモガイ。その強力な毒は、獲物を仕留めるための恐ろしい武器ですが、実はその毒から新しい薬が生まれる可能性を秘めていることをご存知でしょうか?しかし、毒が体内の何に作用するのか(標的)を正確に知ることは、安全で効果的な薬を作るための大きな課題です。イスラエルの科学者たちは、この難問を解決するため、なんと人工知能(AI)と伝統的な研究手法を融合させた画期的な手法を開発しました。イモガイ毒素の謎に迫る最新の研究が、未来の創薬や生態系研究にどんな光を投げかけるのでしょうか?
科学者が農業、種管理、あるいは救命薬の目的で新しい分子を開発する際、その標的が何であるかを正確に知ることが重要です。分子の意図された相互作用と意図しない相互作用の両方を徹底的に理解することは、その安全性と有効性を確保するために不可欠です。昆虫と魚の両方に影響を与えることが知られているあるイモガイ毒素n)は、ワイツマン科学研究所の科学者たちに、分子標的を見つける新しい方法を開発するきっかけを与えました。彼らは、人工知能と従来の研究手法を組み合わせることで、天然毒素がどのタンパク質に影響を与えるかを予測できるパイプラインを構築しました。この成果は、生態学的研究と創薬開発の両方に影響を与える可能性があります。この研究は、2025年2月15日から19日にロサンゼルスで開催された第69回生物物理学会年会で発表されました。
イスラエルのワイツマン科学研究所の科学者であるイツハル・カルバット博士(Izhar Karbat, PhD)とエイタン・レウベニ博士(Eitan Reuveny, PhD)は、イモガイの獲物である魚に、イモガイ毒素の一種であるコンクニチン-S1(acronym: Cs1, Conkunitzin-S1)がどのように影響を与えるかを解明したいと考えていました。Cs1は、細胞機能に不
海のハンター、イモガイ。その強力な毒は、獲物を仕留めるための恐ろしい武器ですが、実はその毒から新しい薬が生まれる可能性を秘めていることをご存知でしょうか?しかし、毒が体内の何に作用するのか(標的)を正確に知ることは、安全で効果的な薬を作るための大きな課題です。イスラエルの科学者たちは、この難問を解決するため、なんと人工知能(AI)と伝統的な研究手法を融合させた画期的な手法を開発しました。イモガイ毒素の謎に迫る最新の研究が、未来の創薬や生態系研究にどんな光を投げかけるのでしょうか?
科学者が農業、種管理、あるいは救命薬の目的で新しい分子を開発する際、その標的が何であるかを正確に知ることが重要です。分子の意図された相互作用と意図しない相互作用の両方を徹底的に理解することは、その安全性と有効性を確保するために不可欠です。昆虫と魚の両方に影響を与えることが知られているあるイモガイ毒素n)は、ワイツマン科学研究所の科学者たちに、分子標的を見つける新しい方法を開発するきっかけを与えました。彼らは、人工知能と従来の研究手法を組み合わせることで、天然毒素がどのタンパク質に影響を与えるかを予測できるパイプラインを構築しました。この成果は、生態学的研究と創薬開発の両方に影響を与える可能性があります。この研究は、2025年2月15日から19日にロサンゼルスで開催された第69回生物物理学会年会で発表されました。
イスラエルのワイツマン科学研究所の科学者であるイツハル・カルバット博士(Izhar Karbat, PhD)とエイタン・レウベニ博士(Eitan Reuveny, PhD)は、イモガイの獲物である魚に、イモガイ毒素の一種であるコンクニチン-S1(acronym: Cs1, Conkunitzin-S1)がどのように影響を与えるかを解明したいと考えていました。Cs1は、細胞機能に不
 私たち人間を人間たらしめる複雑な思考や認知機能。その源である脳の進化について、これまでの常識を覆すかもしれない驚きの発見がありました。鳥と哺乳類は、脳の重要な部分である「外套」が、それぞれ全く異なる道のりを辿って進化したというのです。同じ祖先から枝分かれしたのではなく、別々に賢い脳を手に入れたのでしょうか?この謎めいた進化の物語を、アチュカロ・バスク神経科学センターおよびバスク大学のイケルバスケ研究者が主導し、Science誌に掲載された2つの研究から紐解いていきましょう。
外套は、哺乳類において新皮質が形成される脳領域であり、人間を他の種から最も区別する認知機能や複雑な機能を担う部分です。伝統的に、外套は哺乳類、鳥類、爬虫類の間で比較可能な構造であり、複雑さのレベルが異なるだけだと考えられてきました。この領域には類似したニューロンタイプが存在し、感覚処理や認知処理のための同等の回路があると想定されていました。これまでの研究では、共通の興奮性ニューロン(excitatory neurons)および抑制性ニューロン(inhibitory neurons)の存在や、これらの脊椎動物種における類似した進化経路を示唆する一般的な接続パターンが特定されていました。しかし、今回の新たな研究により、これらのグループ間で外套の一般的な機能は同等であるものの、その発生メカニズムとニューロンの分子的アイデンティティは進化の過程で実質的に分岐していることが明らかになりました。
最初の研究は、アチュカロ・バスク神経科学センターのエネリッツ・ルエダ=アラニャ氏(Eneritz Rueda-Alaña)とフェルナンド・ガルシア=モレノ博士(Fernando García-Moreno)が、バスクの研究センターであるCICバイオグネ(CICbioGUNE)およびBCAM(バスク応用数学センター
私たち人間を人間たらしめる複雑な思考や認知機能。その源である脳の進化について、これまでの常識を覆すかもしれない驚きの発見がありました。鳥と哺乳類は、脳の重要な部分である「外套」が、それぞれ全く異なる道のりを辿って進化したというのです。同じ祖先から枝分かれしたのではなく、別々に賢い脳を手に入れたのでしょうか?この謎めいた進化の物語を、アチュカロ・バスク神経科学センターおよびバスク大学のイケルバスケ研究者が主導し、Science誌に掲載された2つの研究から紐解いていきましょう。
外套は、哺乳類において新皮質が形成される脳領域であり、人間を他の種から最も区別する認知機能や複雑な機能を担う部分です。伝統的に、外套は哺乳類、鳥類、爬虫類の間で比較可能な構造であり、複雑さのレベルが異なるだけだと考えられてきました。この領域には類似したニューロンタイプが存在し、感覚処理や認知処理のための同等の回路があると想定されていました。これまでの研究では、共通の興奮性ニューロン(excitatory neurons)および抑制性ニューロン(inhibitory neurons)の存在や、これらの脊椎動物種における類似した進化経路を示唆する一般的な接続パターンが特定されていました。しかし、今回の新たな研究により、これらのグループ間で外套の一般的な機能は同等であるものの、その発生メカニズムとニューロンの分子的アイデンティティは進化の過程で実質的に分岐していることが明らかになりました。
最初の研究は、アチュカロ・バスク神経科学センターのエネリッツ・ルエダ=アラニャ氏(Eneritz Rueda-Alaña)とフェルナンド・ガルシア=モレノ博士(Fernando García-Moreno)が、バスクの研究センターであるCICバイオグネ(CICbioGUNE)およびBCAM(バスク応用数学センター
 敵か味方か?カビ感染が免疫系を欺き、脳細胞を破壊させるメカニズムを解明
私たちの免疫システムは、体を守るための精鋭部隊です。しかし、もしその部隊が敵の策略にはまり、自らの「城」、つまり脳を攻撃し始めたらどうなるでしょうか?驚くべきことに、ある種のカビ(真菌)に感染すると、ショウジョウバエの免疫系が自身の脳細胞を破壊し、神経変性のような兆候を引き起こすことが新たな研究で明らかになりました。この発見は、感染症がどのようにして脳に影響を与えるか、そして免疫系が時に予期せぬ振る舞いをするのかについて、新たな視点を提供します。
真菌感染が、ショウジョウバエ自身の免疫系を引き金にして脳細胞を破壊させ、神経変性(neurodegeneration)の兆候につながることが、新しい研究で示されました。2025年2月13日にPLOS Biology誌に掲載されたこの論文によると、ボーベリア・バシアーナ(Beauveria bassiana, B. bassiana)と呼ばれる真菌が、ショウジョウバエの自然免疫系に、脳内のニューロンとグリア細胞(glia)を殺すプロセスを引き起こさせることがわかりました。これにより、感染したショウジョウバエの半数以上が7日後に死亡したのに対し、対照群の半数は約50日間生存しました。このオープンアクセスの論文タイトルは「Toll-1-Dependent Immune Evasion Induced by Fungal Infection Leads to Cell Loss in the Drosophila Brain(真菌感染によって誘導されるToll-1依存性の免疫回避がショウジョウバエ脳における細胞喪失を引き起こす)」です。
英国バーミンガム大学の研究チームが行った実験では、ショウジョウバエが感染チャンバー内でボーベリア・バシアーナに曝露されま
敵か味方か?カビ感染が免疫系を欺き、脳細胞を破壊させるメカニズムを解明
私たちの免疫システムは、体を守るための精鋭部隊です。しかし、もしその部隊が敵の策略にはまり、自らの「城」、つまり脳を攻撃し始めたらどうなるでしょうか?驚くべきことに、ある種のカビ(真菌)に感染すると、ショウジョウバエの免疫系が自身の脳細胞を破壊し、神経変性のような兆候を引き起こすことが新たな研究で明らかになりました。この発見は、感染症がどのようにして脳に影響を与えるか、そして免疫系が時に予期せぬ振る舞いをするのかについて、新たな視点を提供します。
真菌感染が、ショウジョウバエ自身の免疫系を引き金にして脳細胞を破壊させ、神経変性(neurodegeneration)の兆候につながることが、新しい研究で示されました。2025年2月13日にPLOS Biology誌に掲載されたこの論文によると、ボーベリア・バシアーナ(Beauveria bassiana, B. bassiana)と呼ばれる真菌が、ショウジョウバエの自然免疫系に、脳内のニューロンとグリア細胞(glia)を殺すプロセスを引き起こさせることがわかりました。これにより、感染したショウジョウバエの半数以上が7日後に死亡したのに対し、対照群の半数は約50日間生存しました。このオープンアクセスの論文タイトルは「Toll-1-Dependent Immune Evasion Induced by Fungal Infection Leads to Cell Loss in the Drosophila Brain(真菌感染によって誘導されるToll-1依存性の免疫回避がショウジョウバエ脳における細胞喪失を引き起こす)」です。
英国バーミンガム大学の研究チームが行った実験では、ショウジョウバエが感染チャンバー内でボーベリア・バシアーナに曝露されま
 免疫系の「諸刃の剣」? 100年来の定説を覆す発見が自己免疫疾患治療に新たな光
私たちの体には、病原体などの脅威から身を守るための精巧な免疫システムが備わっています。その中でも「補体系」は、100年以上前に発見された、感染や組織損傷の兆候をパトロールするタンパク質群からなる強力な防御メカニズムです。しかし、この頼もしいはずの補体系が、時として自身の組織を攻撃してしまうことがあるのはなぜでしょうか?この度、マス・ジェネラル・ブリガムの研究者たちは、「グランザイムK(GZMK: granzyme K)」と呼ばれるタンパク質が、補体系を活性化させ、自身の組織に対する炎症や損傷を引き起こすという驚くべき事実を発見しました。この発見は、補体系に関する長年の理解を覆すだけでなく、自己免疫疾患や炎症性疾患の新たな治療法開発への扉を開くものです。
私たちの免疫システムは、有害な脅威を検知し排除するために設計された様々な防御機構を備えています。その最も強力な防御メカニズムの一つが補体系です。これは、私たちの体をパトロールし、感染や損傷の兆候を常に警戒しているタンパク質群です。補体系が最初に記述されてから100年以上が経過した今、マス・ジェネラル・ブリガムの研究者たちは、グランザイムK(GZMK)として知られるタンパク質が、補体系を自身の組織に対して活性化させることにより、組織損傷と炎症を引き起こすことを発見しました。彼らの発見は、補体系に関する世紀を超えた理解を再構築するだけでなく、自己免疫疾患や炎症性疾患の患者において、この有害な経路を特異的に遮断できる可能性のある治療法への新たな道を開くものです。この研究成果は、2025年2月6日にNature誌に掲載されました。論文タイトルは「Granzyme K Activates the Entire Complement Cascade(
免疫系の「諸刃の剣」? 100年来の定説を覆す発見が自己免疫疾患治療に新たな光
私たちの体には、病原体などの脅威から身を守るための精巧な免疫システムが備わっています。その中でも「補体系」は、100年以上前に発見された、感染や組織損傷の兆候をパトロールするタンパク質群からなる強力な防御メカニズムです。しかし、この頼もしいはずの補体系が、時として自身の組織を攻撃してしまうことがあるのはなぜでしょうか?この度、マス・ジェネラル・ブリガムの研究者たちは、「グランザイムK(GZMK: granzyme K)」と呼ばれるタンパク質が、補体系を活性化させ、自身の組織に対する炎症や損傷を引き起こすという驚くべき事実を発見しました。この発見は、補体系に関する長年の理解を覆すだけでなく、自己免疫疾患や炎症性疾患の新たな治療法開発への扉を開くものです。
私たちの免疫システムは、有害な脅威を検知し排除するために設計された様々な防御機構を備えています。その最も強力な防御メカニズムの一つが補体系です。これは、私たちの体をパトロールし、感染や損傷の兆候を常に警戒しているタンパク質群です。補体系が最初に記述されてから100年以上が経過した今、マス・ジェネラル・ブリガムの研究者たちは、グランザイムK(GZMK)として知られるタンパク質が、補体系を自身の組織に対して活性化させることにより、組織損傷と炎症を引き起こすことを発見しました。彼らの発見は、補体系に関する世紀を超えた理解を再構築するだけでなく、自己免疫疾患や炎症性疾患の患者において、この有害な経路を特異的に遮断できる可能性のある治療法への新たな道を開くものです。この研究成果は、2025年2月6日にNature誌に掲載されました。論文タイトルは「Granzyme K Activates the Entire Complement Cascade(
 マラリアとの闘いに光明:薬剤耐性の謎を解く包括的遺伝子マップが完成
マラリアは、今なお世界中で多くの命を脅かす感染症です。特に、治療薬への耐性を持つマラリア原虫の出現は、深刻な問題となっています。しかし、この困難な状況に立ち向かうための画期的な研究成果が発表されました。ハーバード大学T.H.チャン公衆衛生大学院の研究チームが、人獣共通感染症マラリアを引き起こす「ノウレシマラリア原虫」の包括的な遺伝子マップを作成したのです。このマップは、薬剤耐性の仕組みを解き明かし、新たな治療法開発への道を拓く可能性を秘めています。一体どのような発見があったのでしょうか?
人獣共通感染症マラリアの原因となるノウレシマラリア原虫(Plasmodium knowlesi, P. knowlesi)の包括的な遺伝子マッピングにより、血液感染に必要な遺伝子と薬剤耐性を引き起こす遺伝子が明らかになりました。
このマップは、創薬可能な特定の標的と耐性の決定因子を特定することで、新しい治療法の開発に役立つ知見を提供します。
ハーバード大学T.H.チャン公衆衛生大学院の研究者らは、ヒトにマラリアを引き起こす寄生虫であるノウレシマラリア原虫(P. knowlesi)の血液感染に必須な全遺伝子の新しい包括的なマップを作成しました。このマップは、これまでに報告されたどのマラリア原虫(Plasmodium)種よりも完全な必須遺伝子の分類を含んでおり、創薬可能な寄生虫の標的や薬剤耐性のメカニズムを特定するために利用できます。これは、マラリアの新しい治療法の開発に情報を提供するものです。
「私たちの発見が、マラリア研究と制御の分野における大きな一歩となることを願っています」と、共同責任著者であるマノージ・ドライシング博士(Manoj Duraisingh, PhD)、ジョン・ラポート・ギブン記念免疫
マラリアとの闘いに光明:薬剤耐性の謎を解く包括的遺伝子マップが完成
マラリアは、今なお世界中で多くの命を脅かす感染症です。特に、治療薬への耐性を持つマラリア原虫の出現は、深刻な問題となっています。しかし、この困難な状況に立ち向かうための画期的な研究成果が発表されました。ハーバード大学T.H.チャン公衆衛生大学院の研究チームが、人獣共通感染症マラリアを引き起こす「ノウレシマラリア原虫」の包括的な遺伝子マップを作成したのです。このマップは、薬剤耐性の仕組みを解き明かし、新たな治療法開発への道を拓く可能性を秘めています。一体どのような発見があったのでしょうか?
人獣共通感染症マラリアの原因となるノウレシマラリア原虫(Plasmodium knowlesi, P. knowlesi)の包括的な遺伝子マッピングにより、血液感染に必要な遺伝子と薬剤耐性を引き起こす遺伝子が明らかになりました。
このマップは、創薬可能な特定の標的と耐性の決定因子を特定することで、新しい治療法の開発に役立つ知見を提供します。
ハーバード大学T.H.チャン公衆衛生大学院の研究者らは、ヒトにマラリアを引き起こす寄生虫であるノウレシマラリア原虫(P. knowlesi)の血液感染に必須な全遺伝子の新しい包括的なマップを作成しました。このマップは、これまでに報告されたどのマラリア原虫(Plasmodium)種よりも完全な必須遺伝子の分類を含んでおり、創薬可能な寄生虫の標的や薬剤耐性のメカニズムを特定するために利用できます。これは、マラリアの新しい治療法の開発に情報を提供するものです。
「私たちの発見が、マラリア研究と制御の分野における大きな一歩となることを願っています」と、共同責任著者であるマノージ・ドライシング博士(Manoj Duraisingh, PhD)、ジョン・ラポート・ギブン記念免疫
 「あの人、知らないんだな」 ボノボは相手の心を読んで協力する?
『あ、あの人、知らないんだな』——相手が何かを知らないことに気づき、それを補うようにコミュニケーションをとる。これは、私たちが協力し合ったり、教え合ったりする上で欠かせない、高度な能力だと考えられてきました。もしかしたら、人間だけの特別な力なのかもしれない、と。しかし、驚くべきことに、私たちの最も近縁な親戚である類人猿ボノボも、この能力を持っている可能性を示す研究結果が発表されました。ジョンズ・ホプキンス大学の研究チームが行った巧妙な実験は、ボノボが人間の「知らない状態」を察知し、チームワークのために積極的に情報を伝えようとすることを示唆しています。
これは、人間と類人猿の間に横たわる知性の深いつながり、そしてその進化の歴史に光を当てる発見かもしれません。
おやつをもらうため、類人猿はそれらがどこにあるか知らない人間に対して熱心に指差しをしました。この一見単純な実験は、類人猿がチームワークの名の下に未知の情報を伝達することを初めて実証しました。この研究はまた、類人猿が他者の無知(知らない状態)を直感的に理解できるという、これまで人間特有と考えられてきた能力に関する、現在までで最も明確な証拠を提供します。ジョンズ・ホプキンス大学の社会・認知起源グループ(Social and Cognitive Origins Group)の研究者によるこの研究は、2025年2月3日にPNAS誌(米国科学アカデミー紀要)に掲載されました。このオープンアクセスの論文タイトルは「Bonobos Point More for Ignorant Than Knowledgeable Social Partners(ボノボは知識のある社会的パートナーよりも無知なパートナーに対してより多く指差しをする)」です。
「お互いの知識のギ
「あの人、知らないんだな」 ボノボは相手の心を読んで協力する?
『あ、あの人、知らないんだな』——相手が何かを知らないことに気づき、それを補うようにコミュニケーションをとる。これは、私たちが協力し合ったり、教え合ったりする上で欠かせない、高度な能力だと考えられてきました。もしかしたら、人間だけの特別な力なのかもしれない、と。しかし、驚くべきことに、私たちの最も近縁な親戚である類人猿ボノボも、この能力を持っている可能性を示す研究結果が発表されました。ジョンズ・ホプキンス大学の研究チームが行った巧妙な実験は、ボノボが人間の「知らない状態」を察知し、チームワークのために積極的に情報を伝えようとすることを示唆しています。
これは、人間と類人猿の間に横たわる知性の深いつながり、そしてその進化の歴史に光を当てる発見かもしれません。
おやつをもらうため、類人猿はそれらがどこにあるか知らない人間に対して熱心に指差しをしました。この一見単純な実験は、類人猿がチームワークの名の下に未知の情報を伝達することを初めて実証しました。この研究はまた、類人猿が他者の無知(知らない状態)を直感的に理解できるという、これまで人間特有と考えられてきた能力に関する、現在までで最も明確な証拠を提供します。ジョンズ・ホプキンス大学の社会・認知起源グループ(Social and Cognitive Origins Group)の研究者によるこの研究は、2025年2月3日にPNAS誌(米国科学アカデミー紀要)に掲載されました。このオープンアクセスの論文タイトルは「Bonobos Point More for Ignorant Than Knowledgeable Social Partners(ボノボは知識のある社会的パートナーよりも無知なパートナーに対してより多く指差しをする)」です。
「お互いの知識のギ
 汗で健康を常時チェック! ナノ粒子を印刷して作る次世代ウェアラブルセンサー
一人ひとりの体調を正確に把握し、最適な栄養素や薬を届ける「個別化医療」。それは未来の医療の姿として、大きな期待が寄せられています。しかし、その実現には、体の中の状態を示す「バイオマーカー」を、リアルタイムで、しかも継続的に測る方法が必要不可欠でした。汗をかく、服を着る、そんな日常の中で健康状態をずっと見守れたら…?カリフォルニア工科大学(Caltech)のエンジニアチームが、そんな未来を一歩近づける画期的な技術を開発しました。特殊なナノ粒子をインクジェット印刷することで、まるでシールのように身につけられる汗センサーを大量生産する道を拓いたのです。
このセンサーは、私たちの健康状態を、より手軽に、より深く知るための新しいツールとなるかもしれません。ビタミン、ホルモン、代謝物、薬剤など、様々なバイオマーカーをリアルタイムで監視し、患者とその医師が分子レベルの変化を継続的に追跡することを可能にします。この新しいナノ粒子を組み込んだウェアラブルバイオセンサーは、カリフォルニア州ドゥアルテのシティ・オブ・ホープ(City of Hope)において、COVID後遺症(ロングCOVID)に苦しむ患者の代謝物モニタリングや、がん患者の化学療法薬レベルのモニタリングに成功裏に使用されています。
「これらは可能性のほんの一例に過ぎません」と、カルテック(Caltech)のアンドリュー・アンド・ペギー・チャン医用工学部門(Andrew and Peggy Cherng Department of Medical Engineering)の医用工学教授であるウェイ・ガオ博士(Wei Gao, PhD)は述べています。「これらのセンサーによって、多くの慢性疾患とそのバイオマーカーを継続的かつ非侵襲的に監視できる可能
汗で健康を常時チェック! ナノ粒子を印刷して作る次世代ウェアラブルセンサー
一人ひとりの体調を正確に把握し、最適な栄養素や薬を届ける「個別化医療」。それは未来の医療の姿として、大きな期待が寄せられています。しかし、その実現には、体の中の状態を示す「バイオマーカー」を、リアルタイムで、しかも継続的に測る方法が必要不可欠でした。汗をかく、服を着る、そんな日常の中で健康状態をずっと見守れたら…?カリフォルニア工科大学(Caltech)のエンジニアチームが、そんな未来を一歩近づける画期的な技術を開発しました。特殊なナノ粒子をインクジェット印刷することで、まるでシールのように身につけられる汗センサーを大量生産する道を拓いたのです。
このセンサーは、私たちの健康状態を、より手軽に、より深く知るための新しいツールとなるかもしれません。ビタミン、ホルモン、代謝物、薬剤など、様々なバイオマーカーをリアルタイムで監視し、患者とその医師が分子レベルの変化を継続的に追跡することを可能にします。この新しいナノ粒子を組み込んだウェアラブルバイオセンサーは、カリフォルニア州ドゥアルテのシティ・オブ・ホープ(City of Hope)において、COVID後遺症(ロングCOVID)に苦しむ患者の代謝物モニタリングや、がん患者の化学療法薬レベルのモニタリングに成功裏に使用されています。
「これらは可能性のほんの一例に過ぎません」と、カルテック(Caltech)のアンドリュー・アンド・ペギー・チャン医用工学部門(Andrew and Peggy Cherng Department of Medical Engineering)の医用工学教授であるウェイ・ガオ博士(Wei Gao, PhD)は述べています。「これらのセンサーによって、多くの慢性疾患とそのバイオマーカーを継続的かつ非侵襲的に監視できる可能
 遺伝子治療の新たな扉を開くか? 超小型CRISPRが筋肉への「運び屋」問題を解決へ
遺伝子の異常によって引き起こされる病気を、根本から治す。そんな夢のような治療法として期待されているのが「遺伝子編集」技術です。しかし、この革新的な技術を体の特定の場所に安全かつ効率的に届けることは、大きな壁となって立ちはだかっていました。特に、肝臓以外の組織、例えば筋肉などに治療薬を届けるのは非常に困難でした。今回、画期的な次世代CRISPRプラットフォームを持つバイオテクノロジー企業、Mammoth Biosciences社が、この課題を打ち破る可能性のあるプレクリニカル研究の結果を発表しました。彼らが開発した「NanoCas™」と呼ばれる超小型の新しいCRISPRシステムは、たった1つの運び屋で、これまで難しかった筋肉組織での遺伝子編集を可能にするかもしれません。これは、遺伝子治療の新たな扉を開く可能性を秘めた、注目の成果と言えるでしょう。
2025年1月31日、独自の次世代CRISPR遺伝子編集プラットフォームを活用し、一回投与での根治療法創出を目指すバイオテクノロジー企業、Mammoth Biosciences社(Mammoth Biosciences, Inc.)は、プレプリントサーバーbioRxivで公開された新しい前臨床研究を発表しました。この研究は、NanoCas™の概念実証(proof-of-concept)を確立するものです。NanoCas™は、単一のアデノ随伴ウイルスベクター(AAV: adeno-associated viral vector)を用いて全身投与した場合に、効率的な肝外編集が可能な初の超小型CRISPRシステムです。プレプリントのタイトルは「Single-AAV CRISPR Editing of Skeletal Muscle in Non-H
遺伝子治療の新たな扉を開くか? 超小型CRISPRが筋肉への「運び屋」問題を解決へ
遺伝子の異常によって引き起こされる病気を、根本から治す。そんな夢のような治療法として期待されているのが「遺伝子編集」技術です。しかし、この革新的な技術を体の特定の場所に安全かつ効率的に届けることは、大きな壁となって立ちはだかっていました。特に、肝臓以外の組織、例えば筋肉などに治療薬を届けるのは非常に困難でした。今回、画期的な次世代CRISPRプラットフォームを持つバイオテクノロジー企業、Mammoth Biosciences社が、この課題を打ち破る可能性のあるプレクリニカル研究の結果を発表しました。彼らが開発した「NanoCas™」と呼ばれる超小型の新しいCRISPRシステムは、たった1つの運び屋で、これまで難しかった筋肉組織での遺伝子編集を可能にするかもしれません。これは、遺伝子治療の新たな扉を開く可能性を秘めた、注目の成果と言えるでしょう。
2025年1月31日、独自の次世代CRISPR遺伝子編集プラットフォームを活用し、一回投与での根治療法創出を目指すバイオテクノロジー企業、Mammoth Biosciences社(Mammoth Biosciences, Inc.)は、プレプリントサーバーbioRxivで公開された新しい前臨床研究を発表しました。この研究は、NanoCas™の概念実証(proof-of-concept)を確立するものです。NanoCas™は、単一のアデノ随伴ウイルスベクター(AAV: adeno-associated viral vector)を用いて全身投与した場合に、効率的な肝外編集が可能な初の超小型CRISPRシステムです。プレプリントのタイトルは「Single-AAV CRISPR Editing of Skeletal Muscle in Non-H
 細胞の門番は、どうやって持ち場に戻るのか? 最新技術が解き明かすタンパク質リサイクルの仕組み
私たちの体を作る細胞の中では、日々、生命活動に不可欠な物質のやり取りが絶えず行われています。特に細胞の「門番」とも言える表面のタンパク質は、必要なものを取り込み、情報を伝える重要な役割を担っています。しかし、一度細胞内に取り込まれたタンパク質が、どうやって再び表面に戻ってくるのでしょうか? その巧妙な「リサイクル」の仕組みは、長年、細胞生物学の大きな謎の一つでした。今回、UTサウスウェスタンメディカルセンターの研究チームが、その謎を解き明かす鍵となる発見をしました。彼らは最先端の技術を駆使して、タンパク質が細胞表面へ帰還する重要なメカニズムを分子レベルで明らかにしたのです。この発見は、神経疾患やがんなどの治療法開発にも繋がる可能性を秘めています。
UTサウスウェスタンメディカルセンターの研究者を中心とするチームが、細胞内のエンドソームリサイクリングを担う重要なメカニズムを特定しました。このプロセスは人の健康に不可欠なものです。2024年11月25日にNature Communications誌に掲載されたこの研究成果は、細胞生物学における基本的な問いに答え、神経疾患やがんを含む疾患の治療法につながる可能性があります。このオープンアクセスの論文タイトルは「Structural Basis for Retriever-SNX17 Assembly and Endosomal Sorting(リトリーバー-SNX17複合体の形成とエンドソームソーティングの構造基盤)」です。
「私たちの研究は、タンパク質がエンドソームから細胞膜(形質膜)へとどのようにリサイクルされるかを理解する上で、大きな進歩です」と、UTサウスウェスタンの内科学(Internal Medicine)および免疫
細胞の門番は、どうやって持ち場に戻るのか? 最新技術が解き明かすタンパク質リサイクルの仕組み
私たちの体を作る細胞の中では、日々、生命活動に不可欠な物質のやり取りが絶えず行われています。特に細胞の「門番」とも言える表面のタンパク質は、必要なものを取り込み、情報を伝える重要な役割を担っています。しかし、一度細胞内に取り込まれたタンパク質が、どうやって再び表面に戻ってくるのでしょうか? その巧妙な「リサイクル」の仕組みは、長年、細胞生物学の大きな謎の一つでした。今回、UTサウスウェスタンメディカルセンターの研究チームが、その謎を解き明かす鍵となる発見をしました。彼らは最先端の技術を駆使して、タンパク質が細胞表面へ帰還する重要なメカニズムを分子レベルで明らかにしたのです。この発見は、神経疾患やがんなどの治療法開発にも繋がる可能性を秘めています。
UTサウスウェスタンメディカルセンターの研究者を中心とするチームが、細胞内のエンドソームリサイクリングを担う重要なメカニズムを特定しました。このプロセスは人の健康に不可欠なものです。2024年11月25日にNature Communications誌に掲載されたこの研究成果は、細胞生物学における基本的な問いに答え、神経疾患やがんを含む疾患の治療法につながる可能性があります。このオープンアクセスの論文タイトルは「Structural Basis for Retriever-SNX17 Assembly and Endosomal Sorting(リトリーバー-SNX17複合体の形成とエンドソームソーティングの構造基盤)」です。
「私たちの研究は、タンパク質がエンドソームから細胞膜(形質膜)へとどのようにリサイクルされるかを理解する上で、大きな進歩です」と、UTサウスウェスタンの内科学(Internal Medicine)および免疫
 世界で人気のカフェイン飲料「マテ茶」のゲノム解析で、カフェイン合成の進化に新たな知見
マテ茶(イレックス・パラグアリエンシス:Ilex paraguariensis)は、紅茶やコーヒーと並び、世界で最も人気のあるカフェイン飲料のひとつです。南米では広く消費されており、この驚くべき植物は多様な生理活性化合物を豊富に含んでおり、さまざまな健康効果をもたらすとされています。このたび、国際的な研究者チームがマテ茶のゲノムを解読し、カフェインの生合成に関する新たな知見を得ました。この情報は、特性の異なる新品種の開発に活用できる可能性があります。この研究はブエノスアイレス大学を中心に行われ、欧州分子生物学研究所(EMBL)ハンブルク支部や、アルゼンチン、ブラジル、アメリカ合衆国の複数の研究機関の科学者らも参加しました。成果は2025年1月8日付で『eLife』に掲載され、論文タイトルは「Yerba Mate (Ilex paraguariensis) Genome Provides New Insights Into Convergent Evolution of Caffeine Biosynthesis(マテ茶(Ilex paraguariensis)のゲノムが示すカフェイン生合成の収束進化に関する新たな知見)」です。
マテ茶におけるカフェインの進化
マテ茶の遺伝的特性を明らかにするため、科学者らはゲノム解析を用いました。これにより、植物の生化学的特性や進化の歴史、特にカフェイン生合成の進化に関する驚くべき事実が明らかになりました。
「マテ茶の祖先はおよそ5,000万年前にゲノムを重複させていたことを発見しました」と、今回の論文の筆頭著者であり、EMBLハンブルクのポスドク研究員であるフェデリコ・ヴィニャーレ博士(Federico Vignale PhD)は語ります。
世界で人気のカフェイン飲料「マテ茶」のゲノム解析で、カフェイン合成の進化に新たな知見
マテ茶(イレックス・パラグアリエンシス:Ilex paraguariensis)は、紅茶やコーヒーと並び、世界で最も人気のあるカフェイン飲料のひとつです。南米では広く消費されており、この驚くべき植物は多様な生理活性化合物を豊富に含んでおり、さまざまな健康効果をもたらすとされています。このたび、国際的な研究者チームがマテ茶のゲノムを解読し、カフェインの生合成に関する新たな知見を得ました。この情報は、特性の異なる新品種の開発に活用できる可能性があります。この研究はブエノスアイレス大学を中心に行われ、欧州分子生物学研究所(EMBL)ハンブルク支部や、アルゼンチン、ブラジル、アメリカ合衆国の複数の研究機関の科学者らも参加しました。成果は2025年1月8日付で『eLife』に掲載され、論文タイトルは「Yerba Mate (Ilex paraguariensis) Genome Provides New Insights Into Convergent Evolution of Caffeine Biosynthesis(マテ茶(Ilex paraguariensis)のゲノムが示すカフェイン生合成の収束進化に関する新たな知見)」です。
マテ茶におけるカフェインの進化
マテ茶の遺伝的特性を明らかにするため、科学者らはゲノム解析を用いました。これにより、植物の生化学的特性や進化の歴史、特にカフェイン生合成の進化に関する驚くべき事実が明らかになりました。
「マテ茶の祖先はおよそ5,000万年前にゲノムを重複させていたことを発見しました」と、今回の論文の筆頭著者であり、EMBLハンブルクのポスドク研究員であるフェデリコ・ヴィニャーレ博士(Federico Vignale PhD)は語ります。
 DNA複製は、体内のあらゆる場所で絶え間なく行われており、1日に何兆回も繰り返されている現象です。細胞が分裂するたびに——それが損傷した組織を修復するためであれ、古くなった細胞を置き換えるためであれ、あるいは単に身体の成長を助けるためであれ——DNAはコピーされ、新しい細胞が同じ遺伝情報を保持できるようになります。しかし、この人間生物学の基本的側面は、これまであまり理解されていませんでした。その主な理由は、科学者らがこの複雑な複製の過程を間近で観察する手段を持っていなかったからです。これまでの試みは、DNA構造を損なう化学物質を用いたり、ごく短いDNA断片しか観察できなかったりと、全体像を捉えるには不十分なものでした。
2025年1月9日に『Cell』誌に掲載された新しい研究で、グラッドストーン研究所(Gladstone Institutes)の科学者らは、この課題を解決するための大きな進展を遂げました。彼らは、長鎖DNAシーケンシング(long-read DNA sequencing)と予測型人工知能モデルを組み合わせた新手法を開発し、DNA複製によって新たに形成されたDNAがその後の数分から数時間にわたってどのような変化を辿るのかについて新たな知見を提供しました。
このオープンアクセスの論文「The Single-Molecule Accessibility Landscape of Newly Replicated Mammalian Chromatin(新たに複製された哺乳類クロマチンにおける単一分子レベルでのアクセシビリティ地図)」は、『Cell』誌のオンライン版に掲載されており、著者にはメーガン・オストロウスキ(Megan Ostrowski)、マーティ・ヤン(Marty Yang)、コリン・マクナリー(Colin McNally)、ヌール・アブドゥルヘ
DNA複製は、体内のあらゆる場所で絶え間なく行われており、1日に何兆回も繰り返されている現象です。細胞が分裂するたびに——それが損傷した組織を修復するためであれ、古くなった細胞を置き換えるためであれ、あるいは単に身体の成長を助けるためであれ——DNAはコピーされ、新しい細胞が同じ遺伝情報を保持できるようになります。しかし、この人間生物学の基本的側面は、これまであまり理解されていませんでした。その主な理由は、科学者らがこの複雑な複製の過程を間近で観察する手段を持っていなかったからです。これまでの試みは、DNA構造を損なう化学物質を用いたり、ごく短いDNA断片しか観察できなかったりと、全体像を捉えるには不十分なものでした。
2025年1月9日に『Cell』誌に掲載された新しい研究で、グラッドストーン研究所(Gladstone Institutes)の科学者らは、この課題を解決するための大きな進展を遂げました。彼らは、長鎖DNAシーケンシング(long-read DNA sequencing)と予測型人工知能モデルを組み合わせた新手法を開発し、DNA複製によって新たに形成されたDNAがその後の数分から数時間にわたってどのような変化を辿るのかについて新たな知見を提供しました。
このオープンアクセスの論文「The Single-Molecule Accessibility Landscape of Newly Replicated Mammalian Chromatin(新たに複製された哺乳類クロマチンにおける単一分子レベルでのアクセシビリティ地図)」は、『Cell』誌のオンライン版に掲載されており、著者にはメーガン・オストロウスキ(Megan Ostrowski)、マーティ・ヤン(Marty Yang)、コリン・マクナリー(Colin McNally)、ヌール・アブドゥルヘ
 Gladstone研究所とSanBio社、幹細胞の改変により脳活動の回復を確認―脳卒中から1か月以上経過後でも効果あり
アメリカでは40秒に1人が脳卒中を発症しています。最も一般的なタイプである虚血性脳卒中の生存者のうち、完全に回復するのはわずか約5%です。多くの患者は、長期にわたる筋力低下、慢性疼痛、またはてんかんといった後遺症に苦しみ続けます。このたび、グラッドストーン研究所と再生医療企業SanBio社の科学者らは、幹細胞に由来する細胞治療が、脳卒中後に失われた正常な脳活動のパターンを回復させることを示しました。多くの脳卒中治療は発症直後の数時間以内に投与される必要がありますが、本研究で用いられた細胞治療は、発症から1か月後にラットへ投与しても有効であることが確認されました。
「現在、脳卒中発症から数週間や数か月後に投与できる治療法は存在しないため、これは非常に画期的です。」と述べるのは、本研究を主導したグラッドストーン研究所のジーン・パズ博士(Jeanne Paz, PhD)です。論文は『Molecular Therapy』誌に掲載されました。
「今回の発見は、このタイミングでも介入によって改善が可能であることを示唆しています。」
本研究は、オープンアクセス論文「Modified Human Mesenchymal Stromal/Stem Cells Restore Cortical Excitability After Focal Ischemic Stroke in Rats(改変ヒト間葉系幹細胞によるラット焦点性虚血性脳卒中後の大脳皮質興奮性の回復)」として、2024年12月11日に発表されました。
著者には、グラッドストーン研究所のアグニェシュカ・シェシエルスカ(Agnieszka Ciesielska)、ジェレミー・フォード(Jeremy
Gladstone研究所とSanBio社、幹細胞の改変により脳活動の回復を確認―脳卒中から1か月以上経過後でも効果あり
アメリカでは40秒に1人が脳卒中を発症しています。最も一般的なタイプである虚血性脳卒中の生存者のうち、完全に回復するのはわずか約5%です。多くの患者は、長期にわたる筋力低下、慢性疼痛、またはてんかんといった後遺症に苦しみ続けます。このたび、グラッドストーン研究所と再生医療企業SanBio社の科学者らは、幹細胞に由来する細胞治療が、脳卒中後に失われた正常な脳活動のパターンを回復させることを示しました。多くの脳卒中治療は発症直後の数時間以内に投与される必要がありますが、本研究で用いられた細胞治療は、発症から1か月後にラットへ投与しても有効であることが確認されました。
「現在、脳卒中発症から数週間や数か月後に投与できる治療法は存在しないため、これは非常に画期的です。」と述べるのは、本研究を主導したグラッドストーン研究所のジーン・パズ博士(Jeanne Paz, PhD)です。論文は『Molecular Therapy』誌に掲載されました。
「今回の発見は、このタイミングでも介入によって改善が可能であることを示唆しています。」
本研究は、オープンアクセス論文「Modified Human Mesenchymal Stromal/Stem Cells Restore Cortical Excitability After Focal Ischemic Stroke in Rats(改変ヒト間葉系幹細胞によるラット焦点性虚血性脳卒中後の大脳皮質興奮性の回復)」として、2024年12月11日に発表されました。
著者には、グラッドストーン研究所のアグニェシュカ・シェシエルスカ(Agnieszka Ciesielska)、ジェレミー・フォード(Jeremy
 世界センザンコウの日によせて:最新ゲノム研究が照らす、絶滅危機にあるセンザンコウの未来
うろこに覆われた唯一の哺乳類、センザンコウ。そのユニークな見た目は、写真を見れば「かわいい!」と思わず声が出てしまうほど魅力的です。しかし、愛らしいだけでなく、センザンコウは生態系において非常に重要な役割を担っています。そんな彼らが持つもう一つの「ユニークな特徴」、それは世界で最も多く密猟・密輸されている野生動物であるという悲しい現実です。過去20年間で90万頭以上が犠牲となり、その多くは伝統薬の材料として肉やうろこが高値で取引されるためです。この結果、多くのセンザンコウ種が絶滅の淵に立たされており、特にマレーセンザンコウとチュウゴクセンザンコウは深刻な生存の危機に直面しています。これらの種は、2014年以来、国際自然保護連合(acronym: IUCN)のレッドリストで「深刻な危機にある」とされています。
2月15日の「世界センザンコウの日」に合わせ、これらのセンザンコウ種に関する高品質なゲノムデータを示す新しい研究が発表され、マレーセンザンコウとチュウゴクセンザンコウの遺伝的脆弱性と絶滅リスクに光を当てています。この研究は、国家林業草原局センザンコウ保護研究センターのヤン・フア氏(Yan Hua)のチーム、東北林業大学のティアンミン・ラン教授(Tianming Lan)のチーム、そしてBGI深圳のチーイェ・リー氏(Qiye Li)が参加する中国の科学者たちによる共同研究の成果です。この研究成果は、オープンサイエンスジャーナル『GigaScience』に掲載されました。このオープンアクセス論文のタイトルは「「Enhancing Inbreeding Estimation and Global Conservation Insights Through Chromosome-Le
世界センザンコウの日によせて:最新ゲノム研究が照らす、絶滅危機にあるセンザンコウの未来
うろこに覆われた唯一の哺乳類、センザンコウ。そのユニークな見た目は、写真を見れば「かわいい!」と思わず声が出てしまうほど魅力的です。しかし、愛らしいだけでなく、センザンコウは生態系において非常に重要な役割を担っています。そんな彼らが持つもう一つの「ユニークな特徴」、それは世界で最も多く密猟・密輸されている野生動物であるという悲しい現実です。過去20年間で90万頭以上が犠牲となり、その多くは伝統薬の材料として肉やうろこが高値で取引されるためです。この結果、多くのセンザンコウ種が絶滅の淵に立たされており、特にマレーセンザンコウとチュウゴクセンザンコウは深刻な生存の危機に直面しています。これらの種は、2014年以来、国際自然保護連合(acronym: IUCN)のレッドリストで「深刻な危機にある」とされています。
2月15日の「世界センザンコウの日」に合わせ、これらのセンザンコウ種に関する高品質なゲノムデータを示す新しい研究が発表され、マレーセンザンコウとチュウゴクセンザンコウの遺伝的脆弱性と絶滅リスクに光を当てています。この研究は、国家林業草原局センザンコウ保護研究センターのヤン・フア氏(Yan Hua)のチーム、東北林業大学のティアンミン・ラン教授(Tianming Lan)のチーム、そしてBGI深圳のチーイェ・リー氏(Qiye Li)が参加する中国の科学者たちによる共同研究の成果です。この研究成果は、オープンサイエンスジャーナル『GigaScience』に掲載されました。このオープンアクセス論文のタイトルは「「Enhancing Inbreeding Estimation and Global Conservation Insights Through Chromosome-Le
 UCSFの研究者ら、妊娠初期に活性化しマウスの出産時期に影響する分子タイマーを発見
一般的な人間の妊娠期間は40週とされていますが、多くの親がご存じのように、これはあくまで目安に過ぎません。赤ちゃんは予測困難なタイミングで生まれることが多く、正常な妊娠期間は38週から42週の範囲とされています。また、全出産の10%は在胎37週未満の「早産」に該当し、この場合、さまざまな合併症のリスクが高まります。このたび、カリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF)の研究者らは、マウスにおいて出産時期の制御に関与する「分子タイマー」を発見しました。驚くべきことに、このタイマーは妊娠の最初の数日に子宮内で活性化されます。もし同様の分子機構がヒトにも当てはまるとすれば、早産リスクのある女性を特定するための新しい検査法や、そのリスクを軽減する介入手段の開発につながる可能性があります。
「早産は世界的に非常に大きな問題ですが、そのメカニズムは長らく不明でした。我々の研究が、その根本的な仕組みに光を当てるきっかけになればと願っています。」と語るのは、UCSF臨床検査医学教授であり、本研究の責任著者であるエイドリアン・アールバッカー博士(Adrian Erlebacher MD, PhD)です。本研究成果は2025年1月21日付で『Cell』誌に掲載されました。論文タイトルは「KDM6B-Dependent Epigenetic Programming of Uterine Fibroblasts in Early Pregnancy Regulates Parturition Timing in Mice(妊娠初期における子宮線維芽細胞のKDM6B依存性エピジェネティックプログラミングがマウスの出産時期を制御する)」です。
妊娠中のDNAパッケージング
妊娠を通じて、女性の
UCSFの研究者ら、妊娠初期に活性化しマウスの出産時期に影響する分子タイマーを発見
一般的な人間の妊娠期間は40週とされていますが、多くの親がご存じのように、これはあくまで目安に過ぎません。赤ちゃんは予測困難なタイミングで生まれることが多く、正常な妊娠期間は38週から42週の範囲とされています。また、全出産の10%は在胎37週未満の「早産」に該当し、この場合、さまざまな合併症のリスクが高まります。このたび、カリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF)の研究者らは、マウスにおいて出産時期の制御に関与する「分子タイマー」を発見しました。驚くべきことに、このタイマーは妊娠の最初の数日に子宮内で活性化されます。もし同様の分子機構がヒトにも当てはまるとすれば、早産リスクのある女性を特定するための新しい検査法や、そのリスクを軽減する介入手段の開発につながる可能性があります。
「早産は世界的に非常に大きな問題ですが、そのメカニズムは長らく不明でした。我々の研究が、その根本的な仕組みに光を当てるきっかけになればと願っています。」と語るのは、UCSF臨床検査医学教授であり、本研究の責任著者であるエイドリアン・アールバッカー博士(Adrian Erlebacher MD, PhD)です。本研究成果は2025年1月21日付で『Cell』誌に掲載されました。論文タイトルは「KDM6B-Dependent Epigenetic Programming of Uterine Fibroblasts in Early Pregnancy Regulates Parturition Timing in Mice(妊娠初期における子宮線維芽細胞のKDM6B依存性エピジェネティックプログラミングがマウスの出産時期を制御する)」です。
妊娠中のDNAパッケージング
妊娠を通じて、女性の
 米国国立衛生研究所(NIH)の支援による臨床試験が、デング熱の影響に苦しむ人々を助けるための実験的治療法を検証しています。デング熱は蚊が媒介するウイルス性疾患です。本研究はNIHの一機関であるアレルギー・感染症研究所(NIAID)により支援されており、成人ボランティアに軽症のデング熱を引き起こす弱毒化ウイルス株を曝露し、複数の用量で治験薬を投与することで、その安全性および症状軽減効果を評価する予定です。
米国疾病予防管理センター(CDC)によると、デング熱は感染したネッタイシマカ(Aedes蚊)によって媒介され、世界中の熱帯および亜熱帯地域を中心に、年間最大4億人が罹患しています。2024年にはアメリカ大陸におけるデング熱症例数が過去最高を記録し、アリゾナ州、カリフォルニア州、フロリダ州、ハワイ州、テキサス州で局地的な感染が報告されました。プエルトリコではデング熱が風土病として定着しており、昨年は約1,500例が報告されました。
デング熱に感染しても多くの人は症状を発症しませんが、発症した場合は激しい頭痛や全身痛、吐き気、嘔吐、発熱、発疹などが一般的です。罹患者の20人に1人が重症化し、ショックや内出血、死に至ることもあります。現在、米国食品医薬品局(FDA)に承認された治療法は存在しません。
「デング熱で重症化した患者を診る際、医療提供者には対症療法以外に選択肢がほとんどありません。」と、NIAID所長のジーン・マラッツォ医師(Jeanne Marrazzo, MD, MPH)は述べ、「デング熱に苦しむ人々に必要とされる安全かつ有効な治療法を見つける必要があります。」と語っています。
今回の新たな臨床試験では、「AV-1」と呼ばれる実験的なヒトモノクローナル抗体治療薬(investigational human monoclonal antibody
米国国立衛生研究所(NIH)の支援による臨床試験が、デング熱の影響に苦しむ人々を助けるための実験的治療法を検証しています。デング熱は蚊が媒介するウイルス性疾患です。本研究はNIHの一機関であるアレルギー・感染症研究所(NIAID)により支援されており、成人ボランティアに軽症のデング熱を引き起こす弱毒化ウイルス株を曝露し、複数の用量で治験薬を投与することで、その安全性および症状軽減効果を評価する予定です。
米国疾病予防管理センター(CDC)によると、デング熱は感染したネッタイシマカ(Aedes蚊)によって媒介され、世界中の熱帯および亜熱帯地域を中心に、年間最大4億人が罹患しています。2024年にはアメリカ大陸におけるデング熱症例数が過去最高を記録し、アリゾナ州、カリフォルニア州、フロリダ州、ハワイ州、テキサス州で局地的な感染が報告されました。プエルトリコではデング熱が風土病として定着しており、昨年は約1,500例が報告されました。
デング熱に感染しても多くの人は症状を発症しませんが、発症した場合は激しい頭痛や全身痛、吐き気、嘔吐、発熱、発疹などが一般的です。罹患者の20人に1人が重症化し、ショックや内出血、死に至ることもあります。現在、米国食品医薬品局(FDA)に承認された治療法は存在しません。
「デング熱で重症化した患者を診る際、医療提供者には対症療法以外に選択肢がほとんどありません。」と、NIAID所長のジーン・マラッツォ医師(Jeanne Marrazzo, MD, MPH)は述べ、「デング熱に苦しむ人々に必要とされる安全かつ有効な治療法を見つける必要があります。」と語っています。
今回の新たな臨床試験では、「AV-1」と呼ばれる実験的なヒトモノクローナル抗体治療薬(investigational human monoclonal antibody
 乾癬(かんせん)は、世界中で何百万人もの人々に影響を及ぼす、痛みと不快感を伴う炎症性皮膚疾患です。この疾患は、病原体や感染から身体を守る免疫細胞の活動によって悪化します。ケース・ウェスタン・リザーブ大学医学部の研究者らは、新たな研究において「NF-kB c-Rel(エヌエフ・カッパビー・シーレル)」というタンパク質が、体内の免疫系からのシグナルによって活性化されると、乾癬の症状を悪化させる可能性があることを明らかにしました。研究者らは、この「c-Rel(シーレル)」が皮膚の炎症にどのような影響を与えるのかを理解することで、新たな治療法の開発につながると述べています。
この研究は、2024年11月24日に『eBioMedicine』誌に掲載され、「NF-κB c-Rel Is a Critical Regulator of TLR7-Induced Inflammation in Psoriasis(NF-κB c-RelはTLR7誘導性乾癬炎症の重要な制御因子である)」というタイトルのオープンアクセス論文として公開されました。研究では、免疫細胞の一種である樹状細胞(DC: dendritic cells)の機能にc-Relがどのように関与しているのかが検討されました。さらに、「TLR7(トール様受容体7: Toll-like receptor 7)」という、自然免疫と炎症を制御する受容体を通じた免疫シグナルに対して、c-Relがどのように応答するのかを調べ、乾癬の悪化にどのように関与しているのかを探りました。加えて、研究者らはc-Relが欠損している場合、赤く鱗屑(りんせつ)状の皮膚症状を引き起こす炎症が軽減されることも明らかにしました。
「c-RelおよびTLR7に注目することで、科学者らが炎症を抑え、乾癬の症状を改善するような、より標的を絞った治療法を開発でき
乾癬(かんせん)は、世界中で何百万人もの人々に影響を及ぼす、痛みと不快感を伴う炎症性皮膚疾患です。この疾患は、病原体や感染から身体を守る免疫細胞の活動によって悪化します。ケース・ウェスタン・リザーブ大学医学部の研究者らは、新たな研究において「NF-kB c-Rel(エヌエフ・カッパビー・シーレル)」というタンパク質が、体内の免疫系からのシグナルによって活性化されると、乾癬の症状を悪化させる可能性があることを明らかにしました。研究者らは、この「c-Rel(シーレル)」が皮膚の炎症にどのような影響を与えるのかを理解することで、新たな治療法の開発につながると述べています。
この研究は、2024年11月24日に『eBioMedicine』誌に掲載され、「NF-κB c-Rel Is a Critical Regulator of TLR7-Induced Inflammation in Psoriasis(NF-κB c-RelはTLR7誘導性乾癬炎症の重要な制御因子である)」というタイトルのオープンアクセス論文として公開されました。研究では、免疫細胞の一種である樹状細胞(DC: dendritic cells)の機能にc-Relがどのように関与しているのかが検討されました。さらに、「TLR7(トール様受容体7: Toll-like receptor 7)」という、自然免疫と炎症を制御する受容体を通じた免疫シグナルに対して、c-Relがどのように応答するのかを調べ、乾癬の悪化にどのように関与しているのかを探りました。加えて、研究者らはc-Relが欠損している場合、赤く鱗屑(りんせつ)状の皮膚症状を引き起こす炎症が軽減されることも明らかにしました。
「c-RelおよびTLR7に注目することで、科学者らが炎症を抑え、乾癬の症状を改善するような、より標的を絞った治療法を開発でき
 あの首の長い人気者、キリン。彼らのお腹の中にいる小さな住人たち、つまり腸内細菌の驚くべき秘密が明らかになりました。私たちの常識では「食べるものが腸内環境を作る」と考えがちですが、キリンの場合は少し違うようです。スウェーデンと米国の研究チームがケニアに住む3種のキリンを調査した結果、彼らの腸内細菌の種類は、日々の食事内容よりも、なんと「どの種類のキリンか」によって決まっていることが判明したのです。この発見は、キリンの進化や健康を理解する上で新たな視点を提供するだけでなく、絶滅の危機に瀕する彼らを守るための重要な手がかりとなるかもしれません。2025年2月5日に「グローバル・エコロジー・アンド・コンサベーション」誌で発表されたこの研究では、糞便サンプルからDNAを解析するという最新技術を駆使し、キリンの食生活と腸内細菌叢(gut flora: ガットフローラ)の複雑な関係に迫りました。論文タイトルは「Diet-Microbiome Covariation Across Three Giraffe Species in a Close-Contact Zone(近接接触ゾーンにおける3種のキリン間の食事とマイクロバイオームの共変動)」です。
キリンにおける種特異的な腸内細菌叢
研究者たちは、ケニアの赤道付近に生息するアミメキリン、マサイキリン、キタキリンという3つの異なる種からサンプルを収集しました。科学者たちは、マイクロバイオームが、キリンが何を食べたかではなく、どの種に属するかによって主に決定されることを発見しました。
「私たちは、似たような食事をしているキリンは、マイクロバイオームも似ているだろうと予想していましたが、そのような関連は見つかりませんでした。それどころか、同じ種の中でも個体によって全く異なる植物を食べている場合でさえ、キリンは種特有のマイクロバイオ
あの首の長い人気者、キリン。彼らのお腹の中にいる小さな住人たち、つまり腸内細菌の驚くべき秘密が明らかになりました。私たちの常識では「食べるものが腸内環境を作る」と考えがちですが、キリンの場合は少し違うようです。スウェーデンと米国の研究チームがケニアに住む3種のキリンを調査した結果、彼らの腸内細菌の種類は、日々の食事内容よりも、なんと「どの種類のキリンか」によって決まっていることが判明したのです。この発見は、キリンの進化や健康を理解する上で新たな視点を提供するだけでなく、絶滅の危機に瀕する彼らを守るための重要な手がかりとなるかもしれません。2025年2月5日に「グローバル・エコロジー・アンド・コンサベーション」誌で発表されたこの研究では、糞便サンプルからDNAを解析するという最新技術を駆使し、キリンの食生活と腸内細菌叢(gut flora: ガットフローラ)の複雑な関係に迫りました。論文タイトルは「Diet-Microbiome Covariation Across Three Giraffe Species in a Close-Contact Zone(近接接触ゾーンにおける3種のキリン間の食事とマイクロバイオームの共変動)」です。
キリンにおける種特異的な腸内細菌叢
研究者たちは、ケニアの赤道付近に生息するアミメキリン、マサイキリン、キタキリンという3つの異なる種からサンプルを収集しました。科学者たちは、マイクロバイオームが、キリンが何を食べたかではなく、どの種に属するかによって主に決定されることを発見しました。
「私たちは、似たような食事をしているキリンは、マイクロバイオームも似ているだろうと予想していましたが、そのような関連は見つかりませんでした。それどころか、同じ種の中でも個体によって全く異なる植物を食べている場合でさえ、キリンは種特有のマイクロバイオ
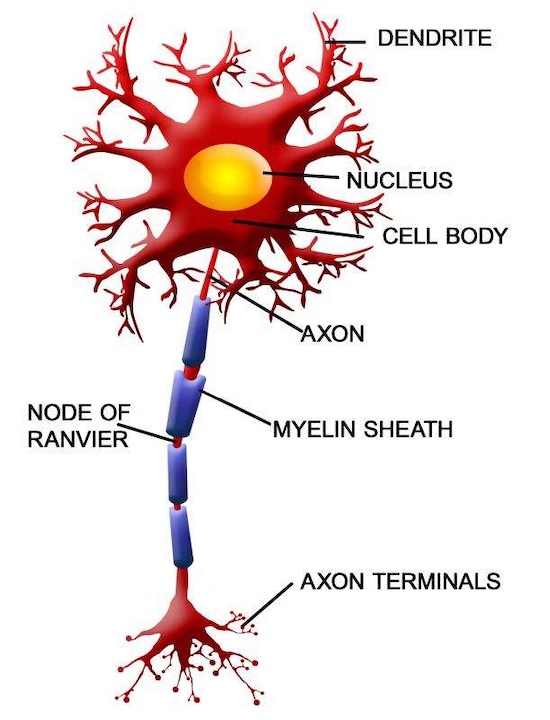 神経細胞が注目を浴びる一方で、グリア細胞なしでは成り立ちません。
脳の神経細胞が神経系における主要な働きを担う一方で、栄養供給、老廃物の除去、神経細胞の保護といった役割を果たしているのがグリア細胞です。2025年1月2日に『Nature Communications』誌に掲載された新たな論文では、これらの重要なサポート役であるグリア細胞が神経細胞の損傷を感知し、反応する新たな仕組みが明らかにされました。この研究では、2つの主要なタンパク質が、線虫(C. elegans)の樹状突起から伸びる毛のような繊毛をグリア細胞が積極的にモニタリングし、損傷時に対応・防御する働きを果たしていることが示されています。この発見は、多嚢胞腎疾患(PKD)など、繊毛の異常が原因となる疾患の治療法開発においても新たな可能性をもたらすかもしれません。
このオープンアクセス論文のタイトルは「Glia Detect and Transiently Protect Against Dendrite Substructure Disruption in C. elegans(グリア細胞はC. elegansの樹状突起構造の破壊を感知し、一時的に保護する)」です。
「グリア細胞が樹状突起とどのように関与するかという経路を明らかにすることが、我々の主な目的でした」と語るのは、ロックフェラー大学 発生遺伝学研究室の責任者、シャイ・シャハム博士(Shai Shaham, PhD)です。
「今後の重要な課題は、この細胞の働きを操作することで、繊毛に関連する疾患に対応できるかどうかです。」
未知の領域へ
神経細胞は、情報を伝達するために軸索と樹状突起を用いており、軸索は信号を送り出す役割、樹状突起は信号を受け取る役割を担っています。一部の樹状突起の先端には繊毛が伸びており、これによってにおいや光、
神経細胞が注目を浴びる一方で、グリア細胞なしでは成り立ちません。
脳の神経細胞が神経系における主要な働きを担う一方で、栄養供給、老廃物の除去、神経細胞の保護といった役割を果たしているのがグリア細胞です。2025年1月2日に『Nature Communications』誌に掲載された新たな論文では、これらの重要なサポート役であるグリア細胞が神経細胞の損傷を感知し、反応する新たな仕組みが明らかにされました。この研究では、2つの主要なタンパク質が、線虫(C. elegans)の樹状突起から伸びる毛のような繊毛をグリア細胞が積極的にモニタリングし、損傷時に対応・防御する働きを果たしていることが示されています。この発見は、多嚢胞腎疾患(PKD)など、繊毛の異常が原因となる疾患の治療法開発においても新たな可能性をもたらすかもしれません。
このオープンアクセス論文のタイトルは「Glia Detect and Transiently Protect Against Dendrite Substructure Disruption in C. elegans(グリア細胞はC. elegansの樹状突起構造の破壊を感知し、一時的に保護する)」です。
「グリア細胞が樹状突起とどのように関与するかという経路を明らかにすることが、我々の主な目的でした」と語るのは、ロックフェラー大学 発生遺伝学研究室の責任者、シャイ・シャハム博士(Shai Shaham, PhD)です。
「今後の重要な課題は、この細胞の働きを操作することで、繊毛に関連する疾患に対応できるかどうかです。」
未知の領域へ
神経細胞は、情報を伝達するために軸索と樹状突起を用いており、軸索は信号を送り出す役割、樹状突起は信号を受け取る役割を担っています。一部の樹状突起の先端には繊毛が伸びており、これによってにおいや光、
 ラトガース・ヘルスの研究者らは、極めてまれな遺伝性疾患である先天性全身性脂肪萎縮症(CGL: congenital generalized lipodystrophy)患者において、糖尿病治療薬の週1回の注射が、痛みを伴う日々のホルモン注射に代わる可能性があることを明らかにしました。この研究結果は、2025年1月29日に『The New England Journal of Medicine』誌に「Tirzepatide for Congenital Generalized Lipodystrophy(先天性全身性脂肪萎縮症に対するチルゼパチド)」というタイトルで掲載されました。CGLは全世界で数千人程度しか罹患していない極めて稀な疾患で、深刻な代謝障害、糖尿病、インスリン抵抗性、そして寿命の短縮を引き起こします。この疾患では脂肪組織がほとんど存在しないため、脂肪の適切な貯蔵が行えず、肝臓などの臓器に脂肪が蓄積してしまい、重度のインスリン抵抗性と糖尿病を引き起こします。
「これらの患者さんは重篤な状態で、深刻なインスリン抵抗性のために著しく寿命が短縮されてしまいます」と、ラトガース・ロバート・ウッド・ジョンソン医科大学の内分泌・代謝・栄養学部門長であり、本研究の責任著者であるクリストフ・ビュトナー博士(Christoph Buettner MD, PhD)は述べています。
現在、CGLの標準的な治療法は、脂肪組織のみが自然に産生するホルモンであるレプチンの合成版「メトレレプチン」の毎日の注射です。しかし、これらの注射は非常に高価で、年間数百万円に及ぶ上に、CGL患者にとって非常に痛みを伴う治療です。
「例えばインスリンを注射する場合、通常は皮下脂肪に注射しますが、CGLの患者さんにはその脂肪がありません」と、本研究の第一著者であるスヴェトラーナ・テン博士(Sv
ラトガース・ヘルスの研究者らは、極めてまれな遺伝性疾患である先天性全身性脂肪萎縮症(CGL: congenital generalized lipodystrophy)患者において、糖尿病治療薬の週1回の注射が、痛みを伴う日々のホルモン注射に代わる可能性があることを明らかにしました。この研究結果は、2025年1月29日に『The New England Journal of Medicine』誌に「Tirzepatide for Congenital Generalized Lipodystrophy(先天性全身性脂肪萎縮症に対するチルゼパチド)」というタイトルで掲載されました。CGLは全世界で数千人程度しか罹患していない極めて稀な疾患で、深刻な代謝障害、糖尿病、インスリン抵抗性、そして寿命の短縮を引き起こします。この疾患では脂肪組織がほとんど存在しないため、脂肪の適切な貯蔵が行えず、肝臓などの臓器に脂肪が蓄積してしまい、重度のインスリン抵抗性と糖尿病を引き起こします。
「これらの患者さんは重篤な状態で、深刻なインスリン抵抗性のために著しく寿命が短縮されてしまいます」と、ラトガース・ロバート・ウッド・ジョンソン医科大学の内分泌・代謝・栄養学部門長であり、本研究の責任著者であるクリストフ・ビュトナー博士(Christoph Buettner MD, PhD)は述べています。
現在、CGLの標準的な治療法は、脂肪組織のみが自然に産生するホルモンであるレプチンの合成版「メトレレプチン」の毎日の注射です。しかし、これらの注射は非常に高価で、年間数百万円に及ぶ上に、CGL患者にとって非常に痛みを伴う治療です。
「例えばインスリンを注射する場合、通常は皮下脂肪に注射しますが、CGLの患者さんにはその脂肪がありません」と、本研究の第一著者であるスヴェトラーナ・テン博士(Sv
 カーネーションのようなナノ構造体が、将来的には創傷治癒を促進するための包帯に使用される可能性があります。研究者らは『ACS Applied Bio Materials』誌において、ナノフラワーでコーティングされた包帯の実験室試験により、抗生物質作用、抗炎症作用、そして生体適合性を示したと報告しています。これらの結果から、タンニン酸とリン酸銅(II)から発芽させたナノフラワー包帯が、感染症や炎症性疾患の治療において有望な候補であると述べています。この論文は2025年1月6日に発表され、タイトルは「Self-Assembled Nanoflowers from Natural Building Blocks with Antioxidant, Antibacterial, and Antibiofilm Properties(抗酸化・抗菌・抗バイオフィルム特性を有する天然構成要素由来の自己組織化ナノフラワー)」です。
ナノフラワーは、自発的に組み上がる微細な構造体ですが、その広い表面積により薬剤分子を多数付着させることができ、薬剤の送達に特に適しています。包帯の「花」を設計するにあたり、ジェノヴァ大学のファテメ・アフマドプール(Fatemeh Ahmadpoor)とピエル・フランチェスコ・フェラーリ(Pier Francesco Ferrari)らは、タンニン酸とリン酸銅(II)を使用しました。両方の試薬が抗菌性および抗炎症性を有するためです。研究者らは、生理食塩水中でナノフラワーを成長させた後、生体模倣構造をエレクトロスピニング法で作製したナノファイバー布地のストリップに付着させました。
その結果、ナノフラワーでコーティングされた包帯は、培養された広範な細菌(大腸菌、緑膿菌、黄色ブドウ球菌など)およびそれらの抗生物質耐性バイオフィルムを不活性化し、活性酸素種(ROS)
カーネーションのようなナノ構造体が、将来的には創傷治癒を促進するための包帯に使用される可能性があります。研究者らは『ACS Applied Bio Materials』誌において、ナノフラワーでコーティングされた包帯の実験室試験により、抗生物質作用、抗炎症作用、そして生体適合性を示したと報告しています。これらの結果から、タンニン酸とリン酸銅(II)から発芽させたナノフラワー包帯が、感染症や炎症性疾患の治療において有望な候補であると述べています。この論文は2025年1月6日に発表され、タイトルは「Self-Assembled Nanoflowers from Natural Building Blocks with Antioxidant, Antibacterial, and Antibiofilm Properties(抗酸化・抗菌・抗バイオフィルム特性を有する天然構成要素由来の自己組織化ナノフラワー)」です。
ナノフラワーは、自発的に組み上がる微細な構造体ですが、その広い表面積により薬剤分子を多数付着させることができ、薬剤の送達に特に適しています。包帯の「花」を設計するにあたり、ジェノヴァ大学のファテメ・アフマドプール(Fatemeh Ahmadpoor)とピエル・フランチェスコ・フェラーリ(Pier Francesco Ferrari)らは、タンニン酸とリン酸銅(II)を使用しました。両方の試薬が抗菌性および抗炎症性を有するためです。研究者らは、生理食塩水中でナノフラワーを成長させた後、生体模倣構造をエレクトロスピニング法で作製したナノファイバー布地のストリップに付着させました。
その結果、ナノフラワーでコーティングされた包帯は、培養された広範な細菌(大腸菌、緑膿菌、黄色ブドウ球菌など)およびそれらの抗生物質耐性バイオフィルムを不活性化し、活性酸素種(ROS)
 数分でゲノム構造を予測:AIが切り拓く新時代のクロマチン解析
特定のDNA配列が細胞核内でどのように配置されるかを予測する新たなアプローチが、これまで数日かかっていた解析をわずか数分で可能にしました。人間の体内のすべての細胞は同じ遺伝情報を持っていますが、実際に発現する遺伝子は細胞ごとに異なります。脳細胞と皮膚細胞が異なる機能を持つのは、三次元的なゲノム構造が各遺伝子のアクセス可能性を調整し、細胞特異的な遺伝子発現パターンを作り出しているためです。
MITの化学者らは、生成型人工知能を用いて、これらの3Dゲノム構造を高速かつ正確に予測する新技術を開発しました。この技術により、従来の実験法よりもはるかに短時間で数千の構造を予測することが可能となり、ゲノムの三次元配置が細胞機能や遺伝子発現にどのような影響を及ぼすのかを解明する研究が加速することが期待されます。
「私たちの目的は、DNA配列から3次元のゲノム構造を予測することでした」と語るのは、MIT化学科の准教授であり、この研究の責任著者であるビン・チャン博士(Bin Zhang, PhD)です。「この技術は最先端の実験技術と同等の精度を持ち、非常に多くの新しい研究機会を切り開くことができます。」
この研究は、MITの大学院生であるグレッグ・シュエッテ(Greg Schuette)氏とズオハン・ラオ(Zhuohan Lao)氏が筆頭著者を務め、2025年1月31日に『Science Advances』誌に掲載されました。論文タイトルは「ChromoGen: Diffusion Model Predicts Single-Cell Chromatin Conformations(ChromoGen:拡散モデルによる単一細胞クロマチン構造の予測)」です。
配列から構造へ:DNAの折りたたみをAIで予測
細
数分でゲノム構造を予測:AIが切り拓く新時代のクロマチン解析
特定のDNA配列が細胞核内でどのように配置されるかを予測する新たなアプローチが、これまで数日かかっていた解析をわずか数分で可能にしました。人間の体内のすべての細胞は同じ遺伝情報を持っていますが、実際に発現する遺伝子は細胞ごとに異なります。脳細胞と皮膚細胞が異なる機能を持つのは、三次元的なゲノム構造が各遺伝子のアクセス可能性を調整し、細胞特異的な遺伝子発現パターンを作り出しているためです。
MITの化学者らは、生成型人工知能を用いて、これらの3Dゲノム構造を高速かつ正確に予測する新技術を開発しました。この技術により、従来の実験法よりもはるかに短時間で数千の構造を予測することが可能となり、ゲノムの三次元配置が細胞機能や遺伝子発現にどのような影響を及ぼすのかを解明する研究が加速することが期待されます。
「私たちの目的は、DNA配列から3次元のゲノム構造を予測することでした」と語るのは、MIT化学科の准教授であり、この研究の責任著者であるビン・チャン博士(Bin Zhang, PhD)です。「この技術は最先端の実験技術と同等の精度を持ち、非常に多くの新しい研究機会を切り開くことができます。」
この研究は、MITの大学院生であるグレッグ・シュエッテ(Greg Schuette)氏とズオハン・ラオ(Zhuohan Lao)氏が筆頭著者を務め、2025年1月31日に『Science Advances』誌に掲載されました。論文タイトルは「ChromoGen: Diffusion Model Predicts Single-Cell Chromatin Conformations(ChromoGen:拡散モデルによる単一細胞クロマチン構造の予測)」です。
配列から構造へ:DNAの折りたたみをAIで予測
細
 2025年1月16日付で『Cell』誌に掲載された新たな研究論文「Long Somatic DNA-Repeat Expansion Drives Neurodegeneration in Huntington’s Disease(長い体細胞DNAリピートの拡大がハンチントン病の神経変性を引き起こす)」では、ハンチントン病(HD)について詳細に検討されており、その進行がHTT遺伝子内のCAGリピートの体細胞内拡大と特定の神経細胞において関連していることが明らかになりました。この研究は、ハーバード・メディカル・スクールおよびマサチューセッツ工科大学・ハーバード大学のブロード研究所に所属するロバート・E・ハンズエイカー(Robert E. Handsaker)、セヴァ・カシン(Seva Kashin)、サビーナ・ベレッタ(Sabina Berretta)、スティーブン・A・マッキャロール(Steven A. McCarroll)ら研究者によって主導されました。本研究は、HDの特徴的な神経細胞変性、特に線条体投射ニューロン(SPN)におけるメカニズムに光を当てるものです。この成果は、HDに関する重要な疑問を明らかにするとともに、同様の遺伝性疾患に対する新たな治療方針を示唆しています。
ハンチントン病のメカニズム
HDは、HTT遺伝子内のCAGリピート配列の生殖細胞系列における拡大によって引き起こされます。通常の人ではこのリピートは15〜30回ですが、HDを発症する人では36回以上となっています。この拡大はハンチンチン(huntingtin)タンパク質内のポリグルタミン配列をコードし、これが疾患の発症に関与していると考えられています。しかしながら、遺伝的に受け継がれたリピートの長さが発症リスクや発症年齢を決定する一方で、どのようにして神経細胞死が起こるのかは長年の謎でし
2025年1月16日付で『Cell』誌に掲載された新たな研究論文「Long Somatic DNA-Repeat Expansion Drives Neurodegeneration in Huntington’s Disease(長い体細胞DNAリピートの拡大がハンチントン病の神経変性を引き起こす)」では、ハンチントン病(HD)について詳細に検討されており、その進行がHTT遺伝子内のCAGリピートの体細胞内拡大と特定の神経細胞において関連していることが明らかになりました。この研究は、ハーバード・メディカル・スクールおよびマサチューセッツ工科大学・ハーバード大学のブロード研究所に所属するロバート・E・ハンズエイカー(Robert E. Handsaker)、セヴァ・カシン(Seva Kashin)、サビーナ・ベレッタ(Sabina Berretta)、スティーブン・A・マッキャロール(Steven A. McCarroll)ら研究者によって主導されました。本研究は、HDの特徴的な神経細胞変性、特に線条体投射ニューロン(SPN)におけるメカニズムに光を当てるものです。この成果は、HDに関する重要な疑問を明らかにするとともに、同様の遺伝性疾患に対する新たな治療方針を示唆しています。
ハンチントン病のメカニズム
HDは、HTT遺伝子内のCAGリピート配列の生殖細胞系列における拡大によって引き起こされます。通常の人ではこのリピートは15〜30回ですが、HDを発症する人では36回以上となっています。この拡大はハンチンチン(huntingtin)タンパク質内のポリグルタミン配列をコードし、これが疾患の発症に関与していると考えられています。しかしながら、遺伝的に受け継がれたリピートの長さが発症リスクや発症年齢を決定する一方で、どのようにして神経細胞死が起こるのかは長年の謎でし
 クリーブランド・クリニックの研究により、パーキンソン病に関与する可能性のある遺伝的要因および再利用可能な治療薬が特定されました。クリーブランド・クリニック ゲノムセンター(Cleveland Clinic Genome Center、以下CCGC)の研究者らは、先進的な人工知能(AI)遺伝学モデルをパーキンソン病に応用することに成功しました。研究者らは、疾患の進行に関与する遺伝的要因と、パーキンソン病(Parkinson’s disease:PD)の治療に再利用できる可能性のある米国食品医薬品局(FDA)承認済みの医薬品を特定しました。この成果は、2025年1月22日に『npj Parkinson’s Disease』誌に発表された公開アクセスの論文「A Network-Based Systems Genetics Framework Identifies Pathobiology and Drug Repurposing in Parkinson’s Disease(ネットワークベースのシステム遺伝学フレームワークによるパーキンソン病の病態生物学と薬剤再利用の特定)」で報告されています。
この研究では、遺伝子、プロテオーム、医薬品、患者データなど複数の情報をAIで統合・解析し、単一のデータだけでは見えないパターンを見つけ出す「システム生物学」というアプローチが用いられました。
本研究の責任著者でありCCGCのディレクターを務めるフェイション・チェン博士(Feixiong Cheng, PhD)は、システム生物学分野の第一人者であり、アルツハイマー病の新たな治療法を見出すための複数のAIフレームワークを開発してきた実績を持ちます。
「パーキンソン病は、認知症に次いで2番目に多い神経変性疾患ですが、世界中でこの病気に苦しむ何百万人もの人々に対し、進行を止めたり遅ら
クリーブランド・クリニックの研究により、パーキンソン病に関与する可能性のある遺伝的要因および再利用可能な治療薬が特定されました。クリーブランド・クリニック ゲノムセンター(Cleveland Clinic Genome Center、以下CCGC)の研究者らは、先進的な人工知能(AI)遺伝学モデルをパーキンソン病に応用することに成功しました。研究者らは、疾患の進行に関与する遺伝的要因と、パーキンソン病(Parkinson’s disease:PD)の治療に再利用できる可能性のある米国食品医薬品局(FDA)承認済みの医薬品を特定しました。この成果は、2025年1月22日に『npj Parkinson’s Disease』誌に発表された公開アクセスの論文「A Network-Based Systems Genetics Framework Identifies Pathobiology and Drug Repurposing in Parkinson’s Disease(ネットワークベースのシステム遺伝学フレームワークによるパーキンソン病の病態生物学と薬剤再利用の特定)」で報告されています。
この研究では、遺伝子、プロテオーム、医薬品、患者データなど複数の情報をAIで統合・解析し、単一のデータだけでは見えないパターンを見つけ出す「システム生物学」というアプローチが用いられました。
本研究の責任著者でありCCGCのディレクターを務めるフェイション・チェン博士(Feixiong Cheng, PhD)は、システム生物学分野の第一人者であり、アルツハイマー病の新たな治療法を見出すための複数のAIフレームワークを開発してきた実績を持ちます。
「パーキンソン病は、認知症に次いで2番目に多い神経変性疾患ですが、世界中でこの病気に苦しむ何百万人もの人々に対し、進行を止めたり遅ら
 マギル大学が主導する新たな研究によると、体の自然な睡眠・覚醒サイクルと連動する脳のリズムが、双極性障害の患者が躁状態と抑うつ状態を交互に経験する理由を説明する可能性があると示されています。この研究成果は2025年1月1日付で『Science Advances』誌に掲載され、双極性障害における二つの状態の切り替わりを引き起こす要因に関する理解において、画期的な前進を示しています。筆頭著者であるカイ=フロリアン・シュトルヒ博士(Kai-Florian Storch, PhD)は、この現象の解明は「双極性障害研究の聖杯」とされています。
このオープンアクセス論文のタイトルは「Mesolimbic Dopamine Neurons Drive Infradian Rhythms In Sleep-Wake and Heightened Activity State(中脳辺縁系のドーパミン神経が睡眠・覚醒および活動亢進状態における亜日周期リズムを駆動する)」です。
「私たちのモデルは、気分のスイッチや周期変動のための初の普遍的なメカニズムを示しており、それは太陽と月が定期的に大潮を引き起こすような仕組みと類似しています」と、マギル大学精神医学部の准教授であり、ダグラス研究センター所属の研究者であるカイ=フロリアン・シュトルヒ博士(Kai-Florian Storch, PhD)は述べています。
本研究によれば、双極性障害の患者における定期的な気分変動は、2つの「時計」によって制御されている可能性があります。一つは24時間周期の生物時計であり、もう一つは通常覚醒状態に関与するドーパミン産生ニューロンによって駆動される第二の時計です。これら異なる速度で動作する2つの時計のタイミングが特定の時点でどのように一致するかにより、躁状態や抑うつ状態が生じると考えられています。
注目す
マギル大学が主導する新たな研究によると、体の自然な睡眠・覚醒サイクルと連動する脳のリズムが、双極性障害の患者が躁状態と抑うつ状態を交互に経験する理由を説明する可能性があると示されています。この研究成果は2025年1月1日付で『Science Advances』誌に掲載され、双極性障害における二つの状態の切り替わりを引き起こす要因に関する理解において、画期的な前進を示しています。筆頭著者であるカイ=フロリアン・シュトルヒ博士(Kai-Florian Storch, PhD)は、この現象の解明は「双極性障害研究の聖杯」とされています。
このオープンアクセス論文のタイトルは「Mesolimbic Dopamine Neurons Drive Infradian Rhythms In Sleep-Wake and Heightened Activity State(中脳辺縁系のドーパミン神経が睡眠・覚醒および活動亢進状態における亜日周期リズムを駆動する)」です。
「私たちのモデルは、気分のスイッチや周期変動のための初の普遍的なメカニズムを示しており、それは太陽と月が定期的に大潮を引き起こすような仕組みと類似しています」と、マギル大学精神医学部の准教授であり、ダグラス研究センター所属の研究者であるカイ=フロリアン・シュトルヒ博士(Kai-Florian Storch, PhD)は述べています。
本研究によれば、双極性障害の患者における定期的な気分変動は、2つの「時計」によって制御されている可能性があります。一つは24時間周期の生物時計であり、もう一つは通常覚醒状態に関与するドーパミン産生ニューロンによって駆動される第二の時計です。これら異なる速度で動作する2つの時計のタイミングが特定の時点でどのように一致するかにより、躁状態や抑うつ状態が生じると考えられています。
注目す
 世界の人口のおよそ10人に1人が、希少遺伝性疾患の影響を受けていますが、急速に進展する遺伝子技術や検査手法にもかかわらず、約50%の患者はいまだに診断されていません。たとえ検査にアクセスできたとしても、診断がつくまでに約5年、あるいはそれ以上かかることが多く、特に患者が子どもである場合、適切な治療を始めるには遅すぎることもあります。この問題の一因は、現在の臨床検査で主に使用されている「ショートリードシーケンシング」という手法にあります。この方法では、ゲノムの一部の領域にアクセスできず、診断に必要な重要な情報が見逃される可能性があります。
カリフォルニア大学サンタクルーズ校(UC Santa Cruz, UCSC)の研究者らは、これに代わる最先端技術「ロングリードシーケンシング(long-read sequencing)」の研究を推進しており、これはより包括的な変異検出データセットを提供し、複数の専門的検査を不要にし、希少疾患の診断を効率化できる可能性があります。
2025年1月24日付で『The American Journal of Human Genetics』誌に掲載された研究論文「Advancing Long-Read Nanopore Genome Assembly and Accurate Variant Calling for Rare Disease Detection(ロングリードナノポアによるゲノムアセンブリと高精度変異検出の進展が希少疾患診断を可能にする)」では、この技術が診断率を向上させ、診断にかかる期間を数年から数日に短縮できる可能性があることが示されました。この研究は、UCSCゲノミクス研究所の中核メンバーであるベネディクト・ペイトン博士(Benedict Paten, PhD)教授、カレン・ミーガ博士(Karen Miga, Ph
世界の人口のおよそ10人に1人が、希少遺伝性疾患の影響を受けていますが、急速に進展する遺伝子技術や検査手法にもかかわらず、約50%の患者はいまだに診断されていません。たとえ検査にアクセスできたとしても、診断がつくまでに約5年、あるいはそれ以上かかることが多く、特に患者が子どもである場合、適切な治療を始めるには遅すぎることもあります。この問題の一因は、現在の臨床検査で主に使用されている「ショートリードシーケンシング」という手法にあります。この方法では、ゲノムの一部の領域にアクセスできず、診断に必要な重要な情報が見逃される可能性があります。
カリフォルニア大学サンタクルーズ校(UC Santa Cruz, UCSC)の研究者らは、これに代わる最先端技術「ロングリードシーケンシング(long-read sequencing)」の研究を推進しており、これはより包括的な変異検出データセットを提供し、複数の専門的検査を不要にし、希少疾患の診断を効率化できる可能性があります。
2025年1月24日付で『The American Journal of Human Genetics』誌に掲載された研究論文「Advancing Long-Read Nanopore Genome Assembly and Accurate Variant Calling for Rare Disease Detection(ロングリードナノポアによるゲノムアセンブリと高精度変異検出の進展が希少疾患診断を可能にする)」では、この技術が診断率を向上させ、診断にかかる期間を数年から数日に短縮できる可能性があることが示されました。この研究は、UCSCゲノミクス研究所の中核メンバーであるベネディクト・ペイトン博士(Benedict Paten, PhD)教授、カレン・ミーガ博士(Karen Miga, Ph
 遺伝的な観点から見ると、これはバクテリアにとって最悪のシナリオです。転写の過程で、新しく合成されたRNAがDNAの鋳型にくっつき、「Rループ(R-loop)」と呼ばれる三本鎖構造を形成します。これらの構造は細胞内で重要な役割を果たす一方で、不適切な場所やタイミングで生じると、DNAの切断、突然変異、そして細胞死を引き起こす原因にもなり得ます。 このたび『Nature Structural & Molecular Biology』誌に掲載された新しい研究論文「RapA Opens the RNA Polymerase Clamp to Disrupt Post-Termination Complexes and Prevent Cytotoxic R-loop Formation(RapAはRNAポリメラーゼのクランプを開き、転写終了後複合体を解体して細胞毒性Rループの形成を防ぐ)」では、大腸菌(E. coli)において酵素RapAがRループの形成を防ぐ仕組みが解明され、全ての細胞がゲノムの安定性をどのように維持しているかについて重要な示唆を与えています。
この研究結果は、DNAをRNAへと転写する役割を担うRNAポリメラーゼ(acronym: RNAP, original English term: RNA polymerase)という酵素が、特定の条件下ではRループを大量に生成してしまう可能性があることを示しています。しかし、それを未然に防いでいるのがRapAというタンパク質です。
「Rループは基本的に細胞にとって厄介な存在なので、それらの形成を防ぐために、細胞は多数の冗長的な機構を備えています」と、ロックフェラー大学分子生物物理学研究室の主任であるセス・ダーシュト博士(Seth Darst, PhD)氏は語ります。「私たちは長年関心を持っていたRapA
遺伝的な観点から見ると、これはバクテリアにとって最悪のシナリオです。転写の過程で、新しく合成されたRNAがDNAの鋳型にくっつき、「Rループ(R-loop)」と呼ばれる三本鎖構造を形成します。これらの構造は細胞内で重要な役割を果たす一方で、不適切な場所やタイミングで生じると、DNAの切断、突然変異、そして細胞死を引き起こす原因にもなり得ます。 このたび『Nature Structural & Molecular Biology』誌に掲載された新しい研究論文「RapA Opens the RNA Polymerase Clamp to Disrupt Post-Termination Complexes and Prevent Cytotoxic R-loop Formation(RapAはRNAポリメラーゼのクランプを開き、転写終了後複合体を解体して細胞毒性Rループの形成を防ぐ)」では、大腸菌(E. coli)において酵素RapAがRループの形成を防ぐ仕組みが解明され、全ての細胞がゲノムの安定性をどのように維持しているかについて重要な示唆を与えています。
この研究結果は、DNAをRNAへと転写する役割を担うRNAポリメラーゼ(acronym: RNAP, original English term: RNA polymerase)という酵素が、特定の条件下ではRループを大量に生成してしまう可能性があることを示しています。しかし、それを未然に防いでいるのがRapAというタンパク質です。
「Rループは基本的に細胞にとって厄介な存在なので、それらの形成を防ぐために、細胞は多数の冗長的な機構を備えています」と、ロックフェラー大学分子生物物理学研究室の主任であるセス・ダーシュト博士(Seth Darst, PhD)氏は語ります。「私たちは長年関心を持っていたRapA
 ミトコンドリアは細胞の恒常性維持において極めて重要な細胞小器官であり、ATP産生、活性酸素種(ROS: reactive oxygen species)の制御、Ca2+シグナリングなどのプロセスを調節しています。特にミトコンドリア内のCa2+は、生理的機能(代謝やATP合成)を可能にする一方で、調節が破綻するとアポトーシス(細胞死)や酸化ストレスといった病理的プロセスにも関与するという二面性を持っています。ミトコンドリア内Ca2+のバランスは、取り込みと排出のメカニズムの相互作用によって維持されています。Ca2+の流入に関与するミトコンドリアCa2+ユニポーター複合体(MCU: mitochondrial calcium uniporter)や、Ca2+の排出を担うNa+/Ca2+交換輸送体(NCLX: Na+/Ca2+ exchanger)といった主要な分子が関与しています。さらに、ミトコンドリアと小胞体との接触部位(MERCS: mitochondria-endoplasmic reticulum contact sites)も、Ca2+の移動を促進する上で重要な役割を果たします。
このシステムのいずれかのレベルで調節異常が起きると、例えば過剰な取り込みや排出機能の障害が発生し、ミトコンドリアCa2+の過剰蓄積を引き起こします。これにより、ROSの産生、ミトコンドリア膜電位の喪失、透過性遷移孔(mPTP: mitochondrial permeability transition pore)の活性化が誘発され、最終的には細胞死へとつながります。
中国科学院の研究者ら(KeAiジャーナル『Mitochondrial Communications』2025年1月14日掲載)は、ミトコンドリアCa2+の恒常性破綻が神経変性疾患に果たす役割について概説した総説「Deco
ミトコンドリアは細胞の恒常性維持において極めて重要な細胞小器官であり、ATP産生、活性酸素種(ROS: reactive oxygen species)の制御、Ca2+シグナリングなどのプロセスを調節しています。特にミトコンドリア内のCa2+は、生理的機能(代謝やATP合成)を可能にする一方で、調節が破綻するとアポトーシス(細胞死)や酸化ストレスといった病理的プロセスにも関与するという二面性を持っています。ミトコンドリア内Ca2+のバランスは、取り込みと排出のメカニズムの相互作用によって維持されています。Ca2+の流入に関与するミトコンドリアCa2+ユニポーター複合体(MCU: mitochondrial calcium uniporter)や、Ca2+の排出を担うNa+/Ca2+交換輸送体(NCLX: Na+/Ca2+ exchanger)といった主要な分子が関与しています。さらに、ミトコンドリアと小胞体との接触部位(MERCS: mitochondria-endoplasmic reticulum contact sites)も、Ca2+の移動を促進する上で重要な役割を果たします。
このシステムのいずれかのレベルで調節異常が起きると、例えば過剰な取り込みや排出機能の障害が発生し、ミトコンドリアCa2+の過剰蓄積を引き起こします。これにより、ROSの産生、ミトコンドリア膜電位の喪失、透過性遷移孔(mPTP: mitochondrial permeability transition pore)の活性化が誘発され、最終的には細胞死へとつながります。
中国科学院の研究者ら(KeAiジャーナル『Mitochondrial Communications』2025年1月14日掲載)は、ミトコンドリアCa2+の恒常性破綻が神経変性疾患に果たす役割について概説した総説「Deco
 Natureに掲載された研究により、双極性障害に関連する約300のゲノム領域と、疾患に関与する36の主要な遺伝子が特定される
この研究から得られた生物学的知見は、より優れた治療法の開発、早期介入、そしてプレシジョン・メディシン(精密医療)への道を開く可能性があります。双極性障害は、(軽)躁状態と抑うつ状態の間を変動することを特徴とする複雑な精神疾患です。世界中で約4,000万~5,000万人がこの疾患を抱えていると推定されています。双極性障害は、自殺を含むさまざまな負の影響と関連しており、診断までに平均8年かかることが知られています。しかし、この疾患の生物学的なメカニズムについては未だ十分に解明されていません。
今回の新たな研究では、約290万人の参加者のデータを分析しました。研究者らは、欧州系、東アジア系、アフリカ系アメリカ人、ラテン系の祖先を持つ参加者(双極性障害患者158,036名、対照群280万人)を対象に、臨床データ、地域社会ベースのデータ、自己申告データを統合して解析しました。その結果、双極性障害に関連する298のゲノム領域が特定され、これまでの発見の4倍に相当する成果となりました。さらに、複数の手法を組み合わせた解析により、双極性障害と強く関連する36の遺伝子が特定されました。
この研究結果は2025年1月22日にNature誌に掲載されました。論文のタイトルは「Genomics Yields Biological and Phenotypic Insights into Bipolar Disorder(ゲノミクスがもたらす双極性障害の生物学的・表現型的洞察)」です。
「これは、双極性障害に関する初の大規模な多民族ゲノム解析であり、双極性障害の異なるタイプを含んでいます。大規模なサンプルサイズのおかげで、双極性障害に関連する遺伝的バリアント
Natureに掲載された研究により、双極性障害に関連する約300のゲノム領域と、疾患に関与する36の主要な遺伝子が特定される
この研究から得られた生物学的知見は、より優れた治療法の開発、早期介入、そしてプレシジョン・メディシン(精密医療)への道を開く可能性があります。双極性障害は、(軽)躁状態と抑うつ状態の間を変動することを特徴とする複雑な精神疾患です。世界中で約4,000万~5,000万人がこの疾患を抱えていると推定されています。双極性障害は、自殺を含むさまざまな負の影響と関連しており、診断までに平均8年かかることが知られています。しかし、この疾患の生物学的なメカニズムについては未だ十分に解明されていません。
今回の新たな研究では、約290万人の参加者のデータを分析しました。研究者らは、欧州系、東アジア系、アフリカ系アメリカ人、ラテン系の祖先を持つ参加者(双極性障害患者158,036名、対照群280万人)を対象に、臨床データ、地域社会ベースのデータ、自己申告データを統合して解析しました。その結果、双極性障害に関連する298のゲノム領域が特定され、これまでの発見の4倍に相当する成果となりました。さらに、複数の手法を組み合わせた解析により、双極性障害と強く関連する36の遺伝子が特定されました。
この研究結果は2025年1月22日にNature誌に掲載されました。論文のタイトルは「Genomics Yields Biological and Phenotypic Insights into Bipolar Disorder(ゲノミクスがもたらす双極性障害の生物学的・表現型的洞察)」です。
「これは、双極性障害に関する初の大規模な多民族ゲノム解析であり、双極性障害の異なるタイプを含んでいます。大規模なサンプルサイズのおかげで、双極性障害に関連する遺伝的バリアント
 古代ウイルスDNAの新たな役割:初期胚発生における「トランスポゾン」の重要性
私たちのゲノムの半分以上は、古代ウイルスDNAの名残である「トランスポゾン(transposable elements)」によって構成されています。このかつて「ゲノムの暗黒面」とも呼ばれた要素が、初期胚発生において重要な役割を果たしていることを、ドイツ・ヘルムホルツミュンヘン研究所およびルートヴィヒ・マクシミリアン大学(LMU)の研究者チームが明らかにしました。
未解決の謎:古代ウイルスDNAの役割
トランスポゾンは、受精直後の数時間から数日にわたり再活性化されます。この初期発生のダイナミックな過程では、胚細胞が顕著な可塑性を示しますが、その分子メカニズムや規制因子については依然不明な点が多いです。マウスをモデルとした研究では、トランスポゾンが細胞の可塑性に重要な役割を果たすことが示唆されていますが、この現象がすべての哺乳類に共通するのかは未解明です。これらのウイルス遺伝子の進化的起源が多様であることから、哺乳類のゲノムにおける保存性についてさらなる疑問が生じています。この規制メカニズムを解明することは、生殖医学の進歩やゲノム規制の基本原則を理解するために重要です。
消滅したはずのウイルス遺伝子が哺乳類胚で再活性化
マリア・エレナ・トーレス=パディリャ博士(Maria-Elena Torres-Padilla, PhD)を中心とする研究チームは、これらの古代DNA配列を研究するための新しい手法を開発しました。この手法により、マウス、ウシ、ブタ、ウサギ、アカゲザル(非ヒト霊長類)など複数の哺乳類種の胚を比較し、単一胚アトラスを作成しました。その結果、消滅したと考えられていた古代のウイルス配列が、哺乳類胚で再活性化されることが判明しました。また、それぞれの種が特有のトランスポ
古代ウイルスDNAの新たな役割:初期胚発生における「トランスポゾン」の重要性
私たちのゲノムの半分以上は、古代ウイルスDNAの名残である「トランスポゾン(transposable elements)」によって構成されています。このかつて「ゲノムの暗黒面」とも呼ばれた要素が、初期胚発生において重要な役割を果たしていることを、ドイツ・ヘルムホルツミュンヘン研究所およびルートヴィヒ・マクシミリアン大学(LMU)の研究者チームが明らかにしました。
未解決の謎:古代ウイルスDNAの役割
トランスポゾンは、受精直後の数時間から数日にわたり再活性化されます。この初期発生のダイナミックな過程では、胚細胞が顕著な可塑性を示しますが、その分子メカニズムや規制因子については依然不明な点が多いです。マウスをモデルとした研究では、トランスポゾンが細胞の可塑性に重要な役割を果たすことが示唆されていますが、この現象がすべての哺乳類に共通するのかは未解明です。これらのウイルス遺伝子の進化的起源が多様であることから、哺乳類のゲノムにおける保存性についてさらなる疑問が生じています。この規制メカニズムを解明することは、生殖医学の進歩やゲノム規制の基本原則を理解するために重要です。
消滅したはずのウイルス遺伝子が哺乳類胚で再活性化
マリア・エレナ・トーレス=パディリャ博士(Maria-Elena Torres-Padilla, PhD)を中心とする研究チームは、これらの古代DNA配列を研究するための新しい手法を開発しました。この手法により、マウス、ウシ、ブタ、ウサギ、アカゲザル(非ヒト霊長類)など複数の哺乳類種の胚を比較し、単一胚アトラスを作成しました。その結果、消滅したと考えられていた古代のウイルス配列が、哺乳類胚で再活性化されることが判明しました。また、それぞれの種が特有のトランスポ
 SIDS(乳幼児突然死症候群)の「指紋」を血液検査で特定:UVA医学部の最新研究
バージニア大学(University of Virginia, UVA)医学部の新しい研究により、乳幼児突然死症候群(SIDS: Sudden Infant Death Syndrome)の特徴が血液サンプルから識別できる可能性が示されました。この発見は、SIDSのリスクが高い乳児を簡単な検査で特定する道を開くと考えられています。さらに、SIDSの原因解明に向けた重要な一歩となり得ます。SIDSは生後1か月から1歳までの乳児の主要な死因であり、その原因は長年にわたり不明のままでした。UVAの研究者らは、SIDSで死亡した乳児の血清サンプルを分析し、特定の生物学的指標を特定しました。これらの指標は、SIDSと関連があるだけでなく、その原因となっている可能性もあります。研究者らは、これらの兆候を早期に検出できる検査が開発されれば、命を救うことにつながると考えています。
UVA健康格差・精密公衆衛生センター(Center for Health Equity and Precision Public Health)の創設ディレクターであり、現在はイーストカロライナ大学(East Carolina University)に所属するキース・L・キーン博士(Keith L. Keene, PhD)は、次のように述べています。
「本研究は、血液中の小分子がSIDSのバイオマーカーとして機能するかどうかを検出しようとした過去最大規模の研究です。我々の発見は、SIDSのリスク増加や診断に関与する可能性のある複数の重要な生物学的経路を示しており、その仕組みを理解する手がかりを提供します。」
SIDSの理解を深める
研究者らによると、本研究は「メタボロミクス」の可能性を示すものです。メタボロミクスとは、
SIDS(乳幼児突然死症候群)の「指紋」を血液検査で特定:UVA医学部の最新研究
バージニア大学(University of Virginia, UVA)医学部の新しい研究により、乳幼児突然死症候群(SIDS: Sudden Infant Death Syndrome)の特徴が血液サンプルから識別できる可能性が示されました。この発見は、SIDSのリスクが高い乳児を簡単な検査で特定する道を開くと考えられています。さらに、SIDSの原因解明に向けた重要な一歩となり得ます。SIDSは生後1か月から1歳までの乳児の主要な死因であり、その原因は長年にわたり不明のままでした。UVAの研究者らは、SIDSで死亡した乳児の血清サンプルを分析し、特定の生物学的指標を特定しました。これらの指標は、SIDSと関連があるだけでなく、その原因となっている可能性もあります。研究者らは、これらの兆候を早期に検出できる検査が開発されれば、命を救うことにつながると考えています。
UVA健康格差・精密公衆衛生センター(Center for Health Equity and Precision Public Health)の創設ディレクターであり、現在はイーストカロライナ大学(East Carolina University)に所属するキース・L・キーン博士(Keith L. Keene, PhD)は、次のように述べています。
「本研究は、血液中の小分子がSIDSのバイオマーカーとして機能するかどうかを検出しようとした過去最大規模の研究です。我々の発見は、SIDSのリスク増加や診断に関与する可能性のある複数の重要な生物学的経路を示しており、その仕組みを理解する手がかりを提供します。」
SIDSの理解を深める
研究者らによると、本研究は「メタボロミクス」の可能性を示すものです。メタボロミクスとは、
 筋肉内に隠れた脂肪が心疾患リスクを高める:BMIでは評価できない新たな指標
2025年1月20日に「European Heart Journal」に掲載された研究によると、筋肉内に蓄積された「異所性脂肪(intermuscular fat)」を多く持つ人は、心筋梗塞や心不全による死亡や入院のリスクが高まることが明らかになりました。このオープンアクセスの論文は「Skeletal Muscle Adiposity, Coronary Microvascular Dysfunction, and Adverse Cardiovascular Outcomes(骨格筋脂肪蓄積、冠微小血管機能障害、および心血管系への悪影響)」と題されています。
この「異所性脂肪」は、牛肉のステーキでは旨味のもととして価値がある一方で、人間の健康への影響についてはほとんど知られていません。本研究は、筋肉内脂肪が心疾患に及ぼす影響を包括的に調査した初の研究です。今回の発見は、従来の指標である体格指数(BMI: Body Mass Index)やウエスト周囲径が、すべての人に対して正確に心疾患リスクを評価するには不十分であることを示唆しています。
この研究は、ハーバード大学医学部(Harvard Medical School)およびブリガム・アンド・ウィメンズ病院(Brigham and Women's Hospital)の心臓ストレス検査室(Cardiac Stress Laboratory)のディレクターであるヴィヴィアニー・タケティ医師(Viviany Taqueti MD, MPH)を中心に行われました。彼女は次のように述べています。
「肥満は現在、心血管の健康に対する最大の脅威の1つですが、肥満を定義し、介入の基準とするための主要指標であるBMIは、心血管予後を評価する上で論争の的
筋肉内に隠れた脂肪が心疾患リスクを高める:BMIでは評価できない新たな指標
2025年1月20日に「European Heart Journal」に掲載された研究によると、筋肉内に蓄積された「異所性脂肪(intermuscular fat)」を多く持つ人は、心筋梗塞や心不全による死亡や入院のリスクが高まることが明らかになりました。このオープンアクセスの論文は「Skeletal Muscle Adiposity, Coronary Microvascular Dysfunction, and Adverse Cardiovascular Outcomes(骨格筋脂肪蓄積、冠微小血管機能障害、および心血管系への悪影響)」と題されています。
この「異所性脂肪」は、牛肉のステーキでは旨味のもととして価値がある一方で、人間の健康への影響についてはほとんど知られていません。本研究は、筋肉内脂肪が心疾患に及ぼす影響を包括的に調査した初の研究です。今回の発見は、従来の指標である体格指数(BMI: Body Mass Index)やウエスト周囲径が、すべての人に対して正確に心疾患リスクを評価するには不十分であることを示唆しています。
この研究は、ハーバード大学医学部(Harvard Medical School)およびブリガム・アンド・ウィメンズ病院(Brigham and Women's Hospital)の心臓ストレス検査室(Cardiac Stress Laboratory)のディレクターであるヴィヴィアニー・タケティ医師(Viviany Taqueti MD, MPH)を中心に行われました。彼女は次のように述べています。
「肥満は現在、心血管の健康に対する最大の脅威の1つですが、肥満を定義し、介入の基準とするための主要指標であるBMIは、心血管予後を評価する上で論争の的
 世界の主要なすべての人口集団において、うつ病の新たな遺伝的リスク因子が初めて特定されました。これにより、科学者らは民族に関係なく、うつ病のリスクを予測できるようになりました。専門家によると、今回の研究は、これまでで最大かつ最も多様性のあるうつ病の遺伝学的研究であり、これまで知られていなかった約300の遺伝的関連が明らかになりました。そのうち100の新たに発見された遺伝的変異—遺伝子を構成するDNA配列のわずかな違い—は、アフリカ系、東アジア系、ヒスパニック系、南アジア系の人々を対象に含めたことによって特定されました。
これまでのうつ病の遺伝学研究は、主にヨーロッパ系の祖先を持つ白人集団を対象として行われてきました。そのため、遺伝学的アプローチを用いて開発された治療法が、他の民族では効果的でない可能性があり、既存の健康格差を広げる要因となる可能性があります。
各遺伝的変異の単体での影響は、うつ病の発症リスク全体に対して非常に小さいものです。しかし、複数の変異を持つ場合、それらの小さな影響が積み重なり、リスクが増加する可能性があります。
研究チームは、新たに特定された遺伝的変異を考慮することで、個人のうつ病リスクをより正確に予測できるようになりました。
この国際的な研究チームは、エディンバラ大学およびキングス・カレッジ・ロンドン(King’s College London)が主導し、世界29か国の500万人以上の匿名化された遺伝情報を分析しました。研究対象者のうち、4人に1人は非ヨーロッパ系の祖先を持つ人々でした。
研究者らは、うつ病の発症と関連する遺伝コードの変異を合計700カ所特定しました。そのうち約半数はこれまでうつ病との関連が知られていなかったものであり、最終的に特定された遺伝子は308種類に及びました。
特定された遺伝的変異は、複数の脳領域に存在するニ
世界の主要なすべての人口集団において、うつ病の新たな遺伝的リスク因子が初めて特定されました。これにより、科学者らは民族に関係なく、うつ病のリスクを予測できるようになりました。専門家によると、今回の研究は、これまでで最大かつ最も多様性のあるうつ病の遺伝学的研究であり、これまで知られていなかった約300の遺伝的関連が明らかになりました。そのうち100の新たに発見された遺伝的変異—遺伝子を構成するDNA配列のわずかな違い—は、アフリカ系、東アジア系、ヒスパニック系、南アジア系の人々を対象に含めたことによって特定されました。
これまでのうつ病の遺伝学研究は、主にヨーロッパ系の祖先を持つ白人集団を対象として行われてきました。そのため、遺伝学的アプローチを用いて開発された治療法が、他の民族では効果的でない可能性があり、既存の健康格差を広げる要因となる可能性があります。
各遺伝的変異の単体での影響は、うつ病の発症リスク全体に対して非常に小さいものです。しかし、複数の変異を持つ場合、それらの小さな影響が積み重なり、リスクが増加する可能性があります。
研究チームは、新たに特定された遺伝的変異を考慮することで、個人のうつ病リスクをより正確に予測できるようになりました。
この国際的な研究チームは、エディンバラ大学およびキングス・カレッジ・ロンドン(King’s College London)が主導し、世界29か国の500万人以上の匿名化された遺伝情報を分析しました。研究対象者のうち、4人に1人は非ヨーロッパ系の祖先を持つ人々でした。
研究者らは、うつ病の発症と関連する遺伝コードの変異を合計700カ所特定しました。そのうち約半数はこれまでうつ病との関連が知られていなかったものであり、最終的に特定された遺伝子は308種類に及びました。
特定された遺伝的変異は、複数の脳領域に存在するニ
Life Science News from Around the Globe
Edited by Michael D. O'Neill

バイオクイックニュースは、サイエンスライターとして30年以上の豊富な経験があるマイケルD. オニールによって発行されている独立系科学ニュースメディアです。世界中のバイオニュース(生命科学・医学研究の動向)をタイムリーにお届けします。バイオクイックニュースは、現在160カ国以上に読者がおり、2010年から6年連続で米国APEX Award for Publication Excellenceを受賞しました。
BioQuick is a trademark of Michael D. O'Neill