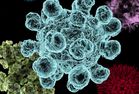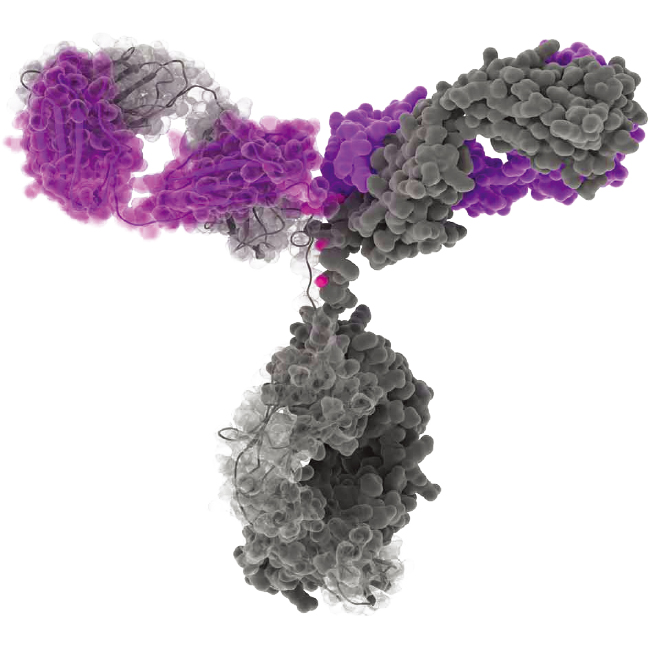まるでSF話のようだが、人間の体内にいて数では人体細胞の100倍もの数になる腸内細胞が、人間の食欲などに影響し、腸内細胞自身の食べたい物を人間が欲するように仕向けている上に人間の肥満をもたらしているのではないかという研究結果が出されている。2014年8月7日付BioEssaysオンライン版に掲載された研究論文で、University of California-San Francisco, (UCSF)、Arizona State University、University of New Mexicoの研究チームは、最近の科学文献のレビューを行い、「腸内細菌は、人間が自分の選択で摂る栄養物を何でも受け身で吸収するのではなく、細菌自体の繁殖に適した栄養素を取るよう人間の摂食行動や食餌選択に影響を与えていると考えられる」との結論を下した。必要とする栄養素は細菌種ごとに異なる。
たとえば脂肪を好む細菌、ショ糖を好む細菌などがある。論文の筆頭著者でUCSFのHelen Diller Family Comprehensive Cancer Center内Center for Evolution and Cancer共同設立者のAthena Aktipis, Ph.D.によると、「ことなる細菌種は、食餌を求め、細菌の生態系である人間の消化器官の中でそれぞれの棲息場所を確保するために互いに競争するだけでなく、人間の行動についても、人間自身の思惑とは異なる目的を持っていること」も多い。
その正確な機序はまだ明らかではないが、研究チームは、全体として腸内微生物叢と呼ばれるこの多彩な微生物の社会は、信号分子を腸内に放出することで人間の選択に影響を与えているのではないかと考えている。腸は免疫系、内分泌系、神経系などとリンクしており、放出された信号分子が人間の生理的な反応、行動的な反応を左右することは十分に考えられる。
BioEssays論文の責任著者でUCSF Center for Evolution and Cancerのdirectorを務めるCarlo Maley, Ph.D.は、「腸内細菌は宿主を操るのが巧みだ。また、マイクロバイオームには様々な利害関係があり、食物摂取の目的が人間に合致している細菌もあれば、合致しない細菌もある」と述べている。
Dr. Maleyは、「幸いなことにそういう影響力は双方向通行だ。人間の方も意図的に摂取する食物を変えることでこの微小な単細胞の宿泊客との相性を変えることもできる。食べ物を変えると24時間以内にマイクロバイオームにはっきりとした変化が現れる」と述べている。
Dr. Maleyは、「人間の食餌は腸内の細菌種の比率を大きく左右する。腸内微生物群全体が一つの生態系であり、分単位で変化している」と述べている。食生活で海藻が好まれる日本では人の体内から海藻を消化する特殊な細菌さえ見つかっている。研究の結果、腸内細菌は、消化管から脳底まで1億個の神経細胞を結んでいる迷走神経に働きかけ、食べ物の選択にまで影響している可能性も示唆されている。現在、Arizona State University Department of Psychologyに所属するDr. Akitipisは、「腸内細菌は迷走神経の神経信号を変更し、味受容器を変化させたり、不快感を与える毒素を生成した上で、快感を与える報酬化学物質を放出したりすることで人の行動や気分を操作することができる」と述べている。マウスでの実験で特定の細菌種が不安行動を激しくすることが明らかになっている。人間の場合、ただ一つだが臨床試験でカセイ菌が含まれたプロバイオティクスを飲むことで落ち込んでいた気分が改善されることも突き止められている。
Dr. Maley、Dr. Aktipisの2人とUniversity of New Mexico, Department of Emergency Medicine勤務でこの論文の第一著者のJoe Alcock, M.D.は、腸内細菌が人間に対してどれほどの支配力があるのか今後の研究を提案している。たとえば、海藻の栄養を必要とする細菌を腸内に植え付けた場合、宿主の人間は海藻をたくさん食べるようになるだろうかということが考えられる。
マイクロバイオームが変化する速さは、腸内細菌種比率を変えることで健康を改善したい人にとっては希望の持てることかも知れない。これは、食物やサプリメントを選んだり、特定細菌種をプロバイオティクスの形で摂取したり、あるいは特定細菌種を抗生物質で根絶するなどで可能になるかもしれない。論文著者によると、腸内細菌種間の勢力関係を最適化すれば、肥満を減らし、健康な生活に改善することも可能であり、腸内微生物叢はプレバイオティクス、プロバイオティクス、抗生物質、糞便移植、食餌変更などで簡単に変えられるため、腸内微生物叢改善が肥満や不健康な食生活など健康上の難しい問題に対する現実的な治療法になる可能性がある。
研究チームは、2年前に進化医学のサマー・スクール会議で顔を合わせ、初めてBioEssays論文でアイデアを話し合った。進化生物学者であり、心理学者でもあるDr. Aktipisは、腸内微生物やその宿主の間の異なる適応上の必要の複雑に作用詩合っていることと、それが人間の日常生活に及ぼす働きを研究する機会を捉えた。
コンピュータ科学者で進化生物学者でもあるDr. Maleyは、どのような経過で正常細胞からがん細胞が発生し、がんが進行するにつれてがん細胞が体内で自然選択を通して発達する仕組みの研究で業績を挙げてきた。
Dr. Aktipisは、「事実、がんの発達と細菌集団の間には関係がある」として、人体内に普通にいるような細菌のあるものが胃がん、あるいはその他のがんの原因になっている」と述べている。さらに、「マイクロバイオームを調べていけば、肥満、糖尿病などから消化器系のがんに至るまで様々な疾患の予防ができるようになる可能性もある。人間の健康に対してマイクロバイオームがどれほど重要な役割を占めているか、人類はようやくその表面をわずかにひっかき始めただけだ」と述べている。
■原著へのリンクは英語版をご覧ください: Gut Bacteria May Rule Human Eating Behavior and Dietary Choices