著者: 中山 登
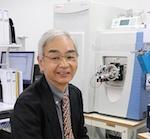
このセクションは、(株)Spectro Decypher 取締役&CTO(元・中外製薬株式会社研究本部化学部分析グループ長)中山 登 氏による創薬研究コラムです。
長年、創薬研究に携わってこられた中山氏が、創薬研究の潮流についての雑感や、創薬研究者が直面している課題の解決法などを体験談を踏まえて語っていただきます。
全文を読むにはログインしてください。(登録無料)
中山氏へのご意見やご質問は各記事ページ下のコメント欄から投稿できます。
【中山 登 氏 ご略歴】
昭和48年3月 立命館大学理工学部卒業
昭和48年5月~
昭和56年4月 電気通信大学材料科学科、コロンビア大学化学部研究員
昭和56年6月 日本ロシュ株式会社研究所 入社
平成8年4月 日本ロシュ株式会社研究所天然物化学部、機器分析グループ長
平成16年10月 中外製薬株式会社研究本部化学部分析グループ長
平成21年4月 中外製薬株式会社 定年 シニア職
平成26年4月 中外製薬株式会社 退職
平成26年5月~現在 株式会社バイオシス・テクノロジーズ 取締役&チィーフ・テクニカル・オフサー(CTO)
平成27年4月~平成31年3月 聖マリアンナ医科大学分子病態情報研究講座講師
平成31年1月~現在 株式会社Spectro Decypher 取締役&チィーフ・テクニカル・オフサー(CTO)
【HP】
株式会社Spectro Decypherのホームページ