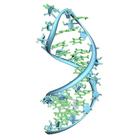2014年1月12日付Nature Methodsオンライン版に掲載されたUniversity of Pennsylvania (Penn) 学際チームの研究論文は、生細胞のmRNAを生体組織の微小環境で周辺の細胞を損傷せずに分離する、この種のものとしては初めてのテクニックを発表している。このテクニックにより、細胞間の化学的接続が個別細胞機能や全体的なタンパク質生成に与える影響を解析することが可能になる。
生体組織は当然ながら様々なタイプの細胞で構成された複雑な構造体であり、また、心臓、皮膚、脳など各組織タイプ内での個別細胞の種類や機能は、どの遺伝子がmRNAに転写されているか、また究極的には生成されるタンパク質と密接に結びついている。結局、生体組織内での単一細胞の遺伝子発現を調べるためにはその細胞内部の働きを観察しなければならない。生態学者が個々の種を研究する際にその種の生息環境との相互影響を観察しなければならないのと同じことである。
たとえば同じタイプと見える細胞同士でさえ、分子レベルで見ればまったく同じということはない。現在の遺伝子発現変異に関する知識のほとんどは培養液中で成長した異質細胞グループを使った研究で得られたものであり、このような不自然な条件で得られた結果から「現実の生物学」を推定することについては研究者も疑問をいだいている。健康な生体組織中の単一細胞にどのタイプのRNAがどれだけ存在するかを調べることのできるツールがあれば、哺乳動物の細胞が生体内でどのように機能するのか、また様々な疾患でその機能がどのように不全になるのかを評価する貴重な機会が得られ、究極的には新薬の試験にも役立てることができるはずである。
Perelman School of MedicineのPharmacology教授でPenn Genome Frontiers Institute (PGFI)のco-directorを務めるJames Eberwine, Ph.D.と、School of Arts and SciencesのChemistry准教授のIvan Dmochowski, Ph.D.とがこの研究の共同監督を務めた。Pennの研究論文共同著者には、Perelman School of MedicineのPharmacology准教授、Jai-Yoon Sul, Ph.D.、Chair of NeurosurgeryのM. Sean Grady, M.D.の両氏の他、Biology教授でPGFI co-directorを務めるJunhyong Kim, Ph.D.も参加している。Dr. Eberwineは、「私たちの研究のデータから、組織の微小環境が個々の細胞の特性を決めることが明らかになった」と述べている。この新しいテクニックは、「transcriptome in vivo analysis (生体解析トランスクリプトーム)」の頭文字を取って「TIVA」と名付けられている。研究チームは、マウスとヒトの細胞を対象に生きた組織の中で単一細胞のmRNAを物理的に分離する非侵襲性の手法を用い、特にヒトの細胞の場合は、脳外科手術が終わった直後に摘出した脳組織を使って実験を行った。TIVAタグは分子レベルのスイス・アーミー・ナイフにたとえることができ、周囲の他の細胞には一切触れることなく、単一の細胞のmRNAだけを獲得するのに必要な複数の化学ツールを巧みにまとめたテクニックである。
第一のツールはアミノ酸の一配列で、これは対象の細胞にも周囲の組織にも損傷を与えることなく分子を細胞壁を抜けて浸透させることができる。しかし、この段階では、研究者は特定細胞を対象にすることはせず、脳から摘出した組織試料全体をTIVAタグを含んだ溶液で洗い、組織の全細胞に分子を浸透させた。このテクニックでは、対象とする単一細胞だけでなく、脳組織の神経細胞全てに分子が入り込んでいるため、時機が来るまで、TIVAタグのmRNA獲得機能のスイッチをオフにしておく方法を考え出さなければならない。そこで、タグの2つめのツールが活躍する。これは分子の結合部分を覆う着脱可能な「檻」の役割を果たす。TIVAタグは、Eberwineラボが以前に行った研究で生細胞からRNA結合タンパクを分離するためにDNAとキャプチャ・シーケンスの光活性化を用いた実績と、Dmochowskiラボが過去10年間、光活性オリゴヌクレオチドの様々な反復の研究を行ってきた実績とを元にして組み立てられている。Dr. Dmochowskiは、「これらの分子は、物理的にその機能が停止されているという意味で『檻』に入れられており、カギを与えるまで機能できない。この研究の場合にはレーザー光というカギを照射することで檻が取り除かれると分子は反応を開始し、mRNAに結合する」と述べている。この分子にはRNAの4つの塩基の一つであるウラシルの長鎖反復がつながっており、それによってmRNAと結合できるようになっている。この「ポリウラシル」配列を対応する「ポリアデニン」配列、mRNA分子すべてに含まれているアデニン塩基の長鎖反復と結合させるのである。しかし、この結合能力を阻むため、TIVAタグには一対のポリアデニン配列を「檻」として加えてある。Dr. Dmochowskiは、「こうしておくと、TIVAタグは自己結合で安定している。ただし、このポリアデニン配列はたった2つのリンカーで分子に結合しているだけであり、このリンカーはレーザーでこわすことができる。この結合を破壊するのに十分なエネルギーを持った青色レーザーを照射し、分子が分解するとポリウラシル配列が露出し、mRNAとの結合を開始する」と説明している。
青色の活性化レーザー照射の精度は標的にした単一細胞内のTIVAタグの「檻」だけを開くことができるほどである。ただし、このTIVAタグを狙った細胞に間違いなく浸透させるためにはまず弱い緑色レーザーをその細胞に照射する。ここでタグのもう一つのツール、一対の蛍光染料の出番になる。緑色レーザーがこの蛍光染料に作用するのである。この二つの染料の一つはpoly-U配列、一つはpoly-A配列の近くに正確に配置されており、分子の「檻」がまだ閉じられている間は、この二つの染料は互いに十分近いため、レーザーのエネルギーを互いの間で移転することができる。PharmacologyのDr. Sulによれば、「緑色レーザーをその細胞に照射し、この2つの染料の間で移転されたエネルギーに対応する発光があれば、タグが無事に細胞内に浸透したことを意味する」のである。その後、強力な青色レーザーでタグを活性化した後、再び緑色レーザーを細胞に照射して対応する発光がなければ二つの染料が分離されてエネルギーの移転ができなくなっているのであり、「檻」が取り除かれたことが分かる。タグの最後のツールはビオチン・マーカーで、これはpoly-U配列のある分子の末端に結合している。タグを活性化した後、ターゲットの細胞を開き、mRNAを引き連れたタグを取り出して完了するのだが、この研究ではタグの取り出しにビオチンに対して強い親和性を持つ細菌タンパク質を仕込んだビードを用いている。タグは細胞内のmRNAと水素結合で化学的に結びつき、細胞内のmRNA全量を分離することができる。タグの活性化はレーザー光で可能なため、生組織内のどの細胞でも標的にすることができる。
ビードを使ってタグを回収すれば、タグに結合しているmRNAを生成、増幅、配列解析することが可能になる。研究チームは、単一ニューロンの遺伝子発現のプロファイルを作成し、異なる成長条件の細胞と比較した。たとえば、健康な脳組織の細胞に含まれているmRNAの量を、神経細胞の混合培養液中の細胞のそれと比較したBiologyのDr. Kimらのチームは、培養液中の細胞では、健康な組織の細胞に比べて遺伝子発現がはるかに多くなっていることを発見して驚いた。分離された細胞は、周辺の細胞から何ら意味のある化学シグナルを受けない結果、どんな状況にも対応できるようRNAを発現させているのではないかと考えられた。研究チームはNeurosurgeryのDr. Gradyの協力のもと、ニューロンの接続を損なわないように作った生体組織スライス・プレパラートの単一ヒト皮質ニューロンからTIVAの手法を使ってRNA全量を分離し、特徴を分析した。このようにTIVAの手法は、これまでヒトのニューロンを取り出して検査するという手法でしか知ることのできなかったヒトの神経生物学と疾患の分野を明らかにできる可能性がある。現在、研究チームはさらに異なる官能基を持ったTIVAタグの開発を進めている。自然状態の組織の中で複数のタグを同じ細胞あるいは複数の細胞に浸透させ、単一細胞中で異なる分子がどのように機能するかを動的に定量化することができるはずである。
この研究の他の共同著者として、PennのPharmacologyのDr. Ditte Lovatt、ChemistryのDr. Brittani Rubleが参加している。
■原著へのリンクは英語版をご覧ください: Unique Molecular Tool Developed to Isolate mRNA from Single Live Cells