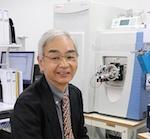まず、本題に入る前に、前回の文章の誤字の修正をお願いします。タイトルの部分と本文冒頭の部分で、AIと書くべきところをATとタイプミスをしてしまいました。誠に申し訳ございませんでした。歳で少し注意が散漫になってきたのかな?それでは、はじめにまだ話していない新しい創薬の手法の、再生医療を応用した創薬開発(iPS創薬)に関して少し説明します。この方法は患者さんの疾患細胞から病気の標的iPS細胞(疾患モデル細胞)を作り、この疾患モデル細胞と健康細胞を比較して違いを解析し、疾患モデル細胞を用いてその違いを無くす、低分子・中分子化合物をスクリーニングして、リード化合物を探索する方法です。
この方法は疾患のメカニズムやターゲットプロテインが解明されていなくても、細胞レベルでリード化合物が探索できるメリットがあります。特に疾患の解明が難しい難病に関しては有効と思われます。現在、ALS(筋萎縮性側索硬化症)を対象にこのiPS創薬の手法を用いて創薬研究が進んでいるようです。更に、糖尿病などの生活習慣病の薬の開発にも有効ではないかと考えられます。
それでは本題の今後の医薬品開発の方向性に関して話すことにします。私は創薬の今後について、核酸医薬とAIを用いた低分子・中分子創薬と、再生医療を応用し作成したiPS細胞を利用した創薬スクリーニングで見つかったリード化合物をDDS技術でターゲット部位に送る方法が中心になってくると考えています。特に毒性と副作用の殆どない医薬品の開発には、DDS化が重要になってきます。
核酸医薬と、AI技術やiPS創薬の低分子・中分子有機化合物のDDSの必要性について説明します。以前にも話したように、核酸医薬の場合siRNAやRNA解析から見つかった疾患ターゲット部位など体内での安定性に問題があります。そのために感染症のワクチンで用いられている無毒化したウイルスや、エクソソームなどのDDSキャリアで保護して標的細胞に輸送する必要があります。更に、AI技術やiPS創薬でリード化合物として見つかった低分子・中分子有機化合物は副作用と毒性を軽減と、体内動態の改善のために、非活性の状態で標的細胞に送り細胞内で活性を発現させることが必要です。そのためにAntibody-drug conjugate(ADC)、Peptide-Drug Conjugate(PDC)やエクソソームなどのDDSキャリアを用いることが重要であると考えています。ただ、DDSキャリアなどを利用した創薬に関しては開発にかなりの時間が掛かります。更に、iPS創薬の有効とされるALSや生活習慣病の様に抗体が生成し難い、疾患細胞改善のリード化合物に対するDDSキャリアの作成が難しい場合の解決が必要で、これらのことが今後の課題になると考えています。
また、癌や感染症に関しては、感染すると体内で癌やウイルスに抵抗する抗原特異的T細胞が生成されます。この抗原特異的T細胞を再生医療のiPS細胞技術を用いて再生し、薬として用いることも可能ではないかと思うのです。